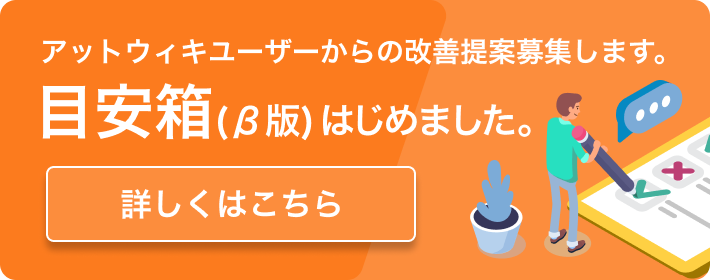「リレー小説 1」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る
リレー小説 1 - (2014/12/17 (水) 21:52:02) のソース
【西口 2013.11/04】 空間そのものを満たすような、不思議な声。 鼓膜を揺すぶられるよりも早く、意味が理解できるような、まるで文字でも読んでいるような感覚に、少年は襲われた。 少年は仰向けに地に倒れ、その上から押さえつけられている。 その全身をすっぽりと覆うように巨大な、白龍の前足に。 四指に備えられた爪が、まるで杭のように地面に突き立てられている。脱出出来ない状況ながら、少年の体には少しばかりの圧迫感があるだけだ。 少年は、ただ龍の姿を見つめていた。 ため息を吐いてしまいそうなほどに、美しい。 総身を被う鱗はまさに純白というべき程に透き通り、漏れ出る木漏れ日を反射して、白々と輝いている。 顔の真横に突き刺さる爪は、抜き身の刀など足元にも及ばないほどに剣呑な雰囲気を醸し出しながらも どこか高貴さが漂っている。 絵画のようだ。芸術品のようだ。陳腐な喩えが幾つも浮かんできては、泡沫のように融けて消え失せていく。 「彼女」を前にして、その様な物は必要ない。人が生み出したような物では、「彼女」の放つ凄絶なまでの美しさを表すには、あまりにも役者不足が過ぎる。 生涯最後の光景がこれならば、良い人生と言えるのかもしれない。少年は、薄く笑った。 「生きたいとは思わないの、貴方?」 急かすような龍の言葉に、少年は「殊更には」と応じた。 「特別死にたいとも、生きたいとも思わない。人は死ぬときには、何をやっても死ぬものだ」 「嘘ね」 龍は断じる。 「自分に嫌気が差している眼。受動的な死を待ち望んでいる眼。疲れきった眼をしている。 能動的に動く気がないだけで、貴方は死にたいのよ」 「だったら、何だ。殺してくれるのか?」 「いえ、質問を少し変えるわ」 ずい、と龍は己の顔を少年の鼻先へと近づけた。 「力、欲しい?」 少年の繭が、ピクリとつり上がった。 「貴方のこと、知ってる。何で死にたいと思い始めたのかも、何で力が欲しいのかも、全部」 少年の双眸が大きく見開かれた。紡ぐべき言の葉を探しているのか、半開きであった口が、忙しなく開閉される。 やがて吐き出された「何で……」という呟きは、そよ風のように微かな物だった。 「聞いたからよ。貴方が力を失った、その元凶から」 がしり、少年は手近な龍の爪を掴んだ。少年が見せた抵抗らしき行動は、それが始めてであった。 「誰だ、それは」 「知ってどうするの? 死にたいんでしょう、貴方」 「やかましいッ!」 嘲るような龍の言葉を遮るように、少年の怒号が響く。死んでいた少年の瞳に、激しい憎しみの炎が灯った。 「聞いたといったな。つまり、あれは人災だということだろう? 誰だ? 誰だ誰だ誰だ誰だ! 俺から力を、総てを奪った奴は!」 「知ってどうするの?」 繰り返し、龍はその前足に、ほんの少しだけ力を込める。 突き立てられた爪がググッと地面に沈み込め、少年にかけられた圧力が、一息に強まる。 「決まっている。この手で殺すッ!」 そんな事など意にも介さず、少年は龍の鼻先で吼える。 「死者に人は殺せない。力無き者に望みは遂げられない」 「なら力を寄越せ! 生を寄越せ! 代償ならば払おう。 命で贖えというのならば、全てが終わった後、この心の臓が抉り出されても構わない! だから――」 ――力を寄越せ! 龍はにこりと微笑んだ。 「うん、どうぞ」 グシャリと音がして、少年の体が潰れる。首から下が、ガラクタへと変わった。 同時に、龍の体が「解ける」。手足から先がどんどんと、糸が解けるように虚空へと消えていく。 最後に残った頭が消えたとき、中から膝を抱いて蹲る少女が、姿を現した。 潰れた少年の亡骸に寄り添うと、唯一無事だった頭部を拾い、己の眼の高さまで持ち上げる。 「これで、契約成立」 どこか陶酔したような口調でそう呟くと、己の唇を少年のそれに重ねた。 湿っぽい音を響かせて、少年の口腔へと流し込まれたそれは、確かに少年を変質させたのだ。 人から――化け物へと。 【Kの人 2013.11/06】 ――無機質な電子音が、未だ暗闇を彷徨う意識に突き刺さる。 水底から緩慢に水泡が浮き上がり、水面にて弾ける。それと同様に、纏わり着くような闇を掻き分け、意識が現実へ到達すると同時、暗闇が弾けて消えた。 視界には六畳一間の殺風景な一室が広がる。 同年代の者の様に何らかの趣味がある訳でもない。それ以前に慢性的な金欠に苛まされている以上、室内が充実することは一切ないだろう。 身体を支配する眠気に眼を細め、依然として喧しく騒ぎ立てる音源……枕元を見やる。 其処には横倒しにした円筒状の機器がある。機界から齎された技術によって作られた目覚まし時計と呼ばれる其れは、所有者が指定した時間になると音を発して所有者に知らせる。目覚まし、と銘打っているだけあって主な使用目的は起床補助なのだが、稀に時間把握のために用いられることもあるようだ。 ともあれ、適切な操作をしなければ延々と鳴り続けてしまうのが、この目覚まし時計と呼称される機器である。面倒だと感じながらゆっくりと手を伸ばし、円筒上部に設けられた釦に触れる。僅かに押し込んでしまえばかちりという小気味の良い音が僅かに響き、目覚まし時計は沈黙した。 訪れた静寂に、再び睡魔が襲い掛かってくる。再び闇の底へと沈んでいこうとする意識を無理矢理掴み上げ、上体を起こす。 同時に布団を軽く払い除け、己自身の身体を確認する。 装飾性よりも機能性、機能性よりも低価格を重視した寝間着。衣服の下にある身体はこの年代の者の平均値と比べて、僅かではあるが筋肉質である。体格は平均より指二本程度高く、体重は少々重い程度。つまり平均的な体格と言っても差し支えない範囲であり、今更しげしげと眺める物ではない。 ならば何故今更になって確認したかと言うと、先ほど見た奇妙極まりない夢のせいである。 幾度無く見た、幾度と無く見てきた夢。森羅万象をも霞ませる姿をした白龍、そしてそれに殺される夢。ただ殺されるだけという訳ではなく、かつて己自身が酷く渇望した"力"に対する代償ではあるのだが、所詮夢は夢でしかなく、その様な力は存在しない。 本来の力はかつて失われた。そのせいで大切な物を幾つも喪失した。絶望も憎悪も、数え切れないほど感じてきた。過去を思い出せば今でもちくりと刺す様な疼痛に苛まされる。持病とも呼べる”死にたがり”は幾分か回復方向へ向かっているが、発作的に想起される喪失の瞬間だけは依然として心身を蝕んでいる。 「……馬鹿馬鹿しい」 喪失した過去を想っても今は変えられない。今を変えられるのは今だけであり、こうして、何もしない間に時間は過ぎていく。 時間自体は無限に存在する様ではあるが、生物に与えられた時間は有限である。限られた時間を無意味に過ごすなど、其れこそ無意味だ。 あふっと欠伸を一つ漏らし、寝台から飛び降りる。足の裏から伝わる床の感触は、間違いなく足まで身体が存在している証拠とも言える。 実に当たり前の事ではあるが、当たり前が当たり前でなくなる世界を経験した身としては、当たり前な日常こそ価値のある物と言える。 寝間着を脱ぎながら、南向きに設けられた窓際へと寄る。加工を施された硝子越しに浴びる陽光はとても柔らかく、春先のそれを髣髴とさせる。 そんな心地良い日差しを浴びながら、窓の外を眺める。 真っ先に飛び込んできた冗談みたいに巨大な塔に、依然として苦笑は禁じ得なかった。 ◇ ――五界統合騒乱。 その昔、世界は単一の存在であった。しかし学者達が血眼になって研究している”何か”が原因で、五つの世界が重なってしまい、そして融合した。純粋に繋がった程度ならば万々歳なのだが現実は実に厳しく、限られた領域内に五つの世界が押し込まれたかのようになってしまった。 器に例えれば分かりやすい。一つの器には、一本分の液体しか入れることは出来ない。五界統合においては一つの器に五本分の液体を入れたのと同様で、それぞれの世界から零れ落ちた領域は、総計四世界分となった。 そうして領域を減らされた五つの世界に住まう住人は、かつてそれぞれの世界でもあったであろう様に、領土を廻った騒乱に身を投じることになった。初めは隣接部分等の局所地域で、それが徐々に拡大し、最終的には世界全土を巻き込んだ騒乱と化してしまった。 以降何十年にも渡って継続されたその戦争は、五界統合騒乱として歴史に記されている。 騒乱に伴い無数の命が失われた。ただでさえ五界統合時に人口を減らしていた各界の重鎮達は其れを重く受け止め、あまりにも遅過ぎる和解の道の模索を始めた。 模索から更に十数年経ち、漸う五界の重鎮達が納得出来る状態での住み分けが行われ、公式の上では和解し、それぞれの世界同士で和親条約が結ばれた。そして和解の象徴として五界の未来を担う若者を育む教育機関設けられる。 「それが此処、五界統合学院です」 凛とした声を響かせる女子生徒の回答を聞きながら、何を今更と思う。 なお、彼女の回答に不適切な点を敢えて上げろと言うのなら、、五界統合学院というのは正式な名称とは言えない点を指摘する。特定世界の言語で命名した場合は反感を覚える者が少なからずいる為、厳密に言えばこの学院に正式な名称は存在しない。ただ不便である為、統合時に中核を成した人間界の言語を通称として用いているだけである。その為、人間界以外……霊界、魔界、天界、機界の元住民は、それぞれ自界の言葉で同じ意味を持つ名称で呼ぶことが多いと聞く。 まるで聞いたことが無いような口ぶりではあるが、実際の所聞いたことはない。 頬杖をつく動作の最中、首に取り付けられたチョーカーを撫でる。 生徒手帳の代わりとも言える其れには、ある意味五界の技術が結集されている。機界が機構を考案し、人間界で小型化、魔界が汎用操作魔法の考案し、天界が実際のエンチャントを実行、霊界で行われた言語の翻訳の結果を反映している。 簡単に言ってしまえば、同時翻訳機構付き生徒証明機構とでも言った所だ。装着している限り見聞きした言葉を自界の言語に自動で翻訳し、また、装着している限り五界統合学院の生徒であると自動的に識別され、学院内で生じる諸々の煩雑な手続きが不要となる。 逆に言ってしまえば常に監視されていることに他ならず、また少々拘束感がある為、生徒からは不人気である。 腕時計型にして時計機能等を複合させたら便利だというのに―― 「――次の問題を……ソウジ」 思考の最中に割り込んできた声に、一瞬だけ心臓が跳ねる。 はっと現実に意識を向け、視線を教室前方の黒板に集中する。其処には見慣れた人間界の言語……教師の出身を考慮すれば元は恐らく天界語なのだろう、其れで一文程度の文章が書かれている。内容としては以下の一文を訳しなさいと書かれており、その続きは、翻訳機能で翻訳できないように呪詛魔法が掛けられていた。 曲線が多く用いられた特徴的な文字。それは書記魔法で用いられる術式言語の一つであり、言語名はアーヴニィルという最も多く用いられている物である。 その一文が意味するのは、”金は銀に、銀は銅に”と言った具合になる。札《カード》を媒体に書記魔法として発動すれば、対象を劣化させる効果にでもなるだろう。 ……と言いたい所ではあるがそうはいかない。敢えてそう記述しているのか、はたまた純粋に書き損じているのか、綴りの一部が間違えている。 「……金は銀に、銀は銅に」 視線を黒板から逸らすことなく答え、ちらりと先生の方を見やる。無言で頷くその光景から察するに正解であるらしく、つまり先生が書き間違えた事に他ならない。 指摘しなくて良かったと思いつつも、後学のために敢えて指摘しても良かったとも思う。尤も、既に終了してしまった事象である為指摘することは適わず、また、無粋であるに違いない。 再び頬杖をつき、教室前方、黒板の上部に設けられた時計を眺める。 時刻は十一時五十分。授業の半分が丁度終わり、もう少しすれば昼休みである。 今日は、凄惨極まる戦乱に身を投じなければならない。 約三十分後に訪れるだろう闘争を考え、溜息を吐かざるを得なかった。 【クロ 2013.11/16】 授業の終わりを告げる鐘が校内に鳴り響く。 それは、紛れも無く試合開始のゴングだ。 五界統合学院の食堂を目掛け、生徒は思い思いの方法で殺到する。 当たり前のことだが五界それぞれは独自の文化を有し、食文化も当然異なる。 機界は置いておくとして、何だかよく分からないものを煮込みがちな魔界、質素で味気ない天界、供物らしき団子が主な霊界、そしてまともな人間界。 それぞれの世界独自の文化を尊重し、それを食堂に反映させたことはとても素晴らしいと思う。実に立派だ。異文化交流だ。 だが現実はどうだ。 人間界のメニューが真っ先に売れきれるのである。俺自身まだ数える程度しかありつけていないレベルでだ。 天界の彼らはいい。基本的に天界の料理を食し、それどころか残ったメニューを率先して注文するような天使のようなお人達なのだ。 まず許せないのは魔界。俺はあいつらが魔界食を食べているのを見たことがない。それどころか俺が仕方なく魔界料理を食べていると決まって、やれ芋虫だのそれは蛙だのと知りたくもないことを吹き込んでくるのだ。お前の世界の料理だろ。文化だろ。 そして厄介なのが霊界だ。壁をすり抜けたりできる奴が多く、大抵奴らが人間界のメニューをごっそり持っていく。しかも実は食事を取る必要がないらしいのだ。ふざけるな。 そんなこんなで人間界の住人は魔界と霊界に良いイメージを持っていないのである。 はっきり言ってこの食堂のシステムは間違っている。 「さて、行くか」 皆より少し遅れて教室を出るのには理由がある。 魔界の連中からの妨害に巻き込まれないためだ。普段は仲が悪いというか自分勝手な連中だがこういう時だけは見事なコンビネーションを見せるから困る。 そう、俺は人間界のメニューを半ば諦めたスタンスなのである。 後方から様子を窺い、隙あらば人並みを掻い潜り前に抜ける。基本的な目標は天界のメニューを食べること。決して美味しいものではないが、天界の彼らに対するイメージからか、体 中が祝福されているかのような気分に浸れるのだ。 まあ、人間界のものが食べられるのならばそれにこしたことはないのだが。さて、今日の様子はと前方の集団を見やったその時だった。 「ああ、ソウジ!調度良かった!」 聞きなれたその声の方へ振り返るとそれもそのはず、先ほどまで授業を行っていた天界出身の教師ダグダエルその人であった。 温厚な性格とおっちょこちょいな愛嬌のある人柄から、“グダグダエル先生”の愛称で割と人気のある教師だ。さっきの綴りの間違いも頷ける。 そんな先生だと言っても一応は教師。生徒である俺が無下に拒むことなどできない。後方でポツンと様子を窺っていたのが仇になったと言える。こうなったら素直に諦めようじゃないか。 さて、一礼をして要件を聞くとしよう。 「何でしょう先生?」 頭を上げて問いかけると満面の笑みの教師ダグダエル。ああ、面倒なことを頼まれるのだとすぐに分かった。 しかしこのごり押しするかのような笑顔は見習いたいものである。まるで断れる気がしない。 「いやー、助かったよー!さっきの問題!間違いを指摘されてたらどうしようかと!綴りのミスに途中で気付いたんだけど言い出せなくて物凄く汗かいたよー!動揺しすぎて授業がぎこちなくなってしまったような……」 「いえ、あの……、どうも。では自分は食堂に向かうので……」 「ああ!ちょっと待って!そうだ、こんなことを話したいんじゃなかった!」 全くこの人は、“グダグダエル先生”と呼ばれる宿命の下に生まれてきたと言っても過言ではあるまい。 「実はここだけの話、クラスに新しい仲間が増えるんだよ!しかも2人も!何ていったかなー?いやー授業中言うように言われてたんだけど言うタイミングが掴めなくて今更になっちゃってさー」 「あの、話を先に進めてください」 「え?ああ、ごめんごめん。それでその二人に軽く学院内を案内してあげて欲しいんだよ。いやー急遽決まってねー。昼休み後から授業に参加することになってるみたいだから、よろしくね」 なるほどやっぱり面倒なことになってしまった。 しかし、そうすると俺の昼食は一体どうなってしまうのか。この人はそのことを全く考えてないような気がして怖い。 「ああ、そうそう。昼食は特別に好きなものを用意してあげよう!この教師だけに与えられた特別な食券を渡しておくよ!食券乱用しちゃあいけないよ」 「いきましょう」 天使だ。やはり天界の人々は素晴らしい。疑った俺が愚かであった。 この祝福を受けし食券があれば他にもう何もいらない。 なるほど、食堂のシステムはこのためにあったのか。 教師から善き生徒に授けられる至上の祝福。この食券に導かれるように皆勤勉で誠実で素直な生徒になっていくだろう。昼食の為に。 この学院の食堂のシステムは何も間違っていなかったのだ。 「さて、職員室で二人が待っているはずだから、ちょっと呼んでくるね。そうだな、とりあえず三人で食堂で昼食をとってからがいいんじゃないかな?いいなー学生は。青春だねこれは」 「あの、転校生も待ってると思うので、昼休みの時間も限られてますし……」 「ああ、そうだね!ごめんごめん!全く急かすんだからー。まあ気持ちはわかるけどねー。先生も昔あったなーそういうの」 そう言いながらダグダエル先生は職員室に入っていった。 転校生か。 一体どんな人なんだろうか。いや人じゃない可能性の方が高いことはわかっているのだが。 できることなら天界人であって欲しい。機界人でも構わない。少なくとも魔界人と霊界人は勘弁していただきたいものである。 いやちょっと待てよ。食券は一枚しか貰ってないのに三人で昼食とはどういうことだ。やっぱりグダグダエル先生じゃないか。 この時間だと残っているのは魔界食のみと考えていい。これは争いの火種になるのではないか。 いや、まだ会ってすらいない生徒のことを疑うのはやめよう。例え仮に魔界人だろうと霊界人だろうと真っ当な生徒もいることはいる。 その生徒本人と真摯に向き合うべきだ。きっと人間食を仲良く分かち合うこともできるはずだ。 それに片方が人間だったり天界人であったりしてくれれば心強い。 そんなことを考えていると職員室の戸が開き、ダグダエル先生が一人の生徒を連れて戻ってきた。 「いやー、ちょっと霊界の子が遅れてるみたいでね。とりあえず魔界出身のこの子と自己紹介でもどうかなと思って」 人間関係とは第一印象が重要らしいが、この時俺は考え事をするあまりとんでもない失敗を犯してしまう。 「うわぁ、最悪だ」 つい、思ったことが口に出てしまったのである。死にたい。 【タタリ 2013.11/18】 俺が漏らした不用意(うっかり)な本音に、ダグダエル先生が連れてきた女生徒の眉根が怒りに歪む。白金の髪から覗く鋭い視線が、俺の脳髄を一息に貫いた。 死んだかと思った。生きてる事が奇跡だと思った。それほどまでに、同年代離れした恐ろしい殺気であった。 「じゃあ、まずは自己紹介しようか。ソウジ、君からいってみよう」 うん、ちょっと待ってくれ。自業自得である事は認めるし謝りもするが、この空気をフォローする事もなく、丸っと無視して話を進めるアンタは間違いなく大物だよグダグダエル先生。 「あー、いや、すまない。さっきのは気にしないでくれ。ちょっと考え事してて、タイミングが悪かったんだ」 「知らねえよ」 何とか誤魔化そうとしたところ、ドスの利いたどぎついお言葉が返ってきた。うはは、怖い。魔界人スゴイ怖い。 「えっと、何だっけ。ああ、うん、俺は伏神ソウジ、人間(ヒューマン)だ。グ……ダグダエル先生からも聞いてると思うが、今日一日、学院の案内をする事になった。よろしく」 「……柳瀬川朝霞(やなせがわアサカ)、雪女」 「よろしく」なんて友好を表す気さくな挨拶は返って来なかったが、うん、本当に、本当にちょっと待ってくれ。ツッコミどころが多すぎて処理できん。 魔界人と一言に言っても種族は豊富だが、基本的に魔界と人間界は密接な関係にある。五界統合以前、神話や伝承に登場してくる空想上の生物は、大抵が魔界か天界の住人に相当する。 今でこそ大々的に五界が融合したものの、元々の世界は隣接したまま干渉する事はなかった。……と、どっかの偉い学者が言っていた。 だが、ごく稀に、偶発的に世界同士の門(ゲート)が開かれ、たまたまそこに居合わせた者が余所の世界に呑まれてしまうケースがある。この時、向こう側から来た存在こそが「魔物」だの「妖怪」だのとして、度々目撃されるのだ。逆にこちらから向こうに行ってしまえば「神隠し」の様な行方不明事件に発展する。 五界統合以後は、妖怪や天使は珍しくない。だから柳瀬川が雪女だとしても、特に驚く事ではないのだが、とりあえずツッコミたい事がある。 どうせ第一印象は悪いのだから、不躾承知で柳瀬川の容姿を眺める。 髪は雪の様に光を反射する眩い白金(プラチナ)。眉毛や睫毛まで同色である事から、それが地毛である事が窺える。 瞳は吹雪の夜を連想させる深い紫。長い白金の髪から覗く紫は、一本一本が光を乱反射し、七色の輝きに変化している。実に神秘的だ。 ここまではいい。雪女というからには雪の儚さを彷彿とさせるイメージが表層に色濃く出ているから、納得も出来よう。 肌は小麦色。夏休みに海の家でアルバイトしてたんですか? と思わず訊ねたくなるほど、健康的な茶褐色。雪の様に透き通る青白い肌などどこにもない。雪女の淡く儚げなイメージにヒビが入る。 着崩した制服。首元はそもそも指定のリボンをしておらず、ブラウスは第二ボタンまで開かれていて、スカートは膝上……というか股下十センチもないくらい気合いの入った超ミニ。雪女の貞淑なイメージが崩壊の兆しを見せる。 強気で尊大な態度。睨まれでもしようものなら即座に財布を差し出して土下座させてしまう程の凶悪な威圧感を、これでもかと発散させている。なんか黄金色のオーラが見えそうな錯覚さえ覚える。雪女の神秘的なイメージが完全に瓦解した。 総じて言うなら、お前の様な雪女がいるか! である。 「くっ、ギャップ萌え狙ったキャラ構成にしても、もうちょっと別の方向性があっただろ! 何でそんなにニッチな黒ギャル路線なんだ……!」 「何言ってんのか全く分かんねーけどテメェがあたしを馬鹿にしてんのだけァ理解したぞ!」 いかん、また本音が出てしまった。ボレロのポケットに手を入れたままの柳瀬川は、今にも掴みがからんばかりの怒気を帯びている。そんな殺伐とした目で見られたら、こっちがドキドキします。……ごめん、何も上手くなかった。 「おお。種族の事もあるし、気が合わなかったらどうしようかと思ってたけど、けっこう仲良さそうで安心したよ」 「「アンタの目は節穴か!?」」 「ほら、息もピッタリ。いやぁあまりに急な話だったから、誰に頼もうか迷ってたんだけど、ソウジが居てくれて助かったよ。それじゃ、アサカをよろしく頼むよソウジ。私はこれから霊界の子の様子を見てくるから、後は若い二人に任せてお先に失礼するよ」 言いたい事を言うだけ言って、一切のフォローもないまま、ダグダエル先生は去っていった。すげぇ、心底尊敬するよ僕らのグダグダエル先生! この程度の仲違いは喧嘩の内に入らないと思ってるとか、天界人はみんな聖人君子か!? 後に残された俺と柳瀬川は、職員室を出入りする教員に道を譲り、しばし呆然とする。昼休みは既に三分の一が浪費されていて、俺の胃袋事情も深刻な事態を招きかねない。 「……とりあえず、学食まで案内するよ」 「そうだな。ただ、テメェは半径三メートル以内に近付くな。砕くぞ」 うん、もうコレどうしようもないほど第一印象サイアクだわ。いや、どうせ昼休みが終わればお役御免なんだし、いいんだけどさ。 ◇ 遅れ馳せながら学食に到着した俺達は、ダグダエル先生に貰った一枚の食券を巡って大バトル……という事もなく、譲ってもらった券で天界食にありつける事に成功した。一汁一菜一膳の素朴な味(※表現をオブラートに包んでる)を堪能しながら、同席した柳瀬川を見る。 「こっち見てんじゃねぇよ。黙って下向いて食え」 ……無茶言うな。お前の昼食を見せ付けられるこっちの身にもなれ。 薄い木板を瓢箪状に切り抜いた簡素なスプーンを使って乳白色の固体に差し込み、すくって口に運ぶ度にやや口元が綻んでいる。サクサクと音がするのは、半結晶体の氷を噛み締めているからだ。 「……その、アイスクリームが昼飯なのか?」 「悪いかよ」 腹に溜まらなそうだ。女子はそんなんで午後の授業を乗り切れるのか。というかお前、あれか。朝食がてらにケーキを食べちゃう系の甘党(スイーツ)な現代っ子か。 先んじて食べ終えたカップアイスの蓋を閉じ、熱々のスープと格闘している俺を眺めてくる柳瀬川。俺の貴重な食料(カロリー)だ、絶対やらんぞ。 「いらねーよ。あたしからすりゃ、よくそんな熱い物食えるな、お前ら」 「猫舌なのか?」 「いや、熱いの全般嫌いだ。ってのに、この世界は春だの夏だのがありやがる。種族区整備が終わるまで、あたしはこの街に住まなきゃいけねぇとか、ほんと最悪だよ」 ──五界統合からそれなりに時間は経ったが、何せ総人口五倍の大惨事である。全国的には環境問題含めて未だに住み分けがハッキリしておらず、人間界でも生存に適した土地の整備が済むまで、本人達には悪辣な環境で過ごさなければならない場合もあるらしい。彼女もその内の「移住手続きが遅れてる」種族の一人なのだろう。 あ、なるほど。だからアイスクリームなのか。日焼けした肌も、そういう事なのだろう。 そう思うと、彼女がカリカリしているのも納得が行く。何の前触れもなく自分の住処を失い、肌に合わない土地で生活する事を余儀なくされているのだ。そりゃ不機嫌にもなるだろう。俺だったら辺り構わず理不尽に当たり散らしているだろう。 「おい、いつまで食ってんだ。さっさと院内案内して即座にあたしの視界から失せろ」 ……いや、全然違うわ。これ単に俺が嫌われてるだけだ。 【どあにん 2013.11/21】 今日はケチが付きっぱなしだ。 ダグダエル先生に捕まって案内役を押し付けられ、そして黒ギャル雪女と狭すぎる層にしか人気が無さそうなのを院内案内させられた挙句 育ち盛り食い盛りの男には非常に貧相な天界食を食う事を強いられて。 ダグダエル先生に出会う事さえ無かったのならば、今頃は人間界の食事を大盛りにして我儘ストマックを満足させる事が出来たであろうに。 そして件の雪女は明らかにイライラしている、人差し指は柔らかそうな二の腕を何度も叩いてリズミカルに怒りを表現している。 「おい」 不意に誰かに声を掛けられるが、ぶっきらぼうな声の掛け方にちょっとムッとしたので聞こえないフリを決め込んだが、これが俺の二度目の失敗だ。 一瞬何か呪文が詠唱されたと思い込んだ瞬間、口に含んでいた(精一杯譲歩して)スパゲティが意志を得たかのように動き始め、突如俺の鼻から侵入を始めた。 しかもこの魔法最悪だ、鼻から口へ出てまた鼻に入っていく、無限ループ超怖ぇ。 「いけすかねぇ天界野郎から聞いた、お前が院内案内してくれんだってな?」 ようやくスパゲティから開放された俺が咳き込みながら後ろを振り向く。 指定の制服を着崩してその上から魔法使いのバアさんが着るような真っ黒なローブを羽織っている男子生徒が一人。 その瞳はドブみてぇな濁った緑色をしていて、氷のように冷たそうな印象を抱く、 冷たいと言えば、あの雪女はさっきのスパゲティ無限ループがウケたのかまだ腹を抱えて笑ってる、泣きてぇ。 「俺は人間の伏神ソウジだ、ダグダエル先生から聞いてるかも知れないが学院内を案内する、よろしくな」 「俺も人間のルシフェリオ=ダミアン=グラストフ……前の黒魔術学校から転入させられた」 俺の脳みそがフル回転して数日前のニュースを思い出す、そうだ……名前はハッキリ思い出せないけど、 霊界にあったどっかの魔法学院の校長が逮捕されたのを雑誌の特集で読んだ、未成年に本格的な黒魔術を教える為に 悪魔崇拝の強制やグロい授業やスポーツを行っていたのを魔法省から咎められ、数回の改善要求にも答えなかった為校長が逮捕、学校は廃校になったと。 その中で精神ダメージが比較的軽い生徒は別の学校に転入させられたと聞いて居た、ダミアンもその口だろうか。 「最初に言っておく、俺の目的は復讐だけだ……仲良しこよしする気は更々無い、さっさと案内しろ」 うん、この雪女が増えたようなもんだ、俺は諦めて残りの食事を胃袋の中へ放り込んだ。 ◇ 学院は非常に広い、一つ一つの教室を案内してたら全部案内し終えるまでに3日は掛かるくらいだ。 だから俺は要所さえ抑えておけばいいやと、良く利用する教室は詳しく、あまり利用されない教室はほぼ口頭のみで案内していく。 しかし空気が重たい、暴力雪女と多分厨二病男に挟まれるなんて85年前後の人生で一度あるか無いかの頻度だと思われる。 なんとか場を和ませられない物か、そう考えてた時に例の厨二病が口を開いた。 「おい、ソウジとか言ったか」 「あーはい、なんでございましょうか」 あのダミアンが初めて口を開いたのだ。 なんだ、仲良しこよしする気は無いとか抜かしといて、やっぱお友達が欲しいんじゃ無いのか? やっぱり厨二病だなコイツ、俺の中でのイメージは固まった、ダミアン=厨二病な。 そんなダミアン君の視線の先には図書館、これから案内しようとしている場所だった、あれコイツ案外ガリ勉系か。 「この図書館は魔術書の貸出はやってるのか?」 「あぁ、易しいレベルのならな……難しいレベルのだと進級するまでお預け喰らうし、中にはここら一体を完全に吹っ飛ばすレベルのもあるって噂だ」 ふぅん、と濁った緑色の瞳で図書館のプレートを眺めているのを見て、あぁコイツ絶対なんかやらかすなと俺の頭の中でその未来が容易に思い浮かんで行く。 ダミアンに釣られるように朝霞も口を開く、なんとなくロクでも無さそうな事になりそうだが。 「じゃあ此処ら一体に雪降らすような魔術が載ってる本もあるのか?」 「探せばあると思うな、確証は無いが」 気が合うなと言わんばかりにダミアンと朝霞が深く頷きあう、なんだろう俺の疎外感。 【西口 2013.12/12】 校内を案内するだけなのに、なんでこんなに疲れなくちゃいけないのか。説明を求めたい。 今日は特に日が照っているためか、図書室を通過して以降、柳瀬川の機嫌がすこぶる悪い。 背後から突き刺さってくる敵意とか苛立ちとかが、具体的な形状をとって背中を刺してきそうなほど濃密に感じ取れた。 しかし、それを気遣ったのがいけなかった。 とりあえず、何か話せば気が紛れるだろうかと思い、ここまでで何か質問はないかと問いかけると 彼女はそれはそれは恐ろしい形相でこちらを睨み、「ねえよ」とはき捨てるように呟いた。 危なかった。四時限目の前にトイレに行ってなかったら確実に粗相をしていたところだ。 やっぱり魔界人って怖い。改めてそう思った。 雪女のなせる業か。パーティ内に、というか主に俺の背筋に、物凄く冷たい風が吹き抜けた。 冷や汗がツゥ、と首筋を滑り落ち、リノリウムの床に落ちる寸前に、「一つだけ聞かせろ」とダミアンが応えた。 こいつ、救世主か……!? と思ったのもつかの間。 「どの人種ならいなくなってもバレにくい?」 「おまえは なにを いっているんだ」 いや、こんなにいるんなら一人や二人や八人くらいなら生贄ってもバレないだろう? などとさも当然のようにのたまう厨二病を諌めるのには中々骨が折れた。 途中でほぼ無意識的に柳瀬川の同意を得ようとしてしまい、文字通り肝を冷やしたりと色々あった。 ふざけやがってグダグダエル先生め。 あんたの授業だけ狙い打ったように居眠りしてやろうか! 俺が恐るべき不良的な怒りを胸に滾らせるのと、彼らが俺たちの一団を発見し、声をかけてくるのはほぼ同時だった。 「うーっす。何してんだお兄ちゃん」 いい加減堪忍袋の緒が切れそうな柳瀬川を何とか宥める為、中庭の木陰に固まっていた俺たちに 半機人の少女一人を連れた少年が、親しげに歩み寄ってきた。 青白い不健康な肌に、薄汚れて痛んだ金髪。 黒目がちの大きめな瞳と、未だあどけなさが残るその顔には見覚えがあった。 「ルカか。お前こそどうしたんだよ、中庭嫌いだったろ?」 「委員長命令。苦手なら慣れろ、って巡回ルートに無理やり捻じ込まれた」 あの人は相も変わらずか……! 「しかし、驚いたな。まさかお兄ちゃんに、昼休みに外で話すほど仲の良い友達がいるなんて」 「その友達ってのがあたしの事なら、てめえをブン殴る理由になるな」 「どんだけ嫌なんだよ……」 人を殺せそうなほどの怒りが込められた柳瀬川の視線を真正面から受けて、少年――ルカの体が一瞬だけ、ビクンと跳ねた。 その表情には如何ほどの変化もないが、内心怯えているのが手に取るように分かる。 長い付き合いのなせる業、とでも言うべきだろうか。 「えーと……。失礼な事を口走ってしまい申し訳ありませんでした、先輩」 「……いや、別にいい。少し苛ついてるだけだ。キレてるわけじゃねえよ」 「それは行けませんね、ミス」 そこで、押し黙っていた見覚えのない半機人の少女が口を挟んだ。 その陽光を吸収してしっとりと濡れたように光る髪は 柳瀬川の宝石めいたそれとは正反対に、黒曜石の様な暗い輝きを宿している。 少々不自然なまでに白いとはいえ、その細面は、半分は人間である事を思い出させる程に自然な作りをしているが 制服の袖口や、スカートから伸びる素肌には、生体部分が一切ない。 金属の持つ独特の威圧感が、その部位の硬質さを如実に表していた。 「お兄ちゃん。機人にも羞恥心ってもんがあるんだぜ?」 「ブタ野郎」 「流石の俺も引くわ」 「セクシャル・ハラスメントはお止めください。正式に抗議いたします」 悪くなっていた空気が、俺をバッシングする事で修復の兆しを見せている……!? というかブタ野郎ってなんだ柳瀬川。お前単に俺の事罵倒したいだけじゃないのか。 「まあエロスはともかく。そちらのレディ、雪女に属する方とお見受けいたしますが」 「……だったらなんだよ」 「この気候ではさぞお辛いでしょう、よろしければ、一時的に極低温帯をお作りいたしましょうか?」 「え、マジ?」 柳瀬川の表情が、俄に明るさを帯びた。 その声音も上ずっており、今までの極低音ではなく、年頃の少女のソレであった。 これにはダミアンも驚いたらしく、視界の隅で一瞬だけ眉根を吊り上げていた。 是非にと頼む柳瀬川を見て取ると、少女は俺たちに自分から離れるように言った。 10メートル程度の距離を開ける俺とダミアンを尻目に、ルカは全速で中庭の端っこまで駆けていた。 その背を目で追って、頭上に疑問符を浮かべる俺を気にする事もなく、少女の魔術が「起動」する。 「内蔵術式展開。詠唱短縮。範囲・識別省略。補助節、その他もろもろ省略。『紅蓮庭園』起動します」 色々と不穏な単語が聞こえてきたときにはすでに遅かった。 少女と、その傍らで座り込む柳瀬川を中心に、凍気の波ともいうべき物が、唸りを上げて拡散した。 ――結論から言うと、用務員さんが丹精込めて育て上げた、中庭の木々や花は全滅した。 ダミアンの盾にされて冷気をもろに引っ被った俺が、薄れ行く景色の中で最後に見たものは 片目を閉じて舌をぺろりと出し、頭をこつんと小突きながら、酷く抑揚のない声で「てへっ」と呟く機人の少女の姿であった。 もし今日が厄日じゃなかったら、自殺しよう。 そう固く心に誓っった瞬間、俺の視界はブラックアウトした。 【Kの人 2013.12/12】 暖かく、其れでいて柔らかな感触に包まれている。 それらを一言で呼称するならば布団と言う一言に集約され、学院内に置いて布団の使用が許可される場所は数少ない。 ぱっと思いついた幾つかの選択肢から最もありえそうな場所を考え、その考えに思い付くと同時に身体を跳ね起こす。 傍から見れば悪夢から醒めた直後とでも思えるような速度で上体を起こし、周囲を窺う。 清潔そうな白が目立つ一室は、天井から下がる幾つかのカーテンによって区切られている。何故か此方が身体を横たえていた区画にはカーテンがされていなかったが、別段その程度でとやかく言うのは馬鹿らしい。 鼻腔を僅かに刺激する消毒液の臭い、此処から窺える棚には諸々の薬品に機界人にでも使うらしい潤滑油が納められており、それらだけで此処が何処かを察するのは容易かった。 ――保健室。 其処は本来ならば怪我や病気を抱えた生徒に処置を施し、一時的に療養させる目的……つまり安らげる方の聖域ではあるが、五界統合学院においてはそうはいかない。 比較的巨大な学院内には幾つか保健室が存在する。理由は二つあり、一つは末端の方で生じた怪我に対する反応が遅れてしまう為。二つ目は比較的身体の構造が似通っている人間界、天界、魔界に住まう種族なら処置の方向性の目処は立つが、どちらかと言うとメカニックの分野である機界人、そもそもよく分からない霊界人等は、その筋の専門家でなければ治療は困難である為だ。 その為前述の通り幾つか存在しているのだが、場所によっては安らげる聖域ではあるが、そうでない保健室も存在している。 音を立てないように寝台から身体を下ろし、カーテンの外に顔だけ出して周囲を窺う。 そして、比較的マシな方の保健室であることを確認し、安堵の溜息を吐く。 第三保健室……通称夢魔の巣。治療術に長ける天界人養護教諭の治める第一保健室と比較すると程度は下がるが、機界人養護教諭の治める第二保健室よりかはマシに過ぎる。第二保健室は、本気で身体改造されかねないからだ。 だからといって第三保健室がまとも、という訳ではない。その通称が物語る通り、此処はある意味では危険地帯である。 第三保健室は魔界出身、種族夢魔の養護教諭が治めている。保健室で夢魔と言えば淫猥な想像を掻き立てられるだろうが、ある意味その通りと言える。 拳を数度開閉し身体の感度を確認。……良好、既に身体は復調している。 ならば何時までも危険地帯にいるのは馬鹿らしい。生肉を吊るしたまま猛獣の檻に留まる程度に、馬鹿らしいのだ。 周囲を確認した限りどうやら今は席を外しているらしい。無言で去るのは不躾だと思われるだろうし、心配されるであろうから、胸ポケットかメモ帳を取り出し、その一頁を破り取ってメモを残す。別段凝った物である必要は無く、ただ淡々と”回復したので戻ります 伏神”とだけ書き残して保健室を後にする。 保健室を出て直後、天井に吊るされた時計を確認する。時計は既に午後三時前を指しており、どう足掻いても六時限目の授業には間に合いそうにはない。そもそも、六時限目の終了時刻が午後三時丁度であるからだ。恐らく、教室に辿り着く頃には終礼を終えて帰りのHRの準備が始まりつつあるだろう。 流石に帰りのHRに遅れる事だけは勘弁願いたい。ただでさえグダグダエルなのだ、きちんと当人から口頭で説明を受けていないと、生徒から又聞きすれば確実に事実と異なる回答が返ってくる。当人から受けても事実とずれるが、其処は触れてはいけないのだろう。 ”廊下は歩くこと、飛ばないこと”という風紀委員会が製作したらしい張り紙を尻目にやや駆け足気味に教室への道を行く。第三保健室は、自身の所属する教室からは程々に離れているからだ。 丁度経路の中頃に差し掛かった頃にチャイムが鳴り響く。多くの生徒が授業から開放された開放感に包まれているだろう、何処からともなく、やっと終わったーという声が聞こえてきた。 廊下を曲がり、その先の階段を駆け上る。三階に到達したら其処で一旦曲がり、再び廊下を駆け足気味で行く。 出来れば全力で走って行きたい所では在るが、チョーカーが存在している以上それは難しい。 同時翻訳機構付き生徒証明機構は生徒の動向を逐一確認している。其れはつまり、規定以上の速度で移動した場合すぐさま風紀委員の厄介になるという事だ。実に煩わしい。 なお非常時、例えば災害時などはその制限が解除されるという。そして食堂へ向かう際は、基本的に全ての生徒は全力を持って移動するが風紀委員は動かない。そもそも風紀委員自体が走っていることを考慮すれば、この学院においては食事の為の移動と、災害が同じ扱いになるらしい。 漸く気がついた実に馬鹿馬鹿しい事実に半ば失笑を浮かべ、一定の速度を保つことに集中していた為、反応が致命的に遅れる。 ――今まさに曲がり角を曲がってくる人影…… あっという声を漏らす事も無い。その存在に気づいた頃には彼我の距離は僅かにしか存在せず、回避の為に速度を上げれば風紀委員に咎められる。かといって立ち止まるには速度が出過ぎている。 必然的に人影と衝突し、突き飛ばされ……ることはなく擦りぬける。 「あ、ごめんねー? ちょーっと急いでるのー」 間の抜けるような可愛らしい声に振り返ってみれば、其れは霊界人らしい少女であった。少女、と言っても着ている服や物理干渉して手に提げている籠に入れられたノートや書類を見る限り、彼女は教師であるらしい。 ごめんなさいという謝罪の言葉も紡ぐ暇を与えずにその教師は付近の教室へ入っていく。案の定籠だけ引っかかって、盛大に転倒していた。 ……其れを眺め続けられるほど暇ではない。 再び駆け出し、教室へと戻った頃にはHRが始まっていた。HRは始まった直後であり、ならば良いと思う人もいるかもしれないが所謂グダグダエルなのだ、話の順序が訳が分からない為始めから聞いていないと意味が通じなくなる事も多々ある。 そうして、案の定今日のHRはまったく持って意味が分からなかった。救いを求めて周囲に視線を向けてみても、原因を作ったと言っても過言ではない面々は盛大なスルーを決め込んでいた。 【クロ 2013.12/15】 結局のところ、俺は今夕陽の射す教室内で一人、課題を黙々と処理している。 HRの件を詳しく尋ねるつもりでダグダエル先生に声を掛けたのだが、どうやら事務手続きに不備があったようで、転校生二人を連れ職員室に行ってしまったのだ。 そうであれば他の生徒に聞いてみるつもりではあったのだが、教室で待っていて欲しいと強く頼まれたため、こうして時間を有効活用させてもらっているのである。 静かだ。今日を台無しにしてくれた騒がしい出来事など、まるで嘘だったかのように穏やかで、課題も思いの外はかどった。 ダグダエル先生が戻ってきたのは、それから1時間程した頃。課題はとうに終わっていたので、夕飯の献立などを考えていたそのときだった。 「いやー、なんかごめんねー……色々と」 そう言うダグダエル先生の笑みは引きつっていてる。何か嫌な予感がしたが、流石のグダグダエル先生ももうこれ以上は何事も起こせまい。予感などゴミ箱に投げ捨てようではないか。 「そうそうHRの話だったね。えーと、そうだ!校舎に遅くまでいるのもあれだからソウジの部屋で話そう!うん、それがいい!」 結局のところ、俺は今陽の沈みかかった空の下二人、ダグダエル先生と歩いている。 怪訝に思うところしかないのだが、この人の場合は考えることをやめた方が精神衛生上良さそうなので、俺は黙って従うことにしたのだ。 おそらく面倒なことが起こるであろうことは間違いないのだが、今日という日の疲れからか、色々どうでもよくなったのである。 もうすぐだ。もしかしたら今日のことは夢で、寝て覚めたら、騒がしくも平穏なあの日々のままだったりするのかもしれない。そう思うと、少しだけ気分が軽くなった。 「うわーなんだこりゃー」 見慣れたドアを開け、部屋に入るとそこには半分に割られた鉄の筒がそこら中に張り巡らされていた。 そして無表情な鉄仮面が自慢げに屹立しているではないか。もう帰りたい。帰ってるんだけど。 「帰ってきたか伏神聡治よ。さあ、転校生歓迎流しそうめん大会を始めようではないか」 クラスメイト、剛機ホオノキ・ダン十二式はHRが終わるなりこんなところでこんなことをしていたらしい。全くふざけた機界人だ。他人の部屋を無断で改造しやがって。 2m半はくだらないその巨体で、よくもまあ六畳一間のこの部屋をこうまで飾りつけたもんだ。あの表情のとりようもない鉄の顔面が無性に腹立たしい。生意気に角なんて生やしやがって。 「いやー、剛機ホオノキ・ダン十二式お疲れ様ー。本当に凄いよー。こんな短時間でこれほどのものが作れるなんて!先生感動しちゃったよー!」 もう嫌だこの人。俺に恨みでもあるのかと。俺を引き止めていたのはこのための時間稼ぎか。 しかし転校生歓迎流しそうめん大会というが、肝心の転校生が見当たらない。そもそもなんで流しそうめんなんだ。 「あのー、それでちょっと言いにくいんだけどね。ダミアンは復習で忙しいらしくてさー、アサカにいたってはにらまれて何も言えなかったんだよね……せっかくアサカの好きそうな冷たい流しそうめんにしたのに……ははは先生困っちゃったよ」 「ならば仕方ありますまい。流しそうめんを始めようではありませんか」 「だ、だよねー!さ、ソウジも早く上がって!」 結局のところ、俺は今鉄の筒が張り巡らされた自室で三人、ダグダエル先生と剛機ホオノキ・ダン十二式とで流しそうめんをしている。 食べながらに話を聞いたのだが、剛機ホオノキ・ダン十二式が人間界に興味があったらしく、提案した複数の人間界食の中からダグダエル先生が流しそうめんを選んだらしい。俺が保健室で休んでいる合間にクラスでそんなやり取りがあったようだ。酷い連中だ。 そもそも転校生が主役であるべき歓迎会に彼らを呼べぬどころか、俺へのサプライズを盛り込むとはどういう了見なのであろうか。流石グダグダエル先生である。 しかしだ。こんなことまでして、ここまで来てくれた二人を、妙に憎めないのは疲れているせいだろうか。冷たい流しそうめんと鉄の筒が、不思議と暖かく思えた。 「安心せよ我が友、伏神聡治。この流しそうめん装置は折りたたみ収納が可能だ。錆対策も万全だから何度でも使えるぞ」 黙っている俺を心配したのか、剛機ホオノキ・ダン十二式は声を掛けてきた。いつから友達になったのだろう。機界には、名を重んじ、常にフルネームで呼び合う風習があるらしく、非常に面倒だったので今まではそれほど接してこなかったのだが、思ったよりは悪くないものだ。ただちょくちょく改名する文化も有しているので面倒なのは面倒なのだが。 剛機ホオノキ・ダン十二式は話を続ける。 「人間界は訳の解らないところが実に興味深い。何故摂取物を流すのか。書物には清涼感を得る為との記載があったのだがどうにも解らぬ」 俺はそうめんを器用に掬いながら答える。流れる水がベランダへ排出されていく音も聞こえた。 「その記載のまんまだよ。水が流れてると涼しい気がしてくるだろ?夏の風物詩ってやつでもある。季節感を楽しみたいのさ」 「直接涼しくした方が賢明なのではなかろうか?涼しい気がするよりも涼しい方がよかろう」 「多分、それで満足なんじゃないか?気分の生き物なのかもしれないな。ひょっとしたら涼しいことより、涼しい気分のほうが心地よいのかもしれない。今ふと思ったんだけどさ」 「理解し難いが、現実的な状況の改善よりも精神的な誤魔化しを好むということか」 「変なことを言ってしまったようだ。イベントだよイベント。仲間と楽しむための催し物だ。それが主な目的。夏なら涼しい気分を味わいたいから水で流す。こいつはオマケだ」 「それならば涼しい部屋でそうめん大会をした方がよかろう」 「…………そうだな。今度は直接涼しくなるように改造して欲しいよ。どうせ改造されるならな」 面倒になった俺がそう話に決着をつけると、それを待っていたのかのようにダグダエル先生の間の抜けた声が響いた。 「わかるなーそういうの。物理的な欲求よりも精神的な充足を重んじるってやつ?天界だと美徳だよー。これって何か異世界交流って感じがするね。今までそんな風に考えてなかったことが異世界の人にはそう捉えられるんだーって。先生も色々考えさせられちゃうなー。っていうかこれ、いつまで先生が流し続けるのかな?そろそろ先生も食べたいなーって。そもそも剛機ホオノキ・ダン十二式は食べないのに何でそこに座ってるのかな?そろそろ交代して欲しいんだけど……」 俺はダグダエル先生より大きい声を響かせる。 「駄目です。先生には転校生歓迎流しそうめん大会をグダグダにした責任を取ってもらいます」 「そんなあああああああああああぁぁぁ…………」 結局のところ、こういう日も、悪くないかもしれない。 【タタリ 2013.12/16】 「あれ、飲み物が足りないね」 そう呟いたのは誰だったのか、とりあえず事の発端はそいつが原因であった事に違いない。 六畳一間の狭い寮室で騒いでいたところ、左右の部屋から苦情が来て、撤収しようとしたのが一時間と半ほど前。騒ぎの中心が流しそうめんである事を知った寮生らが参加しようとしたのがその直後。流石に一部屋に何人も入ってられないので、いっそそうめんレーンを廊下に設置しようと剛機ホオノキ・ダン十二式が提案したのが十分後、設置完了に更に十分。 それからというもの、スーパーまで飲み物や追加のそうめんを買い出しに出掛けてる間にあれよあれよと参加人数が増えていく恐怖は忘れられない。気付けば俺の部屋がある階層の寮生全員が参加していたのだからもう勘弁してほしい。というかうちが角部屋だからって、流水を浴室に流すなポンコツ。水道代って出すだけじゃなく捨てるのも金かかるんだぞ。 その場の雰囲気に負けて流しそうめんを楽しんでいたところ、冒頭の声が上がったのだ。流しそうめん参加総勢でのじゃんけんの結果、この熱帯夜の中、飲み物の買い出しは俺と剛機ホオノキ・ダン十二式に決まった。会場提供者と現場監督をパシらせるってどんなイベントだ。 そんな訳で、俺達は現在、大量の飲料とお菓子を持って歩いていた。重たい荷物のほとんどは剛機ホオノキ・ダン十二式が持ってくれているのが救いだが、ぶっちゃけこの暑さの中を歩く事自体が罰ゲームである。 「いや、実に愉快な催しである。転校生らも参加なされば良かったのに」 「ダグダエル先生には悪いが、断固として御免蒙る。あいつらが俺の部屋に来るとか絶対に穴が空く」 どこが、とは言わないでおこう。むしろ俺の胃だけで済めば御の字である。 夕方に始まった流しそうめん大会はいつしか宵闇を迎え、現在は完全に暗闇と化している。機界の技術によって街灯設備は充実しているので完全な闇という訳でもなく、等間隔に光と闇が交差する空間が広がっている。 かつては広かった空も、現在では数倍に増えた人口を収容する為の集団住居が所狭しと乱立して圧迫している。地上の光が空を喰らい尽くし、一等星の瞬きすら霞んで見えない。 辺りを見渡すと、かつてなら人外魔境と形容するに吝かではない多種族の姿が窺える。人種の問題ではなく、剛機ホオノキ・ダン十二式を含めて彼らはそもそも存在が違う。 「なぁ、剛機ホオノキ・ダン十二式。五界が統合される前の機界ってどんな所だったんだ?」 「なんだ伏神ソウジ、藪から棒に。その様な知識は授業で習っておろう」 「知識だけはな。ちょっとした興味本位だから、答えなくてもいいけど」 「いや、他ならぬ親友の質問だ。こちらも万全に応えねばなるまい」 相変わらずの堅苦しい口調で、剛機ホオノキ・ダン十二式は語る。視界を確保する為の頭部センサーがチュインチュインと音を立てながら明滅したり、ピントを合わせている。何それ機界人特有の感情表現なの? それともレーザー光線でも発射するの? 「統合前の機界には私達の様な自由意思を持つ機融人はいなかった。生物がエネルギーを摂取しながら繁殖を繰り返す様に、資源を発掘して工場を築き、より環境に適合する個体を製造していたのだ」 「生存本能に特化した人工知能でもいたのか?」 「いや、そうではない。そもそもかつての機界人は人工知能など持たず、原初の存在が何であるかの記録が残っていない。矛盾した言い方になるが、我々は生まれる前から次世代機を製造する為に生まれたのだ。意志や本能などを持つ事もなくな」 「生物としては破綻もいいとこだ。生存する目的がないのに生存していたって事になるだろ、それ」 「であるな。矛盾によって生まれた機界人は、矛盾を正さぬまま、矛盾した行為の効率性を求めていた。五界統合した今でこそ人と交わる為の技術が確立し、『機械と融合した生物』として自由意思を持つに至った」 全身のうち殆どが機械である剛機ホオノキ・ダン十二式でも、人としての肉が内蔵されている。無機物に人の因子を移植し、成長する機械として生を受けた機界人は、相手がどんな人格者であろうとも人間を肯定する。 それは、機界が独立していた頃から行い続けた「繁殖の矛盾」が正常であると証明する為なのだろうか。 「機界人って──」 俺達と何も変わらない、天界人や魔界人と同じく風変わりな生き物である。 そんな事を呟こうとした瞬間、 世界が赤く炎上し、辺り一帯にマグマが溢れた。 「──はあっ!?」 隣を歩いていた剛機ホオノキ・ダン十二式が熱でドロドロに溶けていく。内部の肉は一瞬で焼けただれ炭になり、瞬く間に灰に還っていく。 集合住宅も同じだ。先程まで辺りに漂っていた夕餉の香りはタンパク質と無機物が高温で溶けたいやな臭いが充満している。吐き気がする。 赤い、赤い、赤い視界の中で、ただ俺一人だけが正常であった。 「な、な、な?」 「あ、いたいた。お兄さん、ようやく見つけた。いやぁ人の身体って不便だねぇ。探すのも一手間だったよ」 悪夢の様な絶望を引き裂く様な、陽気な少年の声が響く。誰も彼も、何もかもが燃え盛る地獄の中、救いを求めようと俺はそちらを振り返り、 振り向いた事を後悔した。 僅か三メートルほど先に、少年(ドラゴン)がいた。いや、それは本当に少年(ドラゴン)であった。人の知覚限界を容易く凌駕する程の膨大な情報量が、俺の脳を噛み砕く。 赤、赤、赤、赤。赤。赤。赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤。 容姿の整った耽美な少年(ドラゴン)は、見た目は少年であるにも関わらず、脳が巨大な龍であると無理やり認識してしまう。 「あらら、ごめんね、お兄さん。これでもかなり制限してるつもりだったんだけど、やっぱり人の容量じゃ限度があるか」 「ひっ!?」 我ながら情けない悲鳴が喉から漏れた。炎の様に赤い少年は口笛混じりに軽快なステップで俺の目の前までやってきて、こちらを見上げてくる。紅蓮の双眸に魅入られてしまえば、人間の脆弱な身体など一瞬で消し炭になってしまいそうだ。 「んー。やっぱり思った通りだ。お兄さん、いい目をしてるね! 諦観とか悲哀とか、そんな言葉じゃ言い表せない、世界を歪つに捉えてる目だ。お兄さんは、いつ死んでもいい人間なんだね! 素敵!」 「はっ? ひ、や、何、が?」 「うんうん。なるほど。白龍(ヴェイパー)が気に入る筈だ。あいつが契約してなかったら、ボクが代わってあげても良かったかなぁ」 ヴェイパー? 何だ、それは? 人の名前か? 全く理解不能な事をつらつらと語る少年を改めて見下ろす。暴力の様な鮮烈なイメージでこちらを蹂躙し尽くしているものの、少なくとも彼の声音に敵意は感じない事が、多少なりと俺を冷静にさせてくれた様だ。 身長は一三〇センチほどだろうか。上半身は裸で、その上に毛皮のロングコートを着込んでいる。コートの裾は彼の背丈を一切考慮しておらず、地面を擦っている。その端々から火柱が立ち上り、アスファルトをぐつぐつと煮立たせていた。 五界統合以後、色んな種族を見てきたが、彼ほど常識から外れた存在は知らない。人間とほぼ同じ格好でありながら、彼が振りまく情報は全てが桁外れだ。突然現れて、世界を焦土にしてしまう存在なんて聞いた事もない。 「あ、そうそう。ボクは赤龍(アドライグ)。君が契約した白龍とは……何て言えばいいかな? 兄妹? いとこ? 同一体? まぁ、何かそんな感じ」 「ワケが分からない」 「むぅ、そこはニュアンスで感じ取ってよ。おかしいな、人間はそういう曖昧な空気をフィーリングで感じ取る生物だって思ってたのだけど」 無茶言うな。馬鹿言うな。こちとら一切たりとも現状を把握出来てない混乱の極みなんだ。理解を求めるというのならこちらも善処するので、まずは分かりやすく説明を要求する。 「そんなの知らないよ、お兄さんの都合でしょ? ボクには関係ないもーん」 ぶっ飛ばすぞクソガキ。 「あ、ムカチーン! もう、せっかくこのボクが人間如きに興味を持ってあげたのに、その言い草ったら! でも、目の前に理解の範疇を超えた脅威がいるにも関わらず、そんな反応できる人はそうそういないよ。そんな所も素敵だよお兄さん! いいなぁ、ボクもお兄さんが欲しいなぁ」 アドライグと名乗った赤い少年は、俺の周りをクルクル回りながら腹を立てている。少年の華奢な足が地面を跳ねる度、そこからマグマが噴き荒れる。翻るコートの裾から火炎放射。剛機ホオノキ・ダン十二式、消し炭も残らない。集合住宅、土台が溶けて遂に崩壊する。アスファルト、渦巻く溶岩に早変わり。 何これ。夢なら覚めて。マジで。今すぐ。なう。 「夢、で合ってるかな? 白龍の一部がお兄さんの身体を根本から構成しているので、普通なら認識できないボクと同一空間にいられるのです。それでも所詮は人間だからね。他の全機能を停止して、高次空間の処理を全力で行ってるから、ボクとの会話は一瞬での事でしかないもの」 「なるほど、やっぱり分からん。お前バカだろ。人に説明するの苦手だろ」 「いやはや、事ここに来て、まだそんな口を利けるのか。凄いやお兄さん、定命の存在の割に死を恐れないなんて。でもそれ、ボクだから笑って許してあげれるけど、黒龍(ファブニル)とかだったら魂すら残れないよ。気を付けてね」 「え、何? お前、同じ様な奴いっぱいいるの?」 「無数に点在する世界の数だけいるよ。ドラゴンってのもお兄さんが抱いたイメージでしかないから、人によっては天を貫く巨人とか、タコのお化けに見えるかもだけど。でも、この世界に降りて来れるのはボクらだけだ」 手のひらでパーを表現するアドライグ。……あ、いや、これパーじゃなくて五か。五人……人? いるって事か。こんな天災みたいなのが? 神様勘弁してくれ。 というか、何かこの状況に慣れてきた自分が怖い。こんなのが目の前に現れて、もう世界の終わりが近いと思えば開き直りもする。 「うんうん。ボクもお兄さんの事気に入っちゃったし、お兄さんがピンチの時には一回だけ、ボクが颯爽と駆けつけて助けてあげるって約束しよう。ふははは、喜べ人間よー!」 「いらん。助けがどうとか言うならこの状況から助けてくれ」 「そうだね。白龍の補助処理があるとは言え、これ以上ボクといたらお兄さん本当に精神死しそうだし。それはそれで可愛いだろうから、廃人になった暁にはボクが愛でてあげようか?」 「死ね、クソガキ」 「うふふ。そんなお兄さんも素敵だろうねぇ」 俺を中心に周回していたアドライグが背後で停まり、おぞましい視線で俺を眺める。背筋が焼け付く様な恐怖に振り返ると、そこには誰もいなかった。 「またね、お兄さん。白龍によろしく言っといて」 どこからかそんな声が聞こえた気がしたが、その時には既に周りの景色は正常に戻っていた。 剛機ホオノキ・ダン十二式や集合住宅、地面は全て元通り。燃え盛る炎や、噴きだした溶岩などどこにもない。ただ俺の視界がチカチカと赤く映る事以外、先程と何も変わらない。 「どうした、伏神ソウジ? 機界人って──なんだ?」 「あ、いや」 夢でも見ていたのか? 白昼夢? いや今、夜だけど。 さっきまで、何か恐ろしい目に遭っていた気がしたのに、何事もない世界に安堵している自分がいる。 「……忘れた」 そもそも俺、さっき、どんな夢見てたっけ? 【Kの人 2014.01/09】 結局、歓迎される存在を欠いた転校生歓迎流し素麺大会は皆が満腹になり、暫しの談笑が疎らになるにつれ、自然と終了を迎えた。 主犯グダグダエルは片付けを一切せずに逃亡。実行犯剛機ホオノキ・ダン十二式は片付けを含めた諸々の残作業を行い、最終的に帰ったのは日付が変わる寸前であった。同階層に住む生徒達は半数がそのまま帰宅、半数は片付けの手伝いを行ってくれた。 始めこそ帰った先生に不満の意を全員で表していたが、冷静に考えれば先生がいることで片付けが捗る訳でもない。寧ろ手間取る可能性もある。何故なら、奴はグダグダを司る天使、グダグダエルだからだ。 使用機材は剛機ホオノキ・ダン十二式が回収。残った食材は機界人である剛機ホオノキ・ダン十二式を除いた手伝い参加者が分配し、発生したゴミはグダグダエル名義で処分する事が全員賛成で可決、実行され た。 以上が、本日行われた素麺大会の報告である―― ◇ 無機質な電子音が闇を漂う意識を掴み上げた。 眼を閉じたまま手探りで目覚まし時計を探し、釦を押す。人間の意識を覚醒させやすい音色、という名の騒音はそれだけで突如姿を消した。 緩慢な動作で上体を起こし、寝台から身体を下ろす。 普段ならこのまま登校準備に移るのだが、今日は祭日である。それに伴い学校は休みとなっており、生徒達はそれぞれが望む休日を過ごすのだろう。 当然此方としても休日には予定というものが存在している。朝早くから行動しなければならない用事である。 寝間着を脱ぎ捨てて私服へ着替える。装飾よりも機動性を優先したその装いは、同年代が好む物に比べれば聊か地味ではあるが、華美な装いを好まない此方としては十二分である。 私用の鞄に財布、折り畳み傘、ハンカチとティッシュ、カードケース、そして携帯電話を入れる。 元より魔法を用いた術式通話は存在していたのだが、目覚まし時計同様機界から齎された技術により小型化かつ高性能化され、携帯電話という商品名で売り出されているそれは高価だ。その為まだ広く普及している訳ではないが、電波の使用による通話形式のみならず、従来の術式通話に対応しているため使用回数は案外多い。 きちんと必要な物が入っている事を確認し、鞄は一旦置いておく。洗顔と歯磨きがまだであるからだ。 洗面台へと足を運び、歯ブラシに歯磨き粉を付けて歯磨きを開始する。適度な力加減で行うべきであるが、個人的には程々に磨いておけば問題ないという意見である為適当である。一応左右ではなく上下の動きに注意しつつ行っているため、ただ漠然とするよりかは効率的であるに違いない。 水道水で口を二度ほど濯ぎ、歯ブラシを片付ける。そして空いた両手で水道水を受け止め、洗顔。朝の洗顔は洗顔料を使用しないため、濡れた顔面を布で拭えば直ぐに終了する。 あとは寝癖を軽く整えるだけであるが、今日は寝相が良かったらしく目立つ寝癖は存在しない。軽く気になった部分を櫛で整えて、身嗜みを整える事を終える。 時刻を確認すれば午前七時過ぎであり、約束の時刻まではあまり余裕がない。約束の時刻は、七時半なのだ。 少々どころか大分早すぎる集合時刻だが、集めた張本人の気質を考えればまだ良い方かもしれない。 玄関へと歩を進める。使い込まれた運動靴に履き替えれば、あとは待ち合わせ場所へ急ぐだけである。 ◇ ――終戦記念日。 各々の世界にも忘れ難き戦乱は存在するかもしれないが、現代史においてこの単語が出てきた場合、それは五界統合騒乱の終結した日を示す場合が殆どである。 本日がその日であり、どうしても休めない職種以外は十中八九休日であり、各々が思うように休日を過ごすのだろう。 時刻は七時二十五分。約束の時刻より五分早いのだが、召集した張本人……彼女には不満だったらしい。 待ち合わせしていた停留所へ着くなり、彼女が無言のまま拳を閃かせた。 ある程度予想済みであったため如何にかそれを受け止める。以前出会った時よりも重くなった一撃により、掌が痺れを訴えていた。 「一応、集合時刻の五分前なんだが?」 「私を待たせた時点で遅刻だ」 華奢な痩躯に似合わない、傲岸不遜極まりない口振りは以前と変わりない。此方を睨む蒼色の瞳は一年前に会った時よりも鋭さを増しており、それだけ彼女が過酷な状況下に晒されている事を物語っている。 その割には、身体に纏わせる雰囲気が幾分か柔らかくなったように感じる。過酷ではあるが、気を許せる友人が少なからず出来たのであろう。 天界人らしからぬ天界人の知人、エクリエルから視線を逸らし周囲を窺う。 ほぼ全ての業種が休みである為、普段なら喧騒を響かせるこの区画も今は沈黙している。時折聞こえるのは休めない職種の筆頭である運搬業を営む者が行き来する音色だけである。それは駆動音であったり、風切り音だったりと統一はされていないが、彼らが何かを運んでいることには変わりない。 まるで二人きりの世界だなと思いながら、ふと思いついた疑問を彼女へぶつける。 「他の面子は?」 例年ならば二人きりという訳でもない。毎回、此方の”死にたがり”を知っている面々……例えばルカを含める数人はいる。約一名を除きどの面々も約束事には生真面目な性質であり、五分前どころか十分前集合を行う面々ばかりである。 だと言うのにまだ来ていないという事は、何らかのトラブルに巻き込まれたか、あるいは―― 「――呼ぶ必要が無いと判断しただけだ」 此方の問い掛けに対し、エクリエルは簡単にそう呟き、不意に響いてきた駆動音の方へと視線を向ける。 機界由来の技術により、少なくとも人間界社会は飛躍的な文明開化を遂げた。それは生活に関わる部分であることが多いが、特にインフラ面での恩恵が大きい。 乗合駆動機関車、所謂バスと呼ばれる移動手段の確立は、人々の流動性を向上させ、新たな価値観の創造へ干渉している。 停留所付近で留まるそれに、エクリエルと二人で乗り込む。バスは殆ど人が乗っておらず、ほぼ貸切と言っても過言ではない状態であった。 料金は本来ならば人間界通貨で一〇〇〇イェン、共通通貨換算で二〇〇オールであるが、学生割引が利く為半額である。 目的地まではおよそ一時間程度。知人同士ならば談笑に耽る所ではあるが、生憎知人とはいえエクリエルは寡黙極まりない。必要最低限の会話しか行わない為、必然的に互いに沈黙することになる。 初めて行く場所ならば情報交換という形で話すのだが、もう何度も行った場所である上、互いに目的を把握している為言葉を交わす必要はない。 葬式もかくやといった重苦しい雰囲気の中、ゆっくりと瞼を閉じる。 ……目的地での行動の為、極力体力を温存しておきたかったからだ。 ◇ 目的地へと着く。 無言でバスを降りていくエクリエルに続き、此方も下車する。まだ五界統合学院の干渉下である為此処での支払いは必要なく、月末に一括払いである。 駆動音に掻き消される合成電子音声の紡ぐ感謝の言葉を背に受けながら、目的地である眼前の景色を視界に捉える。 其処はただただ広大な敷地であった。しかし草原が広がっているかと思えば巨大な穴が穿たれていたり、不意に機界人居住区域の様な灰色の大地が存在している。頭上の空には白雲と暗雲が混在しており、天候は極めて不安定である。ちらりと停留所の表示を見れば、乱層区画とだけ書かれており、利用者が殆ど居ないのだろう、不安定な天候に晒されて劣化している表示は未だに修正されていない。 相変わらず精神的に不安定になる光景だと思いつつ、無言で歩を進めるエクリエルへと着いていく。 ……五界統合騒乱の原因となった統合においては、殆どの場合はある一界のみの状態で統合されたが、稀に眼前の様に変な具合に統合された部分も存在する。乱層区画とも呼称されるこういった区画では普段観測されない様な事象が観測される事があり、エクリエルが此方を召集した理由も、此れに関係している。 彼女は広大な学院に置いて指折りの才媛である。 ありがちな学園物の設定で、学院内の指折りの実力者は学校中枢部と通じており、何らかの形で暗躍しているとあるが、まさしくその通りだ。 他の者達が何をしているかは不明ではあるが、彼女の場合は乱層区画の調査及びその報告書提出を学院側から依頼されている。 その関係で本来ならば此方と同じ区画の学部へ進学する予定だったが、彼女のみ他区画……様々な区画から優秀な人材が集められる区画に存在する学部へと進学している。 結果一年に一回、こういう形で召集される以外で彼女と会う事はない程までに疎遠となってしまっている。 目的地へ到着した以上、先程質問出来なかった質問をぶつけてもいいだろう。 「……何で、ルカ達に声を掛けなかったんだ?」 例年ならば、此方の”死にたがり”を知る面々が呼び出されるのだが、何故今年はそうしなかったのか、疑問なのだ。 此方の疑問に対し歩みを止めず、首を巡らせ半ば睨みながら彼女は口を開いた。 「必要性が無かったと言わなかったか」 「逆に言えば去年までは必要だったってことか。なら、今年必要じゃなくなった理由は一体なんだ?」 彼女にしてみれば知りたがる子供程度にしか映らなかったのだろう。呆れを孕む溜息のみが返され、彼女は再び前方を向いた。 言いたくないか、あるいは既に回答を彼女が示しているが此方が気づいていないだけか。 恐らくは後者であろうと思いつつ、無言で彼女の背を追う。 そうして、どれ位無言で歩いただろう。時間にした場合は十分弱、精神的には半日分くらい経ったと感じ始めた頃、彼女が唐突に口を開いた。 「……危険だからだ」 「ん?」 「ルカ達を連れてくるのは危険だと判断したからだ」 もうこれ以上は教えないと言わんばかりに、彼女の歩む速度が僅かに速くなる。それに遅れぬ様に歩みを速めるが、思考回路は疑問符で埋め尽くされていた。 ルカ達を連れてくる事が危険だと判断したのに、何故自分は呼び出されたのだろうか。 どう見積もっても、自分は弱い。”死にたがり”発症の原因となったあの一件以降、書記魔法が得意という程度の男子高校生でしかない。 我ながら情けない話だが、”死にたがり”を知る面々と自分を比較すれば、同じ状況下におかれた場合最も早く脱落するに違いない。 だというのに、何故彼女が此方だけを呼び出したのか。 その答えは、次の瞬間に嫌と言う程理解することになった。 【クロ 2014.01/15】 そこに見えたのは足元を横切る後ろ向きで歩く人型の影。影は左回りに回転していて、やがて機界の建造物の陰へ溶けていった。 あそこに見えるのは水滴が天に昇っていく様。雨だったのだろうか。しかし雲は掛かっていない。 「なんだろうねこれ」 俺は奇妙な風景を視角外に置いてエクリエルに訊いた。 答えてくれなくてもそれはそれでよかった。少し、安心したかった。 「それを調査している」 なるほど、調査対象が早速見つかったのは幸運だ。しかしこの光景はなんとも気味が悪く、眩暈がしてくる。もしかしてこれがルカ達を呼ばなかった理由なのだろうか。あっ、鳥がトカゲに。 「これら現象を観測すると真っ当な神経の持ち主は気が狂ってしまうのだ」 そうですか。真っ当じゃないと言われればそうかもしれないが、他の面々も割りと真っ当な神経の持ち主ではないような気もする。これ以上考えるのはやめよう。頭が痛くなりそうだ。あっ、白い草みたいなものがいっぱい生えてる。 「その空中に浮いている木のようなものの隣に立て。写真を撮る」 ああ、あの瞬間を絵のように切り取る機械のことか。流石エリート学生。最先端だ。って何故俺がこんな気味の悪いものと一緒に。 「被写体の大きさをわかりやすく記録に残すためだ。あとで聡治の現身長体重も聞かせてもらう」 お前はエリートでエスパーだったのか。此方が口に出さなくても問題ないらしい。そう言えばこんな奴だったかもしれない。こうなりゃヤケクソだ。 「これは!木のような手触りだ!う、動く!?まるで吊るされているかのように揺れ動くぞ!?む、そして何だか甘い香りがする!なんだこれ……」 と、ちょっと張り切ってはみたが、あまりのわけのわからなさに言葉が詰まる。 機械が駆動する音と光だろうか、薄っぺらい紙で何かを叩くような音と一瞬の閃光が、此方の方を通り過ぎていった。 ふと写真をとる機械がどういったものか気になり、エクリエルを見ると何やらメモを取っているようだ。一体何を。 「そのレポートを一字一句正確に書き記している。無論そのまま発表する」 「やめてくれ」 エクリエルは返事をしなかった。相変わらず勝手な奴だ。 そのまま俺達は、水溜りを中心に散っていく地面だったり、突然耳元で鳴って四方八方に飛んでいく何かの音だったり、よくわからない何かを記録していった。 不条理で、不気味で、不可思議で、どうしようもなく不安になるこの光景が、何故か五界の縮図に思えて、哀しくなった。 「何でもありそうなのに、寂しいところだな」 視界の端で、エクリエルがメモを取っているのが見えた。きっと、哀しい顔をしていた。 【どあにん 2014.02/02】 その後は天界の眩い光に辺りが包まれたかと思えば霊界の嫌な空気がこちらに流れ込んできたりもする。 エクリエルは不可思議な空間の写真を撮りメモを書き、伏神聡治は目まぐるしく変化する不思議な空間に漂う物質を逐一感触や匂い等を事細かに伝える、 そんなやりとりが続いて時が経ってもその空間は収まらない、エクリエルもメモ用紙が足りなくなったのか近場の岩に腰掛けてソウジを手招きする。 「で、何か分かったか?」 「何も分からん……それにだ」 目を閉じて何かの呪文を唱えるエクリエル。 一瞬件の空間が歪曲したかと思った瞬間、パンと乾いた破裂音が辺りに響き渡った。 突如の大きな音に驚いてゆっくりと目を開けたソウジの目の前にいたのは、夥しい量の鼻血を垂らすエクリエル。 純白の衣が血で汚れて悪趣味な水玉模様が広がっていく、慌てるソウジを尻目にエクリエルはハンカチで鼻血を拭いながら続ける。 「空間の魔力を読み取って誰がやったのか推測しようにも、魔力が巨大過ぎて私の力量では測る事が出来ん。 魔力の質も桁も違い過ぎるんだ、分かりやすい例えで言うならば一つの匙で大海を全部掬い取るかのような愚かな行為だ」 「なるほど、すっげぇ分かりやすい例えをありがとう」 ソウジは首を縦に振ってから改めてこの不可思議な空間を見やる。冒涜的で、しかしどこか儚さと美しさを併せ持つこの亀裂。 鼻血を拭き終えたエクリエルが立ち上がり、書き溜めたメモを全て鞄の中へ仕舞い込んだ。 「帰るぞソウジ、コレ以上は何もわからん。 此処ら近辺に結界魔法を張ってから後日調査兵団の派遣を依頼する」 オッケイ、と少々おどけて返事をしたソウジは一歩を踏み出した瞬間何かが割れるような音が聞こえた。 振り向く、見えたのは腕、真っ黒、脳が走れと命令パルスを発する前に掴まれる、引きずり込まれ――。 「ソウジ!?」 何かの音に気付いて振り返ったエクリエルの目に見えたのは、巨大な黒い腕に掴まれたソウジの姿。 明らかにヒトでは無く刺々しい鱗に覆われている腕、太古に滅びたと言われる龍のそれと瓜二つであった。 エクリエルが叫ぶと同時に衝撃魔法の詠唱を開始するとエクリエルの身体に青白い電流を走るが、間に合わない。 亀裂から伸びる腕はソウジをその中へ引きずり込むと耳障りな音を立てながら亀裂が小さくなる、それを見てしまったエクリエルが腕を伸ばすも指先が触れたのみだった。 「うぉぉぁぁぁああああッ!?」 目まぐるしく景色が変化する不可思議な空間に引きずり込まれたソウジは必死に抵抗を試みる。 ゴツゴツとした鱗に覆われたその腕を殴りつけたり、引き剥がそうとしてみたり、果ては噛み付いてみたも歯が立たない、むしろ鱗の欠片が歯の間に挟まって痛い思いをした。 単純に殺すだけならば亀裂から出てきた時に握り潰すなり何なりすれば良かったはずだが、こうして捕まえると言う事はこの腕の主が何か目的を持っていると推測出来る。 希望的観測に過ぎないが殺される心配は無さそうだと思った時、腕がソウジの拘束を解いた。無様に尻もちを付いたソウジは尻を擦りながら立ち上がると、そこには女性が居た。 尻まである長い黒髪、切れ長の瞳は見る者を威圧する。 だがソウジの目を引いたのは大振りの西瓜を思わせる2つの脂肪がくっ付いている人体の神秘、その頂点と股間が必要最低限の漆黒の鱗で覆われている。 そして……細く長いヒトの腕、肘から先は刺々しい鱗に覆われた龍の腕、と言う事は……だ。 「人の子よ、会いたかった」 「だ……誰だお前は!?」 嫌な汗が止まらない、心臓……魂を直接鷲掴みにされているような威圧感、本能がガンガン警鐘を打ち鳴らす。 死。 死そのものが目の前に立っているような感覚にソウジは吐き気を覚える。 いっそこのまま吐き戻して失神出来る物ならばどれほど楽だったか、この時ばかりは無駄に強い自我を呪った。 件の女が肩を竦めると人体の神秘が派手に暴れる、この異常な状況でなければ視線が釘付けになったであろうがそんな余裕は無かった。 「嗚呼、定命の者は初めて出会う者には名を名乗るのが礼儀であったな。 我は黒龍(ファブニル)、世界の……観察者……支配者……でも無い、嗚呼そう……"管理者"が定命の者にとっては一番近しい表現か」 黒龍。そのキーワードから蘇るのは忌まわしき記憶。 白龍(ヴェイパー)、赤龍(アドライグ)が口走った三匹目の龍が、今自分の目の前に立っている。 そもそもその管理者様が何故、何の取り柄も無い極めて普通の魔法が使えるだけの男にこぞって会いたがるのかソウジには理解できなかった、理解したくなかった。 その気になれば自分の命なぞ足元を蟻を踏みつぶすかのような造作で奪えるのだろう、魔力感知はさほど得意では無いソウジでもハッキリとわかる覆しようの無い圧倒的な力量差。 「身構えるな人の子よ、我はただ……お前と対話をしたいだけだ。 無論命の奪い合い……いや、一方的な蹂躙、陵辱を望むのならば我とてやぶさかでないが……な」 「……分かった、ただ俺なんかと話して管理者様のためになるような話はできないと思うがな」 軽口を叩くのが精一杯、額と背中はじっとりと汗で濡れている。 少なくともあちらに敵意は無いと判明しただけでも重畳の結果だ。 ……だがソウジは自分がこの先どうなっていくのか、それ以前に元の場所に生きて戻れるのか不安が募り始めていた。 【クロ 2014.03/15】 「ふむ、お前が……」 黒龍(ファブニル)の威圧的な眼光がソウジを舐め回す。 ソウジはその恐ろしい瞳から目を逸らすことができなかった。目を逸らすことの方がなお恐ろしかった。 ソウジの脳裏にあの夜の記憶が爪を立てる。あの赤龍(アドライグ)の言葉が牙を剥く。 “ボクだから笑って許してあげれるけど、黒龍(ファブニル)とかだったら魂すら残れないよ” ソウジは言葉だけでなく、呼吸も奪われた気分だった。 「臭うな……赤龍とも接触したのか?」 「あ、ああ……」 ソウジは振り絞ったような声を辛うじて出した。 もはや軽口など叩けるはずもなく、極めて簡潔に、最低限の発言にとどめた。 黒龍は、何か面白い玩具を見つけた稚児のような笑みを浮かべる。 「まあいい。いや……もういい。我はお前を選ばない」 何かが鳴る音に気付くことなく、ソウジは最悪の想像をして身構えた。 突如平衡感覚を失ったことに恐怖し、声にならない叫びを自身の中だけで聞いた。 ソウジが目を閉じていることに気付いたのはしばらくしてから。 鳴り響く鈴の音に驚き、目を大きく見開くと鳴っていたのは鞄、ではなくその中にある携帯電話だった。 「無事か……聡治……?」 その弱弱しくも凛とした声の方を向くと、そこには膝をつき、今にも倒れそうなエクリエルがいた。 エクリエルの目、鼻、口からは夥しい出血、服はその血で真っ赤に染まっている。 それは服だけにとどまらず、今も地面を濡らし続けていた。 「エクリエル!!何でこんなことに……っ!?まさか……お前が……?」 ソウジはすぐさまエクリエルを抱きかかえる。驚くほどの冷たさにソウジは全身を強張らせた。 「互いの……携帯電話を座標とした……転移魔法だ……かなり無理は……したがな…………」 ソウジは鞄から取り出したハンカチとティッシュを渡し、エクリエルの膝裏と脇に両手を差し入れ、抱き上げる。 エクリエルは受け取ったハンカチで顔を拭い、そのまま覆った。 ソウジはエクリエルを極力揺らさぬように、そしてできうる限りの速さでバスの停留所へ走る。 運良くバスが停留しており、ソウジが事情を話すと運転手は快諾し、病院へ急いだ。 迅速な救急魔法の甲斐あって容態は安定。大量の失血こそしていたものの、命に別状はなかった。 「……………………」 輸血を受けながら病室のベッドに横たわるエクリエルに、ソウジは声を掛けられないでいた。 「そんな顔をするな。私にはお前を巻き込んだ責任がある」 エクリエルの銀髪は、ところどころ乾いた血で赤黒く染まっていた。 「すまない……」 エクリエルは小さくため息をつく。 とても病室は静かで、少し距離があったソウジにもそれははっきりと聞こえた。 「謝らなければならないのは私のほうだ。……ハンカチを汚してしまった。今度、新しいハンカチを買ってやる」 ソウジが再び謝罪の言葉を口にしようとしたとき、それにかき消すように、エクリエルが語尾を強めて言った。 「休日の予定を詳細に連絡しろ。後日電話をする。出ろ」 「……ああ」 【タタリ 2014.04/05】 エクリエルの病室を出てからというもの、俺の為に……もとい、俺のせいで重体となってしまった彼女の元をやすやすと離れられる程、俺は割り切って生きてはいけない。かと言って病室に戻れば、彼女の機嫌を損ねてしまう事は明白だ。 あれは良くも悪くも、世界は自分を中心に回っていると考えている。彼女の決定は世界の確定であり、示した善意も悪意も例外無く、そう在らねば気が済まないのだ。 なので、彼女が俺の身を案じてくれた上で助けた以上、本来、俺は恩に着てこそあれ謝ってはならなかったのだ。そのエクリエルが俺を帰したのだから、俺は自室に帰ってなければならない。まして、今さら「やっぱり心配だから戻ってきた」など言おうものなら、ろくに動けない体であっても俺を張り倒す為に無茶をしでかす事だろう。 どちらにとっても良い結果にはならない。というかごめん蒙る。 なので、俺は行く宛もなく、病院の中庭で茶なんぞを啜っているのだった。 紙コップの中にはコーヒーなる奇怪な黒水が入っており、これは自動販売機という不思議な装置の中で直に作られていると聞く。あらかじめ炒ったコーヒー豆を自動販売機の中で挽き、お湯を注いで完成する謎の装置だが、あれはどういう原理で製造しているんだ? 実は中に人が入ってるのか? などと益体ない愚考に耽りながら、黒い苦湯を啜っていると、不意に背後から聞き覚えのある声で話しかけられた。 「おいっすー、お兄ちゃん。元気してるぅ?」 「……ああ、ルカか」 「ああ、ってなにさ。傷つくなぁ。死にかけたって聞いて慌てて駆け付けた後輩にかける挨拶じゃないでしょ、それ」 「ん、悪い悪い。ちょっとナーバスになってた」 ルカ=ルー・ガルー。種族的な意味での狼少年は、先日も連れていた機界の少女と共に俺の前に立っていた。 「御機嫌よう、ミスター。息災ですか?」 「見ての通り、俺は傷一つねぇよ」 「それは何より」 名も知らぬ半分機械の少女は抑揚のない口調で、スカートの裾をつまみながら恭しく頭を下げる。仰々しくも白々しい行動に見えてしまうのは、俺が見慣れぬ行動だからか、それとも彼女に入力(インプット)された動作(マクロ)だからなのか、判断がつかない。 改めて二人に向き直り、自販機に背中を預けてから、コーヒーを飲み干す。砂糖もミルクも混入していない黒水はひどく苦いが、どこかクセになってしまう。 「お兄ちゃんがこの調子なら、委員長も無事なの?」 キョロキョロと中庭を見渡しながら、ルカが訊ねる。エクリエルが近くにいると思ったのだろう。その言葉がズキリと俺の心臓に突き刺さる。 「いや、アイツは……病室だ」 「……どういう事?」 俺は訝しげなルカと少女に事の顛末を話す事にした。二人で乱層区画に調査に出た事、俺が次元の狭間──としか言いようのない空間に落ちた事、エクリエルが無茶な魔法術式を用いて俺を救い出した事、そのせいで彼女が重体になってしまった事。 唯一、俺が狭間で起きた出来事だけは伝えなかった。と言うか、正直、その事はほとんど覚えていないというのが正確だ。 あの時の事を思い出そうとしても、頭に黒い靄がかかった様に記憶を寸断し、意識を失いそうになる。何か恐ろしい物と対峙した気がするし、話もした気がするのに、その一切は完全に記憶から失われている。 話を茶化す事なく真剣に、神妙に聞き入っていたルカと少女は、エクリエルが寝ているであろう病室を中庭から見上げつつ、嘆息吐いた。 「はぁ、なるほどねぇ。委員長らしいや。あの人、無茶を無茶と思わないんだから。それで死にかけてりゃ世話ねーよ」 「ルカ氏に肯定です。下に就く者の心労などお構いなしなのは、エクリエル女史の悪い癖です」 お前ら、本人が聞いたらぶっ飛ばされるぞ。物理的に。 「で、お兄ちゃんはそれでナーバスになってたって事か。ゲラゲラ阿呆くせぇ。あんな危険な場所にお兄ちゃんしか連れていかなかった委員長が悪いんだから、お兄ちゃんは気にする必要ないっしょ?」 「ルカ氏に肯定です。そもそも、彼女は正式な依頼を受けた調査員、ミスターはあくまで外部委託。正規の調査員が委託先のアルバイトの安全を確保すべきなのは至極当然と言えましょう」 「そういう事だね。あの人は少し懲りた方がいい。……いや、今回の件で死にかけても懲りないのが委員長なんだけど」 二人で通じ合う物があるのか、お互いにひどい事を言うものだ。ルカは俺の肩を二回ほど軽く叩きながら、委員長、もといエクリエルの陰口を叩いている。機界の少女も概ね同意と言ったところか。 ひとしきり、本人がいないのをいい事に、普段からの不満を垂れ流したルカは、ふと俺を見上げながら、こう囁いた。 「まぁ、悪いのは委員長なんだけど、それとこれとは話が別って事で」 頭二つ分は背の高い俺の肩にかけたルカの指が、突如として力強く肩に食い込む。万力に締め上げられた様な鈍痛が脳裏に迸る。 少女は呆れとも諦めともつかぬ表情を浮かべ、目を閉じた。 ルカの怪力が、俺の体勢を崩した。細い少年の腕のどこにそんな力が宿っていたのか、俺の上体を片手で引き寄せながら、返す拳を振るう。 ──ルカ=ルー・ガルーは、魔界の出身者であると同時、人狼に該当するライカンスロープである。ルー・ガルーの一族は人狼種の中でも最古より厄災であるとされてきた。 その名は、原初のワーウルフとして、恐れられてきた。 一撃。ルカの小さな拳が、俺の頬を捉える。人間など比べるのも烏滸がましい程の脅威的な身体能力を持つライカンスロープ、更に原初のワーウルフの純血を持つルカの拳は、俺の体を自販機から数メートルも吹き飛ばした。 平和な中庭で突如起こった暴力沙汰に、遠くから誰かの悲鳴が聞こえた気がした。どこの誰だか知らんが慌てるな。ルカの拳を受けて俺の意識が保ってるという事は、アイツはかなり手加減してるって事なのだから。 「今回は委員長に全責任があるから、このくらいで済ませておくけど、覚えとけよお兄ちゃん。……委員長に何かあったら、絶対にお前を許さないからな」 犬歯、いや狼の牙を剥き出しに、ルカはさっさと中庭から立ち去ってしまった。 後に残されたのは俺と、機界の少女と、平和な病院で惨劇を目撃した何人かの一般人だけである。 「ルカ氏に代わって、私から謝罪します、ミスター。……だから、彼を許してあげて下さい」 「ん、大丈夫、わかってる」 そもそも諸悪の根源は俺の不注意なのだ。ルカを許すも許さないもない。むしろ、この程度でルカに許してもらえた事が、俺にとってはありがたい。 駆け寄る少女の手を借りて立ち上がろうとしたが、思う様に足が動かない。やばい、ルカやばい。たった一発の拳でこのダメージとかありえない。ほっぺたが痛いというか熱いくらいで済んでる程度のダメージなのに、的確に脳が揺さぶられて立つ事すらままならないとかどんな謎の技術持ってんの、アイツ? 「そこのベンチでしばらく休憩しましょう。肩をどうぞ」 「……うん、すまん、助かる」 這う事も出来ないのだ。機界の少女がいてくれて本当に助かった。 周囲で平和を享受していたモブの方々には何でもないですよと手を振ってアピールしながら、少女の肩を借りてベンチまで移動する。視界がグニャグニャして脳がグラグラしてるのに意識は実に鮮明だ。 「お詫びとして、膝枕でも致しましょうか、ミスター・脚フェチ」 「お前まったく詫びてるつもりないだろ!?」 だから、ツッコむ事くらいは出来るのだ。というか俺に変な属性つけるの今すぐヤメロ。 【どあにん 2014.04/10】 例え誰かが傷付こうとも、もしくは誰かの生命の灯火が消えてしまったとしても世界は無情に時を刻み続ける。 矮小な生命の一つや二つ消え去ろうとも意に介さず、静かに、無情に、残酷に―― 第二節『The Wonderful World』 俺の不可思議体験……もとい鱗おっぱいドラゴンとの邂逅から早くも1週間が過ぎた。 クラスメイト達が興味津々で俺にアレコレ聞いてきた日が早くも懐かしく感じる程、多分俺の人生の中で上位に入るくらいチヤホヤされたと思う。 なんて馬鹿な事を考えている間に授業の開始を告げる魔法鐘の音色が学園中に響き渡ると同時に教室のドアが開……かない。 腹立たしい事にこの学園の先生はグダグダエル先生を除いて始業時間丁度に教室にやってくる場合が多い、 またグダグダエル先生の臨時授業か何かだと教室がざわめき出した時、それは起こった。 煙のような何かが扉から溢れ出てきたかと思った刹那、灰色の若い男が"扉を開けずにすり抜けるように"現れたのだから。 頭からつま先、身に付けている物や教科書まで全てが灰色の煙で構成された不可思議な生物に、流石のクラスメイトも動揺を隠せないようだが、 件の人間は気にせずにチョークを摘むような動作を行うとフワリと浮き上がるチョークが黒板に押し付けられて文字を綴って行く。 「えーっ、まずは皆様初めまして、私は呪詛魔法学担当のユーザス=レイ=リッチモンドです。 霊界出身故に私には実体と言う物がありません、驚かせてしまって申し訳無い」 ユーザスと名乗る先生は笑みを浮かべた、人間で言う口に当たる部分の煙が揺れ動いただけに過ぎないが彼にとってはそれが笑みを浮かべると言う事なのだろう。 多少の自己紹介もそこそこに、ユーザス先生は教科書……のような煙を開くと名前もあまり知らぬ男子生徒の一人が手を挙げた。 「ユーザス先生、先生には実体が無いそうですけど教科書とかは読めるのですか?」 「ん、良い質問だね 確かに私は実体が無いから君達のように本を読んだりする事は出来ない、だから私は魂を少し抜き取って読んでいるんだ」 質問に対する返答の意が分からない、ざわめく教室を意に介さずにユーザス先生は続ける。 「万物には全て魂が宿っている、大切に使い続けた物は魂から生命が生まれる、そう……こんな風にね」 言うが否や。 一番前の席に座っている名前がうろ覚えな男子生徒の教科書にユーザス先生が手を触れると、そこから四角い煙が少しだけ引きずり出される。 驚きで声が出ない男子生徒をそのままに教壇に戻ったユーザス先生は授業を開始した。 「まず呪詛魔法とは何か、呪詛は五界統一騒動が起こる前の物質界……所謂人間の世界で確立された黒魔術が元になっています。 呪詛魔法とはいわば呪いの類であり、対象の体調等を変化させる効力を持っています、ゲームで言えば状態異常魔法の事ですね」 ユーザス先生の話を聞く傍らで俺はふと隣の席をチラリと見やる。 腐ったドブみたいな緑色の瞳を輝かせるのはダミアンだ、あぁそう言えばコイツ復讐が目的って言ってたな……誰にだ? なんて事を考えてたらユーザス先生が浮かせて飛ばしたと思われるチョークが俺の額ド真ん中に命中したので痛む額を擦りながら意識を目の前に戻したのであった。 しかしながら呪詛魔法学初回と言うだけあって、呪詛魔法のルーツや効力について大まかに話す程度だけだ。 視線だけを時計に見やると時刻は早くも終了五分前に迫っていたので教室内で私語を話す声が目立ってきた頃、ユーザス先生はじっとクラスメイト達を見つめ、 そして何か納得したような、子供が自分にとって珍しい物を発見したかのような満足気な笑みを浮かべた時、授業終了のベルが学校内に鳴り響いた。 あの時、ユーザス先生はダミアンと俺を見る時間がほんの数秒長かった気がするが……次の授業が錬成魔法学で教室移動となる為、思考は慌ただしさの中へ置き去りにしておいた。 ◇ 学園地下一階、錬成魔法学の教室はそこにある。 カビ臭くて長い石造りの廊下、その道中は妖精が作った魔法のランプである程度の明かりが確保されている程度の場所を少し歩いた所にその教室はある。 所々錆びている鉄の扉を見た生徒は開けるのを躊躇っているが当然だろう、物語に出てくる意地悪な魔女のバアさんがデカい鍋をかき回していたらそりゃ誰だってビビる。 魔法薬の調合や魔法人形の作成など、地味でカビ臭そうなイメージがこびり付いているからだ、誰だってそうだ、俺もそうだからだ。 だが、致命的な程空気を読まない剛機ホオノキ=ダン十二式がさっさと開けてしまった、その瞬間……俺の鼻孔をくすぐったのは甘い香り。 砂糖とかそういう類では無く植物由来の、しかしながら押し付けがましく無い優しい香りが教室の扉を開けた瞬間から漂ってきたのだ。 見れば教室内も巨大な妖精ランプで全体が明るく照らされている、まるでそこに小さな太陽があるかのような優しく暖かい光で俺達が抱いていたイメージが一瞬で覆された。 【西口 2014.04/11】 「いらっ、しゃいませ……」 そしてすぐに元に戻った。 暖かな光と、心地よく甘い香り。頭の奥底で澱のように固まる不快感を、ひと時とはいえ吹き飛ばせるほどの、清浄な空間。 その中にあって、彼女の存在は異質といっていいだろう。 150センチ程度の小柄な体躯とはいえ、目元を追い隠し、その足元まで届きそうな程長い髪は甚だ不気味だ。 その黒曜石のような艶を見る限り、手入れは行き届いているのだろうが。 その上、全身を黒いローブで多い、わずかに覗く手先や脛までもが、手袋やソックス(言うまでもなく黒)で覆われているとなれば、何をかいわんやである。 唯一露出している部分といえば口元の不健康な青白さの肌と、薄く化粧気の無い唇のみである。 その傍らには、岩で出来た巨人のような彫刻が、丸まって鎮座している。 そんな出で立ちで教壇に立つ彼女は、何というか、暗い。全体的に。 部屋の中は旧校舎の地下とは思えないほど、自然な明るさに満ちているのだが、彼女の周りだけが、まるで真夜中の樹海のように薄暗く感じられた。 教室の変わりように慄き、一瞬遅れて襲い掛かってきた喜びも掻き消えて、呆然としているクラスメイト達。 俺を含めたその全員が、例外なく抱いているであろう疑問を、率直にぶつけてくれたのは我らが剛機ホオノキ・ダン十二式。 空気が読めない彼であるが、こういう時には非常に頼もしい。 「失礼ですが、貴方はどなたでしょうか。練成魔法学の担当は、カザルル・ナゴト女史が勤めていらっしゃった筈ですが」 「あぁ……。やはり連絡が、行き届いて、いないようですね……」 まずは席に座ってほしいと言われたので、促されるままに以前よりの席に向かう。 カザルル先生の頃とは内装や机の配置などが全く違ったので、少しばかりもたついてしまい、頭に疑問符を浮かべた(一部除く)俺たちが席に着いたのは2分ほど経ってからだった。 それを見てとめた闇色の女性は、空中に何らかの文字を描くように軽く指を振る。 小さくではあるが、同時に唇も動いているのを、俺は見逃さなかった。 指が動きを止めた瞬間、女性の傍らで蹲っていた巨人が、ギギギという何かが軋むような音と共に立ち上がった。 彫刻ではなく、傀儡人形であったらしい。となると、先ほどの挙動は即席の駆動術式か。 旋律魔法の区分である詠唱と、書記魔術の領分である陣紡。 強い集中を要する二つを同時に、それも結構な速度で正しく行えている。 エクリエルですら出来るかどうか怪しい上に、仮に出来たとしても極度の疲労を強いられるであろうそれを、この女性は容易くやってのけた上、平然としている。 その尋常ではない力量と、先ほどの物言い。 女性の正体が、何となく分かった気がする。 岩人形が、その巨大な手先からは想像出来ないような器用さでチョークをつまみ上げ、黒板に美麗な字を書いていく。 指があり、それが動いている所を見ると、どうやらあの傀儡は内骨格《インナーフレーム》がきちんと組み込まれているものらしい。 細かい力調節が可能なのも、内骨格の完成度の高さゆえだろう。 あいにく傀儡にはあまり明るくないので、それがどれだけ凄い事かはまるで分からないが。 しげしげと、動く岩人形を見つめていると、一瞬だけ視線を感じる。その元を追ってみると、闇色の女性に行き当たった。 女性は教室の戸を開いたときと変わらない体勢で、床部より一メートルほど高い教壇から、クラス全体を睥睨している。 その前髪に隠れた瞳が、俺に向けられて……いるわけないか。 自意識過剰だな俺は。思春期か。 あ、思春期だった。 「以前から、決まっていた、事なのですが……、前担当の、カザルル先生が、地元にお戻りに、なられるとの事で、代わりに着任致し、ます……。 湊ハヅキと、申します。以後お見知り、おきを……」 黒板には人間界の術式用語にして共通言語である、ヤマトという言葉でその名が綴られている。 深々とお辞儀をする彼女――湊先生に、お願いしますと応じたのは質問主である剛機ホオノキ・ダン十二式だけであった。 「カザルル先生は、お祖母様の御様態が、急変、なされたらしく……、先日、地元の魔界へと、お帰りになられた、ようです」 授業終了五分前。湊先生が話しているのは、連絡に不備があった理由だ。 着任初授業という事で、今回は練成魔法の梗概や、大まかな歴史。次回やる授業内容の予習などが行われたのだが、やる事がなくなってしまったので、その穴埋めだ。 意外、と言っては失礼極まりないのだが、そのインパクトの強い見た目に反して喋る内容は至極普通であった。 内容も理路整然としていて、事前に知っていた事とはいえ、非常に分かりやすかった。 少し調子はずれな喋り方にも慣れてきたし、次回以降がちょっと楽しみになってきた。 「私は元々、ここの特別司書として、働いて、いたのですが……、学園長に、誘われたのです……。少し、やりたい事も、ありまして、お受けさせて頂き、ました」 これには素直に驚いた。 特別司書といえば、古代・現代問わず、現存する魔法の管理を職務とする統合政府直轄の国家公務員だ。 その職務の詳細は多岐に渡り、一般には公開されていない物もあるという。 簡単に言うならば超エリート。さきほどの魔法の腕前にも納得がいくというものだ。 この学校での職務といえば、図書本館での禁書の管理などであろう。 それその物が魔術現象である場合さえあるというそれらの中には、図書文化委員会が管理するには荷が勝ちすぎる物もあると聞く。 しかし、誘う学園長も凄いが、それを受けるこの人もこの人だ。たしかにこの学校は巨大であるし、そこで教鞭をとっているとなれば、そこそこに誇らしい事である。 が、それは飽くまで一般からの目線での話だ。界々を股にかける公務員と比べれば、給料面でも名誉面でも大きく劣る。 それらを天秤の対にかけて、尚あまりある「やりたい事」とは一体なんだろうか。 「ちなみに、内装を整えるのにも、いくつかの、魔法を、使用して、いまして……」 先生の話は続く。 それにしても、よく通る声だ。唇は僅かにしか動いていないし、声量もあまり多いようには思えない。 教室の静寂も幾らかは緩和されてきているので、小さい声では響きようもない。特殊な声質か何かか……? 何となく室内を見渡して、ハタと気づく。教室の隅の八角。壁紙に溶け込むような微かな文字で、何かが書かれている。 呪詛魔法の痕跡が見て取れるそれは、アーヴィニル――汎用術式言語で「響け」「閉じよ」。そう刻まれていた。 「目ざとい、ですね、ソウジ君」 いきなり名前を呼ばれ、思わず飛び上がりそうになった。視点を先生の方へと戻すと、その口元には笑みが浮かんでいた。 「旋律魔法による、拡声……。結界魔法による、作用箇所限定……。そして書記魔法によって、発動条件を作って、無駄な、魔力の消費を抑える……。複合魔法、です」 ――ちなみに、ですが。 「来週より、実施されます、選択授業で……、総合魔法学の担当は、私が勤めさせて、頂きます」 湊先生がそう言い終わると同時に、授業の就労を告げる鐘の音が響き渡った。 礼をし、退室した先生に習って、多くの生徒が席を立つ。椅子の脚が床を擦る音に混じって、耳元で湊先生の声が響く。 「放課後、図書本館へ、お越し下さい……」 ◇ 図書本館というのは、図書文化委員会によって管理される魔導書及びちょっと拙い図書、専門書の類が所蔵されている巨大な図書館だ。 なんで学舎にそんなものがあるんだ。と、この学校に来たものはみんな思う。俺も思った。馬鹿じゃないのか、と。 しかし、この学校が公になっている施設の中で最も安全で、最もどうでもいい場所なのだから仕方がない。 機密情報は殆どないし、重要人物もあんまりいない。 文句を言う保護者もいるが、仮に書物の類が無かったとしても、戦争の遺恨は未だ根強く残っている。 五界の和平の象徴であるこの学校は、格好のテロの獲物である。本があろうが無かろうが危険なことに変わりは無い。 つまらん事で文句を言うな。というのを迂遠に、オブラートで何十にも包み込んでそういう類の人間には説明している。 まあそれ以外にも、ちょっとアレな知識を求める、黒魔術などの古代魔法の担い手などを招くためという理由もあるらしい。 それに一本釣りされたのかダミアン辺りだ。 その敷地は広大で、アホみたいに広い五界統合学院の、およそ10パーセントを占有している。 といっても、実際に生徒が立ち入れるのはその中の三割くらいのものだが。 学年や成績、所属や所持している資格などで立ち入れる区画は厳格に分けられており、生徒会に所属していない人間が利用できる場所は本当に少ない。 ルカが一時期とはいえ、図書委員であったのも、それが理由だ。まあ、エクリエルが風紀委員長に収まるなり、すっ飛んでいってしまったが。 ちなみに、同じ理由で俺も一時期所属していた。 色々と貴重なものも読めて、当時は酷く喜んだものだが、今となってはやめておけば良かったと思っている。 古来、五界統合以前より、人間界を舞台に天使と激しい戦いを繰り広げてきた伝説的な存在、悪魔。 魔族の中でも、未だに地方では信仰対象とされている事さえあるという彼らの中の一人と、俺はここで知り合ってしまった。 堕落と退廃を好む彼女によって、俺の『死にたがり』は悪化した。エクリエルに無理やり引きずり出されなければ、多分自殺でもしていたことだろう。 それでも、俺は彼女のことが嫌いになれなかった。 枯れ果てたように才能が無くなり、周りの人間の嘲笑から逃げるために、俺はこの学校に来た。 幼馴染のルカや、エクリエルと出会えるまで誰も信用できず、常に周りに距離を置き――いや、置かれていたのだろう――友人と呼べる存在など一人としていなかった。 寂しくてたまらなかった。 そんな時に、目的や理由はどうあれ、傍らにいてくれた存在を、どうして拒絶できようか。 エクリエルには罵倒されるだろう。もしかしたら、またもルカにぶん殴られるかもしれない。 分かっている。でも、湊先生に促され、本館内の委員長室へ向かう俺の足が止まる事はなかった。 「ああソウジくん、ソウジくん! 久しぶり久しぶり、元気にしてた!? あのクソッタレ天使に連れて行かれてから全然来てくれないから、私の知らないところで死んじ ゃったんじゃないかって、すっごく心配してたんだよ!」 「それは、自分の見てるところで死んでほしいからって意味か。アシュリー?」 姓は知らない。必要ないとも彼女は言っていた。 肩甲骨辺りから生える蝙蝠めいた翼で室内を飛翔し、纏わりついてくる彼女への対応は、出来る限り冷たくする。 少しでも罪悪感や好意的な態度を覗かせれば、彼女は確実にそこに付け込んでくるだろう。 俺の応答の何が気に召したのか、アシュリーはにんまりと邪悪な笑みを浮かべ、床に降り立った。 「なあんだ。本当に克服しちゃったんだね、『死にたがり』。つまんないの。全く、余計なことしてくれたよ、あのクソ天使」 「……何の用だよ。わざわざ湊先生に言付けてまで連れてこさせたんだ。ただ話したいってだけじゃないんだろ?」 クスクスと笑い声を漏らすアシュリーは、もうちょっと待っててね、と言った。 何なんだ、と疑問符を浮かべる暇もなく、その疑問は氷解した。 ギィと軋む音を立てて扉が開き、室内に三人、新たな人間が入り込んでくる。 ダミアン。ルカ。そして、機界の少女。 「クロガネですよ、ミスター」 心を読まれた……!? 「ああ、本当に知らなかったのですね。名も知らぬ相手に膝枕をさせようとするなんて、いやらしい……」 「お前が自主的にやろうとしたんだろうが!?」 「うわぁ、マジかお前」 「何で一ミリも信じようとしねえんだよ!」 緊張感が解れたといえば解れたが、場がぶち壊しになったと言い換えることも出来る。 唯一口を噤んでいるルカは、どこか居心地が悪そうだ。 まあ、苦手なアシュリーがいる上に、昨日殴り飛ばした相手がいるとなれば、気まずくもなろう。 「良かった。全員来てくれたみたいね」 「それでは、私は、これで……」 先生が退室する直前、頑張って下さいね。と、耳元で彼女の声が聞こえた気がした。 「我々風紀委員への協力要請ということですが、委員会未所属の人間が二名もいる事と併せて、詳細の説明を要求します。ミスアシュリー」 進み出でて、少女――クロガネが挙手と共に質問する。 本当に、毎回ルカと行動を共にしているらしい。その割には姿を見かけたのはつい先日が初めてだし、最近入ってきたばかりなのだろうか。 「ソウジくんがいるのは優秀だから。ダミアンくんがいるのも優秀だから。これ以上に理由が必要?」 「そのような抽象的な理由で、未所属の人間を危険に晒すわけにはいきません」 「あら、図書委員会の外部協力員の決定権は私にあるのよ? 誰を選ぼうと、本人の許可さえ取れば貴方達に文句を言う権限はないわ」 え、何それ。承諾した覚えないんだけど。 「ああ、お前の分は今朝俺が書かせてやったぞ」 耳元でダミアンが囁く。何言ってんのこいつ。 「寝起きの状態で、呪詛にもかかり易かったからな。簡単にできた。覚えていないか?」 「何してくれてんのお前!?」 「元より、拒否するするつもりはないだろう?」 「それは……まあ」 性格を見抜かれている。数日前に出会ったばかりだというのに、だ。 そんなに分かりやすい性格かなあ、俺。 「ほら、退がってクロガネちゃん。今から詳細説明するから」 傍らのダミアンから視線を戻すと、クロガネが渋々といった様子で数歩退いていた。 「えーと、単刀直入に言うわね」 ――禁書が数点、盗難されたわ。 空気が凍りつくのを感じた。