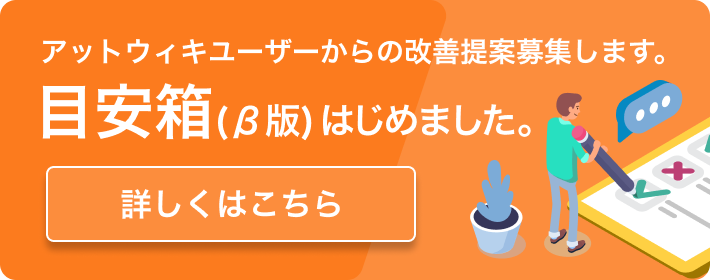「とある化け物の夢見る少女だった頃」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「とある化け物の夢見る少女だった頃」(2011/03/29 (火) 03:33:15) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
夜。
太陽が沈みほとんどの人が家に帰る時間。薄暗い路地を私は走っている。心臓がばっくんばっくんと打って要求している。動くことをやめるように。走ることをやめるように。
でもそんなこと今は聞いていられない。肺の中の酸素をすべて使い切っても、腕や足がぼろぼろになったとしても、私は走らないといけないんだ。だって、そうでしょ?
私の後ろには私を喰らわんとする化け物がいるんだから。
「……はぁ……はぁ……んく……うあ……」
口からはもうまともな言葉も出て気やしない。だらしのなく出てくるよだれもぬぐう暇さえない。ひたすら走って、走って、走るのみ。それ以外私にはどうしようもできなかった。その化け物を一目見て直感でわかった。逃げなくてはいけないんだって。理由なんてわかんない。ただ、変だ、って。そう思った。異質。異常。異なっている。根本的に私とは違うものだって。
「ん……くっ……んん……あっ!」
空き缶。どこかの誰かが捨てたのであろうそれを踏んだ。気をとられてしまい私の足は互いにもつれ合いあっけないほど簡単に転んでしまった。
「いっ……た……」
ひざ、ひじといった部分から伝わってくる痛み。すりむいたんだ、きっと。でも、もうそんなの関係ない。体はとうに限界を迎えていた。足も心臓も肺も何もかもが。立ち上がれない。動けない。逃げられない。
「いや……やぁ……」
目から涙が流れる。痛みのせいなんかじゃない。これから襲いくることへの恐怖が。私の心を芯から染めきっていた。ひたすらに怖くて、仕方がない。震えが止まらない。何もできない。
顔を上げるとそこには。
化け物が立っていた。
目が覚めると地面に寝転がっている。こんな癖、私にあっただろうか。いやない。それではなぜ。
しかし、いくら考えてもその答えは分からない。とりあえず周囲の状況を確認してみることにしてみた。
とりあえず、空が暗い。つまり夜だ。記憶に残っている最後の景色も夜であったことからそんなに時間は経ってはいないはず。
「いったい……何が……?」
服についた汚れを払い、落ちていた荷物を拾い上げる。念のため中身を見てみたが何も盗られていないみたいだ。なぜ、倒れていたのかはわからないが何事もなかったみたいなので気を取り直して家に帰ろうと、一歩前へ進んだそのときだ。
「ふぇ?」
軽い。あまりにも軽すぎる。荷物のことだけではない。とにかく体全体がまるで風船でできているのではないかと疑うほどに軽い。そのことに思わず自分でも間抜けな声を出してしまった。
「気のせいじゃ、ない……?」
実験だ。とりあえずその場で軽く垂直に飛んでみよう。
「およ?」
その場でジャンプしたにもかかわらずほとんど音が立たない。それどころか力を入れた瞬間自身の体は下から誰かに押し上げられたように浮き上がり約一メートルほど飛んでいたのだ。
おかしい。私自身体力に自信があるわけではないし過去にここまでの跳躍したこともない。というよりここまで飛び上がれるものは本当に人間なのか、とそこまで疑える。
けど数分が経過しているが特に体に痛みが出ているわけでもないしこのよくわからない力を利用するのも悪くはないかもしれない。
と、そうこうしているとのどが渇いてきた。
どこかに、自動販売機でも置いてないかな。
なんか飲みたくてしょうがない。
そうだ、珍しく紅茶でも買おう。家に帰ったら、
赤ワインでも飲もう。
「う、ううん……」
地面にうつぶせになって倒れている私。何が、あったんだっけ。とにかくいつまでも寝ているわけにはいかないし、立ち上がらないと。
「よっこら、っと……え?」
立ち上がってみてびっくりした。だって、私の着ている制服が血まみれなんだから。びっくりした私は思わず服を脱いで確認した。ここ、路地裏だし大丈夫だよね……?
「うわどうしよこれ……」
首周りから胸にかけて汚れているようでまだ少しぬれていることから時間はそこまで経っていないみたいだけど。でも、なんで?
不思議に思った私はとりあえず首をさすってみた。すると、予感はしていたが液体の残っている感触があり、その手を見てみるとやはり血でぬれていた。
「え、ていうかこれ大丈夫なの? もしかしたらやばい?」
いったい私は気を失っている間にどれくらいの血液を失ってしまったのだろう。三分の一失っただけでショック状態になるとか聞いたことある気がするけどどうだっけ?
けれども今のところ私の体に異常はないし大丈夫、なのかな。あ、服どうしよう。下に着ていたセーターは大丈夫だったからそれでいいかな。いいよね。どうせ家は近いんだし。
「帰ろうっと」
落ちていた通学かばんを拾い上げていざ歩こうと足を前に出す。うん、大丈夫。ぜんぜん大丈夫じゃん私。あれ? そういえば怪我したような気がするけど傷とかないや。まぁいいよね。それになんか変なことがあったにもかかわらずすごく気分がいい。
それにしてもなんか忘れてる気がするけど……忘れたってことはたいしたことないよね。
あーなんかお腹空いちゃった。それにのども渇いちゃったし。
あ、そういえばダイエット用に野菜ジュース買っといたんだ。
赤い、色の、野菜ジュース。
早く、飲みたいなぁ。
おそらくもし私を見ている人がいたら不審に思うだろう。浴びるようにペットボトルの中の紅茶を飲んでいる変な人がそこにいるのだから。すでに三本目。気づけば私は二千円分の紅茶を買い、そしてもう半分以上を飲み上げてしまっている。
理由はいたって簡単なもの。のどが渇いているからだ。乾いている。渇いている。干からびている。
それこそ砂漠の中にある砂のように。いくらつばを飲み込んでもその渇きは癒えず、とうとうつばさえもでなくなり紅茶をがぶがぶ飲む始末。
それでも、渇きは癒えない。それどころかどんどん酷くなる一方だ。胃の中が紅茶でいっぱいになっているだろうにもかかわらずだ。明らかに異常なこと。けど対処の仕様がない。わからない。
「飲みたい……」
何を? と思わず心で問う。もちろん答えは返ってこない。
「飲みたい……」
いいながらもその口は今もなお紅茶を含んでいるはずなのに。
「ノ……ミ……タ……イ……」
かすれた、音にもならない声が、私にだけ染み渡る。それは、まるで私自身へ私自身が要求しているように。
「AAAAAAAAAAAAAAAAA!!」
気づけば私はガムシャラに走っていた。声という音域を外れ、獣じみた叫びを放ちながら。
頭の中でささやく。甘く、芳醇に、私を誘う。
チヲ、ノメ、ト。
アタタカク、アカク、アマク、イケルモノノ、チ。
チヲ、ノメ、ト。
「ただいまー」
ドアを開き、玄関で靴を脱ぎ、家に上がる。と、ここで向こうからいい匂いが漂ってくる。それは私の鼻をくすぐって、つい反射で口の中でよだれが出てきてしまう。この匂いはたぶんビーフシチュー、なのかな。
「お母さーん、今日ってもしかしてビーフシチュー?」
「そーよー。よくわかったわねそこからー。玄関でしょ今いるの?」
そういえばそうだ。私って、こんなに鼻がよかったっけ。
「まぁいいわ。そんなことよりさっさと着替えて着なさいねー」
はーいと返事をして私は階段を上り自室へ向かう。リズムよくトン、トン、トンと。
部屋に入ってひとまず着ている服を脱ぐ。するりと衣が脱げ落ちていく。人が自分を繕うためにつけている人間としての鎧が。
今の私は下着姿。この状態で部屋の外をうろつけば確実に軽蔑の視線が私に向けられるだろう。
「軽蔑……」
って私はいったい何を考えてるの! そんなの変態じゃない変態! 露出狂じゃあるまいし……
「……あーもー! そんなことよりご飯、ご飯!」
思わず出てきた邪まな考えを振り払いちゃっちゃと着替えを済ませると部屋を逃げるように飛び出した。
「あらあら。いくらおなかが空いたからってそんなにあせらなくても誰も盗らないわ」
あまりにもどたばたと駆け下りたためかお母さんがそんなことを言い出す。息を整えながらイスに着いて料理が出されるのを待つ。
「うふふ、誰に似たのかしらねぇ。お父さんかしら?」
「もうそんなのどうでもいいよぅ……あ、それよりお姉ちゃんは?」
「多分、勉強中よ。あの子は今大事な時期だから。邪魔しちゃだめよ」
お姉ちゃん。私より二つ上で、いわゆる受験生。今、すごく忙しいみたいで、いっしょにご飯を食べることすら滅多にない。いい大学目指してるんだって。
「さ、ご飯にしましょう? 今日はビーフシチューよ? って、知ってるわよね」
「あぁもうお腹ぺっこぺこだよ! いただきまーす!」
全力で走っている私。人間では到底出せそうもないスピードで動くこの体は目的もなくただひたすらに走り回る。
むしろ、考えたくはなかった。私の頭を巡りに巡る思考回路を封鎖するために。自身がそうではなくなる恐怖。いつのまにか人道から外れたことを考え、そして実行してしまうそうな。そんな思考。
走っても走っても、逃げども逃げども、ソレが離れることなどない。なぜなら、それは私の頭の中で生きているからだ。ソレは腐っていて、それでいて、魅惑な息を私の脳髄に吹きかける。落ちてしまえば楽だろう。いや、楽に違いない。けれども、私に残されたヒトカケラの"人"が。ソレをかたくなに拒み続けていた。
走りに走って、いつのまにか路地裏の方に来てしまっていた。ここまで来るのに時間はそんなにかかっちゃいない。三分か、四分くらいだろう。それでも心臓はほとんど正常に鼓動を繰り返している。
どうかしている。普通じゃない。体も、心も。
「どうなっているのか……全くもって……」
途端。心臓の衝動。誰か、いや、何かからの非道なまでの圧力によって締め付けられている。
「アッ……ガッ……ケハ……」
止まる。心臓が。コドウが。イノチが。トマル。オワル。
「ウ、ア、コン、ナ、ノッテ……クヒッ」
カエルがひしゃげたような音を出しながら、私の体は落ちていく。路地の、冷たいアスファルトの上へ。
さようなら。
誰に言うわけでもないが、なんとなく、頭の中でそう呟いていた。
さようなら。
「あーあ。今日ももう終わりかー」
そんなことを、私はお風呂場で誰に言うわけでもないけど、言っていた。
「また明日も学校……あー休みたーい」
口ではこうは言っているが、実際は冗談だ。
もしも、明日いきなり台風が来て学校にいけなくなったりとか、大雪が降っていけなくなったりとか、インフルエンザが急に流行って臨時休校になったりするんだったらいいけど。
どうせ、そんなことはおきっこないんだから。だから、半ば諦めがちに学校に通っている私。
いかなきゃいけない。そう自分に言い聞かせて、毎日、登校する。
「はぁ。やんなっちゃうなぁ」
私は普段はこんなこと、考えない。だってせっかくの晴れてる心も一気に台無し。曇り空。
そういえば私、なんでこんなこと考えちゃったんだろ……?
「う~……あぁもう! 分かんないからパス!」
ぱしゃとお風呂の中に顔だけ潜ってネガティブな思考はシャットダウン。ぶくぶくぶくと泡が出ている。ほんとはお行儀悪いけど誰もいないんだから気にすることはないよね。
「おーい、いもうと~」
「っひゃあ!」
予想だにしていなかったのは私も姉ちゃんもおんなじみたいで向こうも驚いたようで。
「ちょ、ちょっと何、大丈夫!?」
「あ、ごめん驚いちゃってそれで……えへへ」
「まったく……どうせあんたのことだからお風呂でぶくぶくしてたんでしょ」
ばれてる……
「ど、どうして分かったの?」
「だって昔はよくいっしょに入ってたじゃない。あんたいつもやってたし」
「そんなにしてたっけ?」
「してたしてた。それはもうぶくぶくぶくぶく。しまいにはよく母さんにしかられたかな」
そういえばもう何年くらい入ってないのかなお風呂。小学校くらいまではいっしょに入ってたけど二人とも中学にあがってしばらくしたら、いつのまにか入ることはなくなってた。
「いつのまにか、いっしょに入ることなくなったよね」
「え? ああ、そりゃいつまでもいっしょってわけにはいかないでしょ?」
「まぁそうなんだけど……あ、そういえばさっき私のこと呼んだけどなんだったの?」
「いきなり話が変わったわね……そういえば、なんだっけ。ああ次私入るからって言おうとしたのよ」
「なんだ、それだけなのか」
「あのねぇ……それだけなのに話を伸ばしたのはあんたの方でしょ」
「えへへ、ごめんごめん。もうちょっとしたらあがるから」
ほんとに頼むわよ、と言うと姉ちゃんはそのまま洗面所を立ち去っていった。
私も、もう上がらないとね。
もちろん風呂上りは、ダイエットのためのトマトジュースを思いっきり飲み干す。
いつもは、にんじんジュースだけどね。そういう気分なんだ。
そういう、ね。
一つの体が、そこにあった。
薄暗く、ひんやりとした空気がじめっと肌に触るそこはいわゆる路地裏と呼ばれている場所。
その体はピクリとも動きはせず、もしも誰かがそれを見たら救急車を呼ぶかそれともその状態を確かめに行くか。人によっていくらでも取る行動はあるだろう。
だが、もし勘の鋭いものがそれを見たとしたら。おそらくほとんどの者がこうするだろう。
"全力で逃走する"
しかし幸か不幸かそれを目撃したものは誰一人としていなかった。
"それ"が、至って平然と立ち上がる姿を目撃したものも。当然いなかった。
「けひ……キひゃ……」
鳥か獣がか細く啼いたような、そんな音が体の口から洩れた。
体は、周囲に散乱していたプラスチックの群れを全く認識していないのか。踏み、蹴散らし、時にはすっ転びそうになりながら。その場を後にしようとした。
そのとき、体はその動きを停止し、辺りを見回し始めた。
当然その辺にゴミ屑同様に撒き散らされているプラスチックの塊を探しているわけではない。
鼻をヒクヒクと震わせて、何かのニオイを嗅ぎ取ろうとしている。
と、ある一点を向くと、それらの動きを全て停止させた。
そこには、女がいた。
制服を着ていて、通学かばんと思わしき物から携帯電話を取り出している。どこから見ても学生なのは明らかだった。
しかしそんなことはカレにはなんの関係もなかったのだった。
「あ、メール。 なんだお母さんか。 えっと……"ご飯できたから早く帰りなさい"……はいはい。わかってますよーだ」
少女は、そのメールを読み終わるとすぐさまその返事を打ち込み始めた。
「"りょーかいいたしましたお母様。すぐさま帰宅いたします"……っと」
内容を打ち終わりそれを送るべく送信ボタンを押す。携帯電話の画面には、紙が折られ紙飛行機になり、それが飛んでいくという映像が流れている。それが三度ほど繰り返されたとき、画面には"送信完了"の文字が映っていた。
「もぉーこのぐらいでいちいちメールなんか送ってこなくていいのにー」
そう言いながら携帯電話を折りたたむとかばんの中にテキトーに突っ込んだ。
家に帰ろうと、視線をかばんから戻すべく顔を上げると
そこには、見たこともない男の顔があった。
「あーやっぱりお風呂上りはこれだよねー!」
お風呂から上がって早速私はトマトジュースを飲み干していた。よく友人などからは味の事をたびたび聞かれるけどそれはまったく問題ない。なぜならこのトマトジュースを含んだ野菜ジュース類は母が考案しそして何度も行われた細かい調整でようやく完成したジュースなのだ。(そのときの失敗作は私たち姉妹が強制的に始末させられたのだけど)もちろんまずいわけはない。
「そう言ってくれるとこっちも嬉しくなるわねー」
キッチンの流し台でお母さんは今日の晩御飯に使われた食器を洗い流している。手伝ってあげようかとも思ったけど私がお風呂に入っている間にほとんど終わってしまっていたようなので今日はやめておいた。
「それにしてもまたパパ帰りが遅いわ……ここのところいつも残業ばっかり。食事用意してるこっちの身にもなってほしいわ!」
そう言うとお母さんは頬を膨らませる。いい年してるのにって突っ込むと怒られるからしないけど。
「でもさぁ、そういうときって普通先に言っておくもんじゃないの?」
「確かにそうなのよね……ま、今日はたまたま残業が入っちゃったってことにしておくわ。そして食器洗い終了っと」
見てみると確かに流し台には一枚も食器は残っておらずそして全てがきれいに拭かれていた。
と、突然お母さんが欠伸をし始めた。それを見て思わず私も欠伸がうつってしまった。
「あらもう欠伸する時間帯……? 一日ってほんと短いのよね」
背伸びをしながらそんなことを言うお母さん。言ってることは共感できるけど。
「じゃ、私もう寝ちゃうから早百合もさっさと歯磨きして寝なさいね?」
「は~い」
口ではこうだけど実際はそんな気は毛頭ない。だってテレビ見るんだもん。夜更かしは学生の特権なんですって誰か言ってた気がするし。どうしても見たいし。別にいいよね。
すでにお母さんは自分の寝室に移動している。つまりここのテレビ独占し放題。バレると後が怖いけどね。
前に友達に聞いたんだけどわりと自分の部屋にテレビがある人も多いらしく私としては羨ましいの一言。ズルイぞ。
「さてさて、まずはスイッチを……オン!」
プツン、というなんだか歯切れのいい音がなり徐々にテレビの画面が明るくなる。なんかこういう瞬間ってドキドキするの私だけ?
「おっとっと音を下げて……っと。これでよし。何から見ようかな……」
そのとき、あまりテレビから聞くことのないプーンという音が二度すると、画面上部にはニュース速報の文字が流れている。
「こんな時間に速報かー。あれかな。地震とか?」
というより他に思いつかなかっただけなんだけど。
ゆっくりと流れてくるニュース。しかし私の予想に反して、"地震"の二文字はなく。代わりにこの二文字が流れていた。
「殺……人?」
"連続猟奇殺人事件"
普段全くお目にかかることのない文字が勢ぞろいで、私の目に飛び込んできた。
薄暗かった路地に月明かりが差し込む。
劇場の舞台にスポットライトが当てられたように、彼らに光が当てられる。
うつ伏せに倒れた少女と、そこに馬乗りになって少女に抱きついているように見える男。
月明かりの美しさ。それによりさらに極まるその行為から垣間見える異常さ。
よく見れば少女の首筋から血が流れており男はおぞましくもその血を音を立てながら啜り飲んでいた。
「キヒ……キヒヒヒャハ……」
ユラリとよろめきながら立ち上がる男。
淡い青色の月光と、病的なまでに白い肌と、口元にべったりと付いた赤朱色のコントラストはどこか芸術的な絵画のような。そんな印象を思わず抱いてしまうほど、月明かりは美しかった。
「ヒヒヒヒャハハハハハハハ……ヒヒハハハハハハハハ!!」
ケタケタとニヤニヤ笑いながら上に、空に向け、高笑う男。
一度膝を曲げたかと思うと普通では考えられない跳躍で跳び上がると、そのままこの場を風のように去っていった。
男の高笑いは、いつまでもその場にこだまし続けていた。
この倒れている少女が起き上がるのは実にそれから数分後のことである。
しかし一方で、こことは違う場所に話は移る。
「んで、着いた訳なんだよな。相棒?」
「……相棒というのは止して頂けませんか。一応、指揮権は僕にあるので」
そこには、二人の人間がいた。
ただいるだけならばそこまで気にすることはない。問題は彼らの見た目である。
まず一人は、長身で赤色の髪、銀色に輝くそれは見事な鎧を装着し、腰には長めの剣と思わしきものまで差している。
もう一人は、低身長気味で水色の髪、鎧とまではいかないが丈夫そうな革服と胸当てや肘当てといったものを装備し、腰には先ほどの剣よりぐっと短く、おそらくレイピアのようなものを差していた。
二人が並ぶとその身長差はよりはっきりと目立ち、もう一人の方はまるで子供のように思えて仕方がない。
「まあなあ、そりゃこんな見た目じゃどっちが上かなんて人目見ただけじゃ見抜くのは一苦ろ」
「それ以上僕の容姿について言及するということは覚悟ができていると思っていいんですよね?」
ジロリと睨むその蒼眼に思わずたじろいでしまう長身の人。流石にこれはまずいと咄嗟に言い繕う。
「あっははははは……冗談っすよ冗談……ったくちょっと触れただけですぐコレなんだからよ……」
「何か、言いましたか?」
ボソッと呟いた筈の文句が耳に届いたのか、相手には見えぬよう苦々しい顔をしながら返事を返す長身の人。
「いえいえほんとになんでもありませんよほんとうに?」
「……どうやら、任務より先に上の者への口の聞き方を教育しなければならないようですね?」
長身の人、それを聞くと今度は深々と頭を垂れ、実に丁重な雰囲気で言葉を述べ始める。
「……先ほどからのご無礼お許しください。どうやら自分は初任務に舞い上がり多少冷静な判断に欠けていたようで……」
低身長の人、一つため息を吐くと、怒る気力がなくなったような、それでいて重々しく。
「あなたの言葉に付き合っても無意味なので、この件はなかったことにします。ですが」
「もちろんこのことは今後一切口には出しません。誓ってでも」
「よろしい。それじゃ早速行動を開始します」
そういうと、彼らはその場を後にした。
後に残ったのは、ただ静けさばかりだった。
私は、テレビの画面に釘付けになっていた。
そのとき流れていた映像は全てどこかに吹き飛び、映るのは文字だけだった。
"今日午後10時ごろ、浦歩市内で血まみれの死体を見たという人が相次ぎ警察が調査をしたが死体は見つからず
見間違いだと思われていたが一人の警官が死体を発見したと通信機で同僚に報告したがその警官は行方不明に
現在その警官を捜索するとともに今回の騒動の真相を探っている"
「血まみれ……」
そう、私にも覚えがある。あのとき、路地で倒れていたとき。私は少しではあったけれど血が流れていた。
もしかして、何か関係があるのだろうか。そのときの記憶はあいまいなんだけど……できるなら思い出したくない。
なぜかはわからないんだけど、怖い。思い出そうとすると、黒い影がチラチラと頭を横切る。怖くって仕方ない。
「こらっ!」
「ひゃあ! テレビ勝手に見ててごめんなさいごめんなさいごめん」
「バーカ、わたしだよわ・た・し」
後ろから突然怒鳴られた私は思わず自分でもマヌケなほどに飛び上がってしまった。
見てみればお母さんじゃなくてお姉ちゃんだし。
「もう……脅かさないでよ」
「あっはははごめんごめん。あんまり真剣になってテレビ見てるからつい」
「つい、じゃないよもう。ほんとに心臓止まるかと思った」
「悪かったって、ごめん。んで、何か面白そうな番組でもあったの?」
連続殺人事件があったんだってー、なんて、言えるわけない。勉強に集中したいだろうし。それに今私が言わなくたって明日のニュースとかで見るだろうし、今言うべきことじゃないと思った。
「え、あ、ううん……別になかったよ」
「え~? 本当かな~? あんなにまじまじ見てる早百合珍しいと思ったけどね~?」
「ほ、本当だよ! そ、それよりお姉ちゃんは何しに来たのさ!」
なんか私ってごまかすのが下手な気がする……けど、お姉ちゃんはそのことを気にした様子もなく答えた。
「私? いやちょっとのどが渇いたからさ。ジュースでも飲みにきたってわけ」
「そっか。ところでなに飲むの?」
「もちろん母特製スペシャルジュースに決まってるでしょ! あれ美味しいんだよねー」
スペシャルジュースというのはお母さんがお姉ちゃんの健康を気にして作り出したある意味おねえちゃんのためのジュースだ。そのせいかお姉ちゃんもそれを一番のお気に入りにしているみたい。
「やっぱりそうだと思った。あーあ私ものど渇いちゃったなぁ」
「じゃあ飲めばいいんじゃない?」
「だって入れるのめんどくさいし……あ、そうだお姉ちゃんついでに私のも入れてよ」
「やーだよめんどくさい自分でやりな」
「むー、けちー」
「それに私の分はすでにやっちゃったからね」
気づくとお姉ちゃんはすでにコップを持っていてその中にはオレンジ色の液体が入っている。いつのまに。
仕方がないのでぶつぶつ文句を言いながらも私はキッチンの冷蔵庫に向かう。すぐそばでお姉ちゃんが飲んでいる。どう見ても私に対するあてつけだ。全く私の分くらい入れてくれたっていいのに。
とりあえず何を飲むか選ぼう。えーと、うーむ、そうだ。トマトジュースにしよう。お風呂上りにも飲んだけど。
「お、トマトジュースなんて珍しいね。もしや、ダイエット中?」
私が冷蔵庫からトマトジュースの入ったボトルを取り出しているとそんなことを言ってきた。
「違うよ! なんていうか気分?」
「ふーん。あっそ」
それだけいうとさっさとまたジュースを飲み始めた。私も気にしないでさっさと飲むことにした。
不思議と飲み終わるのに大して時間はかからなかった。大きいコップを使ったはずなんだけどな。
隣を見るとお姉ちゃんがまだ飲んでる。
そういえばお姉ちゃんって結構スタイルいいんだよね。でもモテるなんて話し聞いたことないなぁ。
細い。お姉ちゃんの体って。よくこんな体で生きていられるよね。
ほんと、この首なんて、力を入れると折れてしまいそうで。
「ん? どうしたの?」
「っ!?」
急に振り返ったお姉ちゃんに気づいて慌てて私は手を引っ込んだ。
今私なに考えてたの? どうしてお姉ちゃんの首を触ろうとしたの?
「あ、う……」
「さ、早百合? どうしたの、顔色悪いよ?」
「ご、ごめんなんでもない……ちょっと外の空気、吸ってくるね」
「あっ、早百合!」
一分一秒も早くこの場から逃げ出したかった。何もかもが恐ろしくてたまらなかった。何より、私自身に。
私……いったいどうなっちゃったの?
「ったくキリがねぇぜこりゃあよ!」
「確かにこのままでは埒が明きませんね」
人通りの少ない少々寂れた商店街。そこに普段より多くのニンゲンがいた。
いや、正確にはニンゲンの形をしたモノ。とでもいえばいいのだろうか。
なぜなら彼らの動きは明らかに人という枠を超えたまさしく人外と呼ぶに相応しいものでまたそれに対峙している二人も人智を超えた目を疑うような光景を繰り広げていた。
剣を持つ二人の人間に対して老若男女の七体の化け物。しかしそのうちの三体はどういうわけか氷漬けにされている。
残りの四体はバラバラの動きで二人を仕留めようと彼らに襲い掛かる。あるモノは上から、あるモノは回り込んで後ろから、またあるモノは正面からとそれぞれの動きはバラバラながらもそのどれもが強力なパワーで攻めてくる。
それを主に捌いているのが長い剣を持った男。ときどき捌ききれないのがきたらもう一人と見事な連携で立ち回っていた。
「そこまで冷静に言うかフツーよォォ! アイツらはまだ7体もいるんだぞ!?」
「……ちょっと時間を稼いでください。まず僕が奴らの足止めをします……十数秒ほどですが」
「それで! どんくらい! 持たせりゃ! いいんだ!」
そういっているうちにも相手は休むこともなく攻め続けてくる。それを切り払ったり押し返したりしながら長身の男は聞いた。
「そうですね……20……いや15秒持たせてください。何とかしてみせます」
「何でもいいから早いとこ足止めって奴を! こっちは持ちそうにねぇんだぞ!」
「わかりました!」
そういうと手に持っていたレイピアに形状の似た剣を何かの絵を描くかのように振り回し始めた。
そしてさらに何かを唱えている。
水の神よその偉大なる業を我の前に示し給えいかなる時であろうとも我と共に在れ――――
イル・オン・ディヌ・ミカノズミ――――
「フリージス・ミストッ!!」
その言葉を唱えると、化け物たちの周りを薄い霧のようなものが包み込み始める。
それを意に介せず再び攻撃を仕掛けようとする化け物だが、不思議なことにその体は全く動こうとしない。いや、動こうにも動かすことができないのだ。なぜなら、その体は瞬く間に凍りついているからだ。
そして、数秒もしないうちに七個の少々気味の悪いオブジェが出来上がっていた。
「ふぃー。助かったぜぇ……」
「僕は今のうちに次の呪文に取り掛かります。ですから……」
「んなことはわかってんだよォ!!」
そう言うと再び剣を構えなおし七個のオブジェどもへと向かって駆け出した。
しかし、普通ならば凍っている物を斬るというのは簡単なことではない。が、長身の男はそれを気にしている様子はない。
「見せてやるよ。俺のフレイム・エンチャントの力を!」
突如、彼の持っている剣を包み込むように淡い火が出たかと思うと、瞬く間に紅蓮に揺らめく炎へと変わった。それは一見、その剣自体が燃えているようにもとれるがそうではない。あくまでも剣の周りに炎が現れたに過ぎないのだ。
「アンタには悪いがよ、跡形もなく消えてもらうぜ? 後始末が面倒なんでな!」
一番近くにいた化け物へ、紅蓮の剣を頭部へと、振り下ろす。
その炎は、氷を、髪を、皮膚を、肉を、骨を、脳を、何もかもを、焼き尽くした。
剣が完璧に振り下ろされたそのときには、そこにオブジェはなく、ただ少量の水と炭が下に落ちていた。
「か~、やっぱり俺もまだまだって奴か……なんて、無駄口言っている場合じゃねぇな!」
そして彼は突撃する。残りの化け物どもを殲滅するために。
と同時に彼は気づいていた。化け物どもを封じ込めている氷がすでに融け始めていることに。
それでも彼は走る。自身の任務を遂行するために。何より、彼と共にきた相棒を死なせないために。
「オラオラオラァァァッ!!」
横に、縦に、斜めにと剣を振る。化け物は一体、また一体と焼失していく。だが、よく見ると彼の剣を包んでいたはずの炎が化け物を斬るたびにだんだんと弱まってしまっている。それに伴って彼自身も、たった数回剣を振っただけなのにも関わらずまるで全力疾走で400mを走ってきたように呼吸が荒くなってしまっていた。
パキィンといった、何か薄いものが割れるようなそんな音が響いた。
見ると化け物どもは自分を覆ってしまっているその氷を、強引に力業で破り、体の自由を取り戻していた。
そして、長身の男を獲物として確認すると、三体の化け物が、彼に向かって襲い掛かる。
それに対する彼は疲労困憊してしまっているのか剣を構えることもなくだらりとした様子でうつむいていた。
「後は任せても、いいんだよな?」
「ええ、もちろんです」
化け物どもの頭上。そこには、コンクリートなどで固められた巨大な塊ができあがっていた。
よく見れば周囲にある建物の一部の壁などが大きく削れていたり剥がれていたりしている。
重力の影響を受けてそれが落下すると、下にいた化け物どもはその塊に押し潰されてしまった。
「……俺たちの完全勝利……ってところ、だな」
「どうも危なかったようにも見えたのは気のせいですか?」
「あ、あれはほら、演出だ! 演出!」
「その割には本当に疲労していたように見えましたけど……まぁそれはそれとして」
と、ちらりと巨大な塊を見やると困ったような顔をする。
「これ、放置しておくにも行かないので後片付けお願いしますね」
「ちょちょ、おい! さっきの戦いで疲れてるんだぞ! できるわけないだろ!」
「あれ? それは演出じゃなかったんですか?」
「ぐ……わかったよやるよやればいいんだろ! クソ!」
「口の利き方」
「りょ、了解しました……」
「あの塊は僕の方で解除しておきますのでそれの片付けと下敷きになってる体とかも焼いてください」
「……人使い荒くないか」
「それじゃがんばってくださいね」
そこまで言うと言いたい事は全て言ったとでもいうようにその場を離れ商店街の出口の方向へ歩いていく。
「あ、おいちょっと待て……畜生、後で覚えてやがれよ……」
振り返ってその巨大な塊を見て、しばらくそれを眺めているだけだったが、一言だけボソッと呟いた。
「あぁ……帰りてぇ」
「あぁ……帰りたいよもぅ……」
あのとき、お姉ちゃんから逃げ出した私は家から飛び出して当てもなく一人町を彷徨っていた。
流石にパジャマで出たわけじゃないけどそれでも薄着で寒い。玄関にかけてあったコートを着て出たけどそれでも寒くて仕方ない。
「でも、あんなことがあった後で帰れるわけないじゃん……」
自分で自分が、いやになる。ていうか、本当に私はどうしちゃったんだろう。さっきから変なことを考えてる。
家に帰る前も、家に帰ったときも、お風呂のときも、お姉ちゃんのときも。
「ほんとなんでなのかなぁ」
そう口に出してみたけど、本当は違う。心の奥深くで、誰かが叫んでる。今はまだ小さくて聞こえないけど薄々気づいてる。
ただそれに耳を傾けたくないだけなんだ。だって、それを聞いてしまったらもう。
今の私に戻れないような気がして。
「……あ、ここ……」
考え込んでて気づかなかったけど、私はここを知っている。
錆付いてしまったアーチ上の看板と、両端にたくさんのお店が並んでいて。
小さいとき、それも保育園とか小学生のときにお母さんに連れられ一緒に買い物に来た商店街。このころはまだお姉ちゃんとも一緒だったっけ。
「まだあったんだこの商店街……看板が錆びちゃってて何ていう名前なのか結局今もわかんないけど」
子供の頃の足だとなんだか遠く感じていたこの場所も、今となっては数分で着いてしまう。そのことを思うとなんだか感慨深いような気がした。
懐かしさに誘われるままに私は商店街の通りへと歩みを進めていた。右に肉屋さん、左に八百屋さんとそれこそテレビや漫画で出てきそうなそんなお店が立ち並んでいる。他にも居酒屋さんとかあるけどそのどれもが古臭さを感じさせるほどに壁がひび割れていたりシミができていたり。
しばらく歩いていると少し奇妙な物を見つけた。大小と様々な大きさの瓦礫が道路に散らばっているのだ。周囲を見回してみると付近の建物の壁が所々壊れていておそらくそれが瓦礫となったのだろうと考えられるけど。
「でもなんで? 地震とかあったわけじゃないし、普通こういうのって誰かが片付けるもんじゃ……」
いくら考えても答えなんか出るわけもなく。ただむなしく時間が過ぎるだけ。
「というか寒っ……流石にちょっと薄着だったかなぁ」
いつまでも外をぶらぶら歩いてたって仕方ないよね。うん、いい加減帰らないとね。お姉ちゃんも心配してるよきっと。
そう思って今まで来た道を戻ろうと、振り返る。振り返った私の視線の先に誰かがいる。見た感じ男の人だ。でもなんだろう。私はこの人を知っている……というより、見たことがある……?
アレコレ考えているうちに男の人はこちらの方向に近づいている。おぼつかない足取りというか少しふらつきながら。お酒でも飲んで酔っ払ってるのかな。なんて考えていた。
それは、あっという間の出来事。気が付いたそのときには男の姿が消えていて。
私が状況を把握しようとしたそのときには男の姿が目の前に現れていて。
「あ……あ……」
思い出しかけていた記憶が一気にフラッシュバックした。私は帰り道の途中に出会っていたんだ。あの化け物に。
そして、小さくもはっきりと聞こえてしまったんだ。
チヲ、アタタカイチヲノメ、って。
男の顔が月明かりに照らされる。あの時見たのと変わりのない青白い顔。でも、一つだけ違っていたものがあった。
それは、私がそれを見ても。
異質だとは感じなかったことだった。
「ちょっと横にズレてもらえるかいお嬢さんよ!」
大きく響き渡る男の人の声。でもそれは目の前の化け物から発せられたものじゃない。むしろ後ろから聞こえている。
咄嗟の判断で横に飛びのいた私は慣れないことをしたせいか転んでしまった。
「いったた……そ、それより、今のは一体何?」
化け物がいる方を見てみるとそこには変な格好をした人がいる。鎧とか剣とか着けて、髪も赤いし、まるでどこかのゲームから抜け出してきたんじゃないかと思うほどの格好。どんなコスプレでもここまで精巧にはできないんじゃないか。
茫然自失としているともう一人、私の方に近づいてくる。
「大丈夫、ですか」
小さめの身長で青い髪をした人が話しかけてきた。私と同い年、いやもしかしたら年下かも……
「う、うん大丈夫……というかあの人助けなくてもいいの?」
「ええ、どうせ相手は一体、問題ないでしょう。それに、あの人元気が有り余ってるみたいですしね」
「?」
くすくすと笑ってるのはちょっと理由はわかんないけどとにかく問題ないらしい。
それにしても不思議だ。本当に私は現実を見ているんだろうか。人が剣を振り回して化け物と戦うなんて。とてもじゃないけど信じられない。
そもそもこの人たちは一体何者なんだろうか。
「あの、あなたたちは一体……」
「何者か、ですか。確かに気になることです。しかし言ってしまってもいいのか……」
「言っちゃってもいいんじゃねーの?」
いつの間にか、赤髪の人はすでに化け物を倒してしまったようだ。化け物の姿はもうどこにも見えない。何をしたのか見てればよかったかな。
「今回のことを含め、私たちの存在は知られてはならないと言われているのを忘れましたか?」
「だけどよ、もう完全に色々見られちまったし手遅れじゃないか?」
「忘却の術を使えればいいのですが生憎僕は使えませんしその術者はいるのは向こう側ですからね。事態を軽く見すぎていました」
なんだか、私を置いて話がどんどん進んじゃってるけど、どうもこの人たちとは関わってはいけなかったみたいで……
あれ? もしかして私大変なことに巻き込まれてるとか……?
「あと、もう一つ気がかりが残ってるんですよ。彼女について」
「え? わ、私?」
「ええ。そうです」
「おいおい。別にこの子は単なる一般市民ってやつだろ? 特に気になることなんてないんじゃあ?」
そう。私はどこかの秘密捜査官でもないしスーパーヒーローってわけでもない。これといって目をつけられることなんてないはずなんだけど。
ただ、今私が気になっている点を除けばの話だけど。
「なぜあなたは生きているんですか?」
いきなり何を聞いているんだろう。なぜ生きてるって言われても説明できないんだけど。
「なぜ生きてるって言われても……心臓が動いているから?」
「いえ、そうではなく、あの怪物を前にしてなぜ生き延びているかということです。何の力もないはずのあなたが、どうしてです?」
「そ、それは……」
言ってしまってもいいのだろうか?
私が抱いている一つの仮定。それはとても不確かなものだし誰かに言ったとしても信じてもらえそうにもないほどだ。
でもこの人たちなら?
どこかのゲームや漫画から抜け出てきたような「まるでファンタジー世界」なこの人たちなら?
いやでも待って。この人たちの目的はどうみてもあの化け物を退治すること。
もし、もしも私がその仮説を話しちゃったら……
「ん? そりゃ単純に俺たちの発見が早かったからだろ? 何の問題も」
「1分40秒。私たちが彼女を発見してからそこに向かうまでの時間です」
「それがどうかしたのか? というかよく計れたな」
「効率的に考えるのは重要なことだと思っていますから。そんなことより問題はその時間です。考えてみてください。あの怪物たちは満たされることのない欲求を満たすために常に獲物を探し回っているんですよ。そこに格好の相手が現れたら。もうわかりますよね」
「……おい。そりゃ本気で言ってる、ってのかよ……」
「はい。本気も本気ですよ僕は」
そして、ゆっくりと私の方へ向き直る。ああ、とうとう言われてしまうんだ。でも不思議だ。そのことに対しての恐怖はないのだから。
きっと薄々自分でもわかっていたから。今まで悩んでいたのはそれを受け入れる勇気がなかったからなんだって。
これが私の出した結論の答えあわせだ。
「あなたは……恐らくあの怪物と同等の存在。つまり……」
――吸血鬼、なんですよ。
覚悟はしていた。そうであろうとは思っていたし受け入れようとも思っていた。だけどやっぱり現実って言うのは思い通りになんて行くわけはなかったようで。はっきりと明確に告げられた解答を聞いた私は内心、というかすでに足まで震えて動揺しまくりだった。
「ちょっと待て! もし彼女がそうだとして、だとしたら今頃彼女も人を襲ってるんじゃないのか!?」
「恐らくと言ったのはそこが気になるからです。こればかりは彼女から聞き出さないといけないんですが……いいですか?」
その「いいですか」というのが自分にあてられたものだと気づいた私は慌てて返事を返す。
「は、はい。 といっても私自身も混乱してるから説明しにくいんだけど……」
私はこれまでのいきさつを彼らに話した。
帰り道の途中に化け物、彼らの言う吸血鬼に会ったこと。
家に帰ってから変な思考が浮かんでしまうこと。
お姉ちゃんを傷つけてしまいそうになったこと。
家を飛び出してあの吸血鬼と再び会ったこと。
全てを話し終わると彼ら二人はなにやら考え込んでいるようだった。
「なぁ、これってどういうことなんだ?」
「彼女の話から思うに吸血鬼に咬まれているのは間違いないでしょう。ですがどういうわけか彼女はこうして正気を保っている。といっても非常に足場の悪い状態ですが」
「吸血鬼化するのは個人差はあってもほとんどの人間が一時間以内でなることは確認されてるんだろ?」
「はい。しかしすでに数時間は経過してます。通常ならありえないことですが彼女に限っては例外のようです」
「それってこの子は吸血鬼にならないってことか?」
「それは違うでしょう。現に襲われてませんしそれにそれらしい症状のようなものも出てるようですしね」
「だったらいったい……」
「ただの仮説にしか過ぎませんが、もしかしたら彼女には"抵抗力"があるのかもしれません」
「"抵抗力"……?」
あれ、なんだろう。眠くなってきちゃった。ああそういえば今って深夜なんだっけ。とんでもないものを見たせいで忘れてた。
それにしても私が吸血鬼か。人の、もう今は人じゃないみたいだけど。人生っていうのはこうも簡単に変わっちゃうのか。
ごめんねお姉ちゃん、お母さん、お父さん。私もう会えなくなっちゃうかも。
特にお姉ちゃんには、一言謝りたいなぁ。
ごめんって。一言でいいから。
ああ、コレが実は夢で起きたらベッドの上。
ってならないよねうん。
さようなら。みんな。
「一種の抗体みたいなものがあると思っています。だからこそああしていられるのでしょうね」
「……んで、どうするんだい。この子をさ。気が付いたら名前も聞かないうちに眠っちまってるし」
「抗体があろうとなかろうと連れて行くのは決めていました。色々と見られてしまいましたし、それに……」
「それに……なんだ?」
「い、いえ何でもありません! き、気にしないでください!」
「その慌てっぷり……なかなかレアだな」
「そんなニヤニヤと僕のことを見ないでください! み、見ないでったら!」
「クックック……いやぁ今日はいい物を見られたな本当」
「い、いつか酷い目にあわせてやるんだから……!」
――先日起こった奇妙な失踪事件についてのニュースです。新しく入った情報によりますと現時点で失踪者数は40名を超えており今回の調査で新たに、東野 輝美さん、岡島 正志さん、中山 治朗さん、下塚 早百合さん、吉山 晴海さんが今回の事件に関係していると――
終
夜。
太陽が沈みほとんどの人が家に帰る時間。薄暗い路地を私は走っている。心臓がばっくんばっくんと打って要求している。動くことをやめるように。走ることをやめるように。
でもそんなこと今は聞いていられない。肺の中の酸素をすべて使い切っても、腕や足がぼろぼろになったとしても、私は走らないといけないんだ。だって、そうでしょ?
私の後ろには私を喰らわんとする化け物がいるんだから。
「……はぁ……はぁ……んく……うあ……」
口からはもうまともな言葉も出て気やしない。だらしのなく出てくるよだれもぬぐう暇さえない。ひたすら走って、走って、走るのみ。それ以外私にはどうしようもできなかった。その化け物を一目見て直感でわかった。逃げなくてはいけないんだって。理由なんてわかんない。ただ、変だ、って。そう思った。異質。異常。異なっている。根本的に私とは違うものだって。
「ん……くっ……んん……あっ!」
空き缶。どこかの誰かが捨てたのであろうそれを踏んだ。気をとられてしまい私の足は互いにもつれ合いあっけないほど簡単に転んでしまった。
「いっ……た……」
ひざ、ひじといった部分から伝わってくる痛み。すりむいたんだ、きっと。でも、もうそんなの関係ない。体はとうに限界を迎えていた。足も心臓も肺も何もかもが。立ち上がれない。動けない。逃げられない。
「いや……やぁ……」
目から涙が流れる。痛みのせいなんかじゃない。これから襲いくることへの恐怖が。私の心を芯から染めきっていた。ひたすらに怖くて、仕方がない。震えが止まらない。何もできない。
顔を上げるとそこには。
化け物が立っていた。
目が覚めると地面に寝転がっている。こんな癖、私にあっただろうか。いやない。それではなぜ。
しかし、いくら考えてもその答えは分からない。とりあえず周囲の状況を確認してみることにしてみた。
とりあえず、空が暗い。つまり夜だ。記憶に残っている最後の景色も夜であったことからそんなに時間は経ってはいないはず。
「いったい……何が……?」
服についた汚れを払い、落ちていた荷物を拾い上げる。念のため中身を見てみたが何も盗られていないみたいだ。なぜ、倒れていたのかはわからないが何事もなかったみたいなので気を取り直して家に帰ろうと、一歩前へ進んだそのときだ。
「ふぇ?」
軽い。あまりにも軽すぎる。荷物のことだけではない。とにかく体全体がまるで風船でできているのではないかと疑うほどに軽い。そのことに思わず自分でも間抜けな声を出してしまった。
「気のせいじゃ、ない……?」
実験だ。とりあえずその場で軽く垂直に飛んでみよう。
「およ?」
その場でジャンプしたにもかかわらずほとんど音が立たない。それどころか力を入れた瞬間自身の体は下から誰かに押し上げられたように浮き上がり約一メートルほど飛んでいたのだ。
おかしい。私自身体力に自信があるわけではないし過去にここまでの跳躍したこともない。というよりここまで飛び上がれるものは本当に人間なのか、とそこまで疑える。
けど数分が経過しているが特に体に痛みが出ているわけでもないしこのよくわからない力を利用するのも悪くはないかもしれない。
と、そうこうしているとのどが渇いてきた。
どこかに、自動販売機でも置いてないかな。
なんか飲みたくてしょうがない。
そうだ、珍しく紅茶でも買おう。家に帰ったら、
赤ワインでも飲もう。
「う、ううん……」
地面にうつぶせになって倒れている私。何が、あったんだっけ。とにかくいつまでも寝ているわけにはいかないし、立ち上がらないと。
「よっこら、っと……え?」
立ち上がってみてびっくりした。だって、私の着ている制服が血まみれなんだから。びっくりした私は思わず服を脱いで確認した。ここ、路地裏だし大丈夫だよね……?
「うわどうしよこれ……」
首周りから胸にかけて汚れているようでまだ少しぬれていることから時間はそこまで経っていないみたいだけど。でも、なんで?
不思議に思った私はとりあえず首をさすってみた。すると、予感はしていたが液体の残っている感触があり、その手を見てみるとやはり血でぬれていた。
「え、ていうかこれ大丈夫なの? もしかしたらやばい?」
いったい私は気を失っている間にどれくらいの血液を失ってしまったのだろう。三分の一失っただけでショック状態になるとか聞いたことある気がするけどどうだっけ?
けれども今のところ私の体に異常はないし大丈夫、なのかな。あ、服どうしよう。下に着ていたセーターは大丈夫だったからそれでいいかな。いいよね。どうせ家は近いんだし。
「帰ろうっと」
落ちていた通学かばんを拾い上げていざ歩こうと足を前に出す。うん、大丈夫。ぜんぜん大丈夫じゃん私。あれ? そういえば怪我したような気がするけど傷とかないや。まぁいいよね。それになんか変なことがあったにもかかわらずすごく気分がいい。
それにしてもなんか忘れてる気がするけど……忘れたってことはたいしたことないよね。
あーなんかお腹空いちゃった。それにのども渇いちゃったし。
あ、そういえばダイエット用に野菜ジュース買っといたんだ。
赤い、色の、野菜ジュース。
早く、飲みたいなぁ。
おそらくもし私を見ている人がいたら不審に思うだろう。浴びるようにペットボトルの中の紅茶を飲んでいる変な人がそこにいるのだから。すでに三本目。気づけば私は二千円分の紅茶を買い、そしてもう半分以上を飲み上げてしまっている。
理由はいたって簡単なもの。のどが渇いているからだ。乾いている。渇いている。干からびている。
それこそ砂漠の中にある砂のように。いくらつばを飲み込んでもその渇きは癒えず、とうとうつばさえもでなくなり紅茶をがぶがぶ飲む始末。
それでも、渇きは癒えない。それどころかどんどん酷くなる一方だ。胃の中が紅茶でいっぱいになっているだろうにもかかわらずだ。明らかに異常なこと。けど対処の仕様がない。わからない。
「飲みたい……」
何を? と思わず心で問う。もちろん答えは返ってこない。
「飲みたい……」
いいながらもその口は今もなお紅茶を含んでいるはずなのに。
「ノ……ミ……タ……イ……」
かすれた、音にもならない声が、私にだけ染み渡る。それは、まるで私自身へ私自身が要求しているように。
「AAAAAAAAAAAAAAAAA!!」
気づけば私はガムシャラに走っていた。声という音域を外れ、獣じみた叫びを放ちながら。
頭の中でささやく。甘く、芳醇に、私を誘う。
チヲ、ノメ、ト。
アタタカク、アカク、アマク、イケルモノノ、チ。
チヲ、ノメ、ト。
「ただいまー」
ドアを開き、玄関で靴を脱ぎ、家に上がる。と、ここで向こうからいい匂いが漂ってくる。それは私の鼻をくすぐって、つい反射で口の中でよだれが出てきてしまう。この匂いはたぶんビーフシチュー、なのかな。
「お母さーん、今日ってもしかしてビーフシチュー?」
「そーよー。よくわかったわねそこからー。玄関でしょ今いるの?」
そういえばそうだ。私って、こんなに鼻がよかったっけ。
「まぁいいわ。そんなことよりさっさと着替えて着なさいねー」
はーいと返事をして私は階段を上り自室へ向かう。リズムよくトン、トン、トンと。
部屋に入ってひとまず着ている服を脱ぐ。するりと衣が脱げ落ちていく。人が自分を繕うためにつけている人間としての鎧が。
今の私は下着姿。この状態で部屋の外をうろつけば確実に軽蔑の視線が私に向けられるだろう。
「軽蔑……」
って私はいったい何を考えてるの! そんなの変態じゃない変態! 露出狂じゃあるまいし……
「……あーもー! そんなことよりご飯、ご飯!」
思わず出てきた邪まな考えを振り払いちゃっちゃと着替えを済ませると部屋を逃げるように飛び出した。
「あらあら。いくらおなかが空いたからってそんなにあせらなくても誰も盗らないわ」
あまりにもどたばたと駆け下りたためかお母さんがそんなことを言い出す。息を整えながらイスに着いて料理が出されるのを待つ。
「うふふ、誰に似たのかしらねぇ。お父さんかしら?」
「もうそんなのどうでもいいよぅ……あ、それよりお姉ちゃんは?」
「多分、勉強中よ。あの子は今大事な時期だから。邪魔しちゃだめよ」
お姉ちゃん。私より二つ上で、いわゆる受験生。今、すごく忙しいみたいで、いっしょにご飯を食べることすら滅多にない。いい大学目指してるんだって。
「さ、ご飯にしましょう? 今日はビーフシチューよ? って、知ってるわよね」
「あぁもうお腹ぺっこぺこだよ! いただきまーす!」
全力で走っている私。人間では到底出せそうもないスピードで動くこの体は目的もなくただひたすらに走り回る。
むしろ、考えたくはなかった。私の頭を巡りに巡る思考回路を封鎖するために。自身がそうではなくなる恐怖。いつのまにか人道から外れたことを考え、そして実行してしまうそうな。そんな思考。
走っても走っても、逃げども逃げども、ソレが離れることなどない。なぜなら、それは私の頭の中で生きているからだ。ソレは腐っていて、それでいて、魅惑な息を私の脳髄に吹きかける。落ちてしまえば楽だろう。いや、楽に違いない。けれども、私に残されたヒトカケラの"人"が。ソレをかたくなに拒み続けていた。
走りに走って、いつのまにか路地裏の方に来てしまっていた。ここまで来るのに時間はそんなにかかっちゃいない。三分か、四分くらいだろう。それでも心臓はほとんど正常に鼓動を繰り返している。
どうかしている。普通じゃない。体も、心も。
「どうなっているのか……全くもって……」
途端。心臓の衝動。誰か、いや、何かからの非道なまでの圧力によって締め付けられている。
「アッ……ガッ……ケハ……」
止まる。心臓が。コドウが。イノチが。トマル。オワル。
「ウ、ア、コン、ナ、ノッテ……クヒッ」
カエルがひしゃげたような音を出しながら、私の体は落ちていく。路地の、冷たいアスファルトの上へ。
さようなら。
誰に言うわけでもないが、なんとなく、頭の中でそう呟いていた。
さようなら。
「あーあ。今日ももう終わりかー」
そんなことを、私はお風呂場で誰に言うわけでもないけど、言っていた。
「また明日も学校……あー休みたーい」
口ではこうは言っているが、実際は冗談だ。
もしも、明日いきなり台風が来て学校にいけなくなったりとか、大雪が降っていけなくなったりとか、インフルエンザが急に流行って臨時休校になったりするんだったらいいけど。
どうせ、そんなことはおきっこないんだから。だから、半ば諦めがちに学校に通っている私。
いかなきゃいけない。そう自分に言い聞かせて、毎日、登校する。
「はぁ。やんなっちゃうなぁ」
私は普段はこんなこと、考えない。だってせっかくの晴れてる心も一気に台無し。曇り空。
そういえば私、なんでこんなこと考えちゃったんだろ……?
「う~……あぁもう! 分かんないからパス!」
ぱしゃとお風呂の中に顔だけ潜ってネガティブな思考はシャットダウン。ぶくぶくぶくと泡が出ている。ほんとはお行儀悪いけど誰もいないんだから気にすることはないよね。
「おーい、いもうと~」
「っひゃあ!」
予想だにしていなかったのは私も姉ちゃんもおんなじみたいで向こうも驚いたようで。
「ちょ、ちょっと何、大丈夫!?」
「あ、ごめん驚いちゃってそれで……えへへ」
「まったく……どうせあんたのことだからお風呂でぶくぶくしてたんでしょ」
ばれてる……
「ど、どうして分かったの?」
「だって昔はよくいっしょに入ってたじゃない。あんたいつもやってたし」
「そんなにしてたっけ?」
「してたしてた。それはもうぶくぶくぶくぶく。しまいにはよく母さんにしかられたかな」
そういえばもう何年くらい入ってないのかなお風呂。小学校くらいまではいっしょに入ってたけど二人とも中学にあがってしばらくしたら、いつのまにか入ることはなくなってた。
「いつのまにか、いっしょに入ることなくなったよね」
「え? ああ、そりゃいつまでもいっしょってわけにはいかないでしょ?」
「まぁそうなんだけど……あ、そういえばさっき私のこと呼んだけどなんだったの?」
「いきなり話が変わったわね……そういえば、なんだっけ。ああ次私入るからって言おうとしたのよ」
「なんだ、それだけなのか」
「あのねぇ……それだけなのに話を伸ばしたのはあんたの方でしょ」
「えへへ、ごめんごめん。もうちょっとしたらあがるから」
ほんとに頼むわよ、と言うと姉ちゃんはそのまま洗面所を立ち去っていった。
私も、もう上がらないとね。
もちろん風呂上りは、ダイエットのためのトマトジュースを思いっきり飲み干す。
いつもは、にんじんジュースだけどね。そういう気分なんだ。
そういう、ね。
一つの体が、そこにあった。
薄暗く、ひんやりとした空気がじめっと肌に触るそこはいわゆる路地裏と呼ばれている場所。
その体はピクリとも動きはせず、もしも誰かがそれを見たら救急車を呼ぶかそれともその状態を確かめに行くか。人によっていくらでも取る行動はあるだろう。
だが、もし勘の鋭いものがそれを見たとしたら。おそらくほとんどの者がこうするだろう。
"全力で逃走する"
しかし幸か不幸かそれを目撃したものは誰一人としていなかった。
"それ"が、至って平然と立ち上がる姿を目撃したものも。当然いなかった。
「けひ……キひゃ……」
鳥か獣がか細く啼いたような、そんな音が体の口から洩れた。
体は、周囲に散乱していたプラスチックの群れを全く認識していないのか。踏み、蹴散らし、時にはすっ転びそうになりながら。その場を後にしようとした。
そのとき、体はその動きを停止し、辺りを見回し始めた。
当然その辺にゴミ屑同様に撒き散らされているプラスチックの塊を探しているわけではない。
鼻をヒクヒクと震わせて、何かのニオイを嗅ぎ取ろうとしている。
と、ある一点を向くと、それらの動きを全て停止させた。
そこには、女がいた。
制服を着ていて、通学かばんと思わしき物から携帯電話を取り出している。どこから見ても学生なのは明らかだった。
しかしそんなことはカレにはなんの関係もなかったのだった。
「あ、メール。 なんだお母さんか。 えっと……"ご飯できたから早く帰りなさい"……はいはい。わかってますよーだ」
少女は、そのメールを読み終わるとすぐさまその返事を打ち込み始めた。
「"りょーかいいたしましたお母様。すぐさま帰宅いたします"……っと」
内容を打ち終わりそれを送るべく送信ボタンを押す。携帯電話の画面には、紙が折られ紙飛行機になり、それが飛んでいくという映像が流れている。それが三度ほど繰り返されたとき、画面には"送信完了"の文字が映っていた。
「もぉーこのぐらいでいちいちメールなんか送ってこなくていいのにー」
そう言いながら携帯電話を折りたたむとかばんの中にテキトーに突っ込んだ。
家に帰ろうと、視線をかばんから戻すべく顔を上げると
そこには、見たこともない男の顔があった。
「あーやっぱりお風呂上りはこれだよねー!」
お風呂から上がって早速私はトマトジュースを飲み干していた。よく友人などからは味の事をたびたび聞かれるけどそれはまったく問題ない。なぜならこのトマトジュースを含んだ野菜ジュース類は母が考案しそして何度も行われた細かい調整でようやく完成したジュースなのだ。(そのときの失敗作は私たち姉妹が強制的に始末させられたのだけど)もちろんまずいわけはない。
「そう言ってくれるとこっちも嬉しくなるわねー」
キッチンの流し台でお母さんは今日の晩御飯に使われた食器を洗い流している。手伝ってあげようかとも思ったけど私がお風呂に入っている間にほとんど終わってしまっていたようなので今日はやめておいた。
「それにしてもまたパパ帰りが遅いわ……ここのところいつも残業ばっかり。食事用意してるこっちの身にもなってほしいわ!」
そう言うとお母さんは頬を膨らませる。いい年してるのにって突っ込むと怒られるからしないけど。
「でもさぁ、そういうときって普通先に言っておくもんじゃないの?」
「確かにそうなのよね……ま、今日はたまたま残業が入っちゃったってことにしておくわ。そして食器洗い終了っと」
見てみると確かに流し台には一枚も食器は残っておらずそして全てがきれいに拭かれていた。
と、突然お母さんが欠伸をし始めた。それを見て思わず私も欠伸がうつってしまった。
「あらもう欠伸する時間帯……? 一日ってほんと短いのよね」
背伸びをしながらそんなことを言うお母さん。言ってることは共感できるけど。
「じゃ、私もう寝ちゃうから早百合もさっさと歯磨きして寝なさいね?」
「は~い」
口ではこうだけど実際はそんな気は毛頭ない。だってテレビ見るんだもん。夜更かしは学生の特権なんですって誰か言ってた気がするし。どうしても見たいし。別にいいよね。
すでにお母さんは自分の寝室に移動している。つまりここのテレビ独占し放題。バレると後が怖いけどね。
前に友達に聞いたんだけどわりと自分の部屋にテレビがある人も多いらしく私としては羨ましいの一言。ズルイぞ。
「さてさて、まずはスイッチを……オン!」
プツン、というなんだか歯切れのいい音がなり徐々にテレビの画面が明るくなる。なんかこういう瞬間ってドキドキするの私だけ?
「おっとっと音を下げて……っと。これでよし。何から見ようかな……」
そのとき、あまりテレビから聞くことのないプーンという音が二度すると、画面上部にはニュース速報の文字が流れている。
「こんな時間に速報かー。あれかな。地震とか?」
というより他に思いつかなかっただけなんだけど。
ゆっくりと流れてくるニュース。しかし私の予想に反して、"地震"の二文字はなく。代わりにこの二文字が流れていた。
「殺……人?」
"連続猟奇殺人事件"
普段全くお目にかかることのない文字が勢ぞろいで、私の目に飛び込んできた。
薄暗かった路地に月明かりが差し込む。
劇場の舞台にスポットライトが当てられたように、彼らに光が当てられる。
うつ伏せに倒れた少女と、そこに馬乗りになって少女に抱きついているように見える男。
月明かりの美しさ。それによりさらに極まるその行為から垣間見える異常さ。
よく見れば少女の首筋から血が流れており男はおぞましくもその血を音を立てながら啜り飲んでいた。
「キヒ……キヒヒヒャハ……」
ユラリとよろめきながら立ち上がる男。
淡い青色の月光と、病的なまでに白い肌と、口元にべったりと付いた赤朱色のコントラストはどこか芸術的な絵画のような。そんな印象を思わず抱いてしまうほど、月明かりは美しかった。
「ヒヒヒヒャハハハハハハハ……ヒヒハハハハハハハハ!!」
ケタケタとニヤニヤ笑いながら上に、空に向け、高笑う男。
一度膝を曲げたかと思うと普通では考えられない跳躍で跳び上がると、そのままこの場を風のように去っていった。
男の高笑いは、いつまでもその場にこだまし続けていた。
この倒れている少女が起き上がるのは実にそれから数分後のことである。
しかし一方で、こことは違う場所に話は移る。
「んで、着いた訳なんだよな。相棒?」
「……相棒というのは止して頂けませんか。一応、指揮権は僕にあるので」
そこには、二人の人間がいた。
ただいるだけならばそこまで気にすることはない。問題は彼らの見た目である。
まず一人は、長身で赤色の髪、銀色に輝くそれは見事な鎧を装着し、腰には長めの剣と思わしきものまで差している。
もう一人は、低身長気味で水色の髪、鎧とまではいかないが丈夫そうな革服と胸当てや肘当てといったものを装備し、腰には先ほどの剣よりぐっと短く、おそらくレイピアのようなものを差していた。
二人が並ぶとその身長差はよりはっきりと目立ち、もう一人の方はまるで子供のように思えて仕方がない。
「まあなあ、そりゃこんな見た目じゃどっちが上かなんて人目見ただけじゃ見抜くのは一苦ろ」
「それ以上僕の容姿について言及するということは覚悟ができていると思っていいんですよね?」
ジロリと睨むその蒼眼に思わずたじろいでしまう長身の人。流石にこれはまずいと咄嗟に言い繕う。
「あっははははは……冗談っすよ冗談……ったくちょっと触れただけですぐコレだからな……」
「何か、言いましたか?」
ボソッと呟いた筈の文句がなぜ耳に届いたのか、相手には見えぬよう苦々しい顔をしながら返事を返す長身の人。
「いえいえほんとになんでもありませんよほんとうに」
「……どうやら、任務より先に上の者への口の聞き方を教育しなければならないようですね?」
長身の人、それを聞くと今度は深々と頭を垂れ、実に丁重な雰囲気で言葉を述べ始める。
「……先ほどからのご無礼お許しください。どうやら自分は初任務に舞い上がり多少冷静な判断に欠けていたようで……」
低身長の人、一つため息を吐くと、怒る気力がなくなったような、それでいて重々しく。
「あなたの言葉に付き合っても無意味なので、この件はなかったことにします。ですが」
「もちろんこのことは今後一切口には出しません。誓ってでも」
「よろしい。それじゃ早速行動を開始します」
そういうと、彼らはその場を後にした。
後に残ったのは、ただ静けさばかりだった。
私は、テレビの画面に釘付けになっていた。
そのとき流れていた映像は全てどこかに吹き飛び、映るのは文字だけだった。
"今日午後10時ごろ、浦歩市内で血まみれの死体を見たという人が相次ぎ警察が調査をしたが死体は見つからず
見間違いだと思われていたが一人の警官が死体を発見したと通信機で同僚に報告したがその警官は行方不明に
現在その警官を捜索するとともに今回の騒動の真相を探っている"
「血まみれ……」
そう、私にも覚えがある。あのとき、路地で倒れていたとき。私は少しではあったけれど血が流れていた。
もしかして、何か関係があるのだろうか。そのときの記憶はあいまいなんだけど……できるなら思い出したくない。
なぜかはわからないんだけど、怖い。思い出そうとすると、黒い影がチラチラと頭を横切る。怖くって仕方ない。
「こらっ!」
「ひゃあ! テレビ勝手に見ててごめんなさいごめんなさいごめん」
「バーカ、わたしだよわ・た・し」
後ろから突然怒鳴られた私は思わず自分でもマヌケなほどに飛び上がってしまった。
見てみればお母さんじゃなくてお姉ちゃんだし。
「もう……脅かさないでよ」
「あっはははごめんごめん。あんまり真剣になってテレビ見てるからつい」
「つい、じゃないよもう。ほんとに心臓止まるかと思った」
「悪かったって、ごめん。んで、何か面白そうな番組でもあったの?」
連続殺人事件があったんだってー、なんて、言えるわけない。勉強に集中したいだろうし。それに今私が言わなくたって明日のニュースとかで見るだろうし、今言うべきことじゃないと思った。
「え、あ、ううん……別になかったよ」
「え~? 本当かな~? あんなにまじまじ見てる早百合珍しいと思ったけどね~?」
「ほ、本当だよ! そ、それよりお姉ちゃんは何しに来たのさ!」
なんか私ってごまかすのが下手な気がする……けど、お姉ちゃんはそのことを気にした様子もなく答えた。
「私? いやちょっとのどが渇いたからさ。ジュースでも飲みにきたってわけ」
「そっか。ところでなに飲むの?」
「もちろん母様特製スペシャルジュースに決まってるでしょ! あれ美味しいんだよねー」
スペシャルジュースというのはお母さんがお姉ちゃんの健康を気にして作り出したある意味お姉ちゃんのためのジュースだ。そのせいかお姉ちゃんもそれを一番のお気に入りにしているみたい。
「やっぱりそうだと思った。あーあ私ものど渇いちゃったなぁ」
「じゃあ飲めばいいんじゃない?」
「だって入れるのめんどくさいし……あ、そうだお姉ちゃんついでに私のも入れてよ」
「やーだよめんどくさい自分でやりな」
「むー、けちー」
「それに私の分はすでにやっちゃったからね」
気づくとお姉ちゃんはすでにコップを持っていてその中にはオレンジ色の液体が入っている。いつのまに。
仕方がないのでぶつぶつ文句を言いながらも私はキッチンの冷蔵庫に向かう。すぐそばでお姉ちゃんが飲んでいるのはどう見ても私に対するあてつけだ。全く私の分くらい入れてくれたっていいのに。
とりあえず何を飲むか選ぼう。えーと、うーむ、そうだ。トマトジュースにしよう。お風呂上りにも飲んだけど。
「お、トマトジュースなんて珍しいね。もしや、ダイエット中?」
私が冷蔵庫からトマトジュースの入ったボトルを取り出しているとそんなことを言ってきた。
「違うよ! なんていうか気分?」
「ふーん。あっそ」
それだけいうとさっさとまたジュースを飲み始めた。私も気にしないでさっさと飲むことにした。
不思議と飲み終わるのに大して時間はかからなかった。大きいコップを使ったはずなんだけどな。
隣を見るとお姉ちゃんがまだ飲んでる。
そういえばお姉ちゃんって結構スタイルいいんだよね。でもモテるなんて話し聞いたことないなぁ。
細い。お姉ちゃんの体って。よくこんな体で生きていられるよね。
ほんと、この首なんて、力を入れると折れてしまいそうで。
「ん? どうしたの?」
「っ!?」
急に振り返ったお姉ちゃんに気づいて慌てて私は手を引っ込んだ。
今私なに考えてたの? どうしてお姉ちゃんの首を触ろうとしたの?
「あ、う……」
「さ、早百合? どうしたの、顔色悪いよ?」
「ご、ごめんなんでもない……ちょっと外の空気、吸ってくるね」
「あっ、早百合!」
一分一秒も早くこの場から逃げ出したかった。何もかもが恐ろしくてたまらなかった。何より、私自身に。
私……いったいどうなっちゃったの?
「ったくキリがねぇぜこりゃあよ!」
「確かにこのままでは埒が明きませんね」
人通りの少ない少々寂れた商店街。そこに普段より多くのニンゲンがいた。
いや、正確にはニンゲンの形をしたモノ。とでもいえばいいのだろうか。
なぜなら彼らの動きは明らかに人という枠を超えたまさしく人外と呼ぶに相応しいものでまたそれに対峙している二人も人智を超えた目を疑うような光景を繰り広げていた。
剣を持つ二人の人間に対して老若男女の七体の化け物。しかしそのうちの三体はどういうわけか氷漬けにされている。
残りの四体はバラバラの動きで二人を仕留めようと彼らに襲い掛かる。あるモノは上から、あるモノは回り込んで後ろから、またあるモノは正面からとそれぞれの動きはバラバラながらもそのどれもが強力なパワーで攻めてくる。
それを主に捌いているのが長い剣を持った男。ときどき捌ききれないのがきたらもう一人と見事な連携で立ち回っていた。
「そこまで冷静に言うかフツーよォォ! アイツらはまだ7体もいるんだぞ!?」
「……ちょっと時間を稼いでください。まず僕が奴らの足止めをします……十数秒ほどですが」
「それで! どんくらい! 持たせりゃ! いいんだ!」
そういっているうちにも相手は休むこともなく攻め続けてくる。それを切り払ったり押し返したりしながら長身の男は聞いた。
「そうですね……20……いや15秒持たせてください。何とかしてみせます」
「何でもいいから早いとこ足止めって奴を! こっちは持ちそうにねぇんだぞ!」
「わかりました!」
そういうと手に持っていたレイピアに形状の似た剣を何かの絵を描くかのように振り回し始めた。
そしてさらに何かを唱えている。
水の神よその偉大なる業を我の前に示し給えいかなる時であろうとも我と共に在れ――――
イル・オン・ディヌ・ミカノズミ――――
「フリージス・ミストッ!!」
その言葉を唱えると、化け物たちの周りを薄い霧のようなものが包み込み始める。
それを意に介せず再び攻撃を仕掛けようとする化け物だが、不思議なことにその体は全く動こうとしない。いや、動こうにも動かすことができないのだ。なぜなら、その体は瞬く間に凍りついているからだ。
そして、数秒もしないうちに七個の少々気味の悪いオブジェが出来上がっていた。
「ふぃー。助かったぜぇ……」
「僕は今のうちに次の呪文に取り掛かります。ですから……」
「んなことはわかってんだよォ!!」
そう言うと再び剣を構えなおし七個のオブジェどもへと向かって駆け出した。
しかし、普通ならば凍っている物を斬るというのは簡単なことではない。が、長身の男はそれを気にしている様子はない。
「見せてやるよ。俺のフレイム・エンチャントの力を!」
突如、彼の持っている剣を包み込むように淡い火が出たかと思うと、瞬く間に紅蓮に揺らめく炎へと変わった。それは一見、その剣自体が燃えているようにもとれるがそうではない。あくまでも剣の周りに炎が現れたに過ぎないのだ。
「アンタには悪いがよ、跡形もなく消えてもらうぜ? 後始末が面倒なんでな!」
一番近くにいた化け物へ、紅蓮の剣を頭部へと、振り下ろす。
その炎は、氷を、髪を、皮膚を、肉を、骨を、脳を、何もかもを、焼き尽くした。
剣が完璧に振り下ろされたそのときには、そこにオブジェはなく、ただ少量の水と炭が下に落ちていた。
「か~、やっぱり俺もまだまだって奴か……なんて、無駄口言っている場合じゃねぇな!」
そして彼は突撃する。残りの化け物どもを殲滅するために。
と同時に彼は気づいていた。化け物どもを封じ込めている氷がすでに融け始めていることに。
それでも彼は走る。自身の任務を遂行するために。何より、彼と共にきた相棒を死なせないために。
「オラオラオラァァァッ!!」
横に、縦に、斜めにと剣を振る。化け物は一体、また一体と焼失していく。だが、よく見ると彼の剣を包んでいたはずの炎が化け物を斬るたびにだんだんと弱まってしまっている。それに伴って彼自身も、たった数回剣を振っただけなのにも関わらずまるで全力疾走で400mを走ってきたように呼吸が荒くなってしまっていた。
パキィンといった、何か薄いものが割れるようなそんな音が響いた。
見ると化け物どもは自分を覆ってしまっているその氷を、強引に力業で破り、体の自由を取り戻していた。
そして、長身の男を獲物として確認すると、三体の化け物が、彼に向かって襲い掛かる。
それに対する彼は疲労困憊してしまっているのか剣を構えることもなくだらりとした様子でうつむいていた。
「後は任せても、いいんだよな?」
「ええ、もちろんです」
化け物どもの頭上。そこには、コンクリートなどで固められた巨大な塊ができあがっていた。
よく見れば周囲にある建物の一部の壁などが大きく削れていたり剥がれていたりしている。
重力の影響を受けてそれが落下すると、下にいた化け物どもはその塊に押し潰されてしまった。
「……俺たちの完全勝利……ってところ、だな」
「どうも危なかったようにも見えたのは気のせいですか?」
「あ、あれはほら、演出だ! 演出!」
「その割には本当に疲労していたように見えましたけど……まぁそれはそれとして」
と、ちらりと巨大な塊を見やると困ったような顔をする。
「これ、放置しておくにも行かないので後片付けお願いしますね」
「ちょちょ、おい! さっきの戦いで疲れてるんだぞ! できるわけないだろ!」
「あれ? それは演出じゃなかったんですか?」
「ぐ……わかったよやるよやればいいんだろ! クソ!」
「口の利き方」
「りょ、了解しました……」
「あの塊は僕の方で解除しておきますのでそれの片付けと下敷きになってる体とかも焼いてください」
「……人使い荒くないか」
「それじゃがんばってくださいね」
そこまで言うと言いたい事は全て言ったとでもいうようにその場を離れ商店街の出口の方向へ歩いていく。
「あ、おいちょっと待て……畜生、後で覚えてやがれよ……」
振り返ってその巨大な塊を見て、しばらくそれを眺めているだけだったが、一言だけボソッと呟いた。
「あぁ……帰りてぇ」
「あぁ……帰りたいよもぅ……」
あのとき、お姉ちゃんから逃げ出した私は家から飛び出して当てもなく一人町を彷徨っていた。
流石にパジャマで出たわけじゃないけどそれでも薄着で寒い。玄関にかけてあったコートを着て出たけどそれでも寒くて仕方ない。
「でも、あんなことがあった後で帰れるわけないじゃん……」
自分で自分が、いやになる。ていうか、本当に私はどうしちゃったんだろう。さっきから変なことを考えてる。
家に帰る前も、家に帰ったときも、お風呂のときも、お姉ちゃんのときも。
「ほんとなんでなのかなぁ」
そう口に出してみたけど、本当は違う。心の奥深くで、誰かが叫んでる。今はまだ小さくて聞こえないけど薄々気づいてる。
ただそれに耳を傾けたくないだけなんだ。だって、それを聞いてしまったらもう。
今の私に戻れないような気がして。
「……あ、ここ……」
考え込んでて気づかなかったけど、私はここを知っている。
錆付いてしまったアーチ上の看板と、両端にたくさんのお店が並んでいて。
小さいとき、それも保育園とか小学生のときにお母さんに連れられ一緒に買い物に来た商店街。このころはまだお姉ちゃんとも一緒だったっけ。
「まだあったんだこの商店街……看板が錆びちゃってて何ていう名前なのか結局今もわかんないけど」
子供の頃の足だとなんだか遠く感じていたこの場所も、今となっては数分で着いてしまう。そのことを思うとなんだか感慨深いような気がした。
懐かしさに誘われるままに私は商店街の通りへと歩みを進めていた。右に肉屋さん、左に八百屋さんとそれこそテレビや漫画で出てきそうなそんなお店が立ち並んでいる。他にも居酒屋さんとかあるけどそのどれもが古臭さを感じさせるほどに壁がひび割れていたりシミができていたり。
しばらく歩いていると少し奇妙な物を見つけた。大小と様々な大きさの瓦礫が道路に散らばっているのだ。周囲を見回してみると付近の建物の壁が所々壊れていておそらくそれが瓦礫となったのだろうと考えられるけど。
「でもなんで? 地震とかあったわけじゃないし、普通こういうのって誰かが片付けるもんじゃ……」
いくら考えても答えなんか出るわけもなく。ただむなしく時間が過ぎるだけ。
「というか寒っ……流石にちょっと薄着だったかなぁ」
いつまでも外をぶらぶら歩いてたって仕方ないよね。うん、いい加減帰らないとね。お姉ちゃんも心配してるよきっと。
そう思って今まで来た道を戻ろうと、振り返る。振り返った私の視線の先に誰かがいる。見た感じ男の人だ。でもなんだろう。私はこの人を知っている……というより、見たことがある……?
アレコレ考えているうちに男の人はこちらの方向に近づいている。おぼつかない足取りというか少しふらつきながら。お酒でも飲んで酔っ払ってるのかな。なんて考えていた。
それは、あっという間の出来事。気が付いたそのときには男の姿が消えていて。
私が状況を把握しようとしたそのときには男の姿が目の前に現れていて。
「あ……あ……」
思い出しかけていた記憶が一気にフラッシュバックした。私は帰り道の途中に出会っていたんだ。あの化け物に。
そして、小さくもはっきりと聞こえてしまったんだ。
チヲ、アタタカイチヲノメ、って。
男の顔が月明かりに照らされる。あの時見たのと変わりのない青白い顔。でも、一つだけ違っていたものがあった。
それは、私がそれを見ても。
異質だとは感じなかったことだった。
「ちょっと横にズレてもらえるかいお嬢さんよ!」
大きく響き渡る男の人の声。でもそれは目の前の化け物から発せられたものじゃない。むしろ後ろから聞こえている。
咄嗟の判断で横に飛びのいた私は慣れないことをしたせいか転んでしまった。
「いったた……そ、それより、今のは一体何?」
化け物がいる方を見てみるとそこには変な格好をした人がいる。鎧とか剣とか着けて、髪も赤いし、まるでどこかのゲームから抜け出してきたんじゃないかと思うほどの格好。どんなコスプレでもここまで精巧にはできないんじゃないか。
茫然自失としているともう一人、私の方に近づいてくる。
「大丈夫、ですか」
小さめの身長で青い髪をした人が話しかけてきた。私と同い年、いやもしかしたら年下かも……
「う、うん大丈夫……というかあの人助けなくてもいいの?」
「ええ、どうせ相手は一体、問題ないでしょう。それに、あの人元気が有り余ってるみたいですしね」
「?」
くすくすと笑ってるのはちょっと理由はわかんないけどとにかく問題ないらしい。
それにしても不思議だ。本当に私は現実を見ているんだろうか。人が剣を振り回して化け物と戦うなんて。とてもじゃないけど信じられない。
そもそもこの人たちは一体何者なんだろうか。
「あの、あなたたちは一体……」
「何者か、ですか。確かに気になることです。しかし言ってしまってもいいのか……」
「言っちゃってもいいんじゃねーの?」
いつの間にか、赤髪の人はすでに化け物を倒してしまったようだ。化け物の姿はもうどこにも見えない。何をしたのか見てればよかったかな。
「今回のことを含め、私たちの存在は知られてはならないと言われているのを忘れましたか?」
「だけどよ、もう完全に色々見られちまったし手遅れじゃないか?」
「忘却の術を使えればいいのですが生憎僕は使えませんしその術者はいるのは向こう側ですからね。事態を軽く見すぎていました」
なんだか、私を置いて話がどんどん進んじゃってるけど、どうもこの人たちとは関わってはいけなかったみたいで……
あれ? もしかして私大変なことに巻き込まれてるとか……?
「あと、もう一つ気がかりが残ってるんですよ。彼女について」
「え? わ、私?」
「ええ。そうです」
「おいおい。別にこの子は単なる一般市民ってやつだろ? 特に気になることなんてないんじゃあ?」
そう。私はどこかの秘密捜査官でもないしスーパーヒーローってわけでもない。これといって目をつけられることなんてないはずなんだけど。
ただ、今私が気になっている点を除けばの話だけど。
「なぜあなたは生きているんですか?」
いきなり何を聞いているんだろう。なぜ生きてるって言われても説明できないんだけど。
「なぜ生きてるって言われても……心臓が動いているから?」
「いえ、そうではなく、あの怪物を前にしてなぜ生き延びているかということです。何の力もないはずのあなたが、どうしてです?」
「そ、それは……」
言ってしまってもいいのだろうか?
私が抱いている一つの仮定。それはとても不確かなものだし誰かに言ったとしても信じてもらえそうにもないほどだ。
でもこの人たちなら?
どこかのゲームや漫画から抜け出てきたような「まるでファンタジー世界」なこの人たちなら?
いやでも待って。この人たちの目的はどうみてもあの化け物を退治すること。
もし、もしも私がその仮説を話しちゃったら……
「ん? そりゃ単純に俺たちの発見が早かったからだろ? 何の問題も」
「1分40秒。私たちが彼女を発見してからそこに向かうまでの時間です」
「それがどうかしたのか? というかよく計れたな」
「効率的に考えるのは重要なことだと思っていますから。そんなことより問題はその時間です。考えてみてください。あの怪物たちは満たされることのない欲求を満たすために常に獲物を探し回っているんですよ。そこに格好の相手が現れたら。もうわかりますよね」
「……おい。そりゃ本気で言ってる、ってのかよ……」
「はい。本気も本気ですよ僕は」
そして、ゆっくりと私の方へ向き直る。ああ、とうとう言われてしまうんだ。でも不思議だ。そのことに対しての恐怖はないのだから。
きっと薄々自分でもわかっていたから。今まで悩んでいたのはそれを受け入れる勇気がなかったからなんだって。
これが私の出した結論の答えあわせだ。
「あなたは……恐らくあの怪物と同等の存在。つまり……」
――吸血鬼、なんですよ。
覚悟はしていた。そうであろうとは思っていたし受け入れようとも思っていた。だけどやっぱり現実って言うのは思い通りになんて行くわけはなかったようで。はっきりと明確に告げられた解答を聞いた私は内心、というかすでに足まで震えて動揺しまくりだった。
「ちょっと待て! もし彼女がそうだとして、だとしたら今頃彼女も人を襲ってるんじゃないのか!?」
「恐らくと言ったのはそこが気になるからです。こればかりは彼女から聞き出さないといけないんですが……いいですか?」
その「いいですか」というのが自分にあてられたものだと気づいた私は慌てて返事を返す。
「は、はい。 といっても私自身も混乱してるから説明しにくいんだけど……」
私はこれまでのいきさつを彼らに話した。
帰り道の途中に化け物、彼らの言う吸血鬼に会ったこと。
家に帰ってから変な思考が浮かんでしまうこと。
お姉ちゃんを傷つけてしまいそうになったこと。
家を飛び出してあの吸血鬼と再び会ったこと。
全てを話し終わると彼ら二人はなにやら考え込んでいるようだった。
「なぁ、これってどういうことなんだ?」
「彼女の話から思うに吸血鬼に咬まれているのは間違いないでしょう。ですがどういうわけか彼女はこうして正気を保っている。といっても非常に足場の悪い状態ですが」
「吸血鬼化するのは個人差はあってもほとんどの人間が一時間以内でなることは確認されてるんだろ?」
「はい。しかしすでに数時間は経過してます。通常ならありえないことですが彼女に限っては例外のようです」
「それってこの子は吸血鬼にならないってことか?」
「それは違うでしょう。現に襲われてませんしそれにそれらしい症状のようなものも出てるようですしね」
「だったらいったい……」
「ただの仮説にしか過ぎませんが、もしかしたら彼女には"抵抗力"があるのかもしれません」
「"抵抗力"……?」
あれ、なんだろう。眠くなってきちゃった。ああそういえば今って深夜なんだっけ。とんでもないものを見たせいで忘れてた。
それにしても私が吸血鬼か。人の、もう今は人じゃないみたいだけど。人生っていうのはこうも簡単に変わっちゃうのか。
ごめんねお姉ちゃん、お母さん、お父さん。私もう会えなくなっちゃうかも。
特にお姉ちゃんには、一言謝りたいなぁ。
ごめんって。一言でいいから。
ああ、コレが実は夢で起きたらベッドの上。
ってならないよねうん。
さようなら。みんな。
「一種の抗体みたいなものがあると思っています。だからこそああしていられるのでしょうね」
「……んで、どうするんだい。この子をさ。気が付いたら名前も聞かないうちに眠っちまってるし」
「抗体があろうとなかろうと連れて行くのは決めていました。色々と見られてしまいましたし、それに……」
「それに……なんだ?」
「い、いえ何でもありません! き、気にしないでください!」
「その慌てっぷり……なかなかレアだな」
「そんなニヤニヤと僕のことを見ないでください! み、見ないでったら!」
「クックック……いやぁ今日はいい物を見られたな本当」
「い、いつか酷い目にあわせてやるんだから……!」
――先日起こった奇妙な失踪事件についてのニュースです。新しく入った情報によりますと現時点で失踪者数は40名を超えており今回の調査で新たに、東野 輝美さん、岡島 正志さん、中山 治朗さん、下塚 早百合さん、吉山 晴海さんが今回の事件に関係していると――
終
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: