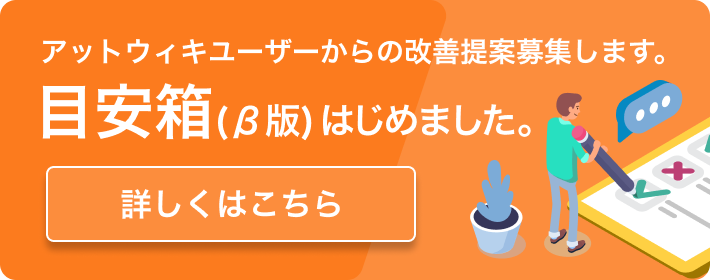「人を助けるのに必要なのは」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「人を助けるのに必要なのは」(2012/06/10 (日) 19:18:44) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
<p> </p>
<p> </p>
<p> ボクは歩いている<br />
ボクはごはんを探している<br />
朝には公園でごはんをもらったけど<br />
魚二個くらいじゃボクは満足できないだよね<br />
だからボクはご飯を探している<br />
いつものところをいつものように歩いている<br />
ボクはここがそんなに好きじゃない<br />
だって、大きくてすごく速いものが走っているから<br />
こんなところは、さっさと歩いていくんだ<br />
そうしようとした、ボクの前を追い越した子がいた<br />
ちょっと構ってほしくて声を出してみたけど<br />
その子はボクの声なんか気にしないで歩いている<br />
今度は足をカリカリしてみたけど<br />
やっぱり気にしないで歩いていってしまう<br />
それでその子はすごい速いものが通るところをまたいで行こうとしているんだけど<br />
でもボクは知っていた<br />
上で赤いものが光っているときはそこを渡っちゃいけないんだってことを<br />
だからボクはさっきよりも大きく声を出してみたんだ<br />
それでもやっぱりボクの声は届かなくて<br />
このままじゃ、この子がぶつかっちゃう<br />
もうすぐぶつかっちゃう<br />
ぶつかっちゃう</p>
<p> だから<br />
<br />
ボクがぶつかった<br />
先にぶつかっちゃえばこの子だって気づいてくれる<br />
<br />
だから</p>
<p> ボクがぶつかった<br />
とってもうるさいくらいに何かが音を出している<br />
何かが擦れたような音を出しながら速いものは止まったけど</p>
<p> ボクは吹き飛ばされてそばの草の中に落ちたみたい<br />
とっても痛いけれど<br />
あの子はきっと大丈夫だって思ってる</p>
<p> 見えるものがぼんやりとしてきた<br />
もう、ボクも動かなくなっちゃうんだな<br />
最後にあの子のことを見たかったけれど<br />
見えるものが光っててよく見えないや<br />
<br />
あれは<br />
<br />
輪っかだ</p>
<p> 丸い輪っかが光ってるんだ</p>
<p> とってもぴかぴかしてる</p>
<p> なんか、まぶしいけど</p>
<p> とっても、きれいだ</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>
陽は落ちて、人通りの少ないその交差点では信号機が自らの役割をただ忠実に三色の輝きを放っている。車は昼間と比べると驚くほどに少ない。それもそのはず、今の時間帯は普通の人間なら眠っているか、眠るための準備をしている時間なのだから。<br />
そんな時間であるにも関わらず、その交差点の歩道に黒いワンピースを着た少女が横たわっていた。闇に溶け込むかのような姿の少女だが、ワンピースにところどころある白いラインと、彼女のつやっとしたほのかに白い肌がその存在を主張している。その少女はしばらくの間身動きしなかったが、そのうち声にならないような呻きを上げながらもそりと動き始めた。<br />
「うみゅ……」<br />
むくり、と起き上がったその少女はきょろきょろと首を回す。どうやら周囲を見ているようだ。その動きに合わせて、ワンピースもシワを作る。そして。<br />
「さむい……」<br />
そう言いながら腕を抱えてカタカタと震えだした。いくら今の時期が緑の増える時期でも、コンクリートの上で寝ていては体も冷えるだろう。<br />
そんな風に体を震わせていたが、ふと少女の上から声が降ってきた。<br />
「どうやら、ようやくお目覚めらしいな」<br />
聞こえてきた方に顔を向けると、不機嫌そうに見下ろしている翼を生やした小人が宙に浮いているのが見えた。小人が空中に浮いているという状態がすでに驚きのことなのだが、少女はそれをなんとも思っていないらしくただじーっと見つめている。<br />
「たく、この俺がこんなマヌケそうなのを見ないといけないなんて……」<br />
独り言を言うその人物はいまいましげに少女を見つめている。一方でマヌケ呼ばわりされた少女はそのことが何のことかわかっていないようで<br />
「まぬけ……?」<br />
逆に聞き返す始末だった。<br />
そんな少女の姿に翼を生やした小人は呆れたようにため息を吐くと、少女の顔面の前にすぅっと移動した。<br />
「ああ、そうだ。 お前はマヌケだ。 少なくとも自分がどうなっているのか把握できないくらいにマヌケでバカだよお前は!」<br />
そういって小人は右手で少女の額を殴った。こつんという小気味のいい音が鳴って、続いて少女の痛がる声。目に涙がうっすら浮かんでいることから結構痛かったに違いない。<br />
「うう、痛い……なんで殴ったの……?」<br />
「なんで、ってあのなぁ……」<br />
右手で後ろ頭をボリボリと、腹の虫の居所が悪いのか、心なしか翼のはためきも大振りになっている。<br />
「今お前が話してる言葉は何だ?」<br />
「何って、ボクはいつもどおりの……」<br />
「いつもどおりだったら俺と会話できるわけねぇだろ!」<br />
「いたぁっ!」<br />
再び額を殴られる少女は、自分が何を言われているのかいまいち飲み込めないらしくなぜ殴られているのか、それさえもよくわからないでいた。次の瞬間までは。<br />
「そんなに殴らないでよ……とりあえず毛並み整えるからちょっとまって、て……?」<br />
少女は、ただいつもどおりに右手をなめようとした。しばらく整えていなかったはずのその毛並みを直すために、ただいつもどおりに。それが、少女にとっての。<br />
猫にとっての、いつもどおりだったから。<br />
「あ、あ、そんな……!」<br />
「ふん、いくらマヌケでも気が付いたか。 そうだ、お前は」<br />
「ボクの毛が抜け落ちちゃってるううううううううううう!?」<br />
「ちげぇよこのマヌケッ!!」<br />
「あいたぁ!?」<br /><br /><br /><br />
「うう……まだ痛い」<br />
「理解力がないお前が悪い」<br />
再度殴られた少女(元猫)は少しだけ不満げに相手を見つめては見たが、逆に「ああ?」と脅しつけられてしまった。<br />
「あー、もう面倒だ。 俺が指差してるとこに行け。 それで透けてる壁を見ればわかる」<br />
指差す場所は、交差点のそばにあった小さなビルの大きな窓ガラスのあるところだった。それを見た少女はなぜか得意げににんまりと笑っている。<br />
「ふふーん、"指差してるとこ"なんて言わなくても、ボクだってあれくらい知ってるもーん! えっと、あれは、えーっと……ああ! "オーバカジュク"だよ! へへん、どう? ボクにもそれくらいわかるんだよ」<br />
自慢気に話された内容のくだらなさに、思わず媚とはエルボーを炸裂させかけるところだった。だがここでいちいち止めていると朝までこの説明を続ける羽目になりそうだったので歯軋りをする程度にどうにかとどめるのであった。ちなみに、あとで小人が名前を確認したとこ"大原塾"だったことは気にとめる必要もないだろう。<br />
さて、二人がビルの窓ガラスに近づくと、うっすらとではあるが少女の体が徐々に窓ガラスに映りこんでくる。頼りない街灯と月明かりの白い輝きがあるからこそ、ガラスが反射しているわけだが、そんな細かいことはわかるわけがなかった。そもそも、気にもならないのだ。なぜなら、彼女が今、とっても夢中になっていることは、まぎれもなく目の前に見えているその少女が人間であり、それが猫だったはずの自分であるという認識だった。<br />
「ほんとに、ボク……これが、この子が、ボク……」<br />
「ああ、正真正銘、お前だよ。 今のお前は、間違いなく人間なんだよ。 というか本当に気が付いていなかったことに俺は驚いてるよ」<br />
そんな小人の皮肉も聞こえてはいないらしく、自分の体をペタペタと興味深そうに触っているだけの少女。その動きに合わせて、ガラスの中にいる少女も同じくペタペタと触っている。そんな当たり前で簡単なことだが、そうやって猫として人間の体の特徴を確かめているのだ。猫の彼女にとって、なんでも自分の体で試していくのが生きていくうえでの常識だからだ。<br />
「ボク、人間なんだねほんとに」<br />
「さっきからそう言ってるだろが。 まったく、本当にこんなんに任せちまって大丈夫なのか? その辺のガキに任せるほうが百倍はマシな気がしてきたぞ……」<br />
「……任せる?」<br />
「ああ、そうだよ。 お前に任せなくちゃならなくなっちまったんだよ。 それの説明も含めて、そろそろ俺のことも説明してもいいか?」<br />
「うん、いいよ」<br />
猫から急に人間になってしまって、おまけにこれから自分の身に降りかかることも知らない。そんな少女がニコニコと無垢な笑顔を小人に向けている。その笑顔を見て、三度目のため息と、これからに対する不安が拭いきれない小人なのであった。<br />
「まずは俺のことからだ。 俺は、あー、まずこう言ってお前に伝わりそうもないが、俺はいわゆる"天使"っていう存在なんだとよ。 お前が人間から猫って呼ばれてるのと似たようなもんだ」<br />
「へー、そうなんだ。 ボクにはよく分からないけれど、よろしくね天使さん」<br />
少女はそう言って笑いかけたが、対する小人――天使は、天使さんと呼ばれると、不機嫌そうな舌打ちを鳴らす。しかし、それがなぜなのか、そんなことがついさっきまで猫だった少女に察せられるわけもない。<br />
「その、天使さんってのはやめろ。 なんか、キモイからな」<br />
「キモイ?」<br />
「要するに気持ち悪いってことだよ。 俺のことは名前で呼べ。 名前」<br />
「名前、名前って何?」<br />
「名前は名前だよ。 ポチとかタマとかあんだろ。 俺は、オリヴィエって名前だけどよ。 お前にも名前くらいあるだろ」<br />
「んー。 ボクは、ボクだよ?」<br />
「だー! チゲェ、そりゃ自分を呼ぶときのあれで名前じゃなくてだな……」<br />
天使――オリヴィエは思った。目の前にいる元猫はこれまた天然で間違えているのだと。だが、そんなオリヴィエの思いはすぐに否定されることになる。<br />
「ボクは、ボクだよ」<br />
その瞳は天使であるオリヴィエの眼を真っ直ぐに射抜くような、そんな視線。一瞬だが、オリヴィエは圧倒された。先ほどまでのおちゃらけたような雰囲気が瞬時に張り詰めるほどの真剣さ。その真剣さに、折れた。<br />
「チッ……まぁ、お前のことは適当に呼ばせてもらうぞ。 そうだな、猫だし――」<br /><br />
にゃー子。<br />
それが、この世界に誕生した、元猫の人間に与えられた最初の名前だった。<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
「そんじゃまぁ名前も付けたところで説明に戻るわけだが」<br />
「だからー、ボクはボクなんだってばー」<br />
「うるせぇ、お前がボクだろうと何だろうと俺はにゃー子と呼ぶからな。 お前に従うのは何か腹が立つ」<br />
少女はオリヴィエに名付けられ――というよりは勝手にそう呼んでいるだけなのだが――にゃー子という名前をもらうことになった。にゃーと鳴くから、という至極単純な理由なわけだがオリヴィエはそんなことは気にもしていないようでにゃー子の反対は無視して自分の話を続けだす。<br />
「で、だ。 なんで、ただの猫だったお前が人間になったかと言うとだな……」<br />
と、威勢よく話し出したのはいいのだが。<br />
「あー、その、あー、そのよぉ……」<br />
そこから先が一向に出てくる気配がない。オリヴィエの顔から察するに、どうもにゃー子に対してこのことを話すのに抵抗感があるようで、ずっと目を逸らしている。<br />
「……?」<br />
一方のにゃー子と言えばやはり自分のことなど何も分かっていないため純粋に相手を見つめ続けるだけである。それが一番されたくないこととは知らずに。<br />
『――オリヴィエ、何をためらっているのですか』<br />
突如、にゃー子は不思議な感覚を覚えた。確かにオリヴィエとは別の女性の声が聞こえた。それは分かった。<br />
けれども、周囲にオリヴィエ以外には見当たらない。そもそも、自分の周りで声がした、などという感覚とは違うものだとにゃー子は気が付いた。それはまるで、自分の中にその女性がいるかのような、そんな感覚だった。<br />
「……いたんですね。 セイラ様」<br />
『あなたがあのようなことをしなければ、私だってこのようにはしていないことぐらいわかるでしょう?』<br />
「クソ……」<br />
その女性はセイラというらしい。しかも、オリヴィエにとっては頭の上がらない、いわゆる上の立場の人物なのだろうということは察することができる。あれだけ上から目線だったオリヴィエが今となっては随分とおとなしくなっているのだから。<br />
『ええと、それであなた……というと混ざってしまうから私もあなたのことをにゃー子と呼びますが……』<br />
「だからーボクはボクだってば!」<br />
と、にゃー子が異議を唱えるのを、オリヴィエは「バカおいてめぇふざけんな」とでも言いたげに慌てた顔をしていたがどうやらそのセイラ様の前では下手なことは言えないらしい。口パクだけに留めている。<br />
『ふふ、ごめんなさいね。 私としてはボク、よりはにゃー子、って呼んだ方がかわいいと思うものですから。 まぁどうせならマジカルにゃん子ちゃんとかって呼びたいんだけど、それはそれであざといというか、いかにも過ぎて今の世の中にウケづらいような気もするし、やっぱりこれくらいの方が軽い感じがして受け入れ安かったりするのかしらねぇ』<br />
「……ふにゃ?」<br />
「セイラ様、ものすごい話が脱線してるから戻してほしいんですけどね」<br />
『あら、ごめんなさい。 私ったらこういうことにうるさくなっちゃってねぇ……オホホホホ』<br />
オリヴィエは何かを言いたそうにしていたが、結局口には出さなかった。とりあえずにゃー子にはその話がよくわからないことだということがよく分かった。<br />
「ええと、それで誰なのさー」<br />
『コホン、名乗るのが遅れましたけど、私はセイラ。 人からは大天使セイラと呼ばれますが、要するにそこのオリヴィエよりすごい天使、と覚えれば十分です』<br />
「へー、オリヴィエよりすごいの?」<br />
『ええもちろん。 例えばそこのオリヴィエは今とても小さい姿でそこにいるでしょう? それはオリヴィエの力が弱いからなの。 そこに私が行けば少なくともにゃー子よりは大きい姿になれるわねー』<br />
「よくわからないけど、オリヴィエより大きいってこと? それはすごいね!」<br />
『でしょ~?』<br />
この間オリヴィエはぐぬぬと唸り続けていたが、口出しできる相手ではないのでこれまた口には出さないで耐えているのであった。できることと言えば、その話を切って次の話に持っていくくらいしかできないのであった。<br />
「セイラ様……肝心なことをお話になられてはどうです?」<br />
『あー、ごめんなさい忘れてましたね。 オホホホホホ』<br />
「絶対わざとだろ……」<br />
セイラはそのことは意にも介さずにさっさと話を切り替えた。<br />
『それで、にゃー子。 あなた覚えているかしら。 あなたが人間の男の子を守るために自らを犠牲にしたこと』<br />
「え、あ。 ああああ!? そういえばそうだったよー!?」<br />
「うるせぇよ! というかそれも今気が付いたのかよ!?」<br />
「そ、それで、あの子、どうなの? 無事なの? 助かったの!? なんともないの!?」<br />
「だぁーッ!! うっさいわ本当に! お前のおかげでケガ一つしてねぇよ!!」<br />
オリヴィエに掴みかかる様に迫ったにゃー子は、それを聞くとほっと、大きく息を吐いて安堵した。それと同時に、彼女の瞳から一つ、二つと水滴が零れる。<br />
「あれ? なん、でだろ……こんな、目から出てくるの……なに、これ……?」<br />
出てくるものをとめられないで、自分の体に異常でも起きたのかという不安に焦るにゃー子だったが、それを優しく諭すようにセイラは言った。<br />
『にゃー子。 それは、涙というものです。 涙を流せるということはですね、にゃー子。 あなたに優しい心があるからなのですよ』<br />
「なみ、だ……それって、いい、こと?」<br />
『ええ。 だってそれは、あなたに立派な心があるってことですもの』<br />
初めての涙に戸惑っていたにゃー子だったが、やがてそれは落ち着いていき。<br />
今の彼女の表情は、涙で濡れてはいたがとても可愛らしげな少女の笑顔だった。<br />
「えへへ……それならいっか」<br />
「なーにが、それならいっか、だよ!」<br />
「あいてぇ!?」<br />
こうして額を殴られるのは三度目のことだった。<br />
「人の話止めて泣き出しやがって、お前は人に説明させるのを止めたくなる癖でもあんのか?」<br />
「う~……だってぇ」<br />
「だってぇ、じゃねぇんだよ。 数分で済みそうな話をお前のせいで数十分に引き伸ばされてるこっちの身にもなれよ」<br />
『オリヴィエに賛成するわけではありませんが……確かに、尺的に少々長く使いすぎてしまいましたので、そろそろ本格的にお話したいことがあります。』<br />
「えうぅ……よくわからないよぉ……」<br />
「わからなくていい、むしろわからないでいろ」<br />
にゃー子が泣き出したことで一時的に話が止まってしまったが、それを仕切りなおすように大きな咳払いをすると話を元に戻した。<br />
『お話したいことと言うのは、なぜあなたが人間として復活したのかについて。 さきほど申しましたが、にゃー子、あなたは男の子を守るために自らを犠牲にしました。 そのためにあなたは車に撥ねられ大怪我を負いました。 そこまではわかっていますね?』<br />
「うん……」<br />
『実はそのとき、オリヴィエも近くにいたのです。 というのも、私がオリヴィエに命じて天使としての仕事をさせるためだったのですが、その命というのがあの男の子を助けることだったのです』<br />
「ええー!? オリヴィエ近くにいたの? じゃあ助けてくれたっていいのにー!」<br />
オリヴィエを非難めいた目でジーっと睨むと、顔を背けられてしまった。おまけに舌打ちも聞こえてきた。<br />
『にゃー子、あなたには難しい話かもしれませんが、本当ならばあの男の子はあの場所で車になど轢かれないはずだったのです。 それが、彼の正しい未来。 けれども、それを誰かが悪意を持って捻じ曲げて、彼に不注意をもたらした』<br />
元々猫だったにゃー子にとって、到底分かるわけがないはずの単語がちらほらと出てきている中。不思議なことにちんぷんかんぷんながらも、その言葉の本質のようなものをなぜか認識できていることに彼女は気がついた。<br />
「にゃう……つまり、誰かのせいであの子が車にぶつかることになっちゃったってこと?」<br />
『そうです、にゃー子。 そして、その誰かから人間を守るために私たち天使はいるのです』<br />
「まぁ、もう一つ、面倒な仕事があるんだけどな」<br />
セイラはそれには触れずに話を続ける。<br />
『にゃー子、あなたはさっき、オリヴィエに"助けてくれたっていいのに"と言いましたね?』<br />
「え? う、うん」<br />
『実は……助けにいこうとはしたのです。 まぁ、少々私に反抗的だったので半ば強制的に命じたのですが……そのおかげで、あの男の子を助けに行くのには七秒ほど遅れました。 ですが、七秒遅れたとしても予定通り助けること自体は可能だったのです。 そこに、予定外の事が起きてしまったのです』<br />
「よてーがい……って、何が?」<br />
「お前だ、お前。 他に誰がいるんだ?」<br />
「えと、ボク?」<br />
『そうです、にゃー子。 オリヴィエが助けに行く前にあなたが飛び込んでしまったこと。 それが私たちには予定外のことでした。 なぜなら、普通であればあの男の子が車に轢かれてしまうことなど誰にもわからないのですから、周囲に人がいたとしてもそのことに誰も"危険だ"などとは気付けないからです。 しかし、あなたは危険を察知してさらにはその身までも捧げてしまった。 私たちがたどり着いたときには、あなたはほとんど瀕死の状態でした』<br />
そのときにゃー子は自分が死ぬ間際のことを思い出した。あのときに見た、丸い輪っか。あれはオリヴィエだったのだということに気が付いた。<br />
『私は悩みました。 というのも、私たちは基本的にこの世界で力を使うのを許されているのは人間を魔法少女にすることぐらいなのです。 なので、少しだけ応用して、特別な救済処置を施したのです。 それが、あなたを人間として――魔法少女として生き返らせることでした』<br />
「まほー……しょーじょ?」 <br />
『簡単に言うと、私たちのお手伝いさん、のようなものです。 おまけに、普通の人間ではできないような不思議なことまでできてしまいます。 この魔法少女というのは何らかの素質ある者しかなることが許されていません。 私たち天使は人間を助ける他にその素質ある者を探し出すという仕事もあるのですよ』<br />
「ふーん……」<br />
そこで一度、セイラは言葉を止めた。そして、次に出す言葉はなんだか溜め込んでいたものを吐き出すようだった。<br />
『本来ならば、あなたが傷つくことも、人間になることも、なかったのです。 全ては私とオリヴィエの招いた失態です。 本当に、申し訳ないと思います。 にゃー子』<br />
姿、顔が見えなくとも、その声色から本当に申し訳ないと思っているのだと感じ取ることができた。しかしにゃー子は、こうなったのも自分の行動が起こしたことだと思っていたので、別に誰かのせいで自分がこうなったなどという風には考えてはいなかった。<br />
「ええと、でも、ボクがあの子を助けたのはボクが助けたかったからだし……いいよ、気にしなくても」<br />
『いえ、いいのです。 これは、私のけじめなのですから』<br />
「……変なの」<br />
『ふふ、そうね。 あなたからすればだいぶ、おかしなものかもしれませんね』<br />
どうしてセイラがこだわるのか、それは猫であったにゃー子には少し理解の難しいものだ。なんとなく、自分のためにこだわっているのだろうと、にゃー子は感じた。それがなんでなのかは、ちょっぴりわからなかったけれども。<br />
『さて、あなたが人間になった理由を話すのと、謝罪ができたのでそろそろ私はいなくなります』<br />
「え!? いなくなっちゃうのー!?」<br />
『いなくなるといっても、一時的にです。 そもそもこうやって話をするのも結構大変だったりするんですよ。 まぁ、折を見てまた来ますから。 そ・れ・か・ら』<br />
もしその場にいたら、たぶん首をぐいぃと回して睨み付けるかのような、そんな念を押すように。<br />
『オリヴィエ、後のこととにゃー子のこと、頼みましたよ?』<br />
と今までの話していたトーンから一オクターブくらい低い声が聞こえたかと思うと、その場からある種の気配のようなものが消失するのをにゃー子は感じる。<br />
そうして、それからいくら待とうとも、セイラの声は聞こえなくなった。<br />
「あー!! マジ疲れたわクソー!!」<br />
最初に声を出したのはオリヴィエだった。セイラがいることで余程ストレスがたまったのか、その鬱憤を放出するような叫びだ。その様子を見て、流石のにゃー子も気遣った。<br />
「だ、大丈夫、オリヴィエ?」<br />
「うっせぇ。 元はと言えばお前が車なんぞに轢かれなけりゃこうはならなかったんだ」<br />
「えう、ごめんなさい……」<br /><br />
<br />
太陽が南に昇っている昼間。誰もいない小さな丘のあるその公園には、そよ風が吹いて木々を細かに揺らしている。心地よい風につられるように、一つのブランコが乾いた金属音を出しながら揺られている。そしてそのブランコには一人の少女が座っていた。<br />
「なんにも起きないね」<br />
「あのなぁ、そう簡単に事が起こっても俺としては困るんだよ。 できることなら何もないほうがいい、というかこんなことは他の奴に任せたいくらいだ」<br />
少女――にゃー子は退屈そうに頭上に顔を向ける。目線の先には、ブランコの鉄柱の上でやる気のない顔で座り込んでいる天使、オリヴィエの姿があった。<br />
「だって、ボクだって人を助けたいんだもん! オリヴィエは天使なんでしょ? あの人言ってたよ? 天使は人を助けるのが仕事なんだって。 オリヴィエは人を助けたくないの? ボクにくれたモノだってそのためのなんでしょ?」<br />
にゃー子はそういいながらオリヴィエに向かって首にぶら下げていたペンダントを突きつけた。問いかけられたオリヴィエは苦々しげに顔を歪ませると、それに答えることもせずサッと丘を越えてどこかに飛んでいってしまった。行き先は知らないが、しばらくするとフラッと帰ってくることをにゃー子は知っている。オリヴィエがああやって怒りながらもにゃ子から離れないのは天使としての仕事があるからだと教えられたが、自分の好きなようにできないその様子ににゃー子はただただ変なものだと感じていた。<br />
「あーあ。 またオリヴィエ怒っちゃったよ。 うーん、どうしてオリヴィエはボクが天使のこと言うといつもああなっちゃうのかなー?」<br />
キィ、キィとブランコをこいで考えてみたものの、分かるはずもなかった。そもそも、オリヴィエの言った"シゴト"さえ、今のところにゃー子は深くは理解していないのだから。<br />
オリヴィエがくれた猫の形のペンダントを空に掲げてしばらくそれを眺めてみたが、やはり何も分かりそうにはなかった。<br />
「うーん、まぁいっか」<br />
オリヴィエの怒る理由について考えるのを早々に諦めると、ぴょんとブランコから降りて、ワンピースの裾を軽く手で払う。それから、うんと背伸びをすると、にっこりと微笑んだ。<br />
「やっぱりここ、いい匂いがする」<br />
ブランコから離れて遊具のない広いスペースに移動して、くるくると回る。両腕を真横に伸ばして、くるくる回る。回転に合わせてワンピースもふわりと浮かんでいる。そんな風に回転していると、今度は木の手前で動きを止めた。なにやら、少し上にある木の枝を見つめている。<br />
「むぅ……にゃっ!」<br />
それから、今度はぴょんぴょんと飛び跳ねだした。枝に向かって飛んでいるのだろうが、どうにも届く気配がない。おそらくは枝を取ってみたいのだろうが、悲しくも彼女の身長がまず小さすぎるのだ。これが中学生以上ならまだ話は別だが、今のにゃー子は小学生と同様の体のため、木の枝に届くはずがなかった。<br />
「ふー! なんで届かないんだよー!」<br />
枝に向かって唸っているが、その様子はまるで猫が唸っているようだ。例え唸ったとしても、その木の枝が一人でに折れて落ちてくれるわけがない。<br />
そんなとき、一つの手が現れて、ぱきんと木の枝を折った。<br />
「ふぇ?」<br />
振り返ってみると、一人の青年が立っていた。にゃー子よりは明らかに身長が高く、手も長い。<br />
自分より大きな者を目にしたことでぽかん、としているにゃー子に、青年は右手に持った木の枝を差し出すと、<br />
「はい、これ」<br />
そう言ってにゃー子の右手に木の枝を握らせた。<br />
「あ、ありがと……?」<br />
「どういたしまして」<br />
青年は自分の背後に置いてある小さなダンボール箱を抱えると、首のペンダントを一度見つめてそれから視線をにゃー子に戻すと。<br />
「かわいいペンダントだね。 それじゃ」<br />
ダンボール箱を抱えたまま丘を登っていってしまった。<br />
その様子をぽわんと上の空状態で眺めているにゃー子だったが、はっとした表情になると首をぶんぶん振って意識を正気に戻そうとする。<br />
「い、今のって……!」<br />
立ち去った青年を追いかけるために慌てて自らも丘を上りだす。ついつい猫のときのように手足を使って走ってしまうほどに今の彼女は慌てていることが伺える。<br />
小高い丘を四足で駆け上るとそこにはいくつかの木々が生えているのが見える。その中でもひときわ大きいケヤキの木の下に、彼はいた。手に持っていたダンボール箱はすでに下ろしている。<br />
「い、いた!」<br />
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> ボクは歩いている<br />
ボクはごはんを探している<br />
朝には公園でごはんをもらったけど<br />
魚二個くらいじゃボクは満足できないだよね<br />
だからボクはご飯を探している<br />
いつものところをいつものように歩いている<br />
ボクはここがそんなに好きじゃない<br />
だって、大きくてすごく速いものが走っているから<br />
こんなところは、さっさと歩いていくんだ<br />
そうしようとした、ボクの前を追い越した子がいた<br />
ちょっと構ってほしくて声を出してみたけど<br />
その子はボクの声なんか気にしないで歩いている<br />
今度は足をカリカリしてみたけど<br />
やっぱり気にしないで歩いていってしまう<br />
それでその子はすごい速いものが通るところをまたいで行こうとしているんだけど<br />
でもボクは知っていた<br />
上で赤いものが光っているときはそこを渡っちゃいけないんだってことを<br />
だからボクはさっきよりも大きく声を出してみたんだ<br />
それでもやっぱりボクの声は届かなくて<br />
このままじゃ、この子がぶつかっちゃう<br />
もうすぐぶつかっちゃう<br />
ぶつかっちゃう</p>
<p> だから<br />
<br />
ボクがぶつかった<br />
先にぶつかっちゃえばこの子だって気づいてくれる<br />
<br />
だから</p>
<p> ボクがぶつかった<br />
とってもうるさいくらいに何かが音を出している<br />
何かが擦れたような音を出しながら速いものは止まったけど</p>
<p> ボクは吹き飛ばされてそばの草の中に落ちたみたい<br />
とっても痛いけれど<br />
あの子はきっと大丈夫だって思ってる</p>
<p> 見えるものがぼんやりとしてきた<br />
もう、ボクも動かなくなっちゃうんだな<br />
最後にあの子のことを見たかったけれど<br />
見えるものが光っててよく見えないや<br />
<br />
あれは<br />
<br />
輪っかだ</p>
<p> 丸い輪っかが光ってるんだ</p>
<p> とってもぴかぴかしてる</p>
<p> なんか、まぶしいけど</p>
<p> とっても、きれいだ</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>
陽は落ちて、人通りの少ないその交差点では信号機が自らの役割をただ忠実に三色の輝きを放っている。車は昼間と比べると驚くほどに少ない。それもそのはず、今の時間帯は普通の人間なら眠っているか、眠るための準備をしている時間なのだから。<br />
そんな時間であるにも関わらず、その交差点の歩道に黒いワンピースを着た少女が横たわっていた。闇に溶け込むかのような姿の少女だが、ワンピースにところどころある白いラインと、彼女のつやっとしたほのかに白い肌がその存在を主張している。その少女はしばらくの間身動きしなかったが、そのうち声にならないような呻きを上げながらもそりと動き始めた。<br />
「うみゅ……」<br />
むくり、と起き上がったその少女はきょろきょろと首を回す。どうやら周囲を見ているようだ。その動きに合わせて、ワンピースもシワを作る。そして。<br />
「さむい……」<br />
そう言いながら腕を抱えてカタカタと震えだした。いくら今の時期が緑の増える時期でも、コンクリートの上で寝ていては体も冷えるだろう。<br />
そんな風に体を震わせていたが、ふと少女の上から声が降ってきた。<br />
「どうやら、ようやくお目覚めらしいな」<br />
聞こえてきた方に顔を向けると、不機嫌そうに見下ろしている翼を生やした小人が宙に浮いているのが見えた。小人が空中に浮いているという状態がすでに驚きのことなのだが、少女はそれをなんとも思っていないらしくただじーっと見つめている。<br />
「たく、この俺がこんなマヌケそうなのを見ないといけないなんて……」<br />
独り言を言うその人物はいまいましげに少女を見つめている。一方でマヌケ呼ばわりされた少女はそのことが何のことかわかっていないようで<br />
「まぬけ……?」<br />
逆に聞き返す始末だった。<br />
そんな少女の姿に翼を生やした小人は呆れたようにため息を吐くと、少女の顔面の前にすぅっと移動した。<br />
「ああ、そうだ。 お前はマヌケだ。 少なくとも自分がどうなっているのか把握できないくらいにマヌケでバカだよお前は!」<br />
そういって小人は右手で少女の額を殴った。こつんという小気味のいい音が鳴って、続いて少女の痛がる声。目に涙がうっすら浮かんでいることから結構痛かったに違いない。<br />
「うう、痛い……なんで殴ったの……?」<br />
「なんで、ってあのなぁ……」<br />
右手で後ろ頭をボリボリと、腹の虫の居所が悪いのか、心なしか翼のはためきも大振りになっている。<br />
「今お前が話してる言葉は何だ?」<br />
「何って、ボクはいつもどおりの……」<br />
「いつもどおりだったら俺と会話できるわけねぇだろ!」<br />
「いたぁっ!」<br />
再び額を殴られる少女は、自分が何を言われているのかいまいち飲み込めないらしくなぜ殴られているのか、それさえもよくわからないでいた。次の瞬間までは。<br />
「そんなに殴らないでよ……とりあえず毛並み整えるからちょっとまって、て……?」<br />
少女は、ただいつもどおりに右手をなめようとした。しばらく整えていなかったはずのその毛並みを直すために、ただいつもどおりに。それが、少女にとっての。<br />
猫にとっての、いつもどおりだったから。<br />
「あ、あ、そんな……!」<br />
「ふん、いくらマヌケでも気が付いたか。 そうだ、お前は」<br />
「ボクの毛が抜け落ちちゃってるううううううううううう!?」<br />
「ちげぇよこのマヌケッ!!」<br />
「あいたぁ!?」<br /><br /><br /><br />
「うう……まだ痛い」<br />
「理解力がないお前が悪い」<br />
再度殴られた少女(元猫)は少しだけ不満げに相手を見つめては見たが、逆に「ああ?」と脅しつけられてしまった。<br />
「あー、もう面倒だ。 俺が指差してるとこに行け。 それで透けてる壁を見ればわかる」<br />
指差す場所は、交差点のそばにあった小さなビルの大きな窓ガラスのあるところだった。それを見た少女はなぜか得意げににんまりと笑っている。<br />
「ふふーん、"指差してるとこ"なんて言わなくても、ボクだってあれくらい知ってるもーん! えっと、あれは、えーっと……ああ! "オーバカジュク"だよ! へへん、どう? ボクにもそれくらいわかるんだよ」<br />
自慢気に話された内容のくだらなさに、思わず媚とはエルボーを炸裂させかけるところだった。だがここでいちいち止めていると朝までこの説明を続ける羽目になりそうだったので歯軋りをする程度にどうにかとどめるのであった。ちなみに、あとで小人が名前を確認したとこ"大原塾"だったことは気にとめる必要もないだろう。<br />
さて、二人がビルの窓ガラスに近づくと、うっすらとではあるが少女の体が徐々に窓ガラスに映りこんでくる。頼りない街灯と月明かりの白い輝きがあるからこそ、ガラスが反射しているわけだが、そんな細かいことはわかるわけがなかった。そもそも、気にもならないのだ。なぜなら、彼女が今、とっても夢中になっていることは、まぎれもなく目の前に見えているその少女が人間であり、それが猫だったはずの自分であるという認識だった。<br />
「ほんとに、ボク……これが、この子が、ボク……」<br />
「ああ、正真正銘、お前だよ。 今のお前は、間違いなく人間なんだよ。 というか本当に気が付いていなかったことに俺は驚いてるよ」<br />
そんな小人の皮肉も聞こえてはいないらしく、自分の体をペタペタと興味深そうに触っているだけの少女。その動きに合わせて、ガラスの中にいる少女も同じくペタペタと触っている。そんな当たり前で簡単なことだが、そうやって猫として人間の体の特徴を確かめているのだ。猫の彼女にとって、なんでも自分の体で試していくのが生きていくうえでの常識だからだ。<br />
「ボク、人間なんだねほんとに」<br />
「さっきからそう言ってるだろが。 まったく、本当にこんなんに任せちまって大丈夫なのか? その辺のガキに任せるほうが百倍はマシな気がしてきたぞ……」<br />
「……任せる?」<br />
「ああ、そうだよ。 お前に任せなくちゃならなくなっちまったんだよ。 それの説明も含めて、そろそろ俺のことも説明してもいいか?」<br />
「うん、いいよ」<br />
猫から急に人間になってしまって、おまけにこれから自分の身に降りかかることも知らない。そんな少女がニコニコと無垢な笑顔を小人に向けている。その笑顔を見て、三度目のため息と、これからに対する不安が拭いきれない小人なのであった。<br />
「まずは俺のことからだ。 俺は、あー、まずこう言ってお前に伝わりそうもないが、俺はいわゆる"天使"っていう存在なんだとよ。 お前が人間から猫って呼ばれてるのと似たようなもんだ」<br />
「へー、そうなんだ。 ボクにはよく分からないけれど、よろしくね天使さん」<br />
少女はそう言って笑いかけたが、対する小人――天使は、天使さんと呼ばれると、不機嫌そうな舌打ちを鳴らす。しかし、それがなぜなのか、そんなことがついさっきまで猫だった少女に察せられるわけもない。<br />
「その、天使さんってのはやめろ。 なんか、キモイからな」<br />
「キモイ?」<br />
「要するに気持ち悪いってことだよ。 俺のことは名前で呼べ。 名前」<br />
「名前、名前って何?」<br />
「名前は名前だよ。 ポチとかタマとかあんだろ。 俺は、オリヴィエって名前だけどよ。 お前にも名前くらいあるだろ」<br />
「んー。 ボクは、ボクだよ?」<br />
「だー! チゲェ、そりゃ自分を呼ぶときのあれで名前じゃなくてだな……」<br />
天使――オリヴィエは思った。目の前にいる元猫はこれまた天然で間違えているのだと。だが、そんなオリヴィエの思いはすぐに否定されることになる。<br />
「ボクは、ボクだよ」<br />
その瞳は天使であるオリヴィエの眼を真っ直ぐに射抜くような、そんな視線。一瞬だが、オリヴィエは圧倒された。先ほどまでのおちゃらけたような雰囲気が瞬時に張り詰めるほどの真剣さ。その真剣さに、折れた。<br />
「チッ……まぁ、お前のことは適当に呼ばせてもらうぞ。 そうだな、猫だし――」<br /><br />
にゃー子。<br />
それが、この世界に誕生した、元猫の人間に与えられた最初の名前だった。<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
「そんじゃまぁ名前も付けたところで説明に戻るわけだが」<br />
「だからー、ボクはボクなんだってばー」<br />
「うるせぇ、お前がボクだろうと何だろうと俺はにゃー子と呼ぶからな。 お前に従うのは何か腹が立つ」<br />
少女はオリヴィエに名付けられ――というよりは勝手にそう呼んでいるだけなのだが――にゃー子という名前をもらうことになった。にゃーと鳴くから、という至極単純な理由なわけだがオリヴィエはそんなことは気にもしていないようでにゃー子の反対は無視して自分の話を続けだす。<br />
「で、だ。 なんで、ただの猫だったお前が人間になったかと言うとだな……」<br />
と、威勢よく話し出したのはいいのだが。<br />
「あー、その、あー、そのよぉ……」<br />
そこから先が一向に出てくる気配がない。オリヴィエの顔から察するに、どうもにゃー子に対してこのことを話すのに抵抗感があるようで、ずっと目を逸らしている。<br />
「……?」<br />
一方のにゃー子と言えばやはり自分のことなど何も分かっていないため純粋に相手を見つめ続けるだけである。それが一番されたくないこととは知らずに。<br />
『――オリヴィエ、何をためらっているのですか』<br />
突如、にゃー子は不思議な感覚を覚えた。確かにオリヴィエとは別の女性の声が聞こえた。それは分かった。<br />
けれども、周囲にオリヴィエ以外には見当たらない。そもそも、自分の周りで声がした、などという感覚とは違うものだとにゃー子は気が付いた。それはまるで、自分の中にその女性がいるかのような、そんな感覚だった。<br />
「……いたんですね。 セイラ様」<br />
『あなたがあのようなことをしなければ、私だってこのようにはしていないことぐらいわかるでしょう?』<br />
「クソ……」<br />
その女性はセイラというらしい。しかも、オリヴィエにとっては頭の上がらない、いわゆる上の立場の人物なのだろうということは察することができる。あれだけ上から目線だったオリヴィエが今となっては随分とおとなしくなっているのだから。<br />
『ええと、それであなた……というと混ざってしまうから私もあなたのことをにゃー子と呼びますが……』<br />
「だからーボクはボクだってば!」<br />
と、にゃー子が異議を唱えるのを、オリヴィエは「バカおいてめぇふざけんな」とでも言いたげに慌てた顔をしていたがどうやらそのセイラ様の前では下手なことは言えないらしい。口パクだけに留めている。<br />
『ふふ、ごめんなさいね。 私としてはボク、よりはにゃー子、って呼んだ方がかわいいと思うものですから。 まぁどうせならマジカルにゃん子ちゃんとかって呼びたいんだけど、それはそれであざといというか、いかにも過ぎて今の世の中にウケづらいような気もするし、やっぱりこれくらいの方が軽い感じがして受け入れ安かったりするのかしらねぇ』<br />
「……ふにゃ?」<br />
「セイラ様、ものすごい話が脱線してるから戻してほしいんですけどね」<br />
『あら、ごめんなさい。 私ったらこういうことにうるさくなっちゃってねぇ……オホホホホ』<br />
オリヴィエは何かを言いたそうにしていたが、結局口には出さなかった。とりあえずにゃー子にはその話がよくわからないことだということがよく分かった。<br />
「ええと、それで誰なのさー」<br />
『コホン、名乗るのが遅れましたけど、私はセイラ。 人からは大天使セイラと呼ばれますが、要するにそこのオリヴィエよりすごい天使、と覚えれば十分です』<br />
「へー、オリヴィエよりすごいの?」<br />
『ええもちろん。 例えばそこのオリヴィエは今とても小さい姿でそこにいるでしょう? それはオリヴィエの力が弱いからなの。 そこに私が行けば少なくともにゃー子よりは大きい姿になれるわねー』<br />
「よくわからないけど、オリヴィエより大きいってこと? それはすごいね!」<br />
『でしょ~?』<br />
この間オリヴィエはぐぬぬと唸り続けていたが、口出しできる相手ではないのでこれまた口には出さないで耐えているのであった。できることと言えば、その話を切って次の話に持っていくくらいしかできないのであった。<br />
「セイラ様……肝心なことをお話になられてはどうです?」<br />
『あー、ごめんなさい忘れてましたね。 オホホホホホ』<br />
「絶対わざとだろ……」<br />
セイラはそのことは意にも介さずにさっさと話を切り替えた。<br />
『それで、にゃー子。 あなた覚えているかしら。 あなたが人間の男の子を守るために自らを犠牲にしたこと』<br />
「え、あ。 ああああ!? そういえばそうだったよー!?」<br />
「うるせぇよ! というかそれも今気が付いたのかよ!?」<br />
「そ、それで、あの子、どうなの? 無事なの? 助かったの!? なんともないの!?」<br />
「だぁーッ!! うっさいわ本当に! お前のおかげでケガ一つしてねぇよ!!」<br />
オリヴィエに掴みかかる様に迫ったにゃー子は、それを聞くとほっと、大きく息を吐いて安堵した。それと同時に、彼女の瞳から一つ、二つと水滴が零れる。<br />
「あれ? なん、でだろ……こんな、目から出てくるの……なに、これ……?」<br />
出てくるものをとめられないで、自分の体に異常でも起きたのかという不安に焦るにゃー子だったが、それを優しく諭すようにセイラは言った。<br />
『にゃー子。 それは、涙というものです。 涙を流せるということはですね、にゃー子。 あなたに優しい心があるからなのですよ』<br />
「なみ、だ……それって、いい、こと?」<br />
『ええ。 だってそれは、あなたに立派な心があるってことですもの』<br />
初めての涙に戸惑っていたにゃー子だったが、やがてそれは落ち着いていき。<br />
今の彼女の表情は、涙で濡れてはいたがとても可愛らしげな少女の笑顔だった。<br />
「えへへ……それならいっか」<br />
「なーにが、それならいっか、だよ!」<br />
「あいてぇ!?」<br />
こうして額を殴られるのは三度目のことだった。<br />
「人の話止めて泣き出しやがって、お前は人に説明させるのを止めたくなる癖でもあんのか?」<br />
「う~……だってぇ」<br />
「だってぇ、じゃねぇんだよ。 数分で済みそうな話をお前のせいで数十分に引き伸ばされてるこっちの身にもなれよ」<br />
『オリヴィエに賛成するわけではありませんが……確かに、尺的に少々長く使いすぎてしまいましたので、そろそろ本格的にお話したいことがあります。』<br />
「えうぅ……よくわからないよぉ……」<br />
「わからなくていい、むしろわからないでいろ」<br />
にゃー子が泣き出したことで一時的に話が止まってしまったが、それを仕切りなおすように大きな咳払いをすると話を元に戻した。<br />
『お話したいことと言うのは、なぜあなたが人間として復活したのかについて。 さきほど申しましたが、にゃー子、あなたは男の子を守るために自らを犠牲にしました。 そのためにあなたは車に撥ねられ大怪我を負いました。 そこまではわかっていますね?』<br />
「うん……」<br />
『実はそのとき、オリヴィエも近くにいたのです。 というのも、私がオリヴィエに命じて天使としての仕事をさせるためだったのですが、その命というのがあの男の子を助けることだったのです』<br />
「ええー!? オリヴィエ近くにいたの? じゃあ助けてくれたっていいのにー!」<br />
オリヴィエを非難めいた目でジーっと睨むと、顔を背けられてしまった。おまけに舌打ちも聞こえてきた。<br />
『にゃー子、あなたには難しい話かもしれませんが、本当ならばあの男の子はあの場所で車になど轢かれないはずだったのです。 それが、彼の正しい未来。 けれども、それを誰かが悪意を持って捻じ曲げて、彼に不注意をもたらした』<br />
元々猫だったにゃー子にとって、到底分かるわけがないはずの単語がちらほらと出てきている中。不思議なことにちんぷんかんぷんながらも、その言葉の本質のようなものをなぜか認識できていることに彼女は気がついた。<br />
「にゃう……つまり、誰かのせいであの子が車にぶつかることになっちゃったってこと?」<br />
『そうです、にゃー子。 そして、その誰かから人間を守るために私たち天使はいるのです』<br />
「まぁ、もう一つ、面倒な仕事があるんだけどな」<br />
セイラはそれには触れずに話を続ける。<br />
『にゃー子、あなたはさっき、オリヴィエに"助けてくれたっていいのに"と言いましたね?』<br />
「え? う、うん」<br />
『実は……助けにいこうとはしたのです。 まぁ、少々私に反抗的だったので半ば強制的に命じたのですが……そのおかげで、あの男の子を助けに行くのには七秒ほど遅れました。 ですが、七秒遅れたとしても予定通り助けること自体は可能だったのです。 そこに、予定外の事が起きてしまったのです』<br />
「よてーがい……って、何が?」<br />
「お前だ、お前。 他に誰がいるんだ?」<br />
「えと、ボク?」<br />
『そうです、にゃー子。 オリヴィエが助けに行く前にあなたが飛び込んでしまったこと。 それが私たちには予定外のことでした。 なぜなら、普通であればあの男の子が車に轢かれてしまうことなど誰にもわからないのですから、周囲に人がいたとしてもそのことに誰も"危険だ"などとは気付けないからです。 しかし、あなたは危険を察知してさらにはその身までも捧げてしまった。 私たちがたどり着いたときには、あなたはほとんど瀕死の状態でした』<br />
そのときにゃー子は自分が死ぬ間際のことを思い出した。あのときに見た、丸い輪っか。あれはオリヴィエだったのだということに気が付いた。<br />
『私は悩みました。 というのも、私たちは基本的にこの世界で力を使うのを許されているのは人間を魔法少女にすることぐらいなのです。 なので、少しだけ応用して、特別な救済処置を施したのです。 それが、あなたを人間として――魔法少女として生き返らせることでした』<br />
「まほー……しょーじょ?」 <br />
『簡単に言うと、私たちのお手伝いさん、のようなものです。 おまけに、普通の人間ではできないような不思議なことまでできてしまいます。 この魔法少女というのは何らかの素質ある者しかなることが許されていません。 私たち天使は人間を助ける他にその素質ある者を探し出すという仕事もあるのですよ』<br />
「ふーん……」<br />
そこで一度、セイラは言葉を止めた。そして、次に出す言葉はなんだか溜め込んでいたものを吐き出すようだった。<br />
『本来ならば、あなたが傷つくことも、人間になることも、なかったのです。 全ては私とオリヴィエの招いた失態です。 本当に、申し訳ないと思います。 にゃー子』<br />
姿、顔が見えなくとも、その声色から本当に申し訳ないと思っているのだと感じ取ることができた。しかしにゃー子は、こうなったのも自分の行動が起こしたことだと思っていたので、別に誰かのせいで自分がこうなったなどという風には考えてはいなかった。<br />
「ええと、でも、ボクがあの子を助けたのはボクが助けたかったからだし……いいよ、気にしなくても」<br />
『いえ、いいのです。 これは、私のけじめなのですから』<br />
「……変なの」<br />
『ふふ、そうね。 あなたからすればだいぶ、おかしなものかもしれませんね』<br />
どうしてセイラがこだわるのか、それは猫であったにゃー子には少し理解の難しいものだ。なんとなく、自分のためにこだわっているのだろうと、にゃー子は感じた。それがなんでなのかは、ちょっぴりわからなかったけれども。<br />
『さて、あなたが人間になった理由を話すのと、謝罪ができたのでそろそろ私はいなくなります』<br />
「え!? いなくなっちゃうのー!?」<br />
『いなくなるといっても、一時的にです。 そもそもこうやって話をするのも結構大変だったりするんですよ。 まぁ、折を見てまた来ますから。 そ・れ・か・ら』<br />
もしその場にいたら、たぶん首をぐいぃと回して睨み付けるかのような、そんな念を押すように。<br />
『オリヴィエ、後のこととにゃー子のこと、頼みましたよ?』<br />
と今までの話していたトーンから一オクターブくらい低い声が聞こえたかと思うと、その場からある種の気配のようなものが消失するのをにゃー子は感じる。<br />
そうして、それからいくら待とうとも、セイラの声は聞こえなくなった。<br />
「あー!! マジ疲れたわクソー!!」<br />
最初に声を出したのはオリヴィエだった。セイラがいることで余程ストレスがたまったのか、その鬱憤を放出するような叫びだ。その様子を見て、流石のにゃー子も気遣った。<br />
「だ、大丈夫、オリヴィエ?」<br />
「うっせぇ。 元はと言えばお前が車なんぞに轢かれなけりゃこうはならなかったんだ」<br />
「えう、ごめん……」<br /><br />
<br />
太陽が南に昇っている昼間。誰もいない小さな丘のあるその公園には、そよ風が吹いて木々を細かに揺らしている。心地よい風につられるように、一つのブランコが乾いた金属音を出しながら揺られている。そしてそのブランコには一人の少女が座っていた。<br />
「なんにも起きないね」<br />
「あのなぁ、そう簡単に事が起こっても俺としては困るんだよ。 できることなら何もないほうがいい、というかこんなことは他の奴に任せたいくらいだ」<br />
少女――にゃー子は退屈そうに頭上に顔を向ける。目線の先には、ブランコの鉄柱の上でやる気のない顔で座り込んでいる天使、オリヴィエの姿があった。<br />
「だって、ボクだって人を助けたいんだもん! オリヴィエは天使なんでしょ? あの人言ってたよ? 天使は人を助けるのが仕事なんだって。 オリヴィエは人を助けたくないの? ボクにくれたモノだってそのためのなんでしょ?」<br />
にゃー子はそういいながらオリヴィエに向かって首にぶら下げていたペンダントを突きつけた。問いかけられたオリヴィエは苦々しげに顔を歪ませると、それに答えることもせずサッと丘を越えてどこかに飛んでいってしまった。行き先は知らないが、しばらくするとフラッと帰ってくることをにゃー子は知っている。オリヴィエがああやって怒りながらもにゃ子から離れないのは天使としての仕事があるからだと教えられたが、自分の好きなようにできないその様子ににゃー子はただただ変なものだと感じていた。<br />
「あーあ。 またオリヴィエ怒っちゃったよ。 うーん、どうしてオリヴィエはボクが天使のこと言うといつもああなっちゃうのかなー?」<br />
キィ、キィとブランコをこいで考えてみたものの、分かるはずもなかった。そもそも、オリヴィエの言った"シゴト"さえ、今のところにゃー子は深くは理解していないのだから。<br />
オリヴィエがくれた猫の形のペンダントを空に掲げてしばらくそれを眺めてみたが、やはり何も分かりそうにはなかった。<br />
「うーん、まぁいっか」<br />
オリヴィエの怒る理由について考えるのを早々に諦めると、ぴょんとブランコから降りて、ワンピースの裾を軽く手で払う。それから、うんと背伸びをすると、にっこりと微笑んだ。<br />
「やっぱりここ、いい匂いがする」<br />
ブランコから離れて遊具のない広いスペースに移動して、くるくると回る。両腕を真横に伸ばして、くるくる回る。回転に合わせてワンピースもふわりと浮かんでいる。そんな風に回転していると、今度は木の手前で動きを止めた。なにやら、少し上にある木の枝を見つめている。<br />
「むぅ……にゃっ!」<br />
それから、今度はぴょんぴょんと飛び跳ねだした。枝に向かって飛んでいるのだろうが、どうにも届く気配がない。おそらくは枝を取ってみたいのだろうが、悲しくも彼女の身長がまず小さすぎるのだ。これが中学生以上ならまだ話は別だが、今のにゃー子は小学生と同様の体のため、木の枝に届くはずがなかった。<br />
「ふー! なんで届かないんだよー!」<br />
枝に向かって唸っているが、その様子はまるで猫が唸っているようだ。例え唸ったとしても、その木の枝が一人でに折れて落ちてくれるわけがない。<br />
そんなとき、一つの手が現れて、ぱきんと木の枝を折った。<br />
「ふぇ?」<br />
振り返ってみると、一人の青年が立っていた。にゃー子よりは明らかに身長が高く、手も長い。<br />
自分より大きな者を目にしたことでぽかん、としているにゃー子に、青年は右手に持った木の枝を差し出すと、<br />
「はい、これ」<br />
そう言ってにゃー子の右手に木の枝を握らせた。<br />
「あ、ありがと……?」<br />
「どういたしまして」<br />
青年は自分の背後に置いてある小さなダンボール箱を抱えると、首のペンダントを一度見つめてそれから視線をにゃー子に戻すと。<br />
「かわいいペンダントだね。 それじゃ」<br />
ダンボール箱を抱えたまま丘を登っていってしまった。<br />
その様子をぽわんと上の空状態で眺めているにゃー子だったが、はっとした表情になると首をぶんぶん振って意識を正気に戻そうとする。<br />
「い、今のって……!」<br />
立ち去った青年を追いかけるために慌てて自らも丘を上りだす。ついつい猫のときのように手足を使って走ってしまうほどに今の彼女は慌てていることが伺える。<br />
小高い丘を四足で駆け上るとそこにはいくつかの木々が生えているのが見える。その中でもひときわ大きいケヤキの木の下に、彼はいた。手に持っていたダンボール箱はすでに下ろしている。<br />
「い、いた!」<br />
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
</p>
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: