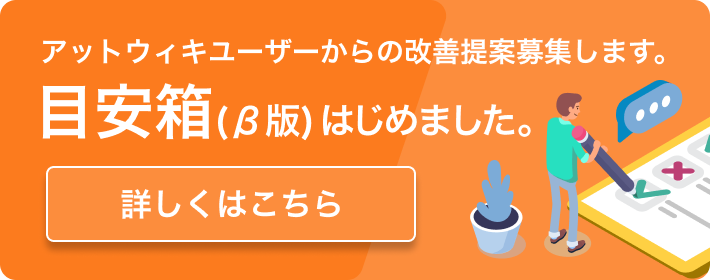大切という言葉は
どうして大きく切ないのかな?
きっと失うことを知ってるからだよ
どうして大きく切ないのかな?
きっと失うことを知ってるからだよ
赤く暗い世界。
異臭が辺りにたちこめる。
いつも感じられどれだけ洗っても落ちない臭い。
悪魔が僕の後ろで笑っている。
激しく息をする度にその臭いが感じられて吐き気がする。
脂汗が頬を伝い落ちる感覚にすら鳥肌が立つ。
必死に足を動かしても地面は足が着いた場所から沈み込み遅々として進まない。
なりふりかまわず壁に手を着けばそこすらも沈み込む。
道路は沼に壁は肉に。
視界を埋めるものは全て赤黒く脈動し僕のほうに押し寄せてくる。
いっそ力を抜いて倒れこんでしまいたいけど僕にはそれすら許されない。
誰かに強制されているかのように僕の足は動き続ける。
ただ機械的に。
何に追われているのかもわからないまま僕は逃げ続ける。
何時間?何日?何ヶ月?それとも何年?
口の中には血の味をする唾が溜まっている。
疲れの溜まった足は思い通りに動かなくて鉛のように重い。
「もう……いいだろ……や、休んでも……いいだろ?」
何度目かわからない弱音が喉から搾り出される。
誰に言っているのかも定かではない言葉。
自分の足で走っているのだから自由に止まれるはずなのに。
そんな簡単なことが僕には出来ない。
体の動かし方ではなく止め方を忘れてしまった。
逃げる。
どうしてだろう。
いつからだろう。
逃げ続けているのは。
ああ、思い出した
僕は簡単なことに気が付く。
あんまりにも身近なことで忘れてた。
思い出した瞬間世界がひび割れた。
僕は悪魔に襲われた。
異臭が辺りにたちこめる。
いつも感じられどれだけ洗っても落ちない臭い。
悪魔が僕の後ろで笑っている。
激しく息をする度にその臭いが感じられて吐き気がする。
脂汗が頬を伝い落ちる感覚にすら鳥肌が立つ。
必死に足を動かしても地面は足が着いた場所から沈み込み遅々として進まない。
なりふりかまわず壁に手を着けばそこすらも沈み込む。
道路は沼に壁は肉に。
視界を埋めるものは全て赤黒く脈動し僕のほうに押し寄せてくる。
いっそ力を抜いて倒れこんでしまいたいけど僕にはそれすら許されない。
誰かに強制されているかのように僕の足は動き続ける。
ただ機械的に。
何に追われているのかもわからないまま僕は逃げ続ける。
何時間?何日?何ヶ月?それとも何年?
口の中には血の味をする唾が溜まっている。
疲れの溜まった足は思い通りに動かなくて鉛のように重い。
「もう……いいだろ……や、休んでも……いいだろ?」
何度目かわからない弱音が喉から搾り出される。
誰に言っているのかも定かではない言葉。
自分の足で走っているのだから自由に止まれるはずなのに。
そんな簡単なことが僕には出来ない。
体の動かし方ではなく止め方を忘れてしまった。
逃げる。
どうしてだろう。
いつからだろう。
逃げ続けているのは。
ああ、思い出した
僕は簡単なことに気が付く。
あんまりにも身近なことで忘れてた。
思い出した瞬間世界がひび割れた。
僕は悪魔に襲われた。
僕は閉じたまぶたの裏にうっすらとした明るさを感じて目を覚ます。
目に入るのは見慣れたワンルームマンションの白い天井。
つまり僕の家だ。
少し開いた遮光カーテンからは朝日が差し込んでいる。
日の出からあまり時間は経ってないみたいだけどその光は眠りを妨げるには十分だ。
「寒っ」
春といえども朝はまだ寒い。
これだけ寝汗をかいてればなおさらだ。
枕もとの時計を見ると角ばった無機質な文字があらわすのは午前五時。
朝食を食べるのには少し早い時間だ。
空腹感よりもまず気が付くのがかいた汗と口の中に広がる苦い味。
経験的に夢の内容にも想像がつく。
内容は覚えてないがきっと悪い夢だったのだろう。
そして経験的に今日があまり良くない日になるであろうことも。
悩んでても仕方ない。
汗で湿ったままってのも気持ち悪い。
気分転換もかねて口に出して言ってみる。
「よっしシャワーでも浴びるか」
うん、いつも通り今日も最悪な日だろう。
目に入るのは見慣れたワンルームマンションの白い天井。
つまり僕の家だ。
少し開いた遮光カーテンからは朝日が差し込んでいる。
日の出からあまり時間は経ってないみたいだけどその光は眠りを妨げるには十分だ。
「寒っ」
春といえども朝はまだ寒い。
これだけ寝汗をかいてればなおさらだ。
枕もとの時計を見ると角ばった無機質な文字があらわすのは午前五時。
朝食を食べるのには少し早い時間だ。
空腹感よりもまず気が付くのがかいた汗と口の中に広がる苦い味。
経験的に夢の内容にも想像がつく。
内容は覚えてないがきっと悪い夢だったのだろう。
そして経験的に今日があまり良くない日になるであろうことも。
悩んでても仕方ない。
汗で湿ったままってのも気持ち悪い。
気分転換もかねて口に出して言ってみる。
「よっしシャワーでも浴びるか」
うん、いつも通り今日も最悪な日だろう。
「あ゛ぁ~~」
いかんいかん油断しすぎてオヤジ臭い声が出てしまった。
「やはり朝風呂に入ると気持ちいいものだね?うむ」
気分がよくなってきたので芝居がかった調子で呟いてみる。
いいね朝風呂。
目も覚めるしこれからの時期は暑くなるから夜に風呂に入っても朝には汗まみれでべとべとする。
クーラーをつけられればいいのだがいかんせん環境破壊が気にかかる。
やはり地球に住まう一人として環境破壊は防がねばなあないことなのだ!……いやごめん嘘です。
僕はそんな人が出来ていません。
南の島が海に沈んでも「しょうがないね」で済ませてしまうような薄情な人間なんです。
クーラーつけると電気代がかかるんです。
家計のやりくりが辛くなるんです。
貧乏だから贅沢できないんです。
いかんいかん油断しすぎてオヤジ臭い声が出てしまった。
「やはり朝風呂に入ると気持ちいいものだね?うむ」
気分がよくなってきたので芝居がかった調子で呟いてみる。
いいね朝風呂。
目も覚めるしこれからの時期は暑くなるから夜に風呂に入っても朝には汗まみれでべとべとする。
クーラーをつけられればいいのだがいかんせん環境破壊が気にかかる。
やはり地球に住まう一人として環境破壊は防がねばなあないことなのだ!……いやごめん嘘です。
僕はそんな人が出来ていません。
南の島が海に沈んでも「しょうがないね」で済ませてしまうような薄情な人間なんです。
クーラーつけると電気代がかかるんです。
家計のやりくりが辛くなるんです。
貧乏だから贅沢できないんです。
バスタオルのみで台所に立っているのにはわけがある。
風呂を出たらすることはただ一つ。
そう牛乳の一気飲みだ。
これはもやは日本人の常識、いや人類の常識。
サルから進化した人間に遺伝子レベルで刻み込まれてることなのだ。
牛乳飲めば女は胸が成長する。
おっぱいですよおっぱい。
牛乳飲んでおっぱいが大ききなるということはおっぱいは牛乳でできているという証明だ。
牛乳=おっぱい。
あの豊満で柔らかな胸の中身は牛乳だ。
つまり僕がこれから飲み尽くすのはおっぱい。
エ、エロい。
さてさてはやる気持ちを抑えつつ、
「オープン・ザ・冷蔵庫……な!?」
無い。
牛乳が無い。
おっぱいが無い。
僕のおっぱいはどこに行った!?
「誰が僕のおっぱいを盗んだんだぁぁああ!!」
……
落ち着いてみれば冷蔵庫の中がほぼ空だ。
内壁の白さが目立つほどに中には何もない。
「忘れてた……」
そういえば昨日きりがいいからと掃除もかねて余っていた食材を全て使い切って買い物に行こうとして結局行かなかったんだ。
冷蔵庫の中には練りわさびと醤油とヨーグルト。
しかもヨーグルトはふたを開けてみると不自然に黄色みがかっていた。
賞味期限を見てみると数字があらわすのは三月ほど前だ。
これを食べるのは無茶と言うものだ。
悪夢を見た不運が早速始まった。
「これでどうしろと?」
両手になけなしの食材を持って思考する。
早朝でまだ開いてる店は少ない。
コンビニまでは少し遠い。
ついでに駅までも遠い。
まあそれがこのマンションが安い理由でもあるのだから文句も言えない。
朝から自転車をこいで朝飯を買いに行くのもめんどくさい話しだ。
「は!?」
これはまさかアレか?
天からの啓示か?
つまり練りわさび&醤油inヨーグルトか?
新しき味覚。
食べ物は腐る直前が一番うまいと言う。
若干黄ばんでいるように見えるが腐ってはいないだろう。
人類は常に挑戦によって発展してきた。
人類に挑戦する意思が無ければここまで発展はしてこなかっただろう。
ならば僕もそのフロンティアスピリットに従うべきではないか。
「炭水化物が無いのが若干つらいところではあるが、いざ行かん未知なる世界へ!」
風呂を出たらすることはただ一つ。
そう牛乳の一気飲みだ。
これはもやは日本人の常識、いや人類の常識。
サルから進化した人間に遺伝子レベルで刻み込まれてることなのだ。
牛乳飲めば女は胸が成長する。
おっぱいですよおっぱい。
牛乳飲んでおっぱいが大ききなるということはおっぱいは牛乳でできているという証明だ。
牛乳=おっぱい。
あの豊満で柔らかな胸の中身は牛乳だ。
つまり僕がこれから飲み尽くすのはおっぱい。
エ、エロい。
さてさてはやる気持ちを抑えつつ、
「オープン・ザ・冷蔵庫……な!?」
無い。
牛乳が無い。
おっぱいが無い。
僕のおっぱいはどこに行った!?
「誰が僕のおっぱいを盗んだんだぁぁああ!!」
……
落ち着いてみれば冷蔵庫の中がほぼ空だ。
内壁の白さが目立つほどに中には何もない。
「忘れてた……」
そういえば昨日きりがいいからと掃除もかねて余っていた食材を全て使い切って買い物に行こうとして結局行かなかったんだ。
冷蔵庫の中には練りわさびと醤油とヨーグルト。
しかもヨーグルトはふたを開けてみると不自然に黄色みがかっていた。
賞味期限を見てみると数字があらわすのは三月ほど前だ。
これを食べるのは無茶と言うものだ。
悪夢を見た不運が早速始まった。
「これでどうしろと?」
両手になけなしの食材を持って思考する。
早朝でまだ開いてる店は少ない。
コンビニまでは少し遠い。
ついでに駅までも遠い。
まあそれがこのマンションが安い理由でもあるのだから文句も言えない。
朝から自転車をこいで朝飯を買いに行くのもめんどくさい話しだ。
「は!?」
これはまさかアレか?
天からの啓示か?
つまり練りわさび&醤油inヨーグルトか?
新しき味覚。
食べ物は腐る直前が一番うまいと言う。
若干黄ばんでいるように見えるが腐ってはいないだろう。
人類は常に挑戦によって発展してきた。
人類に挑戦する意思が無ければここまで発展はしてこなかっただろう。
ならば僕もそのフロンティアスピリットに従うべきではないか。
「炭水化物が無いのが若干つらいところではあるが、いざ行かん未知なる世界へ!」
ええ、いきましたとも。
見事に逝きました。
食卓に現れた人外魔境へ逝って参りました。
「脳汁でちゃう……」
あれはやばかった。
おもにヨーグルトが。
味覚もさることながら賞味期限切れだったのがまずかった。
だから僕はやめていた方がいいと言ったんですよ……
誰にでもなく弁明する。
つい数分前まで意識が飛んでた。
今でも床から立ち上がることが出来ない。
というよりもちゃぶ台に伏せっぱなしだが。
今……何時だ?
意識が飛んでて時間の感覚も無い。
部屋は明るくなってるから結構な時間が経ったのだろう。
下手したら昼下がりかも知れない。
何日も気絶してたけど誰も気が付いてくれなかったのかもしれない。
これがいわゆる孤独死と言うヤツか。
時計はちょうど見えない位置にある。
「……しょうがない」
力の入らない体に精一杯の意思で立つように命令を送る。
「おお?」
人体の限界を意思は凌駕するのか?
少しずつ持ち上がっていく上半身。
そして背が真っ直ぐになった瞬間――後ろに倒れる。
駄目でした。
僕には限界は超えられません。
やっぱり意志の力が限界を凌駕するなんてことも無くて後頭部を床に打ち付ける。
しかもフローリングの床に。
痛みに悶えたくても腕が上がらない。
先立つ不幸をお許しください。
……そうじゃないか、と。
ピンポーン。
誰か来たみたいだ。
しかし悲しいかな僕に玄関まで行って鍵を開けるだけの力は無い。
僕にはその救い主を迎え入れることが出来ない。
来訪者はそのまま何度もチャイムを鳴らす。
そしてドアノブを回そうとする。
きっと彼もしくは彼女は僕がいないと思って帰ってしまうのだろう。
無人島に漂流して飛行機に助けを求めるけど気付かれず飛んでいってしまったときはこんな気持ちになるのだろう。
無力な僕を笑うがいい。
無様な僕を笑うがいい。
僕はこのまま孤独死するのさ。
「フフフ……ハハハ……アッハハハハハ」
気が狂ったかのように僕は笑い出す。
そしてついにはノブを回す音さえ止んだ。
見捨てられた僕は死を待つのみだ。
「もーお兄ちゃんはまた変な声上げて」
「ハハハ……は?」
ノブに鍵が差し込まれる。
この家の鍵を持っているのは僕と叔父さんともう一人。
勢い良くドアが開けられる。
「大丈夫お兄ちゃん!……何やってるの?」
そう彼女、秋野奏だ。
姓の違う僕の妹がスーパーの袋に大量の食材を詰めて訪ねてきたのだ。
見事に逝きました。
食卓に現れた人外魔境へ逝って参りました。
「脳汁でちゃう……」
あれはやばかった。
おもにヨーグルトが。
味覚もさることながら賞味期限切れだったのがまずかった。
だから僕はやめていた方がいいと言ったんですよ……
誰にでもなく弁明する。
つい数分前まで意識が飛んでた。
今でも床から立ち上がることが出来ない。
というよりもちゃぶ台に伏せっぱなしだが。
今……何時だ?
意識が飛んでて時間の感覚も無い。
部屋は明るくなってるから結構な時間が経ったのだろう。
下手したら昼下がりかも知れない。
何日も気絶してたけど誰も気が付いてくれなかったのかもしれない。
これがいわゆる孤独死と言うヤツか。
時計はちょうど見えない位置にある。
「……しょうがない」
力の入らない体に精一杯の意思で立つように命令を送る。
「おお?」
人体の限界を意思は凌駕するのか?
少しずつ持ち上がっていく上半身。
そして背が真っ直ぐになった瞬間――後ろに倒れる。
駄目でした。
僕には限界は超えられません。
やっぱり意志の力が限界を凌駕するなんてことも無くて後頭部を床に打ち付ける。
しかもフローリングの床に。
痛みに悶えたくても腕が上がらない。
先立つ不幸をお許しください。
……そうじゃないか、と。
ピンポーン。
誰か来たみたいだ。
しかし悲しいかな僕に玄関まで行って鍵を開けるだけの力は無い。
僕にはその救い主を迎え入れることが出来ない。
来訪者はそのまま何度もチャイムを鳴らす。
そしてドアノブを回そうとする。
きっと彼もしくは彼女は僕がいないと思って帰ってしまうのだろう。
無人島に漂流して飛行機に助けを求めるけど気付かれず飛んでいってしまったときはこんな気持ちになるのだろう。
無力な僕を笑うがいい。
無様な僕を笑うがいい。
僕はこのまま孤独死するのさ。
「フフフ……ハハハ……アッハハハハハ」
気が狂ったかのように僕は笑い出す。
そしてついにはノブを回す音さえ止んだ。
見捨てられた僕は死を待つのみだ。
「もーお兄ちゃんはまた変な声上げて」
「ハハハ……は?」
ノブに鍵が差し込まれる。
この家の鍵を持っているのは僕と叔父さんともう一人。
勢い良くドアが開けられる。
「大丈夫お兄ちゃん!……何やってるの?」
そう彼女、秋野奏だ。
姓の違う僕の妹がスーパーの袋に大量の食材を詰めて訪ねてきたのだ。
「いやー本っ当に助かった」
「もう朝から馬鹿な事ばっかやって」
怒りつつも奏の作ってくれた朝食で僕は全快した。
体とは欲求に正直なものだ。
奏が料理を作ってくれたとたん僕の体は限界を凌駕し今に至るわけだ。
空きっ腹におかしな物を食べたのがいけなかったらしい。
「お父さんに様子を見てきてほしいって頼まれて来てみればこんなことに。
これはもう捨てちゃうからね」
エプロン姿の彼女の手には練りわさび&醤油inヨーグルトが。
「ま、待てそれは結構いけるぞ?
サラダにドレッシングとしてかけてみたりするとおいしいかもしれん」
必死で止めに入る。
「そんなことばっか言って。こんなもの食べるからダウンしてたんでしょ」
それを言っちゃおしまいだ。
反論のしようが無い正論に無力な僕はヨーグルトを見捨てることしか出来ない。
ああ、人類の開拓精神よ。
ヨーグルトは水に流れて大海原へと旅立っていった。
さらば友よ。
短い付き合いだったがお前の事は忘れないぜ。
流れていく瞬間ヤツも笑っていた気がした。
「相棒、俺は先に旅に出るぜ。俺達また会えるよな?」
そんな幻聴まで聞こえてくる。
僕は必死に涙を堪えながら、
ああ絶対に追いついてみせる、絶対だ。
声に出さずに僕は決意する。
そんな風に僕が友と書いて「ライバル」を見送ってると半目で奏が僕のことを見つめていた。
「ん?何見てるの?アレに未練があるの?」
正直に言っても馬鹿にされるだけだろう。
「いやエプロン姿の奏に見とれてたのさ」
「あわわな、何馬鹿な事言ってるの。学校に遅れるよ!さ、先に出てるからね!」
顔を真っ赤にして慌ててく出て行く奏。
全くからかいがいがあるな。
そうは言いつつも奏もなかなか整った顔立ちをしてるから全く嘘というわけでもない。
くっきりとした二重に大きな瞳。
小さめの顔に後ろで結んだ綺麗な黒髪。
胸は若干盛りが足りない。
牛乳飲め牛乳。
妹である贔屓目を抜きにしても可愛いほうだとは思う。
上の下くらいかな?
中の上と上の下だと上の下のほうが可愛い感じがするね。
流石日本語気遣いが出来てるぜ。
学年で見たらトップハンドレットに入るくらいだ。
まあ一学年男女合わせて200人くらいなわけだが。
しかし実際結構もてるらしい。
この前もわざわざうちに来て愚痴っていったっけ。
本当に何のために来たんだか。
僕に行っても何かが変わるわけでもないのに手紙も見せびらかすようにしながら。
ちなみに告白を手紙で済ませようとするヤツは信用できんね。
男なら正々堂々正面から当たって欠片すら残さず玉砕粉砕しなきゃいかん。
そんなヤツと付き合いはじめたら「貴様にワシの妹はやらん!」とびしっと言ってやらねばならん。
と、いけない。
このままでは学校に遅刻してしまう。
急いで制服を着こんでほとんど空っぽのカバンを掴んで外に出る。
学校に教材をすべて置いてあるので持っていくものは何も無い。
ドアを開けて廊下に出ると奏がいない。
「遅いと置いてくよ」
既に彼女は階段の前に立っている。
「じゃ」
僕の返事を聞かないうちに階段を下りていく。
「まったく」
せっかちなのは誰の影響だか。
葉山と書かれた表札に一瞬だけ目を向ける。
湧き上がるこの気持ちはなんだろう。
あいまいな気持ちを振り切り鍵をかけて奏を追う。
「もう朝から馬鹿な事ばっかやって」
怒りつつも奏の作ってくれた朝食で僕は全快した。
体とは欲求に正直なものだ。
奏が料理を作ってくれたとたん僕の体は限界を凌駕し今に至るわけだ。
空きっ腹におかしな物を食べたのがいけなかったらしい。
「お父さんに様子を見てきてほしいって頼まれて来てみればこんなことに。
これはもう捨てちゃうからね」
エプロン姿の彼女の手には練りわさび&醤油inヨーグルトが。
「ま、待てそれは結構いけるぞ?
サラダにドレッシングとしてかけてみたりするとおいしいかもしれん」
必死で止めに入る。
「そんなことばっか言って。こんなもの食べるからダウンしてたんでしょ」
それを言っちゃおしまいだ。
反論のしようが無い正論に無力な僕はヨーグルトを見捨てることしか出来ない。
ああ、人類の開拓精神よ。
ヨーグルトは水に流れて大海原へと旅立っていった。
さらば友よ。
短い付き合いだったがお前の事は忘れないぜ。
流れていく瞬間ヤツも笑っていた気がした。
「相棒、俺は先に旅に出るぜ。俺達また会えるよな?」
そんな幻聴まで聞こえてくる。
僕は必死に涙を堪えながら、
ああ絶対に追いついてみせる、絶対だ。
声に出さずに僕は決意する。
そんな風に僕が友と書いて「ライバル」を見送ってると半目で奏が僕のことを見つめていた。
「ん?何見てるの?アレに未練があるの?」
正直に言っても馬鹿にされるだけだろう。
「いやエプロン姿の奏に見とれてたのさ」
「あわわな、何馬鹿な事言ってるの。学校に遅れるよ!さ、先に出てるからね!」
顔を真っ赤にして慌ててく出て行く奏。
全くからかいがいがあるな。
そうは言いつつも奏もなかなか整った顔立ちをしてるから全く嘘というわけでもない。
くっきりとした二重に大きな瞳。
小さめの顔に後ろで結んだ綺麗な黒髪。
胸は若干盛りが足りない。
牛乳飲め牛乳。
妹である贔屓目を抜きにしても可愛いほうだとは思う。
上の下くらいかな?
中の上と上の下だと上の下のほうが可愛い感じがするね。
流石日本語気遣いが出来てるぜ。
学年で見たらトップハンドレットに入るくらいだ。
まあ一学年男女合わせて200人くらいなわけだが。
しかし実際結構もてるらしい。
この前もわざわざうちに来て愚痴っていったっけ。
本当に何のために来たんだか。
僕に行っても何かが変わるわけでもないのに手紙も見せびらかすようにしながら。
ちなみに告白を手紙で済ませようとするヤツは信用できんね。
男なら正々堂々正面から当たって欠片すら残さず玉砕粉砕しなきゃいかん。
そんなヤツと付き合いはじめたら「貴様にワシの妹はやらん!」とびしっと言ってやらねばならん。
と、いけない。
このままでは学校に遅刻してしまう。
急いで制服を着こんでほとんど空っぽのカバンを掴んで外に出る。
学校に教材をすべて置いてあるので持っていくものは何も無い。
ドアを開けて廊下に出ると奏がいない。
「遅いと置いてくよ」
既に彼女は階段の前に立っている。
「じゃ」
僕の返事を聞かないうちに階段を下りていく。
「まったく」
せっかちなのは誰の影響だか。
葉山と書かれた表札に一瞬だけ目を向ける。
湧き上がるこの気持ちはなんだろう。
あいまいな気持ちを振り切り鍵をかけて奏を追う。
「待ってってば」
「早くしないと学校にも遅刻するしチカ姉たちも行っちゃうよ」
待ち合わせ場所までそんなに無いだろ。
すぐ先の十字路だ。
待ち合わせまでは後五分以上もある。
どんなにゆっくり行っても間に合う。
ほら、もう見えてきた。
二人も僕達のことを確認したみたいだ。
僕が軽く手を上げると声が返ってきた。
「おーいカナちゃーん」
「おう、奏ちゃんおはよう」
ほれ見ろまだ二人ともいるじゃないか。
と言うか僕に挨拶がないのはデフォですか?。
イジメですか?
ムシですか?
そうですか。
まあ、あれだ光の加減か何かで見えなかったんだろう。
大人な僕は挨拶がなかったくらいじゃ拗ねたりしませんよ、ええ。
そんなことにたいしたショックは受けたりしませんよ。
まあ黙ってれば向こうから挨拶してくるだろ。
自分から?
いえいえ、負けた気がするからしませんよ。
そのまま奏は二人の横に並んで歩き出す。
僕はと言うと少し離れた位置で散歩ほど遅れながらついていく。
「…………」
「おはよう、タカ兄チカ姉」
「…………」
「奏ちゃんはどこかの馬鹿と違って今日も可愛いね」
「やだ口がうまいんだから、もう」
「…………」
「いやいやカナちゃんは可愛いわよ」
千華がそれに追随する。
「…………」
つかそろそろ挨拶してもいいんじゃない?
他人が見たら僕はまるで輪に入れてもらいたいけど入れてもらえないかわいそうな子じゃないか。
まさに「三人用なんだ」ってセリフが似合う感じだよね。
「チカ姉もそんこと言って……あれ?シャンプー変えた?」
そういえばさっきからいつもの千華とは違う香りがするな。
「…………」
でもここで声を出すと負けた気がするので無言。
これは試されているのだ。
絶対に話しかけてやるもんか。
何気なく空に視線を逸らして待ってみる。
さあカモンカモン、お前ら挨拶するなら今がチャンスだぜ。
さも今気が付いたかのように自然に挨拶してくるが良い。
これは要求ではなく機会を与えると言う情けなのだよ。
「わかる?そうなのよ。ちょっと淡いラベンダーの香りのにしてみたの」
「…………」
「え?そうだったのか?全く気が付かなかった」
「…………」
「タカ兄ヒドーイ。ファッションは女の命なんだから」
そう言って奏が隆司の背中を軽く叩く。
「…………」
さあさあ無言でいるのがつらくなってまいりました。
……なんだろうこの孤独感は。
ええい、負けでいい負けでいい。
いや、挨拶するのは負けじゃないよね?
つまらない意地を張る奴らに対しての穏便な対応。
大人な僕に幼稚な三人と言う構図になるわけだ。
うんうんこれで大義名分は立ったわけだ。
さて分別のある大人な僕が先に折れてあげようじゃないか。
ちょっとわざとらしく片手を挙げて白い歯を見せ微笑みかける。
顔は正面ではなく少し傾けて。
この向きこそがいつも僕が寝る前に練習しているベストな角度。
いつもの僕に比べてさわやかさ三厘増しだ。
「おは「隆司はいつも鈍感なんだから~」
あれ?
被っちゃったー。
やっちゃたよー。
「そりゃ言いすぎだろ」
「そんなことないよタカ兄は鈍感だよー」
あれ?なんか僕を拒絶する眩しい空間が出来てますよ?
周りにはうっすらとピンク色のグラデーションまでかかって笑い声の絶えない、
そう、まるで陽だまりのような暖かさが。
僕は完全に蚊帳の外で見ているこちらが恥ずかしくなりそうだ。
いいもんいいもんどうせ俺は無視される存在だもん。
ちょっと涙ぐんでみる。
そんな僕を気にも留めずに奏と千華は話し続ける。
「……お前らなんか……お前らなんかぁぁぁぁぁぁ!!!!」
「あ、おい!?」
両手を胸の前まであげて女の子走りで道を走り出す。
まさに悲劇のヒロインだ。
「……ちくせう汗で目が滲むぜ」
まさに今まさに僕の目からは涙が噴水のように噴出している(イメージ)。
その涙をぬぐいながら前を見ると大通りが見えた。
なかなか交通量の多い通りでこの時間から車が絶えず通っている。
三人とも結構後ろに置いてきた事だしそろそろ止まるか。
拭っていた手を下ろした瞬間それが目に入った。
「早くしないと学校にも遅刻するしチカ姉たちも行っちゃうよ」
待ち合わせ場所までそんなに無いだろ。
すぐ先の十字路だ。
待ち合わせまでは後五分以上もある。
どんなにゆっくり行っても間に合う。
ほら、もう見えてきた。
二人も僕達のことを確認したみたいだ。
僕が軽く手を上げると声が返ってきた。
「おーいカナちゃーん」
「おう、奏ちゃんおはよう」
ほれ見ろまだ二人ともいるじゃないか。
と言うか僕に挨拶がないのはデフォですか?。
イジメですか?
ムシですか?
そうですか。
まあ、あれだ光の加減か何かで見えなかったんだろう。
大人な僕は挨拶がなかったくらいじゃ拗ねたりしませんよ、ええ。
そんなことにたいしたショックは受けたりしませんよ。
まあ黙ってれば向こうから挨拶してくるだろ。
自分から?
いえいえ、負けた気がするからしませんよ。
そのまま奏は二人の横に並んで歩き出す。
僕はと言うと少し離れた位置で散歩ほど遅れながらついていく。
「…………」
「おはよう、タカ兄チカ姉」
「…………」
「奏ちゃんはどこかの馬鹿と違って今日も可愛いね」
「やだ口がうまいんだから、もう」
「…………」
「いやいやカナちゃんは可愛いわよ」
千華がそれに追随する。
「…………」
つかそろそろ挨拶してもいいんじゃない?
他人が見たら僕はまるで輪に入れてもらいたいけど入れてもらえないかわいそうな子じゃないか。
まさに「三人用なんだ」ってセリフが似合う感じだよね。
「チカ姉もそんこと言って……あれ?シャンプー変えた?」
そういえばさっきからいつもの千華とは違う香りがするな。
「…………」
でもここで声を出すと負けた気がするので無言。
これは試されているのだ。
絶対に話しかけてやるもんか。
何気なく空に視線を逸らして待ってみる。
さあカモンカモン、お前ら挨拶するなら今がチャンスだぜ。
さも今気が付いたかのように自然に挨拶してくるが良い。
これは要求ではなく機会を与えると言う情けなのだよ。
「わかる?そうなのよ。ちょっと淡いラベンダーの香りのにしてみたの」
「…………」
「え?そうだったのか?全く気が付かなかった」
「…………」
「タカ兄ヒドーイ。ファッションは女の命なんだから」
そう言って奏が隆司の背中を軽く叩く。
「…………」
さあさあ無言でいるのがつらくなってまいりました。
……なんだろうこの孤独感は。
ええい、負けでいい負けでいい。
いや、挨拶するのは負けじゃないよね?
つまらない意地を張る奴らに対しての穏便な対応。
大人な僕に幼稚な三人と言う構図になるわけだ。
うんうんこれで大義名分は立ったわけだ。
さて分別のある大人な僕が先に折れてあげようじゃないか。
ちょっとわざとらしく片手を挙げて白い歯を見せ微笑みかける。
顔は正面ではなく少し傾けて。
この向きこそがいつも僕が寝る前に練習しているベストな角度。
いつもの僕に比べてさわやかさ三厘増しだ。
「おは「隆司はいつも鈍感なんだから~」
あれ?
被っちゃったー。
やっちゃたよー。
「そりゃ言いすぎだろ」
「そんなことないよタカ兄は鈍感だよー」
あれ?なんか僕を拒絶する眩しい空間が出来てますよ?
周りにはうっすらとピンク色のグラデーションまでかかって笑い声の絶えない、
そう、まるで陽だまりのような暖かさが。
僕は完全に蚊帳の外で見ているこちらが恥ずかしくなりそうだ。
いいもんいいもんどうせ俺は無視される存在だもん。
ちょっと涙ぐんでみる。
そんな僕を気にも留めずに奏と千華は話し続ける。
「……お前らなんか……お前らなんかぁぁぁぁぁぁ!!!!」
「あ、おい!?」
両手を胸の前まであげて女の子走りで道を走り出す。
まさに悲劇のヒロインだ。
「……ちくせう汗で目が滲むぜ」
まさに今まさに僕の目からは涙が噴水のように噴出している(イメージ)。
その涙をぬぐいながら前を見ると大通りが見えた。
なかなか交通量の多い通りでこの時間から車が絶えず通っている。
三人とも結構後ろに置いてきた事だしそろそろ止まるか。
拭っていた手を下ろした瞬間それが目に入った。
なんでだ。
なんでお前は僕の心をかき乱す?
理性悟性感情情熱それら全てが合唱を始める。
頭の中で大きな音が鳴り響きわたる
意識が一瞬遠のく。
それはただの犬だった。
通りの向こう側に黒い大型犬がいる。
ただそれだけのことだ。
ドクンドクン。
耳のすぐ近くで心臓が鼓動する。
走っている感覚すらあいまいで僕は奴を見る。
丸いガラス球の様な瞳。
その瞳に心をかき乱される。
ドクンドクン。
隠し事がばれたかのように。
道化の化粧が剥がれてしまったのかのように。
むき出しになった心が現実に削り取られてしまう。
ただ見つめあうだけただそれだけで僕は落ち着かなくなる。
その雄雄しさ堂々たる姿はまさに王者。
犬ではなく獅子ではないかと疑うほどだ。
走っても近づけない。
道路の向こうはまるで彼岸。
走っても走っても近くなりはしない。
誰かが僕の手を掴む。
放せよ。
亡者の手だ。
僕を生かせまいとする亡者が僕を引き止める。
それでも僕は振り返らない。
僕はあの犬から目が放せない。
血液が沸騰し眼が奴以外を映さなくなる。
あいつは――
あいつだけは――
後ろから強い力で引かれた。
うるさい。
僕の邪魔をするな。
赤い紐がするりと首に巻きつく。
一際強く引かれ僕はたたらを踏む。
鼻先を鉄の塊が通り抜ける。
空を見ていた。
三半規管が僕の体が傾いてることを教えてくれた。
一瞬遅れて背中に衝撃が来る。
意思とは無関係に体が息を絞り出す。
ビルで区切られた狭い空に三人の人間が写りこむ。
「――――」
何を言ってるのか聞こえない。
あいつは。
あいつはどうした。
受身を取ることの出来なかった体は満足に動かず起き上がろうとして惨めにのたうつ。
急に頭が持ち上げられた。
「――――」
頭の下に差し込まれるのは柔らかい温もり。
その温もりすら踏みにじるようにして僕は体を起こした。
道路の向こうには――何もいない。
冷静になる。
たかが犬じゃないか。
何を必死になることがある。
あばら骨だった浮いてたし毛並みだった汚れてた。
どこかの路地にいるような貧相な奴でどうせ野良犬だ。
亡くなった大金持ちの飼い主の遺産を相続してるわけじゃないだろうしCIAの暗号文書を持ってるわけでもない。
そう、なんてことはないただの犬だ。
そのまま僕は力を失って後ろに倒れた。
迎えてくれるのは先ほどの温もり、千華の膝枕だ。
「おい!コウ!」
「光!」
「お兄ちゃん!」
三人とも馬鹿みたいに必死な顔をしている。
千華と奏が心配そうに見つめる中隆司が僕の頬を何度も叩く。
痛いな畜生。
「叩くなよ」
僕はそれだけ呟くとその手を受け止めた。
「後ろに引き倒すなんてふざけ過ぎだろ」
僕と隆司じゃそもそものスペックが違いすぎる。
隆司はどの運動部でも即レギュラークラスで僕はしがない帰宅部。
軽く襟首を引かれるだけで後ろにひっくり返ってしまう。
「ふざけ過ぎって……お前自分が何したか覚えてないのか!?」
「?」
横から涙目の奏が口を挟む。
「お、お兄ちゃん……道路に飛び出しそうになって。
道路の真ん中に立ってそれでタ、タカ兄が引っ張ろうとしたの……う、ひっぐひぐ」
あちゃちゃ完全に泣き出しちゃったよ。
そこから千華が引き継ぐ。
「それでもあんた隆司のこと存在しないみたいにぼけっと突っ立ってて二人ともトラックに轢かれそうになったとこを私も引っ張ってようやく……」
声はあげないけど千華の瞳からも涙の雫が零れ落ちそうだ。
僕が犬を見てる間にも迷惑かけてみたいだ。
「なんだそんなことがあったのか。いやはやビックリ」
三人ともきょとんとあっけにとられた顔をした。
涙で顔がぐちゃぐちゃになってる奏までが泣き止んで僕のことを見ている。
ん?何か変なことを言ったかな?
ただ僕は思ったことを口にしただけなんだけど。
僕が気付いてないだけで見当違いのこと言っちゃったのかな?
「おま……いや、きっとまだショックが抜けてないんだろ。
ほら立てるか?」
そう聞きつつ僕の意思を無視して引っ張り起こす。
少しよろめきながらも僕は無事立ち上がる。
倒された拍子に飛んでったカバンを拾うと千華が胸に飛び込んできた。
何も言わないけど僕の服の胸の辺りを掴んで俯いている。
「…………馬鹿ぁ、あんたは大馬鹿よ」
結局無事だったんだからそんな心配することでもないだろうに。
それにしてもいつまで抱きついてるつもりだろう。
白昼堂々とそんなことをされたら僕も居心地が悪い。
視線を逸らして話題を変えるように
「そろそろ時間やばいんじゃない?早く行こうぜ」
少し強引に千華を引き剥がし三人を置いてくように歩き出す。
現実感が希薄だった。
自分のことなのにまるで画面の向こう側のことのようで。
僕はそれを見ているだけの他人のようで。
さっきの話もそうだ。
なんの感慨もなくあくまで事実を確認しただけだった。
なんでこうなんだろう?
僕は誰なんだろう?
お前は誰だ?
なんでお前は僕の心をかき乱す?
理性悟性感情情熱それら全てが合唱を始める。
頭の中で大きな音が鳴り響きわたる
意識が一瞬遠のく。
それはただの犬だった。
通りの向こう側に黒い大型犬がいる。
ただそれだけのことだ。
ドクンドクン。
耳のすぐ近くで心臓が鼓動する。
走っている感覚すらあいまいで僕は奴を見る。
丸いガラス球の様な瞳。
その瞳に心をかき乱される。
ドクンドクン。
隠し事がばれたかのように。
道化の化粧が剥がれてしまったのかのように。
むき出しになった心が現実に削り取られてしまう。
ただ見つめあうだけただそれだけで僕は落ち着かなくなる。
その雄雄しさ堂々たる姿はまさに王者。
犬ではなく獅子ではないかと疑うほどだ。
走っても近づけない。
道路の向こうはまるで彼岸。
走っても走っても近くなりはしない。
誰かが僕の手を掴む。
放せよ。
亡者の手だ。
僕を生かせまいとする亡者が僕を引き止める。
それでも僕は振り返らない。
僕はあの犬から目が放せない。
血液が沸騰し眼が奴以外を映さなくなる。
あいつは――
あいつだけは――
後ろから強い力で引かれた。
うるさい。
僕の邪魔をするな。
赤い紐がするりと首に巻きつく。
一際強く引かれ僕はたたらを踏む。
鼻先を鉄の塊が通り抜ける。
空を見ていた。
三半規管が僕の体が傾いてることを教えてくれた。
一瞬遅れて背中に衝撃が来る。
意思とは無関係に体が息を絞り出す。
ビルで区切られた狭い空に三人の人間が写りこむ。
「――――」
何を言ってるのか聞こえない。
あいつは。
あいつはどうした。
受身を取ることの出来なかった体は満足に動かず起き上がろうとして惨めにのたうつ。
急に頭が持ち上げられた。
「――――」
頭の下に差し込まれるのは柔らかい温もり。
その温もりすら踏みにじるようにして僕は体を起こした。
道路の向こうには――何もいない。
冷静になる。
たかが犬じゃないか。
何を必死になることがある。
あばら骨だった浮いてたし毛並みだった汚れてた。
どこかの路地にいるような貧相な奴でどうせ野良犬だ。
亡くなった大金持ちの飼い主の遺産を相続してるわけじゃないだろうしCIAの暗号文書を持ってるわけでもない。
そう、なんてことはないただの犬だ。
そのまま僕は力を失って後ろに倒れた。
迎えてくれるのは先ほどの温もり、千華の膝枕だ。
「おい!コウ!」
「光!」
「お兄ちゃん!」
三人とも馬鹿みたいに必死な顔をしている。
千華と奏が心配そうに見つめる中隆司が僕の頬を何度も叩く。
痛いな畜生。
「叩くなよ」
僕はそれだけ呟くとその手を受け止めた。
「後ろに引き倒すなんてふざけ過ぎだろ」
僕と隆司じゃそもそものスペックが違いすぎる。
隆司はどの運動部でも即レギュラークラスで僕はしがない帰宅部。
軽く襟首を引かれるだけで後ろにひっくり返ってしまう。
「ふざけ過ぎって……お前自分が何したか覚えてないのか!?」
「?」
横から涙目の奏が口を挟む。
「お、お兄ちゃん……道路に飛び出しそうになって。
道路の真ん中に立ってそれでタ、タカ兄が引っ張ろうとしたの……う、ひっぐひぐ」
あちゃちゃ完全に泣き出しちゃったよ。
そこから千華が引き継ぐ。
「それでもあんた隆司のこと存在しないみたいにぼけっと突っ立ってて二人ともトラックに轢かれそうになったとこを私も引っ張ってようやく……」
声はあげないけど千華の瞳からも涙の雫が零れ落ちそうだ。
僕が犬を見てる間にも迷惑かけてみたいだ。
「なんだそんなことがあったのか。いやはやビックリ」
三人ともきょとんとあっけにとられた顔をした。
涙で顔がぐちゃぐちゃになってる奏までが泣き止んで僕のことを見ている。
ん?何か変なことを言ったかな?
ただ僕は思ったことを口にしただけなんだけど。
僕が気付いてないだけで見当違いのこと言っちゃったのかな?
「おま……いや、きっとまだショックが抜けてないんだろ。
ほら立てるか?」
そう聞きつつ僕の意思を無視して引っ張り起こす。
少しよろめきながらも僕は無事立ち上がる。
倒された拍子に飛んでったカバンを拾うと千華が胸に飛び込んできた。
何も言わないけど僕の服の胸の辺りを掴んで俯いている。
「…………馬鹿ぁ、あんたは大馬鹿よ」
結局無事だったんだからそんな心配することでもないだろうに。
それにしてもいつまで抱きついてるつもりだろう。
白昼堂々とそんなことをされたら僕も居心地が悪い。
視線を逸らして話題を変えるように
「そろそろ時間やばいんじゃない?早く行こうぜ」
少し強引に千華を引き剥がし三人を置いてくように歩き出す。
現実感が希薄だった。
自分のことなのにまるで画面の向こう側のことのようで。
僕はそれを見ているだけの他人のようで。
さっきの話もそうだ。
なんの感慨もなくあくまで事実を確認しただけだった。
なんでこうなんだろう?
僕は誰なんだろう?
お前は誰だ?
学校に着いてみると靴箱に手紙が入っていた。
飾り気のない茶封筒で裏には「蠢くグッピーより葉山光へ」と書いてあった。
蠢くグッピーってなんだよ。
いつの時代のセンスだ?
もしかしてこれは過去からの手紙だったりするのか?
いろいろと湧き上がるせん無きことを押し込めて千華たちに気付かれる前にカバンに押し込む。
「なあ、タイムマシンってあると思うか?」
そう僕は問いかけた。
問いかけた?
問いかけた。
僕は誰に問いかけた?
まるで答えが返ってくるのが当たり前であるかのように。
無視されるなんて微塵も考えてないような気安さで。
誰に?
袖を引っ張られた。
「お兄ちゃん」
いつの間にか背後に来ていた奏だった。
「ん?どうした?教室でお兄ちゃんと離れるのが寂しいのか?
残念だな学年が違って。お兄ちゃん今年は留年するようにがんばるから奏はちゃんと進級しろよ」
「変」
「変?」
この僕が?
大丈夫だよ。
僕の頭はいつもどおり冴えてますよ。
「どうしたんだよ?そんなこと言い出す奏の方が変だよ」
「なにか違うのお兄ちゃん。今日のお兄ちゃんどこかおかしいよ。さっきから、道路に飛び出したときからおかしいよ?
頭ぶつけたの?」
おいおいこの妹は。
言うに事欠いて僕がおかしいだって?
僕は正常さ。
今までも今もこれからもずっと正常さ。
「大丈夫だよ」
「大丈夫じゃない。保健室いこ。つれてってあげるから」
真剣な顔をして奏は僕の腕を引っ張って歩き出す。
後ろから靴を履き替えた隆司の声が聞こえる。
「おい、カナちゃん?どうしたん?」
「ちょっとこの人保健室まで連れて行きます」
「ああ、それがいいかもしれんね」
そういって奏は人の流れから外れたほうに僕を引き摺っていく。
きっと後ろでは隆司が千華に説明していることだろう。
やれやれ面倒くさいな。
飾り気のない茶封筒で裏には「蠢くグッピーより葉山光へ」と書いてあった。
蠢くグッピーってなんだよ。
いつの時代のセンスだ?
もしかしてこれは過去からの手紙だったりするのか?
いろいろと湧き上がるせん無きことを押し込めて千華たちに気付かれる前にカバンに押し込む。
「なあ、タイムマシンってあると思うか?」
そう僕は問いかけた。
問いかけた?
問いかけた。
僕は誰に問いかけた?
まるで答えが返ってくるのが当たり前であるかのように。
無視されるなんて微塵も考えてないような気安さで。
誰に?
袖を引っ張られた。
「お兄ちゃん」
いつの間にか背後に来ていた奏だった。
「ん?どうした?教室でお兄ちゃんと離れるのが寂しいのか?
残念だな学年が違って。お兄ちゃん今年は留年するようにがんばるから奏はちゃんと進級しろよ」
「変」
「変?」
この僕が?
大丈夫だよ。
僕の頭はいつもどおり冴えてますよ。
「どうしたんだよ?そんなこと言い出す奏の方が変だよ」
「なにか違うのお兄ちゃん。今日のお兄ちゃんどこかおかしいよ。さっきから、道路に飛び出したときからおかしいよ?
頭ぶつけたの?」
おいおいこの妹は。
言うに事欠いて僕がおかしいだって?
僕は正常さ。
今までも今もこれからもずっと正常さ。
「大丈夫だよ」
「大丈夫じゃない。保健室いこ。つれてってあげるから」
真剣な顔をして奏は僕の腕を引っ張って歩き出す。
後ろから靴を履き替えた隆司の声が聞こえる。
「おい、カナちゃん?どうしたん?」
「ちょっとこの人保健室まで連れて行きます」
「ああ、それがいいかもしれんね」
そういって奏は人の流れから外れたほうに僕を引き摺っていく。
きっと後ろでは隆司が千華に説明していることだろう。
やれやれ面倒くさいな。
「じゃあお兄ちゃんちゃんと寝てるんだよ。歩き回ったりしちゃ駄目だよ?」
医務の先生に事情を説明してベッドで休ませてもらう。
奏の言いつけはまるで健忘症か夢遊病患者に言い聞かせるかのようだった。
ひどく頭が痛い。
眠らせてくれ。
「わかったわかったから。早く行かないと遅刻するぞ」
正論を疲れたのが悔しいのか奏は少しむくれてみせる。
「ほら可愛い顔が台無しだ」
「え……」
顎に手を当て上を向かせる。
瞬間頭に衝撃。
殴られた。
奏に。
「もう馬鹿ばっか言って。ちゃんと休んでるんだよ!?」
そういって奏は踵を返して保健室を出て行く。
――お前の妹も美味しそうだな。
誰かが僕にささやいた。
猛烈な眠気が僕を襲う。
ベッドに横になって気が付く。
この部屋には今僕しかいない。
医務の先生はさっき出て行った。
じゃあ僕は誰の声を聞いた?
寝ぼけた頭で考えても良くわからない。
まあいいや寝よう。
医務の先生に事情を説明してベッドで休ませてもらう。
奏の言いつけはまるで健忘症か夢遊病患者に言い聞かせるかのようだった。
ひどく頭が痛い。
眠らせてくれ。
「わかったわかったから。早く行かないと遅刻するぞ」
正論を疲れたのが悔しいのか奏は少しむくれてみせる。
「ほら可愛い顔が台無しだ」
「え……」
顎に手を当て上を向かせる。
瞬間頭に衝撃。
殴られた。
奏に。
「もう馬鹿ばっか言って。ちゃんと休んでるんだよ!?」
そういって奏は踵を返して保健室を出て行く。
――お前の妹も美味しそうだな。
誰かが僕にささやいた。
猛烈な眠気が僕を襲う。
ベッドに横になって気が付く。
この部屋には今僕しかいない。
医務の先生はさっき出て行った。
じゃあ僕は誰の声を聞いた?
寝ぼけた頭で考えても良くわからない。
まあいいや寝よう。
「もうお兄ちゃんたら……」
扉を閉めた奏の頬が真っ赤に染まっている。
鼓動は早くなり触れられたところが熱を持つ。
廊下を歩く。
「お兄ちゃん」
頭を占めるのはお兄ちゃんのことばかり。
「お兄……コウ……」
扉を閉めた奏の頬が真っ赤に染まっている。
鼓動は早くなり触れられたところが熱を持つ。
廊下を歩く。
「お兄ちゃん」
頭を占めるのはお兄ちゃんのことばかり。
「お兄……コウ……」
ひどく嫌な夢だ。
命をかき消す永遠の冬の嵐が吹き荒れる。
大河も小川も須らく戒めの蔦に囚われる。
谷間には豪華の絶望が紅に燃え盛っている。
太陽は一切全ての生き物に容赦しない。
磔刑の罪人の血で染まった赤い土に風雨で削られた岩山。
その尖った頂上。
頭上を二羽のカラスが飛び回る。
麓では魔女が笑い獣が踊りだす。
正直言って目を逸らしたくなるような光景だ。
風は鋭い牙をむき出しにして僕の身を削っていく。
鋭く尖った舌が酷薄そうな薄い唇を嘗め回す。
吹き荒れる風の中たっている人間が僕のほかにもう一人いる。
いや人間かどうかも怪しい。
そいつは漆黒の鎧を纏うことで僕から隠れている。
時折ささやく言葉は男でもないし女でもない、年寄りのようでも子供のようでもある。
ただわかるのはそいつはそこにいて僕もここにいる。
だから聞いた。
「お前は僕か」
疑問じゃない。
それは断定だ。
それはわかりきったことだから。
聞くまでもないことは断定する。
「ああそうさ」
一瞬の間もなく、そう打ち合わせされていたかのように一瞬の間もなく答えが返ってくる。
「じゃあ僕はお前なわけだ」
「おや、そうなのか?」
全く嫌な性格だ。
こちらの言うことをすべて知っていてそれでもあたかも今始めて聞いたかのように問い返してくる。
それは僕も同じ。
全てが手に取るようにわかる。
騎士と記憶を共有している。
見たことの無い惨劇。
聞いたことの無い悲鳴。
そんなものが流れ込んでくる。
でもこれはきっと一時的なもの。
硝子のコップは大海の器たりえない。
知っては忘れ、忘れてはまた知覚する。
かけ流しの知識が僕の中を通り抜けていく。
「ここは夢の名残ヴァルプルギスの夜」
必要な情報を流れの中から取り出していく。
「既に滅びた世界。それでも広がる未練の形骸」
「お前の世界は侵食されている」
「それがお前であり奴ら」
「そう。それが災厄の根源」
「だから僕には力が与えられた」
「全てを滅ぼす悪魔の力」
「何も救えない無力」
手を伸ばす。
漆黒の鎧と触れ合った。
強く押す。
鏡が割れた。
そこに映っていた僕の姿も無数の欠片となり刹那の時を落ち続ける。
命をかき消す永遠の冬の嵐が吹き荒れる。
大河も小川も須らく戒めの蔦に囚われる。
谷間には豪華の絶望が紅に燃え盛っている。
太陽は一切全ての生き物に容赦しない。
磔刑の罪人の血で染まった赤い土に風雨で削られた岩山。
その尖った頂上。
頭上を二羽のカラスが飛び回る。
麓では魔女が笑い獣が踊りだす。
正直言って目を逸らしたくなるような光景だ。
風は鋭い牙をむき出しにして僕の身を削っていく。
鋭く尖った舌が酷薄そうな薄い唇を嘗め回す。
吹き荒れる風の中たっている人間が僕のほかにもう一人いる。
いや人間かどうかも怪しい。
そいつは漆黒の鎧を纏うことで僕から隠れている。
時折ささやく言葉は男でもないし女でもない、年寄りのようでも子供のようでもある。
ただわかるのはそいつはそこにいて僕もここにいる。
だから聞いた。
「お前は僕か」
疑問じゃない。
それは断定だ。
それはわかりきったことだから。
聞くまでもないことは断定する。
「ああそうさ」
一瞬の間もなく、そう打ち合わせされていたかのように一瞬の間もなく答えが返ってくる。
「じゃあ僕はお前なわけだ」
「おや、そうなのか?」
全く嫌な性格だ。
こちらの言うことをすべて知っていてそれでもあたかも今始めて聞いたかのように問い返してくる。
それは僕も同じ。
全てが手に取るようにわかる。
騎士と記憶を共有している。
見たことの無い惨劇。
聞いたことの無い悲鳴。
そんなものが流れ込んでくる。
でもこれはきっと一時的なもの。
硝子のコップは大海の器たりえない。
知っては忘れ、忘れてはまた知覚する。
かけ流しの知識が僕の中を通り抜けていく。
「ここは夢の名残ヴァルプルギスの夜」
必要な情報を流れの中から取り出していく。
「既に滅びた世界。それでも広がる未練の形骸」
「お前の世界は侵食されている」
「それがお前であり奴ら」
「そう。それが災厄の根源」
「だから僕には力が与えられた」
「全てを滅ぼす悪魔の力」
「何も救えない無力」
手を伸ばす。
漆黒の鎧と触れ合った。
強く押す。
鏡が割れた。
そこに映っていた僕の姿も無数の欠片となり刹那の時を落ち続ける。
僕は閉じたまぶたの裏に強い日差しを感じて目を覚ます。
目に入るのは見慣れない白い天井。
つまり保健室だ。
誰かが様子を見にきたのか隙間の開いたカーテンからは西日が差し込んでいる。
日の入りまで結構時間はあるみたいでその光は眠りを妨げるにはおつりが来る。
「暑っ」
毛布を肩までかけていたせいだ。
そのせいでこれだけの寝汗をかいてしまった。
壁にかかったの時計の針を見ると午後四時。
学校が終わるには少し遅い時間だ。
虚無感よりもまず気が付くのがかいた汗と口の中に広がる苦い味。
始めてみる夢で全く覚えていない。
内容は覚えてないが強く印象に残る夢だった。
きっと今日は何かある気がする。
根拠のない感想を述べても仕方ない。
なぜこんな時間まで放置されていたのかわからないが気味が悪い。
確認の意味を持って口に出して言ってみる。
「よっし早く帰って寝るか」
やっぱり、いつも通り今日も最悪な日だった。
目に入るのは見慣れない白い天井。
つまり保健室だ。
誰かが様子を見にきたのか隙間の開いたカーテンからは西日が差し込んでいる。
日の入りまで結構時間はあるみたいでその光は眠りを妨げるにはおつりが来る。
「暑っ」
毛布を肩までかけていたせいだ。
そのせいでこれだけの寝汗をかいてしまった。
壁にかかったの時計の針を見ると午後四時。
学校が終わるには少し遅い時間だ。
虚無感よりもまず気が付くのがかいた汗と口の中に広がる苦い味。
始めてみる夢で全く覚えていない。
内容は覚えてないが強く印象に残る夢だった。
きっと今日は何かある気がする。
根拠のない感想を述べても仕方ない。
なぜこんな時間まで放置されていたのかわからないが気味が悪い。
確認の意味を持って口に出して言ってみる。
「よっし早く帰って寝るか」
やっぱり、いつも通り今日も最悪な日だった。
なぜ僕は帰るつもりだったのに階段を上っているんだろう。
「八、九、十」
もうすぐ四階だ。
三年生の教室と特別教室がありその上は屋上しかない
僕のクラスは三階にある。
自分のクラスに行きたいのならここまで階段を上がって来る必要はない。
ただ最上階まで上らなくてはいけない気がした。
強迫観念にしたがって僕はここまで来た。
西日が差し込む階段は僕の影が長く伸びている。
それにしても奇妙だ。
この時間帯なら部活動をしている人間にあってもいいだろうに。
今の今まで誰ともすれ違わない。
誰もいないまるで世界が僕を取り残して静止してしまったかのようだ。
「十一、十二、十三……あれ?この階段って十三段だっけ?」
まあいいかいつも階段の段数を数えてるわけじゃないし四階に来たこともあまりない。
覚える違和感も根拠のないものだ。
さて何をしようか。
ここにこなくちゃいけないと言う思いはあったが何かをしなくちゃいけないという思いはない。
ただ待っている。
そんな気持ちだ。
歩き回ってみることにした。
西日は廊下も紅に染めている。
教室のガラスが朱を反射してまぶしい。
そうして歩いているうちにそろそろ廊下も終点。
あとは理科室があるだけだ。
だから僕は振り返った。
重なる金属音。
そこにいた。
生きているかのような金属の鎧に腕の盾。
細かい細工がされた兜の面の隙間から漏れ出す黒い闇。
明らかに違うものだった。
学校にあって異質。
日本にあって異質。
世界にあって異質。
別世界の存在だ。
背を向けて駆け出した。
ただ怖かった。
走った先にあるのは袋小路。
幸いあの鎧は重装甲みたいだから追いつくのに時間がかかるだろう。
走った。
何も考えてなかったがそれでも考える時間がほしかった。
少しでも時間があれば良い案が浮かぶ気がした。
必死に逃げた。
あの鎧が歩いてくる音はしない。
僕は何か打開策を考え出そうとして振り返った。
甘かった。
盾の内側にあった砲が火を噴いた。
六本の筒から一発だけ撃ち出される。
砲身が六十度回転した。
本来は連続して撃つものなのだろう。
それでも十分だった。
一つの害意が駆け抜ける。
狙いの甘い弾が脇を抜けたとき体が軽くなった気がした。
付け根から肩を引っこ抜くように爆散した。
痛みはなかった。
妙に冷静な意識が後ろに吹っ飛んでいることを知覚した。
廊下が衝撃波で破壊される。
当たってもいないのに床が剥がれ飛び窓ガラスが四散する。
破片が容赦なく打ちつけ食い込み貫いていく。
それらに押されるようにして僕は吹き飛んだ。
粉砕された壁から僕は外へ飛び出す。
通っただけで廊下を破壊するような弾丸が壁に当たって止まるわけがない。
破壊の意思は触れる物全てを穿ち壁に大穴を空けていた。
西日に横から照らされる。
その赤さは血のようでありなぜか瞳を連想させた。
見つめられながら僕は落ちていく。
傷口から噴出すのは黒い黒い液体。
痛みは麻痺してた。
でも怖かった。
高みから落ちることが。
既に腕は致命傷。
それでも落ちることが怖かった
迫ってくる地面は既に夕日で赤く血が撒き散らされているようだった。
感情だけは麻痺せずにただ願った。
やだ。
――もっと。
死にたくない。
――もっとだ。
「僕は死にたくない!!死にたくない!!」
「八、九、十」
もうすぐ四階だ。
三年生の教室と特別教室がありその上は屋上しかない
僕のクラスは三階にある。
自分のクラスに行きたいのならここまで階段を上がって来る必要はない。
ただ最上階まで上らなくてはいけない気がした。
強迫観念にしたがって僕はここまで来た。
西日が差し込む階段は僕の影が長く伸びている。
それにしても奇妙だ。
この時間帯なら部活動をしている人間にあってもいいだろうに。
今の今まで誰ともすれ違わない。
誰もいないまるで世界が僕を取り残して静止してしまったかのようだ。
「十一、十二、十三……あれ?この階段って十三段だっけ?」
まあいいかいつも階段の段数を数えてるわけじゃないし四階に来たこともあまりない。
覚える違和感も根拠のないものだ。
さて何をしようか。
ここにこなくちゃいけないと言う思いはあったが何かをしなくちゃいけないという思いはない。
ただ待っている。
そんな気持ちだ。
歩き回ってみることにした。
西日は廊下も紅に染めている。
教室のガラスが朱を反射してまぶしい。
そうして歩いているうちにそろそろ廊下も終点。
あとは理科室があるだけだ。
だから僕は振り返った。
重なる金属音。
そこにいた。
生きているかのような金属の鎧に腕の盾。
細かい細工がされた兜の面の隙間から漏れ出す黒い闇。
明らかに違うものだった。
学校にあって異質。
日本にあって異質。
世界にあって異質。
別世界の存在だ。
背を向けて駆け出した。
ただ怖かった。
走った先にあるのは袋小路。
幸いあの鎧は重装甲みたいだから追いつくのに時間がかかるだろう。
走った。
何も考えてなかったがそれでも考える時間がほしかった。
少しでも時間があれば良い案が浮かぶ気がした。
必死に逃げた。
あの鎧が歩いてくる音はしない。
僕は何か打開策を考え出そうとして振り返った。
甘かった。
盾の内側にあった砲が火を噴いた。
六本の筒から一発だけ撃ち出される。
砲身が六十度回転した。
本来は連続して撃つものなのだろう。
それでも十分だった。
一つの害意が駆け抜ける。
狙いの甘い弾が脇を抜けたとき体が軽くなった気がした。
付け根から肩を引っこ抜くように爆散した。
痛みはなかった。
妙に冷静な意識が後ろに吹っ飛んでいることを知覚した。
廊下が衝撃波で破壊される。
当たってもいないのに床が剥がれ飛び窓ガラスが四散する。
破片が容赦なく打ちつけ食い込み貫いていく。
それらに押されるようにして僕は吹き飛んだ。
粉砕された壁から僕は外へ飛び出す。
通っただけで廊下を破壊するような弾丸が壁に当たって止まるわけがない。
破壊の意思は触れる物全てを穿ち壁に大穴を空けていた。
西日に横から照らされる。
その赤さは血のようでありなぜか瞳を連想させた。
見つめられながら僕は落ちていく。
傷口から噴出すのは黒い黒い液体。
痛みは麻痺してた。
でも怖かった。
高みから落ちることが。
既に腕は致命傷。
それでも落ちることが怖かった
迫ってくる地面は既に夕日で赤く血が撒き散らされているようだった。
感情だけは麻痺せずにただ願った。
やだ。
――もっと。
死にたくない。
――もっとだ。
「僕は死にたくない!!死にたくない!!」
ただ無我夢中だった。
ただ死にたくないことを願ったら声が聞こえた。
だから叫んだ。
生きたいと。
――我が名はメフィスト。
さあコウよ。
終わりを綴ろう。
傷口からあふれ出した液体が指向性を持つ。
滑らかでありながら触れるもの全てを切り裂く鎧となる。
肩を覆いつくした鎧は背中に伸張する。
僕が心に思い描いた形を作る。
背中から突き出すのは黒き骨組み。
落ちないこと。
液体が空を飛び膜となり骨組みは片翼へと変貌する。
空を飛ぶこと。
数瞬のうちに数度羽ばたき落下速度を減衰する。
着地は羽毛が落ちるよりも滑らかで優雅に。
初めてのことだが体は知っていた。
――敵を滅ぼせ。
足がコンクリートを掴む。
限界まで押し縮めたばねは開放される時を待つ。
――飛べ!
足が大地を放射状に踏み砕く。
水蒸気の輪を突き抜け片翼が線を引く。
もっと速く。
――広き空へ。
翼が尋常でない空気抵抗の中悠々と羽ばたく。
何度も空気を打つ。
加速は積み重ねられ人間には超えられない速度を容易く凌駕する。
違いを理解する。
今の僕は悪魔だ。
人じゃない。
先ほど落ちた穴まで数秒。
最もこれは僕の体感時間だからはたから見たら数瞬だ。
見えたあの鎧姿だ。
行け!
――行け!
行け!
ただ手を前に突き出し校舎を突き抜ける。
コンクリートを寒天のように砕いた右手は鎧の兜を掴み加速する。
天井を突き破り到達するのは屋上。
翼を使い空中で反転し勢いで敵を叩きつける。
騎士は音速を超え屋上に叩きつけられる。
土煙が上がり視界がふさがる。
その噴煙を抜けるように飛翔する。
構造物であばたな地平線を見下す。
周りを見れば日は沈むところだ。
これから訪れるのは夜。
魔の時間だ。
粉塵の中から何かが飛んできた。
弾丸。
一発や二発ではない。
数千発だ。
先ほどまでは視認することすらかなわなかった弾頭が手に取るように。
――それでもお前には脅威じゃない。
避けるまでもない受け止める。
右手を突き出し受け止める。
衝撃はほとんどない。
ひしゃげて消滅していく弾丸が画面の向こう側のことのようだ。
全ての音が連なりとなり打撃音を継続させる。
無駄だと悟ったのか銃撃が止む。
衝撃で土煙が晴れる。
陥没した四階に立つ騎士は無傷。
もちろんダメージを期待していたわけじゃない。
コンクリートを容易く砕けるからこそ敵の固さもよくわかる。
騎士が動きを見せた。
両手を合わせ組む。
そこに集まる力を今の僕は敏感に感じ取れる。
両手が変質し一つの砲を作り出す。
「……砲?」
――あれは多少まずいな。抜け。
悪魔の助言が己のうちから聞こえる。
言ってることは最小限だが僕にはわかる。
だから躊躇うことなく右手を胸に突き込む。
そこからも黒き液体が噴出す。
激痛とともに柄を感じる。
深く埋め込んだ右手を動かし掴む。
これが僕の力。
向こう側の住人と戦うための破壊の武器。
完全に融合した砲が僕に狙いをつける。
引き抜くのと射撃は同時だった。
ただ死にたくないことを願ったら声が聞こえた。
だから叫んだ。
生きたいと。
――我が名はメフィスト。
さあコウよ。
終わりを綴ろう。
傷口からあふれ出した液体が指向性を持つ。
滑らかでありながら触れるもの全てを切り裂く鎧となる。
肩を覆いつくした鎧は背中に伸張する。
僕が心に思い描いた形を作る。
背中から突き出すのは黒き骨組み。
落ちないこと。
液体が空を飛び膜となり骨組みは片翼へと変貌する。
空を飛ぶこと。
数瞬のうちに数度羽ばたき落下速度を減衰する。
着地は羽毛が落ちるよりも滑らかで優雅に。
初めてのことだが体は知っていた。
――敵を滅ぼせ。
足がコンクリートを掴む。
限界まで押し縮めたばねは開放される時を待つ。
――飛べ!
足が大地を放射状に踏み砕く。
水蒸気の輪を突き抜け片翼が線を引く。
もっと速く。
――広き空へ。
翼が尋常でない空気抵抗の中悠々と羽ばたく。
何度も空気を打つ。
加速は積み重ねられ人間には超えられない速度を容易く凌駕する。
違いを理解する。
今の僕は悪魔だ。
人じゃない。
先ほど落ちた穴まで数秒。
最もこれは僕の体感時間だからはたから見たら数瞬だ。
見えたあの鎧姿だ。
行け!
――行け!
行け!
ただ手を前に突き出し校舎を突き抜ける。
コンクリートを寒天のように砕いた右手は鎧の兜を掴み加速する。
天井を突き破り到達するのは屋上。
翼を使い空中で反転し勢いで敵を叩きつける。
騎士は音速を超え屋上に叩きつけられる。
土煙が上がり視界がふさがる。
その噴煙を抜けるように飛翔する。
構造物であばたな地平線を見下す。
周りを見れば日は沈むところだ。
これから訪れるのは夜。
魔の時間だ。
粉塵の中から何かが飛んできた。
弾丸。
一発や二発ではない。
数千発だ。
先ほどまでは視認することすらかなわなかった弾頭が手に取るように。
――それでもお前には脅威じゃない。
避けるまでもない受け止める。
右手を突き出し受け止める。
衝撃はほとんどない。
ひしゃげて消滅していく弾丸が画面の向こう側のことのようだ。
全ての音が連なりとなり打撃音を継続させる。
無駄だと悟ったのか銃撃が止む。
衝撃で土煙が晴れる。
陥没した四階に立つ騎士は無傷。
もちろんダメージを期待していたわけじゃない。
コンクリートを容易く砕けるからこそ敵の固さもよくわかる。
騎士が動きを見せた。
両手を合わせ組む。
そこに集まる力を今の僕は敏感に感じ取れる。
両手が変質し一つの砲を作り出す。
「……砲?」
――あれは多少まずいな。抜け。
悪魔の助言が己のうちから聞こえる。
言ってることは最小限だが僕にはわかる。
だから躊躇うことなく右手を胸に突き込む。
そこからも黒き液体が噴出す。
激痛とともに柄を感じる。
深く埋め込んだ右手を動かし掴む。
これが僕の力。
向こう側の住人と戦うための破壊の武器。
完全に融合した砲が僕に狙いをつける。
引き抜くのと射撃は同時だった。
白い熱線が空を焼く。
宇宙からでも観測できるだろう。
二本に分かたれた白線が。
僕は右手に構えた剣で受け止める。
空気は熱で焼け辺りは昼間のような明るさだ。
大剣は溶ける事もなくその熱線を分断する。
鉄板の様な剣は重さを感じさせずそれでも絶対の存在を持つ。
白光が側面の金細工を彩る。
――さあ行け。
そして討ち滅ぼせ。
ああ言われなくてもわかってるさ。
一度羽ばたくと僕は急降下する。
熱線をたどる様にして僕は敵に突撃する。
そのままたいした敵の胸をぶち抜く。
敵は衝撃で四散する。
――まだだ。
知ってる。
こいつはまだ死なない。
床に足が着いた瞬間その足を支点にしてターンを決める。
圧力のかかった床が抉れる。
優雅なターンのまま剣をぶち込む。
再生した敵を二分する。
剣の勢いを力で曲げて振り上げる。
抉れた足場が無理な力で沈む。
床まで振り下ろす。
既に胴体をくっつけた敵が頭から股まで左右対称に分かたれる。
徹底的に攻める。
鎧のふちにに指をかけ思いっきり投げる。
廊下を蹴る。
飛ぶ騎士に後ろから追いつきその兜と鎧の継ぎ目に手を差し込む。
手首まで埋めて強引に向きを変えた。
その頭を剣の腹で迎撃する。
鉄球より硬い兜がスイカのようにはじけ飛ぶ。
頭のなくなった胴体を壁にこすり付けるようにして静止させる。
そのまま埋まった手を回し首をねじ切る。
床に崩れ落ちるより先に胸に剣を差し込んだ。
差し込まれた剣により体は空中に固定される。
左手を伸ばし手甲の上から騎士の腕を握る。
鉄板がひしゃげる。
つぶされた腕から中身が搾り出された。
ぬめる左手を伸ばし腹部の鎧を突き破る。
温かい。
そのまま股下まで引き裂く。
剣を引き抜く。
ぐちゃぐちゃびなった肉塊に刃物を突き立てる。
人間ならひき肉になるような斬撃を何度も受けまだ再生する。
だから剣で破壊する。
斬ると言うよりも砕くような斬撃で。
何度も何度も。
廊下を跳躍しありとあらゆる斬撃を叩き込む。
蹴った床が砕け滑った壁が抉れる。
めまぐるしく上下が入れ替わる。
再生するしたそばから斬り飛ばす。
窓ガラスが斬撃ごとに割れ壁に皹が走る。
刹那の間に無数の斬撃を。
反撃は無意味。
抵抗の腕をこれ幸いと掴んで引き寄せて斬る。
ただの的だ。
再生しなくなるまで。
戦う意思がなくなるまで。
生きる意志がなくなるまで。
――死にたいと願うまで。
機械的に振り上げて振り下ろす。
その繰り返しだ。
既に原型はとどめていない。
申し訳程度に復元された体を上から串刺しにする。
床に接触しさらに加速する。
降下速度は自然落下の限界を超えてなお速くなる。
四階の床をぶち抜き三回の床をぶち抜き二階の床もぶち抜く。
大地に突き立った瞬間僕は手を放した。
上階が衝撃で一瞬内側にたわみ反動で外側に崩れ落ちていく。
落ちてくる瓦礫の中騎士は磔刑に処された聖者のようだった。
その胸を腕で貫いた。
粘ついた感触を掻き分ける。
腕との隙間から液体が吹き出す。
熱を掴んだ。
生々しい音と共に引き抜かれた手には心臓が収まっている。
鈍く鳴動する光りの塊。
それを掴んだ腕を天にかざし握りつぶした。
光りの飛沫と共に澄んだ高音が響き渡る。
鎧から燐光が散り空気に溶けていく。
剣を引き抜くと甲冑は大地へと落下した。
中身は既に無。
高い音を立てた鎧はもう一度跳ねる前に世界に溶け込む。
僕は飛び上がった。
先ほど空けた大穴を上昇する。
瞬時に校舎は豆粒ほどの大きさとなり周囲の建物と見分けが付かなくなる。
雲を突き抜けた。
雲海の上に。
穢れなき月が空に浮かぶ。
周りには何もない。
ただ月だけがずれた僕を照らしていた。
宇宙からでも観測できるだろう。
二本に分かたれた白線が。
僕は右手に構えた剣で受け止める。
空気は熱で焼け辺りは昼間のような明るさだ。
大剣は溶ける事もなくその熱線を分断する。
鉄板の様な剣は重さを感じさせずそれでも絶対の存在を持つ。
白光が側面の金細工を彩る。
――さあ行け。
そして討ち滅ぼせ。
ああ言われなくてもわかってるさ。
一度羽ばたくと僕は急降下する。
熱線をたどる様にして僕は敵に突撃する。
そのままたいした敵の胸をぶち抜く。
敵は衝撃で四散する。
――まだだ。
知ってる。
こいつはまだ死なない。
床に足が着いた瞬間その足を支点にしてターンを決める。
圧力のかかった床が抉れる。
優雅なターンのまま剣をぶち込む。
再生した敵を二分する。
剣の勢いを力で曲げて振り上げる。
抉れた足場が無理な力で沈む。
床まで振り下ろす。
既に胴体をくっつけた敵が頭から股まで左右対称に分かたれる。
徹底的に攻める。
鎧のふちにに指をかけ思いっきり投げる。
廊下を蹴る。
飛ぶ騎士に後ろから追いつきその兜と鎧の継ぎ目に手を差し込む。
手首まで埋めて強引に向きを変えた。
その頭を剣の腹で迎撃する。
鉄球より硬い兜がスイカのようにはじけ飛ぶ。
頭のなくなった胴体を壁にこすり付けるようにして静止させる。
そのまま埋まった手を回し首をねじ切る。
床に崩れ落ちるより先に胸に剣を差し込んだ。
差し込まれた剣により体は空中に固定される。
左手を伸ばし手甲の上から騎士の腕を握る。
鉄板がひしゃげる。
つぶされた腕から中身が搾り出された。
ぬめる左手を伸ばし腹部の鎧を突き破る。
温かい。
そのまま股下まで引き裂く。
剣を引き抜く。
ぐちゃぐちゃびなった肉塊に刃物を突き立てる。
人間ならひき肉になるような斬撃を何度も受けまだ再生する。
だから剣で破壊する。
斬ると言うよりも砕くような斬撃で。
何度も何度も。
廊下を跳躍しありとあらゆる斬撃を叩き込む。
蹴った床が砕け滑った壁が抉れる。
めまぐるしく上下が入れ替わる。
再生するしたそばから斬り飛ばす。
窓ガラスが斬撃ごとに割れ壁に皹が走る。
刹那の間に無数の斬撃を。
反撃は無意味。
抵抗の腕をこれ幸いと掴んで引き寄せて斬る。
ただの的だ。
再生しなくなるまで。
戦う意思がなくなるまで。
生きる意志がなくなるまで。
――死にたいと願うまで。
機械的に振り上げて振り下ろす。
その繰り返しだ。
既に原型はとどめていない。
申し訳程度に復元された体を上から串刺しにする。
床に接触しさらに加速する。
降下速度は自然落下の限界を超えてなお速くなる。
四階の床をぶち抜き三回の床をぶち抜き二階の床もぶち抜く。
大地に突き立った瞬間僕は手を放した。
上階が衝撃で一瞬内側にたわみ反動で外側に崩れ落ちていく。
落ちてくる瓦礫の中騎士は磔刑に処された聖者のようだった。
その胸を腕で貫いた。
粘ついた感触を掻き分ける。
腕との隙間から液体が吹き出す。
熱を掴んだ。
生々しい音と共に引き抜かれた手には心臓が収まっている。
鈍く鳴動する光りの塊。
それを掴んだ腕を天にかざし握りつぶした。
光りの飛沫と共に澄んだ高音が響き渡る。
鎧から燐光が散り空気に溶けていく。
剣を引き抜くと甲冑は大地へと落下した。
中身は既に無。
高い音を立てた鎧はもう一度跳ねる前に世界に溶け込む。
僕は飛び上がった。
先ほど空けた大穴を上昇する。
瞬時に校舎は豆粒ほどの大きさとなり周囲の建物と見分けが付かなくなる。
雲を突き抜けた。
雲海の上に。
穢れなき月が空に浮かぶ。
周りには何もない。
ただ月だけがずれた僕を照らしていた。