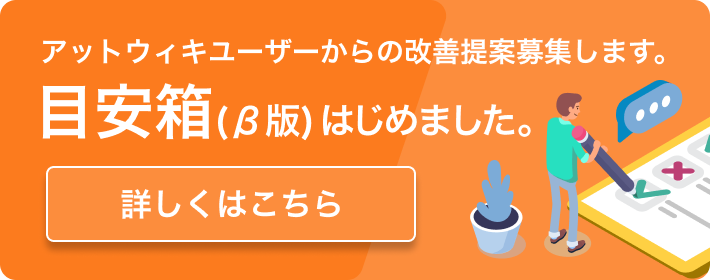痛いのは生きているから
転んだのは踏み出したから
迷ってるのは進みたいから
逃げ出したいのは戦ってるから
転んだのは踏み出したから
迷ってるのは進みたいから
逃げ出したいのは戦ってるから
灼熱の世界。
燃える火の玉は命を焼く。
東からの風は希望を掠め取っていく。
生ける者はいないのに岩肌に散らばる血痕。
それを踏みつけて会話する
「じゃあお前は逃げてきた奴らを殺すために来たわけだ」
前の夢と同じ岩山の頂き。
「ああ概ねそういうことだ」
鏡の前。
そこに映るのは僕であって僕じゃない。
「つまりこの世界の救世主かな?」
「ふ……俺はただ踏み倒された契約を果たしに来ただけだ」
そう言ってそいつは僕の顔で憎たらしく笑った。
「契約?」
「踏み倒していった俺なんて及びも付かない悪い悪い奴がいるからな」
映像が直接伝わってくる。
僕とは正反対の純白の鎧。
無骨な僕の剣とは似ても似つかない優雅な剣を持っている。
「こいつが?」
「ああこいつを殺すためにこちらに来た」
二人の間を風が吹き抜ける。
「どうやって?」
「心の隙間をこじ開けてきた。
お前のはずいぶん通りやすかったぞ」
「隙間ってなんだ?」
「ククククク」
さもおかしそうに笑っていた。
「どうした?」
「思いだせるだろう?
忘れたことなどないはずだ。
血に塗れたお前がやったんだから」
「黙れ」
「そうは言っても事実は変わらない」
「黙れ!」
「どんな手ごたえだった?」
「黙れっ!!」
「人間を殺すのは」
燃える火の玉は命を焼く。
東からの風は希望を掠め取っていく。
生ける者はいないのに岩肌に散らばる血痕。
それを踏みつけて会話する
「じゃあお前は逃げてきた奴らを殺すために来たわけだ」
前の夢と同じ岩山の頂き。
「ああ概ねそういうことだ」
鏡の前。
そこに映るのは僕であって僕じゃない。
「つまりこの世界の救世主かな?」
「ふ……俺はただ踏み倒された契約を果たしに来ただけだ」
そう言ってそいつは僕の顔で憎たらしく笑った。
「契約?」
「踏み倒していった俺なんて及びも付かない悪い悪い奴がいるからな」
映像が直接伝わってくる。
僕とは正反対の純白の鎧。
無骨な僕の剣とは似ても似つかない優雅な剣を持っている。
「こいつが?」
「ああこいつを殺すためにこちらに来た」
二人の間を風が吹き抜ける。
「どうやって?」
「心の隙間をこじ開けてきた。
お前のはずいぶん通りやすかったぞ」
「隙間ってなんだ?」
「ククククク」
さもおかしそうに笑っていた。
「どうした?」
「思いだせるだろう?
忘れたことなどないはずだ。
血に塗れたお前がやったんだから」
「黙れ」
「そうは言っても事実は変わらない」
「黙れ!」
「どんな手ごたえだった?」
「黙れっ!!」
「人間を殺すのは」
「黙れぇぇぇぇえええええ!!!!」
布団を跳ね上げた。
一人っきりの部屋に怒号が響く。
胸を掻き毟る様にしながら叫ぶ。
「うるさい、お前には関係ないことだろう!!」
――ククク……わかったわかった。
「はぁはぁ」
――しかしな覚えておけ。
俺がこちらにこれたのはいまだにお前が過去に囚われているからだ。
それだけは間違いのない事実だ。
「畜生ッ!」
ブランケットを勢い良く床に叩きつける。
誰もいない部屋の中で虚空に向かって聞くに堪えないような罵声を叫ぶ。
続けざまに言葉を発するものだから息が続かない。
はたから見ればとんでもなく異様な光景だ。
しかも当り散らす相手は僕自身だ。
と言うかこいつは僕なのか?
それなら僕はもう一人の僕と会話するなんて離れ業をやってのけてる≪ピー≫じゃないか。
僕は正気なのか?
気が付かないうちに悪魔なんていうもう一つの人格を作り出しているのか?
――おいおいそんな風に考え込むなよ。
昨日の戦いを忘れたのか?
戦い……戦い……
「あ!?」
そう言えば昨日僕は校舎破壊してんじゃん。
それも盛大に縦穴空けちゃったし。
いくら鈍感でもあんな穴なけちゃえば誰でも気付きますよ、棟梁。
棟梁って誰だよ!?
――大絶賛暴走中だな。
お前が言うか。
お前が現れたせいで僕はこんなに悩んでるんだろうが。
「ああもう!」
――俺がいなかったらこの世界は滅びるぞ?
それは困る。
だけど僕を困らせるな。
お前も昨日の奴見たく一人で行動しろよ。
――?
ああなるほどな……ククク。だが安心しろ。
昨日の戦闘においては結界の中だ。
貴様が奴の用意した場所に誘い込まれたのだ。
マジで!?
――夕方の時点で校舎全体が結界に包まれていた。
仮想的に作り出した空間が昨日のあの場だ。
じゃあ何にもないのか?
学校に言ったら誰も何になかったかのように友達と話したりしてるのか?
――安心しろ。校舎は何の変わりもなく誰も気付くことなく存在している。
「しゃー!!」
僕は一人でガッツポーズする。
――面白い男だな。
お前は既にこの世界の住人とはかけ離れているのに。
別にいいだろ。
ただ学校に隆司がいて千華がいて奏がいる。
そんないつもを壊したくないんだ。
例え僕があいつらとは違っても僕は守りたいんだ。
お前は笑うかもしれないけど僕達は親友なんだ。
――いやいや笑いはしないさ。
お前達は確かに親友だ。
若干含みのあるような芝居ががった言動だ。
その言葉に僕は気をよくする。
たとえメフィストが機嫌取りに言ってたとしても言わせたことに意味があるのだ。
「じゃあちょっと早いけど学校に行くか」
布団を跳ね上げた。
一人っきりの部屋に怒号が響く。
胸を掻き毟る様にしながら叫ぶ。
「うるさい、お前には関係ないことだろう!!」
――ククク……わかったわかった。
「はぁはぁ」
――しかしな覚えておけ。
俺がこちらにこれたのはいまだにお前が過去に囚われているからだ。
それだけは間違いのない事実だ。
「畜生ッ!」
ブランケットを勢い良く床に叩きつける。
誰もいない部屋の中で虚空に向かって聞くに堪えないような罵声を叫ぶ。
続けざまに言葉を発するものだから息が続かない。
はたから見ればとんでもなく異様な光景だ。
しかも当り散らす相手は僕自身だ。
と言うかこいつは僕なのか?
それなら僕はもう一人の僕と会話するなんて離れ業をやってのけてる≪ピー≫じゃないか。
僕は正気なのか?
気が付かないうちに悪魔なんていうもう一つの人格を作り出しているのか?
――おいおいそんな風に考え込むなよ。
昨日の戦いを忘れたのか?
戦い……戦い……
「あ!?」
そう言えば昨日僕は校舎破壊してんじゃん。
それも盛大に縦穴空けちゃったし。
いくら鈍感でもあんな穴なけちゃえば誰でも気付きますよ、棟梁。
棟梁って誰だよ!?
――大絶賛暴走中だな。
お前が言うか。
お前が現れたせいで僕はこんなに悩んでるんだろうが。
「ああもう!」
――俺がいなかったらこの世界は滅びるぞ?
それは困る。
だけど僕を困らせるな。
お前も昨日の奴見たく一人で行動しろよ。
――?
ああなるほどな……ククク。だが安心しろ。
昨日の戦闘においては結界の中だ。
貴様が奴の用意した場所に誘い込まれたのだ。
マジで!?
――夕方の時点で校舎全体が結界に包まれていた。
仮想的に作り出した空間が昨日のあの場だ。
じゃあ何にもないのか?
学校に言ったら誰も何になかったかのように友達と話したりしてるのか?
――安心しろ。校舎は何の変わりもなく誰も気付くことなく存在している。
「しゃー!!」
僕は一人でガッツポーズする。
――面白い男だな。
お前は既にこの世界の住人とはかけ離れているのに。
別にいいだろ。
ただ学校に隆司がいて千華がいて奏がいる。
そんないつもを壊したくないんだ。
例え僕があいつらとは違っても僕は守りたいんだ。
お前は笑うかもしれないけど僕達は親友なんだ。
――いやいや笑いはしないさ。
お前達は確かに親友だ。
若干含みのあるような芝居ががった言動だ。
その言葉に僕は気をよくする。
たとえメフィストが機嫌取りに言ってたとしても言わせたことに意味があるのだ。
「じゃあちょっと早いけど学校に行くか」
不安が再発した。
学校が近づくにつれて再び心配事が頭をもたげる。
「で、聞いてるのお兄ちゃん?」
「え?あ、ああ」
「もういつまで寝ぼけてるのよ」
「こいつはいつも通りだろ」
三人して笑い出す。
しかし今の僕にはそれよりも大事な心配事がある。
もしもこいつの言ってることが嘘だったら。
――嘘は言ってない。
嘘“は”ってなんだよ。
“は”って。
本当のことは言ってないってことだろ?
なんなんだよ?
何を僕に隠してるんだよ。
さあ言ってみろ。
怒らないから言ってみろ。
――さぁてな。
クソ!
性悪悪魔め。
「お兄ちゃんなにやってるの?」
「え?何が?」
「それ」
いつの間にか僕は一人で頭を抱えて悶えていた。
体を捻りいかにも悩んでいますという風だ。
「コウ何か悩み事でもあるのか?話し相手にはなるぞ」
隆司が心配してくる。
しかし言えるわけがありません。
僕は昨日学校を壊してしまったので学校に行きたくないなんて言えません。
「い、いやなんでもないよ」
「コウがはぐらかすときは絶対何かあるな。恋か?恋なんか?」
「「え!?」」
千華と奏が一緒に反応する。
「何!?光に好きな人がいるの?誰?誰なのよ?」
「まさか私が知らないうちにお兄ちゃんに彼女でも出来たの?」
なんだよこいつら一斉に。
僕のことをからかって楽しもうと腹か。
女って恋の話が好きだな。
「そんなんじゃないよ。本当にたいしたことじゃなし」
「ホント!?ホントだね!?」
「あ、ああ嘘じゃない。第一出来てたらお前らと一緒に登校なんてしてないよ」
過剰なまでの反応に面食らう。
納得したのに落ち着く動作まで二人一緒だ。
友人の恋の話にそんな貪欲になることもあるまいに。
そうこうしているうちに学校に近づいてきた。
胃が痛い。
「なんだあれ?」
ギク!?
隆司の一言に心臓が飛び跳ねる。
背を粘ついた汗が流れていく。
表情を取り繕うにもうまく顔が動かない。
「ドウカシマシタカ?フジタタカシクン」
やっとそれだけ絞り出した。
願わくばわざとらしい声になってないことを祈るばかりだ。
「コウどうかしたか?」
「ナンデモナイデスヨ」
「あれー?」
奏も何かに気付いたようだ。
「校門の前に止まってるのってパトカー?」
ギク!?
いやまさかね。
僕がやったなんてばれてないはずだ。
大体あれを一高校生がやったなんて思う奴はいない。
きっと何かほかのことがあったんだ。
学校が近づくにつれて再び心配事が頭をもたげる。
「で、聞いてるのお兄ちゃん?」
「え?あ、ああ」
「もういつまで寝ぼけてるのよ」
「こいつはいつも通りだろ」
三人して笑い出す。
しかし今の僕にはそれよりも大事な心配事がある。
もしもこいつの言ってることが嘘だったら。
――嘘は言ってない。
嘘“は”ってなんだよ。
“は”って。
本当のことは言ってないってことだろ?
なんなんだよ?
何を僕に隠してるんだよ。
さあ言ってみろ。
怒らないから言ってみろ。
――さぁてな。
クソ!
性悪悪魔め。
「お兄ちゃんなにやってるの?」
「え?何が?」
「それ」
いつの間にか僕は一人で頭を抱えて悶えていた。
体を捻りいかにも悩んでいますという風だ。
「コウ何か悩み事でもあるのか?話し相手にはなるぞ」
隆司が心配してくる。
しかし言えるわけがありません。
僕は昨日学校を壊してしまったので学校に行きたくないなんて言えません。
「い、いやなんでもないよ」
「コウがはぐらかすときは絶対何かあるな。恋か?恋なんか?」
「「え!?」」
千華と奏が一緒に反応する。
「何!?光に好きな人がいるの?誰?誰なのよ?」
「まさか私が知らないうちにお兄ちゃんに彼女でも出来たの?」
なんだよこいつら一斉に。
僕のことをからかって楽しもうと腹か。
女って恋の話が好きだな。
「そんなんじゃないよ。本当にたいしたことじゃなし」
「ホント!?ホントだね!?」
「あ、ああ嘘じゃない。第一出来てたらお前らと一緒に登校なんてしてないよ」
過剰なまでの反応に面食らう。
納得したのに落ち着く動作まで二人一緒だ。
友人の恋の話にそんな貪欲になることもあるまいに。
そうこうしているうちに学校に近づいてきた。
胃が痛い。
「なんだあれ?」
ギク!?
隆司の一言に心臓が飛び跳ねる。
背を粘ついた汗が流れていく。
表情を取り繕うにもうまく顔が動かない。
「ドウカシマシタカ?フジタタカシクン」
やっとそれだけ絞り出した。
願わくばわざとらしい声になってないことを祈るばかりだ。
「コウどうかしたか?」
「ナンデモナイデスヨ」
「あれー?」
奏も何かに気付いたようだ。
「校門の前に止まってるのってパトカー?」
ギク!?
いやまさかね。
僕がやったなんてばれてないはずだ。
大体あれを一高校生がやったなんて思う奴はいない。
きっと何かほかのことがあったんだ。
パトカーの止まってる辺りは人ごみになっていた。
結果からいうと校舎はちゃんと存在した。
校門から見たところ昨日までと変わりなく校舎が建っている。
壁に着いた染みまで同じだ。
よかったです。
校舎は無事です。
――言っただろう?
今だけはこいつに感謝してもいいかもしれない。
ん?
じゃあ何でここにパトカーが止まってるんだ?
「聞いてくるね」
僕が疑問に思ってると千華が野次馬根性発揮して突っ込んでいく。
「ちょっとおい」
呼び止める声も聞こえないのかそのまま人ごみにまぎれてしまう。
あいつ人を泳ぐように掻き分けてたよ。
「何か見えるか?」
背の高い隆司に聞いてみる。
こいつは憎たらしいことに僕より十数センチ強。
簡単に言うと二十センチほど背が高いので人ごみの中を見渡せるはずだ。
いや、僕の背が低いということじゃないよ?
僕の背はおまけしてみれば大体高校二年生の平均弱くらいありますから。
ええ何とか千華を見上げずにも済んでますよ。
まあそんなわけで僕から見えないものでも隆司には見えるかな?と思って聞いてみたわけです。
「えっと、パトカーが一台と……おっ千華発見最前列にいるな」
特に意味のない情報しか聞き出せない。
隆司は中心を何とか覗こうとしてるしこれは千華待ちかな。
そう思っていると奏が袖を引っ張ってきた。
人ごみから少し離れる。
「ねえお兄ちゃん何か知ってるの?」
「え?」
奏は何か感づいてるのか?
こいつは昔から鋭いところがあるからな。
でもパトカーと僕は無関係だろう。
「サアナンノコダカボクニハワカラナイナ」
「嘘」
あれ?この子断定してきましたよ。
まさか本当に知ってるのか?
「お兄ちゃんパトカーのとこに来てから露骨に態度変わったもん」
ああそれは校舎があったからだよといってもわからないだろう。
「そんなことないよ」
奏が身を寄せてくる。
計算してるのかしてないのか上目遣いだ。
「ホント?誰にも話したりしないよ」
「本当本当」
胸を押し付けるな。
「そう?ならいいんだけど」
そこに千華が隆司を連れて帰ってくる。
奏が慌てて体を放した。
反動で僕はよろめいた。
恥ずかしいなら始めからするなよと僕は言いたい。
「今、何かしてた?」
「え!?ううん何もしてないよ、それより、それよりさ。何の騒ぎだって?」
「えっとね」
釈然としない様子ながらも中心で知ったことを話してくれる。
「何かね、昨日居残ってた生徒の一人が倒れて意識不明なんだって」
「どうして?」
「いやそれがね原因不明なんだって。ガス漏れかもしれないって今四階を業者が調べてるんだって。
警察はそのおまけ」
「はー怖いもんだな」
――くくく
悪魔だけが不謹慎に笑っていた。
人の不幸を笑う人間は絶対いい死に方しないね。
結果からいうと校舎はちゃんと存在した。
校門から見たところ昨日までと変わりなく校舎が建っている。
壁に着いた染みまで同じだ。
よかったです。
校舎は無事です。
――言っただろう?
今だけはこいつに感謝してもいいかもしれない。
ん?
じゃあ何でここにパトカーが止まってるんだ?
「聞いてくるね」
僕が疑問に思ってると千華が野次馬根性発揮して突っ込んでいく。
「ちょっとおい」
呼び止める声も聞こえないのかそのまま人ごみにまぎれてしまう。
あいつ人を泳ぐように掻き分けてたよ。
「何か見えるか?」
背の高い隆司に聞いてみる。
こいつは憎たらしいことに僕より十数センチ強。
簡単に言うと二十センチほど背が高いので人ごみの中を見渡せるはずだ。
いや、僕の背が低いということじゃないよ?
僕の背はおまけしてみれば大体高校二年生の平均弱くらいありますから。
ええ何とか千華を見上げずにも済んでますよ。
まあそんなわけで僕から見えないものでも隆司には見えるかな?と思って聞いてみたわけです。
「えっと、パトカーが一台と……おっ千華発見最前列にいるな」
特に意味のない情報しか聞き出せない。
隆司は中心を何とか覗こうとしてるしこれは千華待ちかな。
そう思っていると奏が袖を引っ張ってきた。
人ごみから少し離れる。
「ねえお兄ちゃん何か知ってるの?」
「え?」
奏は何か感づいてるのか?
こいつは昔から鋭いところがあるからな。
でもパトカーと僕は無関係だろう。
「サアナンノコダカボクニハワカラナイナ」
「嘘」
あれ?この子断定してきましたよ。
まさか本当に知ってるのか?
「お兄ちゃんパトカーのとこに来てから露骨に態度変わったもん」
ああそれは校舎があったからだよといってもわからないだろう。
「そんなことないよ」
奏が身を寄せてくる。
計算してるのかしてないのか上目遣いだ。
「ホント?誰にも話したりしないよ」
「本当本当」
胸を押し付けるな。
「そう?ならいいんだけど」
そこに千華が隆司を連れて帰ってくる。
奏が慌てて体を放した。
反動で僕はよろめいた。
恥ずかしいなら始めからするなよと僕は言いたい。
「今、何かしてた?」
「え!?ううん何もしてないよ、それより、それよりさ。何の騒ぎだって?」
「えっとね」
釈然としない様子ながらも中心で知ったことを話してくれる。
「何かね、昨日居残ってた生徒の一人が倒れて意識不明なんだって」
「どうして?」
「いやそれがね原因不明なんだって。ガス漏れかもしれないって今四階を業者が調べてるんだって。
警察はそのおまけ」
「はー怖いもんだな」
――くくく
悪魔だけが不謹慎に笑っていた。
人の不幸を笑う人間は絶対いい死に方しないね。
人ごみを抜け昇降口で別れる。
三人とはクラスが違うため靴を履き替えてから合流する。
「あ、ねえコウ」
「?」
別れたはずの千華が追いかけてくる。
「どうかした?」
「えっとさ……」
躊躇いがちに口を開く。
「今日の放課後……暇?」
「ん?暇だけど」
いつも通り暇です。
そんなわかりきった事聞かなくてもわかりそうなもんだけどな。
「えっとじゃあ教室で待っててくれる……昨日の手紙のこと話したいしさ」
「うん?いいけど」
「待っててね、約束だよ。そ、それじゃ!」
それだけ言うと慌てて逃げるように走っていく。
おいおいどうしたんだ?
ちらりと見えた耳は真っ赤だったような気がしないでもない。
三人とはクラスが違うため靴を履き替えてから合流する。
「あ、ねえコウ」
「?」
別れたはずの千華が追いかけてくる。
「どうかした?」
「えっとさ……」
躊躇いがちに口を開く。
「今日の放課後……暇?」
「ん?暇だけど」
いつも通り暇です。
そんなわかりきった事聞かなくてもわかりそうなもんだけどな。
「えっとじゃあ教室で待っててくれる……昨日の手紙のこと話したいしさ」
「うん?いいけど」
「待っててね、約束だよ。そ、それじゃ!」
それだけ言うと慌てて逃げるように走っていく。
おいおいどうしたんだ?
ちらりと見えた耳は真っ赤だったような気がしないでもない。
「手紙……」
思い出した。
昨日受け取った差出人不明の手紙。
あのあと奏に保健室に連れて行かれて結局有耶無耶になってしまったからカバンの中に入れっぱなしだった。
「さてそれがこれなわけか……」
席に着いた僕の手に握られているのはしわくちゃになった茶封筒。
「しかしもっと選択肢はなかったのか……」
茶封筒はないだろ。
あと変てこな差出人。
どうも僕の周りの奴は変わり者が多いようだ。
中身もノートを切って作ったような、お洒落とは程遠い便箋だ。
「あいつらしいか」
僕の知ってる千華はどこかセンスがずれていて力いっぱい空回りをしてしまうような娘だ。
「やっぱりそうなんだろうな……」
便箋に書いてある内容は簡単だ。
要約すると今日の放課後、一日たっているので昨日の放課後に教室で待っていて欲しいというものだ。
昨日の僕が上履きを取り出すときには既にあったから一昨日から仕込んでいたんだろうな。
まあ大体の目的はあれだろうな告白とかその類だろう。
――モテモテじゃないか。
この悪魔はどこでモテモテとか現代言葉覚えますか。
問題山積みですよ。
奏の反応だの隆司の反応だの。
答えられない思いだの。
面倒くさいことこの上ない。
でもなんだろう。
この胸を締め付ける感覚は……
思い出した。
昨日受け取った差出人不明の手紙。
あのあと奏に保健室に連れて行かれて結局有耶無耶になってしまったからカバンの中に入れっぱなしだった。
「さてそれがこれなわけか……」
席に着いた僕の手に握られているのはしわくちゃになった茶封筒。
「しかしもっと選択肢はなかったのか……」
茶封筒はないだろ。
あと変てこな差出人。
どうも僕の周りの奴は変わり者が多いようだ。
中身もノートを切って作ったような、お洒落とは程遠い便箋だ。
「あいつらしいか」
僕の知ってる千華はどこかセンスがずれていて力いっぱい空回りをしてしまうような娘だ。
「やっぱりそうなんだろうな……」
便箋に書いてある内容は簡単だ。
要約すると今日の放課後、一日たっているので昨日の放課後に教室で待っていて欲しいというものだ。
昨日の僕が上履きを取り出すときには既にあったから一昨日から仕込んでいたんだろうな。
まあ大体の目的はあれだろうな告白とかその類だろう。
――モテモテじゃないか。
この悪魔はどこでモテモテとか現代言葉覚えますか。
問題山積みですよ。
奏の反応だの隆司の反応だの。
答えられない思いだの。
面倒くさいことこの上ない。
でもなんだろう。
この胸を締め付ける感覚は……
「えっとさ……」
千華は恥ずかしそうに口を開いた。
彼女の顔が赤いのは窓から差し込む夕日のせいだけじゃないんだろう。
「その改まって言うのもなんだけどさ……」
約束をしたときからある程度は予測していた。
言わないで……怖い……怖いよ
「私さ、光のことね、好き……」
好きと言う言葉を聞いた瞬間心臓が跳ねた気がした。
そこで一旦彼女は言葉に詰まってしまう。
嫌だ…嫌だ…嫌だ嫌だ嫌だ!
しかし耳まで真っ赤にして千華は搾り出すように言う。
「……昔から光の事大好き!」
「――」
僕は何もいえなかった。
視界が真っ暗になる。
その言葉は想定していたはずだったのに。
僕らの距離感は仲良し四人組それ以上でもそれ以下でも無い。
誰かが大切なんじゃなくて誰もが大切。
男と女とか関係ない三人とも僕の親友だ。
ここで何か言葉を返してしまうことが僕らの関係を壊してしまいそうで僕は何も言う事が出来なかった。
その沈黙をどう受け取ったのか千華は手を振りながら誤魔化すように笑って言った。
「いや、うん、困っちゃうよね。急にこんなこと言われてもね」
じゃ、っと彼女は手を上げて逃げていった。
「え、あ……」
彼女がいなくなってからやっと搾り出した言葉は情け無いものだった。
千華は恥ずかしそうに口を開いた。
彼女の顔が赤いのは窓から差し込む夕日のせいだけじゃないんだろう。
「その改まって言うのもなんだけどさ……」
約束をしたときからある程度は予測していた。
言わないで……怖い……怖いよ
「私さ、光のことね、好き……」
好きと言う言葉を聞いた瞬間心臓が跳ねた気がした。
そこで一旦彼女は言葉に詰まってしまう。
嫌だ…嫌だ…嫌だ嫌だ嫌だ!
しかし耳まで真っ赤にして千華は搾り出すように言う。
「……昔から光の事大好き!」
「――」
僕は何もいえなかった。
視界が真っ暗になる。
その言葉は想定していたはずだったのに。
僕らの距離感は仲良し四人組それ以上でもそれ以下でも無い。
誰かが大切なんじゃなくて誰もが大切。
男と女とか関係ない三人とも僕の親友だ。
ここで何か言葉を返してしまうことが僕らの関係を壊してしまいそうで僕は何も言う事が出来なかった。
その沈黙をどう受け取ったのか千華は手を振りながら誤魔化すように笑って言った。
「いや、うん、困っちゃうよね。急にこんなこと言われてもね」
じゃ、っと彼女は手を上げて逃げていった。
「え、あ……」
彼女がいなくなってからやっと搾り出した言葉は情け無いものだった。
「はぁ~」
カバンを手にため息を搾り出す。
吐き気もおさまって幾分か気分も落ち着いた。
若干ふらつきながらも昇降口に向かう。
忘れてしまいたかった。
逃げてしまいたかった。
出来ることなら時を巻き戻して欲しい。
難なく受け流せると思っていた朝の僕を殴り倒してやりたい。
そして千華との約束をすっぽかしてしまいたかった。
適当に流してまた仲良し四人組が続けられるなんて甘いことを僕は考えていた。
でも僕には無理だ。
千華の恋を散らせることも。
隆司の気持ちを踏み潰すことも。
奏の思い無下にすることも。
僕にはできない。
そんな度胸も覚悟も存在しない。
どんな状況になっても対処できるなんて思い込んでいたのは僕の思い上がりで、分かれ道を怖がって決断から逃げて変わらないことを望み続けるだけの臆病者でしかない。
壊す勇気も変わっていく勇気も無い。
悪魔と手を組んでも何の足しにもならない。
僕はいつまでも弱い僕から逃げることは出来ない。
――おっと誰かいるぞ。
ずっと黙っていた悪魔が呟く。
気を使っていたのかただ楽しんでいたのか。
前を見ると靴箱のところから影が伸びていた。
沈みかけている太陽を背にする様に立っていた。
「えっと」
誰かと口にしようとしたところで向こうから声が飛んできた。
「おっそいよ~お兄ちゃん。一緒に帰ろ」
奏だった。
カバンを手にため息を搾り出す。
吐き気もおさまって幾分か気分も落ち着いた。
若干ふらつきながらも昇降口に向かう。
忘れてしまいたかった。
逃げてしまいたかった。
出来ることなら時を巻き戻して欲しい。
難なく受け流せると思っていた朝の僕を殴り倒してやりたい。
そして千華との約束をすっぽかしてしまいたかった。
適当に流してまた仲良し四人組が続けられるなんて甘いことを僕は考えていた。
でも僕には無理だ。
千華の恋を散らせることも。
隆司の気持ちを踏み潰すことも。
奏の思い無下にすることも。
僕にはできない。
そんな度胸も覚悟も存在しない。
どんな状況になっても対処できるなんて思い込んでいたのは僕の思い上がりで、分かれ道を怖がって決断から逃げて変わらないことを望み続けるだけの臆病者でしかない。
壊す勇気も変わっていく勇気も無い。
悪魔と手を組んでも何の足しにもならない。
僕はいつまでも弱い僕から逃げることは出来ない。
――おっと誰かいるぞ。
ずっと黙っていた悪魔が呟く。
気を使っていたのかただ楽しんでいたのか。
前を見ると靴箱のところから影が伸びていた。
沈みかけている太陽を背にする様に立っていた。
「えっと」
誰かと口にしようとしたところで向こうから声が飛んできた。
「おっそいよ~お兄ちゃん。一緒に帰ろ」
奏だった。
奏は帰りの道中終始無言だった。
なんの用があるのかもわからないまま僕は彼女の横を歩いている。
僕はと言えばさっきの出来事のせいで口を開くのも億劫でずっと黙っていた。
一緒にいられる時間も短い。
兄弟と言えども住んでいる家が違う。
もうすぐある交差点が別れる場所だ。
そこを過ぎれば僕も奏も別々の道を行く。
「じゃ」
僕はそれだけ言って奏の顔を見ないまま道を東に曲がろうとする。
「お兄ちゃんは……」
声が後ろから追いかけてきた。
「お兄ちゃんはあの人のこと好きなの?」
「え?」
振り向こうとして振り向けなかった。
怖かったのかもしれない。
「お兄ちゃんはチカ姉と付き合うの」
「えっとなんのこと?」
背中から声が飛んでくる。
あくまで誤魔化そうとした僕に対する鋭い刃だ。
「私もタカ兄も置いてきぼりなの?」
奏の影が僕の前にまで伸びている。
「お兄ちゃんは私達を切り捨てちゃうの?」
僕の足元に伸びていた影が膨らんでいく。
「奏!?」
振り返った僕を衝撃が襲った。
なんの用があるのかもわからないまま僕は彼女の横を歩いている。
僕はと言えばさっきの出来事のせいで口を開くのも億劫でずっと黙っていた。
一緒にいられる時間も短い。
兄弟と言えども住んでいる家が違う。
もうすぐある交差点が別れる場所だ。
そこを過ぎれば僕も奏も別々の道を行く。
「じゃ」
僕はそれだけ言って奏の顔を見ないまま道を東に曲がろうとする。
「お兄ちゃんは……」
声が後ろから追いかけてきた。
「お兄ちゃんはあの人のこと好きなの?」
「え?」
振り向こうとして振り向けなかった。
怖かったのかもしれない。
「お兄ちゃんはチカ姉と付き合うの」
「えっとなんのこと?」
背中から声が飛んでくる。
あくまで誤魔化そうとした僕に対する鋭い刃だ。
「私もタカ兄も置いてきぼりなの?」
奏の影が僕の前にまで伸びている。
「お兄ちゃんは私達を切り捨てちゃうの?」
僕の足元に伸びていた影が膨らんでいく。
「奏!?」
振り返った僕を衝撃が襲った。
視界が回転する。
わき腹に生まれた鋭い痛みが神経を犯していく。
斬撃に近い打撃だ。
存在しない足場を空間に意識して体に制止をかける。
空中に四肢を突き立てるようにして斜めに立つ。
「奏!」
とっさに奏を探す。
奏はいなかった。
目の前にいたのは奏に良く似た髪飾りを足元に落とした鎧姿の化け物だ。
まるで奏の中から現れたかのように奏の制服の切れ端を鎧の節々に引っ掛けながら唸っている。
手にしていた奏のものに良く似た鞄を投げ捨てると動物じみた雄たけびをあげた。
昨日見た騎士とは違い動物が鎧を着込んだかのような不恰好な外見だ。
僕は目の前の怪物を視界の中心に収めながら己の内の悪魔に呼びかける。
「おい!奏はどうした!」
――目の前に答えがあるだろう?
わからないわけが無いだろ、考えてる通りだ。
いやらしい笑い声と共に答えが返ってくる。
「なん――!?」
往来に弾き飛ばされる。
空中で体勢を立て直そうとして一つのものを見つける。
僕と着地地点の間に走ってくるのは一台の車だ。
「人!?」
一瞬の間に眼を凝らしてみれば視界のそこかしこに人がいる。
こちらに気がついて携帯電話で写真を撮っているものも入れば怯えたように逃げ出そうとしているものも入る。
頭を占めるのは何故。
奏は何処に行った。
何故奏のいた場所に化け物が立っていた。
何故僕の落ちる先に車がある。
後部座席にいる子供と眼が合った。
何故化け物は僕に追撃を入れるように飛んだ。
僕の目の前に拳が迫る。
ゆっくりと迫ったそれは僕の顔面を捉えそのまま押し込んでくる。
後から紙の箱が潰れるような音がする。
きっとさっきの車だ。
金属の破砕音。
地面に埋まる。
打ち込まれる。
車を貫通して。
地下数メートル
目の前には僕の空けた穴がある。
空が見える。
綺麗な夕焼け空だ。
綺麗な夕焼け空が見えたら明日は晴れなんだっけ?
明日もみんなで他愛の無い馬鹿みたいな話をしながら登校するんだろうか。
そういえば千華に告白もされたっけ。
明日どんな顔をして会えばいいのかな?
いつも通りでいいのかな?
早めに返事したほうがいいんだろうか?
僕にそんな決断が出来るとも思えないけどね。
自嘲気味に哂うと頬に水滴が落ちてきた。
雨?
涙?
穴の底から見える空は晴れている。
僕は泣いていない。
手で拭うと薄闇の中でもわかる赤だった。
血?
僕は怪我をしていない。
化け物に殴られて。
車に衝突して。
乗っている人を押し潰して。
地面を掘り下げて。
でも無傷だ。
軽い痛みはあるが血は流れていない。
埋め込まれても怪我一つ無い頑丈な体だ。
普通の人間はこうはいかない。
まるでトマトの様に潰れてしまう。
真っ赤な血も流れるだろう。
とても痛いかもしれない。
逆に麻痺して全然痛く無いかもしれない。
けど普通の人間は死んでしまう。
誰の血?
走っている車に乗っている子供と眼が合った。
両親と買い物にでも行っていたのか笑っていた。
さっきまでは。
僕が押しつぶした車に乗っていた子供。
頬に一滴の血。
笑っていた顔が恐怖に引きつる。
誰の血?
笑っていた子供。
滴る血。
普通の人間は無傷では済まない。
血。
トマトの様に潰れてしまう。
人。
ぐちゃっと
血。
惨たらしく中身を搾り出して
人。
死ぬ。
血。
人は簡単に死ぬ。
「うあああああああああああああああああああ」
僕は土がむき出した穴を登り始めた。
爪の隙間に土が入り込むどころか指先が固められた土に難なく突き刺さる。
普通の人間はこうはいかない。
数メートルの高さを一度も落ちることなく上りきる。
普通の人間はこうはいかない。
穴を囲むようにひしゃげた車を片手で持ち上げる。
普通の人間はこうはいかない。
僕は普通じゃなかった。
僕も化け物だ。
――やっぱりお前らは似たもの同士の親友だ。
わき腹に生まれた鋭い痛みが神経を犯していく。
斬撃に近い打撃だ。
存在しない足場を空間に意識して体に制止をかける。
空中に四肢を突き立てるようにして斜めに立つ。
「奏!」
とっさに奏を探す。
奏はいなかった。
目の前にいたのは奏に良く似た髪飾りを足元に落とした鎧姿の化け物だ。
まるで奏の中から現れたかのように奏の制服の切れ端を鎧の節々に引っ掛けながら唸っている。
手にしていた奏のものに良く似た鞄を投げ捨てると動物じみた雄たけびをあげた。
昨日見た騎士とは違い動物が鎧を着込んだかのような不恰好な外見だ。
僕は目の前の怪物を視界の中心に収めながら己の内の悪魔に呼びかける。
「おい!奏はどうした!」
――目の前に答えがあるだろう?
わからないわけが無いだろ、考えてる通りだ。
いやらしい笑い声と共に答えが返ってくる。
「なん――!?」
往来に弾き飛ばされる。
空中で体勢を立て直そうとして一つのものを見つける。
僕と着地地点の間に走ってくるのは一台の車だ。
「人!?」
一瞬の間に眼を凝らしてみれば視界のそこかしこに人がいる。
こちらに気がついて携帯電話で写真を撮っているものも入れば怯えたように逃げ出そうとしているものも入る。
頭を占めるのは何故。
奏は何処に行った。
何故奏のいた場所に化け物が立っていた。
何故僕の落ちる先に車がある。
後部座席にいる子供と眼が合った。
何故化け物は僕に追撃を入れるように飛んだ。
僕の目の前に拳が迫る。
ゆっくりと迫ったそれは僕の顔面を捉えそのまま押し込んでくる。
後から紙の箱が潰れるような音がする。
きっとさっきの車だ。
金属の破砕音。
地面に埋まる。
打ち込まれる。
車を貫通して。
地下数メートル
目の前には僕の空けた穴がある。
空が見える。
綺麗な夕焼け空だ。
綺麗な夕焼け空が見えたら明日は晴れなんだっけ?
明日もみんなで他愛の無い馬鹿みたいな話をしながら登校するんだろうか。
そういえば千華に告白もされたっけ。
明日どんな顔をして会えばいいのかな?
いつも通りでいいのかな?
早めに返事したほうがいいんだろうか?
僕にそんな決断が出来るとも思えないけどね。
自嘲気味に哂うと頬に水滴が落ちてきた。
雨?
涙?
穴の底から見える空は晴れている。
僕は泣いていない。
手で拭うと薄闇の中でもわかる赤だった。
血?
僕は怪我をしていない。
化け物に殴られて。
車に衝突して。
乗っている人を押し潰して。
地面を掘り下げて。
でも無傷だ。
軽い痛みはあるが血は流れていない。
埋め込まれても怪我一つ無い頑丈な体だ。
普通の人間はこうはいかない。
まるでトマトの様に潰れてしまう。
真っ赤な血も流れるだろう。
とても痛いかもしれない。
逆に麻痺して全然痛く無いかもしれない。
けど普通の人間は死んでしまう。
誰の血?
走っている車に乗っている子供と眼が合った。
両親と買い物にでも行っていたのか笑っていた。
さっきまでは。
僕が押しつぶした車に乗っていた子供。
頬に一滴の血。
笑っていた顔が恐怖に引きつる。
誰の血?
笑っていた子供。
滴る血。
普通の人間は無傷では済まない。
血。
トマトの様に潰れてしまう。
人。
ぐちゃっと
血。
惨たらしく中身を搾り出して
人。
死ぬ。
血。
人は簡単に死ぬ。
「うあああああああああああああああああああ」
僕は土がむき出した穴を登り始めた。
爪の隙間に土が入り込むどころか指先が固められた土に難なく突き刺さる。
普通の人間はこうはいかない。
数メートルの高さを一度も落ちることなく上りきる。
普通の人間はこうはいかない。
穴を囲むようにひしゃげた車を片手で持ち上げる。
普通の人間はこうはいかない。
僕は普通じゃなかった。
僕も化け物だ。
――やっぱりお前らは似たもの同士の親友だ。
「……だよ。……なんでだよ。……なんでなんだよ!」
化け物が人を殺していた。
好奇心で近寄る人を握り潰した。
恐怖で逃げ惑う人を踏み潰した。
人を殺した。
「奏は……奏はどこだ……」
――そこで人を殺してるだろ?
また一人殺した。
「何で昨日と違うんだよ……昨日の奴は勝手に現れて、周りには人がいなくて。
僕が叩きのめして、僕は正義の味方で……なんでだよ」
――何も違わないさ。
「じゃあなんで奏が化け物になるんだよ!なんで人が死ぬんだよ!」
――ヘレナの中に人がいないとでも思ったか?
「え?」
――結界の中と外で少しかっては違うがヘレナもこちらの人間を核としていた。
「!?」
化け物が人を殺していた。
好奇心で近寄る人を握り潰した。
恐怖で逃げ惑う人を踏み潰した。
人を殺した。
「奏は……奏はどこだ……」
――そこで人を殺してるだろ?
また一人殺した。
「何で昨日と違うんだよ……昨日の奴は勝手に現れて、周りには人がいなくて。
僕が叩きのめして、僕は正義の味方で……なんでだよ」
――何も違わないさ。
「じゃあなんで奏が化け物になるんだよ!なんで人が死ぬんだよ!」
――ヘレナの中に人がいないとでも思ったか?
「え?」
――結界の中と外で少しかっては違うがヘレナもこちらの人間を核としていた。
「!?」
「えっとね」
釈然としない様子ながらも中心で知ったことを話してくれる。
「何かね、昨日居残ってた生徒の一人が倒れて意識不明なんだって」
「どうして?」
「いやそれがね原因不明なんだって。ガス漏れかもしれないって今四階を業者が調べてるんだって。
警察はそのおまけ」
釈然としない様子ながらも中心で知ったことを話してくれる。
「何かね、昨日居残ってた生徒の一人が倒れて意識不明なんだって」
「どうして?」
「いやそれがね原因不明なんだって。ガス漏れかもしれないって今四階を業者が調べてるんだって。
警察はそのおまけ」
――お前はそれを倒した。
意気揚々と。
今も変わらないさ今から妹を殺せば言いだけだ。
「――だ、あ、え?」
――殺すんだよ。
奏が口から血を滴らせながらこちらを向いた。
聞き取れない言葉を発しながらこちらを見ている。
「奏……」
そしてこちらに飛び掛ってきた。
僕は……
意気揚々と。
今も変わらないさ今から妹を殺せば言いだけだ。
「――だ、あ、え?」
――殺すんだよ。
奏が口から血を滴らせながらこちらを向いた。
聞き取れない言葉を発しながらこちらを見ている。
「奏……」
そしてこちらに飛び掛ってきた。
僕は……
暗い場所。
寒い場所。
日の当たらない場所。
暖かさの無い場所。
僕の唯一の居場所。
僕の心の中。
僕は此処以外に存在を許されていない。
暗闇の中で冷たく冷えた手足の感覚すらない。
温かさは無くて、優しさも無くて。
ただただ寒さと飢えをしのいだ。
始まりの場所。
そして終わる場所。
信じられるのは自分だけ。
誰も信じられない。
暗闇だけが安心できた。
隙間から忍び込んでくる光すらも怖かった。
安息の地が照らし出された時僕は逃げた。
少しでも奥へ。
出来るだけ暗がりへ。
どんなに辛くても光りはもっと恐ろしいから。
暗闇の底だけが僕を傷つけることなく受け入れてくれたから。
寒い場所。
日の当たらない場所。
暖かさの無い場所。
僕の唯一の居場所。
僕の心の中。
僕は此処以外に存在を許されていない。
暗闇の中で冷たく冷えた手足の感覚すらない。
温かさは無くて、優しさも無くて。
ただただ寒さと飢えをしのいだ。
始まりの場所。
そして終わる場所。
信じられるのは自分だけ。
誰も信じられない。
暗闇だけが安心できた。
隙間から忍び込んでくる光すらも怖かった。
安息の地が照らし出された時僕は逃げた。
少しでも奥へ。
出来るだけ暗がりへ。
どんなに辛くても光りはもっと恐ろしいから。
暗闇の底だけが僕を傷つけることなく受け入れてくれたから。
路上に少年が立ち尽くしていた。
布切れ同然となった血まみれの服をまといながらも少年の体には傷一つ無い。
彼の目の前では惨劇が引き起こされていた。
普段は帰路に着く学生や買い物を終えた主婦が歩いている道は紅に染まっていた。
夕焼けに染まる通学路をなお紅く染め上げる。
布切れ同然となった血まみれの服をまといながらも少年の体には傷一つ無い。
彼の目の前では惨劇が引き起こされていた。
普段は帰路に着く学生や買い物を終えた主婦が歩いている道は紅に染まっていた。
夕焼けに染まる通学路をなお紅く染め上げる。
アスファルトに染み入る血、血、血。
ひび割れた路上に撒き散らされた人、人、人。
原型をとどめている死体はなくどれも圧倒的な力で破壊されている。
その惨劇を起こしたのは
「――――」
雄たけびを上げる鎧に包まれた異形の化け物だ。
成人男性の二倍近くある体躯は重厚な鎧に包まれている。
ガントレットを突き破り伸びる爪には先ほどまで人間だったものが引っかかっている。
一滴の憐憫もなく一瞬の躊躇もなく化け物は辺りにいる全ての人間を処理した。
最後の獲物は穴の近くに立つ少年だ。
少年はその光景に対して何も反応をしない。
空ろな瞳は何を写すでもなくただ開かれていた。
化け物が飛び上がる。
少年に向けて跳躍する。
少年はその光景を見ているはずなのに動かない。
ただただ視界の中で大きくなっていく化け物を見つめている。
右の鉤爪が叩き込まれる。
人が宙を舞う。
腕が飛ぶ。
足がちぎれる。
耳を塞ぎたくなるような異音共に路上を跳ねた芋虫の上に怪物が飛び上がる。
そして重力加速を超える速さで落ちた。
少年が地面に広がる。
しかし燐光を発し巻き戻しのように少年の体は修復される。
幾たび吹き飛び。
幾たび千切れようとも。
鉤爪が穿つ。
拳が砕く。
幾度も幾度も。
殺されては蘇り。
壊されては直る。
穿たれては塞ぎ。
斬られては繋ぎ。
もがれては生やし。
何度も何度も。
少年は抵抗をすることなく苦痛のうめきを漏らす事もなく殺される。
しかし同じように繰り返される光景にも変化がある。
少年の傷が治る速度が徐々に遅くなっていく。
そして気のせいか纏う蛍火も輝きを失ってゆく。
彼らにとって負傷とはたいした問題ではない。
どんな傷も意識するまでもなく直って行く。
例え腕がもげようとも、全身が灰もなくなるまで焼かれようとも。
それが彼らの異能だ。
いや異能と言うほどのことでもない呼吸と変わらないただの何気ない生命活動だ。
どんな凶器も寄せ付けずどんな傷にも死に至らしめられることの無い存在それが彼らだ。
彼らが死ぬときは唯一つ、心の底から死を願ったときだ。
心が死んだ時に彼らは死ぬ、いや死ねる。
怪物が少年を押さえつける。
いや押さえつけるといえるほど生易しいものではない。
握り拳が腹部を貫通し右腕が握りつぶされる。
牙が突き刺さりそうなほど顔を近づける。
原型をとどめていない化け物が少女の声でささやく。
「オニイチャンコレデズットイッショダヨ。オニイチャンハワタシガマモッテアゲルカラ」
牙を生やした裂け目から漏れ出す声は先ほどまでと全く変わりなくしかし狂気を孕んでいた。
少年の腹部の傷がふさがってゆく。
修復ではない侵食だ。
怪物と少年が触れ合ったところから少年の体が染まってゆく。
一つになるために。
ひび割れた路上に撒き散らされた人、人、人。
原型をとどめている死体はなくどれも圧倒的な力で破壊されている。
その惨劇を起こしたのは
「――――」
雄たけびを上げる鎧に包まれた異形の化け物だ。
成人男性の二倍近くある体躯は重厚な鎧に包まれている。
ガントレットを突き破り伸びる爪には先ほどまで人間だったものが引っかかっている。
一滴の憐憫もなく一瞬の躊躇もなく化け物は辺りにいる全ての人間を処理した。
最後の獲物は穴の近くに立つ少年だ。
少年はその光景に対して何も反応をしない。
空ろな瞳は何を写すでもなくただ開かれていた。
化け物が飛び上がる。
少年に向けて跳躍する。
少年はその光景を見ているはずなのに動かない。
ただただ視界の中で大きくなっていく化け物を見つめている。
右の鉤爪が叩き込まれる。
人が宙を舞う。
腕が飛ぶ。
足がちぎれる。
耳を塞ぎたくなるような異音共に路上を跳ねた芋虫の上に怪物が飛び上がる。
そして重力加速を超える速さで落ちた。
少年が地面に広がる。
しかし燐光を発し巻き戻しのように少年の体は修復される。
幾たび吹き飛び。
幾たび千切れようとも。
鉤爪が穿つ。
拳が砕く。
幾度も幾度も。
殺されては蘇り。
壊されては直る。
穿たれては塞ぎ。
斬られては繋ぎ。
もがれては生やし。
何度も何度も。
少年は抵抗をすることなく苦痛のうめきを漏らす事もなく殺される。
しかし同じように繰り返される光景にも変化がある。
少年の傷が治る速度が徐々に遅くなっていく。
そして気のせいか纏う蛍火も輝きを失ってゆく。
彼らにとって負傷とはたいした問題ではない。
どんな傷も意識するまでもなく直って行く。
例え腕がもげようとも、全身が灰もなくなるまで焼かれようとも。
それが彼らの異能だ。
いや異能と言うほどのことでもない呼吸と変わらないただの何気ない生命活動だ。
どんな凶器も寄せ付けずどんな傷にも死に至らしめられることの無い存在それが彼らだ。
彼らが死ぬときは唯一つ、心の底から死を願ったときだ。
心が死んだ時に彼らは死ぬ、いや死ねる。
怪物が少年を押さえつける。
いや押さえつけるといえるほど生易しいものではない。
握り拳が腹部を貫通し右腕が握りつぶされる。
牙が突き刺さりそうなほど顔を近づける。
原型をとどめていない化け物が少女の声でささやく。
「オニイチャンコレデズットイッショダヨ。オニイチャンハワタシガマモッテアゲルカラ」
牙を生やした裂け目から漏れ出す声は先ほどまでと全く変わりなくしかし狂気を孕んでいた。
少年の腹部の傷がふさがってゆく。
修復ではない侵食だ。
怪物と少年が触れ合ったところから少年の体が染まってゆく。
一つになるために。
言いつけに逆らったら手が挙がった。
顔を守ったら腹に拳が叩き込まれた。
床に伏し呻いていたらつま先がめり込んだ。
始めに覚えたのは絶えることだった。
手が挙がったら身構えてはいけない。
身構えればもっと手ひどい目にあう。
ただ耐えるだけだった。
歯を食いしばってはいけない。
表情を変えてはいけない。
声を漏らしてはいけない。
あらゆる動作が次の暴力の理由になる。
少年に求められるのは人として役割ではない。
ただの内臓と血が詰まったサンドバックだ。
親の気がすむまで殴り続けられた。
骨がおれることも珍しくは無い。
大人の力では子供の骨が折れるのも当然だ。
病院には連れて行ってもらえなかった。
体罰が終わったあと悲鳴を漏らさないように力任せに戻すだけだった。
自らの名前も知らない子供が骨折の治療法も止血法も我流だが知っていた。
四肢の骨はともかく肋骨なんかは自らでは治せない。
内臓に刺さらなかったのは行幸と言うほか無い。
きっと今でも変形した骨が肺やらなにやらに食い込んでいるのだろう。
食事はきっと近所の野良猫のがいいものを食べていただろう。
勝手に動くことも許されていなかったから食べ物を手に入れることなんて出来なかった。
日中がそうなのだから夜もたいして変わりなかった。
少年に与えられたのは半畳にも満たない押入れの隙間だった。
埃っぽく床の硬いそこの寝心地は最悪だった。
いや寝れた事すら珍しい。
痛みに耐えて夜が明けるか気絶したまま放り込まれることがざらだった。
冬は土壁が冷気を放ち凍死寸前だった。
毛布すらない暗闇の中体を震わせることなく少年は耐えた。
体を震わせ音を立てれば待っているのは折檻だった。
染み入る冷気と染み出す体温。
毎日が生きるか死ぬかだった。
だから――
だからこんな子供が親を殺そうと決心しするのもしょうがなかったのだろう。
計画を立てた。
事故死に見せかけるために。
隙を見て徐々に計画を進めていった。
子供だったからボロも多かっただろう。
一歩の間違えで計画が破綻したかもしれない。
きっと警察には真相はばれていただろう。
小学校にも入らないような子供だから罪に問わなかったのかもしれないし境遇から見た温情だったのかもしれない。
ともかく少年は遠縁の親戚に引き取られた。
顔を守ったら腹に拳が叩き込まれた。
床に伏し呻いていたらつま先がめり込んだ。
始めに覚えたのは絶えることだった。
手が挙がったら身構えてはいけない。
身構えればもっと手ひどい目にあう。
ただ耐えるだけだった。
歯を食いしばってはいけない。
表情を変えてはいけない。
声を漏らしてはいけない。
あらゆる動作が次の暴力の理由になる。
少年に求められるのは人として役割ではない。
ただの内臓と血が詰まったサンドバックだ。
親の気がすむまで殴り続けられた。
骨がおれることも珍しくは無い。
大人の力では子供の骨が折れるのも当然だ。
病院には連れて行ってもらえなかった。
体罰が終わったあと悲鳴を漏らさないように力任せに戻すだけだった。
自らの名前も知らない子供が骨折の治療法も止血法も我流だが知っていた。
四肢の骨はともかく肋骨なんかは自らでは治せない。
内臓に刺さらなかったのは行幸と言うほか無い。
きっと今でも変形した骨が肺やらなにやらに食い込んでいるのだろう。
食事はきっと近所の野良猫のがいいものを食べていただろう。
勝手に動くことも許されていなかったから食べ物を手に入れることなんて出来なかった。
日中がそうなのだから夜もたいして変わりなかった。
少年に与えられたのは半畳にも満たない押入れの隙間だった。
埃っぽく床の硬いそこの寝心地は最悪だった。
いや寝れた事すら珍しい。
痛みに耐えて夜が明けるか気絶したまま放り込まれることがざらだった。
冬は土壁が冷気を放ち凍死寸前だった。
毛布すらない暗闇の中体を震わせることなく少年は耐えた。
体を震わせ音を立てれば待っているのは折檻だった。
染み入る冷気と染み出す体温。
毎日が生きるか死ぬかだった。
だから――
だからこんな子供が親を殺そうと決心しするのもしょうがなかったのだろう。
計画を立てた。
事故死に見せかけるために。
隙を見て徐々に計画を進めていった。
子供だったからボロも多かっただろう。
一歩の間違えで計画が破綻したかもしれない。
きっと警察には真相はばれていただろう。
小学校にも入らないような子供だから罪に問わなかったのかもしれないし境遇から見た温情だったのかもしれない。
ともかく少年は遠縁の親戚に引き取られた。
「それがお前だ」
悪魔のささやきが聞こえた。
白い部屋だ。
どこに光源があるわけでも無いのに明るい。
僕は影を持たずどこか現実感が伴わない。
僕は声の源を探した。
「人の思い出なんか勝手に語って悪趣味だなどこにいるんだ?」
「語ったのは俺じゃないそいつさ」
部屋の中を見渡す。
「!?」
部屋の隅に先ほどまではいなかった子供がいる。
顔を伏せすすり泣く。
「おい、どうした」
僕の声にこたえることも泣く少年はただ涙を流し続ける。
「さあよくその選択が全てを分ける」
僕は天井を振り仰いで答えた。
「隠れてないで出て来いよ」
――それで少年は幸せになれるはずだった。
でも少年の心に打ち込まれた楔は抜けなかった。
心に楔が打ち込まれている。
深く深く。
その楔は亀裂をもたらした。
心は二つに分かたれた――
「!?」
声がした。
耳で聞く音ではない。
頭に響くような心がうずくような言葉だ。
「お前……か?」
少年はそれでも泣き続ける。
「いい加減泣きやめよ」
僕は少年の肩に手をかけた。
「それがお前の選択か」
悪魔のささやきが聞こえた。
白い部屋だ。
どこに光源があるわけでも無いのに明るい。
僕は影を持たずどこか現実感が伴わない。
僕は声の源を探した。
「人の思い出なんか勝手に語って悪趣味だなどこにいるんだ?」
「語ったのは俺じゃないそいつさ」
部屋の中を見渡す。
「!?」
部屋の隅に先ほどまではいなかった子供がいる。
顔を伏せすすり泣く。
「おい、どうした」
僕の声にこたえることも泣く少年はただ涙を流し続ける。
「さあよくその選択が全てを分ける」
僕は天井を振り仰いで答えた。
「隠れてないで出て来いよ」
――それで少年は幸せになれるはずだった。
でも少年の心に打ち込まれた楔は抜けなかった。
心に楔が打ち込まれている。
深く深く。
その楔は亀裂をもたらした。
心は二つに分かたれた――
「!?」
声がした。
耳で聞く音ではない。
頭に響くような心がうずくような言葉だ。
「お前……か?」
少年はそれでも泣き続ける。
「いい加減泣きやめよ」
僕は少年の肩に手をかけた。
「それがお前の選択か」
ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
僕は泣いていた。
白い部屋の隅で泣いていた。
触られていないのに背中に感じる重み。
絶え間ないささやき声。
僕は頭を抱え懇願した。
すぐ後ろから聞こえる声。
怖い。
僕を責め立てる。
父さんの声。
母さんの声。
許してください。許してください。許してください。
許してください。許してください。許してください。
許してください。許してください。許してください。
許してください。許してください。許してください。
許してください。許してください。許してください。
もう何日も僕にささやき続ける。
声を枯らして懺悔した。
償いの傷も刻んだ。
それでも許してはもらえなかった。
体にかかる重圧。
言葉が僕を締め付ける。
肌に呪詛が刻み込まれる。
お前が殺した。
僕を助けてください。
僕を救ってください。
僕を守ってください。
僕を癒してください。
僕を好いてください。
僕を嫌わないでください。
僕を憎まないでください。
僕を恨まないでください。
僕を否定しないでください。
僕を認めてください。
僕を必要としてください。
誰も助けてくれなかった。
誰も救ってくれなかった。
誰も守ってくれなかった。
誰も認めてくれなかった。
誰も僕を必要としてくれなかった。
僕は一人だった。
だった。
何かが音を立てて切れた気がした。
「ほら、いつまで泣いてるの?」
懐かしくて温かい声がした。
顔を上げると二つの大きな影が僕の前に立っていた。
「光は泣き虫だな」
少し笑いを含んだ声が聞こえた。
「もうあなたったら。立って光」
涙に歪む視界に白くて細い手が差し出される。
「ママたちと一緒に行こ?」
優しい救いの手だ。
きっとその手を握れば苦しいことは何も無くて。
きっとその手を握れば幸せな未来が待っていて。
僕はその手を取った――
ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
僕は泣いていた。
白い部屋の隅で泣いていた。
触られていないのに背中に感じる重み。
絶え間ないささやき声。
僕は頭を抱え懇願した。
すぐ後ろから聞こえる声。
怖い。
僕を責め立てる。
父さんの声。
母さんの声。
許してください。許してください。許してください。
許してください。許してください。許してください。
許してください。許してください。許してください。
許してください。許してください。許してください。
許してください。許してください。許してください。
もう何日も僕にささやき続ける。
声を枯らして懺悔した。
償いの傷も刻んだ。
それでも許してはもらえなかった。
体にかかる重圧。
言葉が僕を締め付ける。
肌に呪詛が刻み込まれる。
お前が殺した。
僕を助けてください。
僕を救ってください。
僕を守ってください。
僕を癒してください。
僕を好いてください。
僕を嫌わないでください。
僕を憎まないでください。
僕を恨まないでください。
僕を否定しないでください。
僕を認めてください。
僕を必要としてください。
誰も助けてくれなかった。
誰も救ってくれなかった。
誰も守ってくれなかった。
誰も認めてくれなかった。
誰も僕を必要としてくれなかった。
僕は一人だった。
だった。
何かが音を立てて切れた気がした。
「ほら、いつまで泣いてるの?」
懐かしくて温かい声がした。
顔を上げると二つの大きな影が僕の前に立っていた。
「光は泣き虫だな」
少し笑いを含んだ声が聞こえた。
「もうあなたったら。立って光」
涙に歪む視界に白くて細い手が差し出される。
「ママたちと一緒に行こ?」
優しい救いの手だ。
きっとその手を握れば苦しいことは何も無くて。
きっとその手を握れば幸せな未来が待っていて。
僕はその手を取った――
「……っれ」
「ん?何か言った光?」
「くそったれぇ!!!」
その手を引き寄せ交差法で拳を叩き込む。
薄い手ごたえだ。
驚いた顔をした男の腹部に蹴りを打ち込む。
何も無い虚空に拳を叩き付けた。
砕けた。
破片が宙でぶつかり合ってさらに細かく割れる。
甘い幻想は露と消える。
光に満ちた空間は幻のように立ち消える。
夢は終わりを告げる。
前に立つのは優しそうな顔をした見覚えの無い奴でも温和そうな赤の他人でもない。
鎧を纏った悪魔だ。
「見覚えの無い奴だとか赤の他人だとかひどい言い草だな」
ここは心の中。
思ったことが相手にすぐ伝わる。
「あいつらは僕にあんな顔をしない。
あいつらは獣だ」
兜の亀裂の中で奴が笑った。
「獣を狩るのは化け物か」
僕はあいつの顔面に拳を叩き込んだ。
「僕は全ての罪を受け入れよう。
苦痛も絶望も辛酸も困難も悲嘆も孤独も拒絶も全てを。
全ての罰も受け入れよう。
親殺しの罰も受け入れよう。
僕はもう逃げない。
僕はもう迷わない」
自分の殻に篭り全てを拒絶して。
でもそんなことじゃ何も解決しなくて。
だから、あいつが満足そうに笑った気がした。
「僕を必要としてくれる奴がいる。
だからてめぇは黙って引っ込んでろ」
「ん?何か言った光?」
「くそったれぇ!!!」
その手を引き寄せ交差法で拳を叩き込む。
薄い手ごたえだ。
驚いた顔をした男の腹部に蹴りを打ち込む。
何も無い虚空に拳を叩き付けた。
砕けた。
破片が宙でぶつかり合ってさらに細かく割れる。
甘い幻想は露と消える。
光に満ちた空間は幻のように立ち消える。
夢は終わりを告げる。
前に立つのは優しそうな顔をした見覚えの無い奴でも温和そうな赤の他人でもない。
鎧を纏った悪魔だ。
「見覚えの無い奴だとか赤の他人だとかひどい言い草だな」
ここは心の中。
思ったことが相手にすぐ伝わる。
「あいつらは僕にあんな顔をしない。
あいつらは獣だ」
兜の亀裂の中で奴が笑った。
「獣を狩るのは化け物か」
僕はあいつの顔面に拳を叩き込んだ。
「僕は全ての罪を受け入れよう。
苦痛も絶望も辛酸も困難も悲嘆も孤独も拒絶も全てを。
全ての罰も受け入れよう。
親殺しの罰も受け入れよう。
僕はもう逃げない。
僕はもう迷わない」
自分の殻に篭り全てを拒絶して。
でもそんなことじゃ何も解決しなくて。
だから、あいつが満足そうに笑った気がした。
「僕を必要としてくれる奴がいる。
だからてめぇは黙って引っ込んでろ」
僕は久しぶりに呼吸をした。
肺に新鮮な空気が流れ込んでくる。
遮断されていた痛みが伝達される。
歯を食いしばって痛みに耐える。
僕は生きている。
僕は逃げない。
僕は迷わない。
腹部の傷から奏の腕を侵食する。
腕から肩へ。
肩から胴体へ。
胴体から全身へ。
奏の全ての機能を奪い取る。
心にも触れた。
僕を思う気持ち。
隆司を慕う気持ち。
千華を羨む気持ち。
恨み。
妬み。
嫉み。
殺意。
普段の明るく快活な奏からは想像できない澱があった。
淀みの源は僕だ。
僕が植えつけた気持ち。
僕が汚した奏。
僕が奏を苦しめ傷つけた。
そっと腕を抱きしめる。
想像するのは奏の姿。
いつもの奏。
その姿を想像し奏を再構成する。
「お兄……ちゃん」
華奢な体を抱きしめる。
「おやすみ、奏」
「……うん」
奏から光が一斉に舞い上がる。
開放されたことを喜ぶように天に舞い上がる。
僕は涙を流さず泣いていた。
肺に新鮮な空気が流れ込んでくる。
遮断されていた痛みが伝達される。
歯を食いしばって痛みに耐える。
僕は生きている。
僕は逃げない。
僕は迷わない。
腹部の傷から奏の腕を侵食する。
腕から肩へ。
肩から胴体へ。
胴体から全身へ。
奏の全ての機能を奪い取る。
心にも触れた。
僕を思う気持ち。
隆司を慕う気持ち。
千華を羨む気持ち。
恨み。
妬み。
嫉み。
殺意。
普段の明るく快活な奏からは想像できない澱があった。
淀みの源は僕だ。
僕が植えつけた気持ち。
僕が汚した奏。
僕が奏を苦しめ傷つけた。
そっと腕を抱きしめる。
想像するのは奏の姿。
いつもの奏。
その姿を想像し奏を再構成する。
「お兄……ちゃん」
華奢な体を抱きしめる。
「おやすみ、奏」
「……うん」
奏から光が一斉に舞い上がる。
開放されたことを喜ぶように天に舞い上がる。
僕は涙を流さず泣いていた。