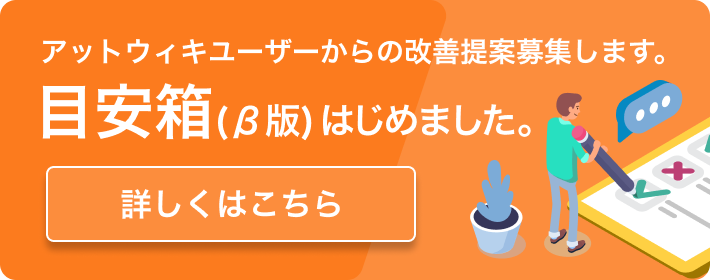「えっほ、げほ……」
「大丈夫ですか、春樹君?」
「な、なんとかね……げほっ」
宮久地に背中をさすってもらって、なんとか普通に呼吸できる状態になった。危うく答える前に死ぬところだった。
「マリア、いくら友達といえど今のは許せないですよ」
「な、何よ、だってこうやった方が手っ取り早いし、それに悪魔っぽいかなって……」
「相手が死に掛けてて、それがマトモな交渉だと本当に思ってるんですか!?」
「う、うみゅう……だって、だって……」
あからさまにマリアがへこみだした。まぁ、実の友人に本気で怒られれば落ち込むものだろうとは思うが。
「あんな風に首を絞めたら死んでしまうに決まってるでしょう!? それをマリアは――」
「ありがとう、宮久地。 けど、僕にも言いたい事があるから怒るのはそれくらいにしてくれないか」
「け、けれど春樹君が……」
「頼むよ、宮久地、話させてほしい」
「……わかりました。 春樹君がそういうのなら」
そういうと宮久地はスッと下がってくれた。流石は幼馴染――本当は違うらしいが、まぁどちらでも僕にはどうでもいいことだ――聞き分けのいい人は、僕は嫌いじゃない。むしろ好感を持てる。それよりもとりあえずマリアに答えなくては。
「――マリア」
「なに……」
「とりあえず悪の道にも誘われる気も君の下僕にも執事にもなる気はない。そんなことよりもだ」
「……え?」
「君は悪魔なのに、悪魔らしさを気にしているのはなぜなんだ?」
そう、彼女は先ほどから言葉のどこかに悪魔らしさを入れ込んでいる。悪魔っぽい、悪魔らしい。それが僕にとってはとても不思議だった。だから僕は聞きたくなった。なぜ、そんなにも悪魔ということにこだわるのか。彼女、マリアは悪魔であるはずなのに。
「何よ、悪魔が悪魔らしさを気にしたら何かいけないって言うの?」
「いやそんなことを言う気はない。ただ気になっただけだよ。宮久地は――君にとってはセリナか、彼女は一度だって天使だからとか、天使らしくとかそんなことは口にしなかったのに、君はやたらと気にしているようだからね」
「むぐ……」
僕がこういうと、マリアは苦い顔をしながら口を閉じてしまった。やはり何か原因があるようだが、それが何なのかは今の僕にはわからない。
「マリア……ひょっとして、今でも気にしてるんですか?」
「セリナと話すことなんて、ない」
「マリアのお父さんの――」
「だぁかぁら! 私はセリナと話すことなんてない! 今の私の相手はこいつ、池田春樹! セリナは関係ない!」
激昂したような叫びをあげながら、僕の目の前には巨大な槍が突きつけられている。下手に動くと串刺しより酷いことになりそうなので今は黙っておこう。
「池田春樹……今日はこの辺で勘弁したげるけど、絶対に、私はあんたを悪の道に堕としてみせるんだから」
そう宣言すると、この間のようにバサバサとその黒い翼をはためいてどこかへと飛び去ってしまった。僕がそれを確認すると、後ろから走りよってくる音が聞こえる。
「春樹君、大丈夫ですか!?」
「ああ、あの馬鹿でかい槍には刺さってないよ」
「よかった……春樹君がマリアに何されるか、ほんとに心配で……」
そういいながら僕の手を握り締める宮久地。どうやら、だいぶ彼女には心配を掛けさせてしまったらしい。なぜそこまで僕のことを気にするのかはよく分からないが。心配を掛けさせてしまったならそれは僕の不手際だろう。
「ええと、すまない」
「いえそんな、私が春樹君に謝ることがあっても、春樹君が謝ることはありませんよ! 私が、ちょっと目を離した隙にこんなことになって……」
「いや、僕がここに一人できたのは独断だ。 責任が生じるならそれは僕にある。 宮久地が責任を負うことじゃない」
「で、ですけど春樹君が危うく大変なことに……」
「ちょうどいいところで君は来てくれただろう? それだけで十分だよ。 それに――」
そして僕は宮久地の右手を握って僕の胸に当てた。制服越しとはいえ、恐らく心臓の鼓動の振動くらいは伝わるはずだ。
「あわ!?……ひゃ、ひゃるきしゃん……?」
宮久地の顔がなぜかゆでだこになっているが、まぁどうでもいいだろう。きっとこの間の風邪でも続いているんだろう。
彼女の状態など気にせず、僕は自身の話を続けた。
「君のおかげで、僕は一切怪我は負わなかった。 少しだけ首は痛むけど、問題は無い。 だから、それでいいだろう」
「え、えと……!」
「僕の体を触る以上の証拠が、まだ必要なのかい?」
「か、体を触る――以上――う、うひゅう――」
僕の話が終わるのと、宮久地がばったりと倒れるのはほぼ同時のことだった。彼女の頭がコンクリートに重力に任せた衝突をする前に一応支えてはおいたけど。
しかし、顔をここまで真っ赤にさせて倒れるなんて、普通じゃないだろう。今まで僕は風邪だ風邪だと思っていたが。
「……まさか、天使の世界でインフルエンザが流行中なのか」
それなら納得がいく。現に倒れているわけだし、これはもう重症以外の何物でもないわけだし。
とりあえず、僕の六時間目の授業は宮久地を保健室に運ぶことになりそうだ。まぁ、宮久地はそこまで重くはないからできないことはないだろう。
僕は宮久地の体を一番抱えやすい格好で抱え込むと、そのまま保健室に運び込んだのだった。
しかし、後でクラスの人間全員から宮久地について質問を投げかけられまくったのだが、あれは一体なんだったんだろう。僕のクラスにはどうやら宮久地のファンが多いのかもしれない。まぁ、僕には関係ないが。
「そろそろ、だろうか」
あれから翌日、僕は家にいた。学校は既に放課後となっており、校舎に残っている人間は恐らく生徒会や委員会などの役員たちや部活動で個人個人の技術を磨いているような人たちばかりだろう。そんなことは今の僕には関係ないが。
「私を呼びつけるなんて、いい根性してるじゃないのあんた」
「ああ、来てくれたか。 いや、もしかしたら文字が読めないかもと学校で無償に気になって仕方が無かった」
「文字が読めないって、あんた私を馬鹿にしてるわよね?」
「そうあからさまな怒りを見せないでくれ。 君やセリナは僕の認識からすれば別の世界の存在だし、使ってる言語体型も違うのかとも思ったんだよ」
「……あんたが何を言いたいのかいまいちわかんないけど、馬鹿にはしていないのよね?」
「うん、してるつもりはないけど」
「だったらいいわ」
馬鹿にはしていないが、どうも僕の話がきちんと通じていない気がする。まぁ、大まかなことが伝わればそれでいいか、と僕は自分自身を納得させることにする。
「で、どうして私を呼んだわけ?」
「昨日君が知らない人間が大勢いるのは好まないと言ったから、君が僕に接触しやすいようにいつ会えばいいのかを教えようと思ったんだよ」
「それで家の窓にメモを置いたってわけ?」
「うん、そう。 しかし言葉が伝わってよかったよ。 少し気になっていたけど、この世界とそっちの世界の言葉は同じなのかい?」
「え、ええ。 そうみたいね。 何でかは知らないけど」
ひょっとしたら僕らの世界の言葉は向こうでは使われることが少なくて、こっちで言うところの外国語みたいな扱いなのかとも思っていたけど、どうやら根本的に同じらしい。しかし地球では圧倒的に英語と中国語を使ってる人間が多いはずなのによく日本語なんてきっちりと使ってるな。うん、この辺りのことは宮久地に改めて聞き直した方がよさそうだ。
「あんたがなんであんな窓にメモを置いたのかはわかった。 けど、肝心などうして私を呼んだかを説明してないわよ。 ああ、もしかしてやっぱり私の下僕になりたいっていう申し出かしら?」
「いや、違う」
昨日も断ったはずなんだけど、おかしいな、マリアの顔がみるみると赤くなっている。とりあえず話を続けて気でも逸らそうか。
「昨日聞き損ねたことを、改めて質問しようと思ってね」
「昨日のって、何よ」
「君がやたらと悪魔らしさを気にすることだよ」
「……そのことね。 とりあえず、あんたには関係ないし、話したくもないの。 わかる?」
やはり彼女はこのことに答えたくないようだ。となると、それ以上のことを知るには何かしらの状況変化が起こるか、僕が推理するかのどちらかしかない。
「まぁ、そうだろうね。 昨日君がいなくなったその後に、宮――セリナに君の事を聞いたんだけど、彼女は言わなかったからね。 自分の友達が知られたくないことを、私が話すわけにはいかないって、そう言われたよ」
「……セリナ」
「どうやらセリナは君のことが大切らしいな。 いい友達だと僕は思うけど」
「――うっさいわね、あんたは何よ――何なのよ――」
「僕はただ、気になるだけだ。 宮久地のこと、天使のこと、マリアントワージュ・セロディアスと名乗る君のこと、そして悪魔のこと。 全く知らない世界が僕の目の前にやってきた。 それが気にならないわけがないだろう」
「セリナ――」
彼女、マリアは、少しだけ声を震わせていた。そんな声の揺らぎは、それに呼応するかのように全身で表され始める。そしてとうとう振動が顕著になったとき、彼女の体は膝からストンと崩れ落ちた。
「悪魔のことは、今は聞かないことにするよ。 しばらく、君のしたいようにしてるといい」
「……礼なんて絶対言わないから」
「そうか」
彼女は床に座り込む中、僕はベッドへと向かいそのまま寝転がった。特にすることがないときは、大抵はこうしてる。そのまま眠ることも多い。今は、マリアという存在がいるので眠るとどうなるかはわかったものではないけれども。
マリアのすすり泣く音が聞こえながら、僕は寝転がっている。そんな状態が恐らく三分くらい続いただろう。唐突に、ベッドのバネがより深く沈みこむのを感じた。見れば、マリアがベッドに座っていた。泣くのは、もうやめたようだ。少しだけ目の周りが紅くなっているのは、人間も悪魔も同じらしい。
「……あんたの質問、他の事だったら一つだけ答えてあげる」
「なんか、唐突だな」
「な、何よ! なんかあんたに借り作ってる気がして癪だからっていうだけの話! それだけだからっ!」
「そうか、それじゃあ質問があるんだけど」
「……あんた、人からロボットみたいって言われたことない?」
「いや、ないけど。 なんでだ?」
「別に……」
そんなことよりロボットを知っていることのほうが衝撃なんだけど。意外とこちらの文化は向こうでも通じるものなのかもしれない。
「君は前に、天使のこと、そしてセリナと君の父親に対して怒っていたけど。 何を気にしているのかな」
「ぐっ……あんた、それさっきの奴と大して変わらないじゃない!」
「ん、そうなのか。 てっきり原因は違うのかと思ってた」
「うー……でもあんたに借りを作るのも癪だし……」
頭まで抱えて、相当悩んでいる。とりあえずわかったのは、彼女が悪魔らしさを気にするのも天使という種族を気にするのも同じ原因であるということ。そしてそのことは間違いなく彼女の父親が関わっているということだ。しかしあのとき彼女はなんて言っていたかな。ええと、確か。
「はぁ……天使、なんて……」
ああ、思い出した。「天使、天使って、そんなんだからセリナもオヤジも」だった。
そういえば、マリアは悪魔だよな。それなら父親だって当然、悪魔のはず。それなのになんで天使の話で父親が出てくるんだろう。まさかとは思うが。
「なぁ、君の父親は、どんな感じなんだ?」
「な、なんでいきなり私のオヤジのこと聞くの!?」
「だって、君が父親に対しても怒っていたから。 余程酷い悪魔なのかと」
よくよく考えると、酷い悪魔って肩書きとしてどうなんだろう。悪魔界からしたら名誉なのかもしれない。
「……まぁ、そうね。 酷い悪魔よ。 悪魔として、甘ったれで、腑抜けた最低な悪魔」
ああ、そうか。悪魔側で酷いってなるとむしろ優しい人が酷いってことになるのか。価値観が逆で分かりにくい。しかし、父親は悪魔にしては珍しく優しい悪魔だった、ということはわかった。恐らく、その辺のことが彼女の問題として立ちふさがっているんだろう。
「そうか。 つまり君は、自分の父親が悪魔らしくないから気に食わないのか」
「……そう、そうよ。 だけどねあんた、人の繊細なとこそんな簡単に突っつくんじゃないわよっ!」
「……ん、すまない」
彼女の右腕がまた僕の首筋に向けられそうな雰囲気を感じ取ったので、ここは素直に謝っておく。正直、僕としても何度も首を絞められたくない。あと、意外と力あるから結構痛い。
「あーもう、腹立つったらありゃしないんだから!」
うん、そこまで強く床を蹴られると後が怖いんだけど。バキッて壊れたりしないだろうな。そうなったら宮久地呼ばないといけないんだけど。こないだ家に呼んだとき、なぜか顔が赤くなって大変なことになったから宮久地のためにもあまり呼びたくないんだけどな。
結構な勢いでマリアが床を蹴り続けて12回目。それでようやく蹴るのをやめてくれた。残念なことに床には傷どころか一部抜け落ちかねない部分が出来上がっていた。どうやら、宮久地を呼ばなくてはならないらしい。とりあえず僕の睡眠時間を返してほしい。
「……ねぇ、あんた。 悪の道に入る気はない?」
「さっきも断ったけど、そんな気はないよ。 なぜ聞いたんだ」
「別に。 どうせあんたのことだからそう答えるだろうと思ってたし」
「そうか」
「それじゃ、もう帰る。 言っとくけど、絶対にあんたは堕としてやるから」
力強く宣告すると、彼女はそのまま窓から颯爽と飛んでいってしまった。いい加減、窓からじゃなくて玄関から帰ることを覚えてほしいんだけど。
まだ肌寒い春の風が入り込む窓を静かに眺めながら、僕は呟いた。
「とりあえず、宮久地を呼ぶか……」
数分後、やはり宮久地が倒れることになった。どうしろというんだ、僕に。
そして翌日。僕はベッドの上で考え事をしてた。時刻は午前11時。
今日は、休みだった。こういう日は大抵やることがない。人によっては両親から面倒ごとを頼まれることもあるかもしれないが、僕の父親は結構な割合で家にいないことが多い人間だ。母親も似たようなものだ。父親よりは家にいるってだけであまり変わらない。
ふむ、学校の宿題が面倒なものならやるけれども、宿題は出なかったしな。いつもどおり寝てるか。一応インターネットで悪魔と天使について調べものをするっていう選択肢もあるけれども。
僕がそうやって思案していると、行動を決めるより先に、僕のお腹がその欲求を直に伝えだした。
「なんか食べるか」
部屋を出て、階段を下りて、右にあるリビングに僕はたどり着いた。今この家は両親共に不在だ。朝食を食べているときに母親から、昼食は用意しておくから食べて、と伝えられているのでソレを食べることにする。
リビングを通り抜けてそのままキッチンへ向かい、僕は冷蔵庫を開ける。冷蔵庫の上から二段目、そこにあんまりパラパラとしていなさそうなチャーハンが静かにそのときを待っていた。そいつを取り出した僕は、迷わず電子レンジに突っ込んで温めた。最近の電子レンジはある程度の温度になると勝手に止まってくれるらしいのだが、僕にとってその温度は舌を焦がされるんじゃないかと思えるほどに熱い。あの温度で食事している人間は本当に食べ物の味を感じ取れているのだろうか。僕にとって疑問でしかない。
一分経つか経たないかというところで僕はチャーハンを取り出した。これ以上温めると舌を焦がす温度となりかねないからだ。流し台のそばにある引き出しからスプーンを出して、チャーハンの器と共にリビングへと戻った。清潔に保たれている木製のテーブルに器を載せて、ラップを剥がす。そうしてから、いざ食べようと思ったとき、テーブルの上に一枚の紙が置いてあることに気がついた。
「朝にはなかったはずだけどな」
朝食の時には、これは置かれていなかったはず。つまり、この紙はそれ以降に置かれた物だろう。しかしこんな紙残す人なんて限られてくるが。
「まさか、マリア?」
その可能性は当然あった。前に僕が彼女にメモを見せたわけだしその意趣返しとして置いたのかもしれない。まぁ、そんなことするくらいなら僕に直接会った方が早いとは思うけれども。
若干の興味を紙に抱きながら、僕は紙に書かれた文面を確認するために右手で手繰り寄せた。さてと、内容はいかほどのものか。
"ごめんね春樹! ままど~しても大事な用事があるから、お昼のタイムセールに間に合わないの! だから春樹が代わりに行ってきて! どこのお店かはチラシ置いとくから ほんとごめんね! ままより"
「…………」
言うまでなく、母親のだった。ある意味残念な置手紙にため息が出てくるぞ。ちょっと期待していた分、精神的打撃もなかなかに大きかったわけで。
残念なメモをぺいっとテーブルの上に手放した僕は、とりあえずお店のチラシを探すことにした。珍しいことだが、頼まれてしまったものは仕方がないし。やらないわけにもいかないだろう。母親のことだから近いけれど変なところに置いてるに違いない。
そんな風に探して二分後、使ってないイスの座るところにあった。テーブルのそばとはいえ、ここに置くのはどうかと思うんだよね。ぶっちゃけるけど。どうせ置くならメモのそばに置けばいいじゃないか。
そんな風にも思ったが、まぁそんなことは些細なことだろうし、どうでもいいか。タイムセールの時間は、午後一時半から始まるらしい。
それじゃ、ご飯食べたらすぐ行くか。食べ終わるのはおそらく十二時半ごろ。スーパーにつくのは遅くとも一時。あとはぶらぶらとすればいいわけだし。
今日の予定を適当に打ち立てた僕は、それから両手を合わせてから、静かに唱えた。
「いただきます」
右手につけた腕時計をちらりと覗いた。時刻は、午後二時。頼まれた買い物は既に済まして、僕はスーパーの出口にいた。
買い物自体はすぐに終わった。タイムセールが始まったら商品をすっと取って、次のタイムセールの場所で待ち、またすっと取る。商品を取り終えたらすっとレジに行って。ただそれだけのことだ。ただそれだけのことのはずなのに、スーパー内部の熱気は凄まじいことになっていた。僕が手に取った後はもうご近所のおばさんたちが、アリのようにわらわらと群がる様子
は流石に僕でも何か心に渦巻く気味の悪さを感じた。
「まぁ、買い物は終わったからいいか」
と、僕は右手に提げたレジ袋を見つめた。流行のエコバッグとやらは僕は持っていないし、家では誰も持ってない。なぜならレジ袋をゴミ箱の中に突っ込んで後で捨ててるからだ。規定のゴミ袋があったかは覚えてないが、もしあるならたぶんその袋の中にそのまま突っ込んでそうだが。
とにかく、僕の役目は終わった。僕はスーパーから家へと向かうために、歩き始める。
休日の昼間、交通量は時折車が通る程度。僕の住む町は、道路的に主要の部分ではないらしく、大量の車が通ったことは一度もないぐらいだ。それでも時々車はやってくるんだけど。
比較的大きな道路だった場所から、小さな道路ばかりしかない住宅地へと足を進めた。当然、こちらの方が家へと直線的に近づけるからだ。
住宅地というのは、文字通り住宅が密集している地域だ。既に十六軒ほどの家を見ている。それだけの密集地のはずなのに、不思議と静かだった。聞こえるのは遠くから響く車の走る音。近所にあるのか、公園で子供たちの遊ぶ声ぐらいで。
本当に静かな住宅地だった。もしや、この場所には誰もいないんじゃないだろうかと思わず錯覚するほどに。
――今ならボール投げ込んでも見つからないんじゃない?
僕の中に、悪魔のささやきが聞こえる。おかしいな、普段ならそんなことは考えるはずはないんだけど。
――なんだったら爆竹でも放り投げちゃったら?
まだ悪魔は僕を引きずり込もうとする。僕は、そんな幻聴を聞くような人間だっただろうか。
――ねぇ、それともモーニングスターでもぶん投げとく?
幻聴の癖に、モーニングスターとかいう僕の知らない物の名前まで出してきた。これはもう本格的に病院にでも行くべきなのかもしれないな。
――ちょっと、聞いてるの?
いや、聞こえてなかったらこんなにも深く考えないよ。僕は今、自らを病院に連れて行くか行かないかという数年に一度の決断を迫られているわけだし。ああ、でも保険証は家の中にあるし、やはり一度帰って
「死ねっ!!」
「うご……?」
な、殴られた。いきなり横から殴られた。おかしい。僕は誰かからいきなり殴られるようなことをしたつもりはないし、というかそもそも僕を殴る相手なんかこの場にはいないはずなのに。どうしてなんだ。
「私を無視できるなんて……やっぱりあんた、ほんとのほんとは私をバカにしてるんでしょ!」
上を見上げて、僕は全てを悟った。殴ったのは、マリアだった。
「あの、さっきまでの声って、君だよね」
「そりゃそーに決まってるでしょ! 私の他に誰がここにいるっていうの? あんた見えないものでも見えちゃうわけ?」
悪魔に言われたら世話はないなと僕は思った。
僕の頭がおかしくなったわけではなく、単に考え込みすぎて彼女の存在を認識してないだけだった。内心ほっとしている。
「悪魔に見えないものが僕に見えるわけないだろう。 少し考え事してたからわからなかったんだ」
「ふーん、あっそ。 それで、何考えてたの?」
「いや、ここが不思議なくらい静かだなって」
「はぁ? それだけ?」
「うん、そうだけど、何?」
「……あんた、やっぱり変な奴だわ」
数回の会話のやり取りで勝手に変人扱いされた。僕が何か変なことしただろうか。ため息までつかれたぞ。ため息したいのはむしろ僕のほうなんだけど。
「で、話は戻るけど、今ならイタズラしほーだいだと思わない?」
「……家に誰もいないという保証はないけど」
「こんなに静かな上にたくさん家があるわけだし、窓の一つや二つ割ったところで問題にならないはずよ!」
「いや、それって家主が帰ってきたら結局は問題になると思うんだけど」
「いいのよ、イタズラっていうのはそーいうもんなの! で、なに投げ込むわけ? ここは手堅く野球のボールで行く? それともサッカーボールでもシュートする? なんだったらバレーボールでも叩き込んだりとか。 ああ、それともボーリングの球でストライクとか?」
「うん、とりあえずそのボールがどこから出てきたかは突っ込まないことにするね。 それよりも最後の方のチョイスが酷いと思うよ。 大体僕には重くて塀を越えてストライクする自信はない」
「ええー? じゃあ何よ。 私のモーニングスターもダメっていうわけ?」
「さっきから僕にこれでもかと見せ付けているその物騒な物のことか」
彼女が手にしているそれは、武器というよりかは凶器と呼んだほうが早そうな、明らかに人を傷つける気が満々な形状をしていた。ボーリングの球より確実に大きそうな鉄球。しかも、トゲトゲしい。投げつけたらそのまま刺さりそうだ。そんな鉄球が、鎖で柄に繋がれていた。柄は手で握るより少し大きい程度で、鎖はどう考えても三メートルは超えてると思う。使用方法は、あまり考えたくない。
ジャラ、と鎖を鳴らしながら鉄球を平然と僕のほうに差し出してくるあたり、僕に対する遠慮のなさを感じ取れる。
「ほらほら、投げ込んだら酷く冒涜的で背徳的な開放感のある窓割りができそうだと思わない?」
「窓割るのにそこまでたいそうな武器使わなくても良いと思うんだ」