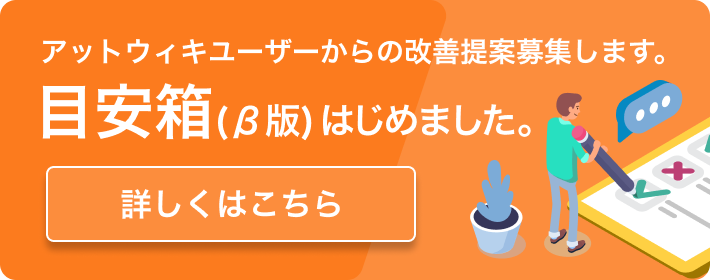題名「リングのパロディに見せかけた貞子らしき山村さんと中村くんが暮らすそうです」
「ああ、やっぱVHSのビデオだよなぁ」
俺以外には誰もいない自室。そこでテレビを観賞しながら、時折コメントを呟く俺。暇人だなとか突っ込むな。悲しくなるから。
「今じゃ世間だとDVDばっかで、だんだん数も減ってきたし、そろそろ本格的にお別れかもしれねぇな」
まぁ、この世からVHSが消えたとしても自分のだけは死守するだろうけどな。なんて、一人どうでもいい決心を固めたところでビデオの映像が終わってしまった。終わった後の砂嵐もいいもんで、ビデオが切れるまで再生を続ける、なんてこともよくやっている。ついついビデオ流しっぱなしで眠ってしまっていることも多々あるがそれはまぁ気にしないことにしている。
同僚から「そんなんだから彼女いないんですよ」とか言われたが、毎月女をとっかえひっかえしているような奴には言われたくねぇ。まぁ、実際正論なんだろうが。
「――と、もうビデオが終わっちまったし、次のでも見るか」
さて、ここまでで俺の趣味はよくわかるだろうが、ビデオ鑑賞だ。VHSのビデオ限定だが。ただし、残念ながらそのほとんどはレンタル品だ。流石にアナログ放送が終了してからはいちいちVHSのビデオにするのも労力がいるのでしていないし、元々そこまでビデオを持っていたわけでもない。
だから、大体二週間に一度レンタルビデオ店に行って数本借りてはそれを見る、というのが俺のお決まりの行動になっている。誤解しないでほしいのが、俺は別にDVDが嫌いとか、最近の映像が面白くないとかそういうことでビデオが好きなんじゃない。とりわけVHSのビデオの映像が好きなだけだ。
まぁ、昔の方が性に合ってるといえば確かにそうなんだが。ちなみに特に嫌いなジャンルもないのでビデオであるなら大体片っ端から借りているぞ。流石に優先順位くらいはあるがな。
そんなどうでもいいことをいまさら頭の中で考えながら俺はビデオデッキからカセットテープを取り出して別のカセットテープと入れ替えた。
「さてと、これで確か借りたのは全部だったかな、と言ってもまた見直すけど」
前述の通り俺は大のビデオ好きなので(暇とか言うな)借りたビデオを数日後にもう一回見る、なんていうことは当たり前のことだ。
ビデオデッキのリモコンを手にとって、再生ボタンを押す。
「そういや、何借りたんだったかな。 確かホラー物からゴソっと取ってきたんだが」
再生ボタンが押されたことで、ビデオデッキからテープを流す音が聞こえる。それと同時に、今まで真っ暗だったテレビ画面はビデオの映像を流し始める。そう、それが普通のことだ。そんなことはDVDですら変わらないことだ。
今の場合、レンタルビデオであれば当然、著作権を含めた取り扱いの注意が映ることだろう。
テレビ画面は、なぜか砂嵐から始まっていた。
「ああ? 戻し忘れか……?」
個人経営のレンタルビデオ店だと時々そんなことも起こったりするものだが、ビデオデッキに表示されているビデオ残量はきちんと始まったばかりであることを示している。
そんな風に俺が戸惑っていると、映像に変化があった。砂嵐から、暗闇になった。真ん中にはぽっかりと穴が開いていて、そこから光がこちらに向かって入り込んでいるようだった。
「なんだ……?」
俺が疑問に思う間に映像は切り替わる。時々妙な人影が写りこみながら意味不明な映像は尚も続いていく。頭の中ではちょっとした焦りと困惑ばかりが充満し、リモコンの停止ボタンを押すという簡単なことさえ思い浮かばず。ただ淡々と映像が流れる。
そうしていると、突如映像が固定された。それはどうやら鬱蒼とした林の中で、奥の方には小さな井戸がぽつんとあるだけの寂しい風景だ。と同時に、俺の中で決定的とも言える予測が浮かび上がった。
「もしかしてこれ、リングじゃないか?」
リング――1998年に公開されたジャパニーズホラーブームの火付け役とも言われる映画で、「見たら一週間で死ぬ」と言われる呪いのビデオを見てしまった主人公がどうにかして死なない方法を探る、そんな映画だ。
その映画では、作中における「呪いのビデオ」の映像が流れるわけだが、その内容が先ほどの映像とだいたい一緒だった気がする。最後には貞子と呼ばれる女性の幽霊が井戸から上ってくるはずだが。
「しかし、そんな冒頭で流れるものだったかな……とりあえず、一回出してみるか」
と、俺がビデオのタイトルを確認するためにテレビに近づいた、まさにそのときだった。
映像が勝手に途切れたのだ。
「……消えた?」
不審に思うが、今はとりあえずビデオのタイトルを確認しよう。
デッキからビデオを取り出して、俺はそのタイトルを見た。
タイトルは、何もなかった。
「……ラベルが貼ってない?」
いくらなんでも、ラベルの貼ってないビデオがレンタルビデオ店で貸し出されているわけがない。じゃあ、俺が今見たこのビデオはどっから来たんだ。そこで俺は、ビデオを借りたときのレシートの存在に思い当たった。
「そ、そうだレシートだ! レシートなら俺が何を借りたか分かる!」
まず、レンタルしたビデオが何本あるのか確認するためベッドの側に積んであった視聴済みの奴を引っ張ってくる。ちょうど五本ある。ということは持ってるのと合わせて俺は六本借りた、ということになる。
次に俺はレシートを見た。上から順に、一本、二本、三本、四本と見ていく。
レシートは、五本で終わっていた。
「……嘘だろ?」
だが、紛れもなくレシートにはビデオタイトルは五本しかない。値段も五本分で間違いない。ではそれなら。
「存在しない、六本目――?」
それからの一週間は、よく覚えていない。
俺は生気のない顔をしながら淡々と業務をこなすだけの何の面白みもない七日を過ごした。
そして、七日目。
もしもあのビデオが本物なら、俺は今日、テレビから貞子が出てきて殺される。
俺は一人きりで、そのときを待ち構えていた。というより、何をする気にもなれないからぼーっとしていた、の方が正しい気がする。
「そろそろ、時間か」
その時が来たとわかるのはとても簡単だった。テレビが、勝手に映像を映し出したからだ。
映し出されたのは鬱蒼とした林。中央には小さな古い井戸。
「とうとう、映っちまったな……」
記憶が正しければ、この後白い服を来た髪の長い女が井戸を上ってきて、こちらにゆっくりと歩み寄ってきて。最終的にテレビから出てきて、俺は死ぬ。
まさか、呪いのビデオで死んじまうとはな。まぁビデオが好きだった俺にはある意味ぴったりなのかもしれないな。
自分の心臓が、まるで井戸の中に引きずり込まれるような、そんな絶望を抱きながら、俺はただ画面を見つめている。
そのときだった。
テレビの中の井戸から、白い服の女がすごい勢いで上ってきたかと思うと、ボルトもビックリするほどの足の早さで走り出し、って、ちょっとまていくら記憶が曖昧だったとしても映画でそんな高速で走ってきた貞子みたことねぇってちょおま。
「うおおおおおおおおおおおおおおおっ!?」
30インチのテレビの画面に白い服の女がドアップになったかと思えば、次の瞬間には俺の視界いっぱいに広がって、そして。
「……家のテレビ、3Dだったかな」
そんなわけがないのは家主である俺が良く知ってることだ。じゃあ、それなら今の不可思議光景はどうせつめいすりゃいいんだよ。
俺は、今起こっている現実を認めたくないと思いながらも、背後にあるであろう怪奇を確かめるために、振り向かざるを得なかった。だから、首を、ゆっくりと、後ろに回した。
そこには、ボロい白い服の女がうずくまって、じっとしていた。なるほど、確かに俺の思い描いていたものに似ているといえば似ている。例の、貞子という幽霊に。信じがたいが、俺が夢や幻を見ているのではなければ間違いなく、コイツは……
「……や」
やばい、貞子(と思わしき幽霊)が何か言葉を発したぞ。つか、「や」ってなんだよ。「や」ってなんなんだよ!?俺はこれから何言われるんだ?
「やったーーーーー!! やったやったやったわーーーーー!!」
えー、全国のオカルトマニアおよび霊媒師の類の連中よ教えてくれ。
突如現れた幽霊が恨み言を俺に振り掛けるわけでもなく小躍りしながら喜んだときはどういう対処をすりゃいいんだ。
「やったわ私……長らくあの中だったけどとうとう外に出られる日が来たわ! ほんともうあの井戸の中とか退屈を通り越してただただ異臭がするわすることがないわ誰もビデオ見てくれないわ臭いわでほんとウンザリ!!
フフフフ……どうしましょう私、これから私ほんとどうしましょう、フフ、ウフフ、アハハハハ!」
いや、どうしましょうは、こっちなんだが。
とにかく、この幽霊らしからぬテンションで高らかに笑っているこの貞子(仮)をどうにかしなきゃならん。というか、コイツ、本当に人を呪い殺すような存在なんだろうか。近所にもいるぞこういう痛々しいの。
「おい、そこの。 そこのおそらくは幽霊さんよ」
「フフフフ……外に出れたんだしこのまましばらく外をさまようのも悪くないかもしれないわぁ……いえ、そもそもまずはここを調べるのが先かしら。 ええそうね、大体どれくらいの時間がたったのかそれもわからないわけだしやっぱりそれも調べないとだめよねぇ……」
聞いてないぞコイツ……というか、幽霊ならまず目の前の俺を驚かすなりなんなりしろよ。何一人考えにふけってるんだよ。触れるなら思いっきり殴ってやりたいくらいだが、そこは流石に幽霊。さっきから右手で触ろうとしてるんだが一向に触れる気配がない。空気とまったく同じみたいだ。見えてるはずなのにちっとも触れない。
「おい、マジでそこの。 そこの幽霊らしき痛い奴! おい!」
「むぅ……何よ、人がせっかく久しぶりの外を満喫しながら考えているっていうの、に……」
ようやくこっちを見てくれた――そもそも幽霊に見てほしいっていうのも意味がわからんが――幽霊は、俺の姿を確認すると、明らかに「あ……」と言いかねない表情で見つめている。
さて、ここで幽霊がどれだけ恐ろしい顔をしているんだろうかと期待と恐怖の混じった気持ちで覚悟していたわけなんんだが、はっきり言ってこりゃ拍子抜けだ。そこに恐ろしさは微塵もない。ただの、普通の女と変わらねぇいじゃねぇか。
「い、いきなりスーパーマンみてぇに飛び出してきやがって、なんなんだお前は?」
試しに幽霊に突っかかってみる。だが、答えることはしないで、ただ「うう……」と唸ってるだけだ。
「おい、なんとか言えよ……」
正直こっちだって微妙にビビってるんだぞ。
しかし、目の前の幽霊らしくない幽霊にそれを言うのも癪だ。どうにかその言葉は喉元で抑え込んで相手を睨んでやる。
「う……」
「……う?」
「うらめしや……」
「それ言うの数分くらい遅ぇから」
「う、うぅ……」
というか、うらめしやって……ここ最近聞いたことないぞホラー映画で。センスが古すぎないか。
「と、とりあえず聞くぞ。 お前、ゆ、幽霊、なのか?」
「……うらめし」
「話通じないフリすんじゃねぇ! さっきまで盛大に独り言喋ってただろうが!」
「――うらめし」
「顔を怖くしても素がバレてるからな」
怖くするのに白目になるのはマジでやめろ。地味に心臓に来る。
「じゃあどうしろっていうのよ!」
「幽霊に逆切れされた!?」
「やっと外に出られたと思ったらぁ! いきなり怒られるし訳わかんないもん! うぇええん!!」
「さらに泣かれた!? いや、待て、頼むから泣くな。 そういうときの対処わからんし!」
「助けてぇええ!!」
「こっちが言いたいわ!」
それから数十分の間、俺はこの貞子らしき幽霊を宥める羽目になった。
普通、幽霊を慰めるなんてありえないと思うんだがなぁ。
「泣き止んでもらったところで、聞きたいことがあるんだがいいか?」
「えぅ、ひっぐ、い、いいけど……」
幽霊でも、泣いたら目が赤くなるんだな。そもそも、幽霊から涙が出てることの方が怪奇現象な気がするが無視するか。
「まず、幽霊、なんだよな?」
「そ、そうだけど……」
「まぁ、そうだろうな。 で、結局のところなんだが……お前は、あの"貞子"なのか?」
「……そうよ?」
「なんで疑問符付いてんだよ!」
「ひぃっ! いやぁ、怒らないで……」
俺が突っ込むために叫んだだけで怯えているんだが、幽霊がトラウマ植えつけられてどうするんだよ。
「……あのなぁ、お前が貞子であるなら素直に肯定して、違うなら否定してくれれば……」
「わ、私はその、さ、貞子なの!」
少し挙動不審で怪しいけれども、本人がそうだと言う以上こちらからはどうともできないからなぁ。まぁ信じるしかないだろう。
「あー、お前が貞子であるとしてだな。 ということは俺が見ていたビデオ。 あれは呪いのビデオだった、っていうことでいいのか?」
「……そ、そうよ」
「つまり俺は死ぬ、ってか? ハハハ……お先、真っ暗ってか?」
井戸から浮き上がってきた心臓が、再び底に叩き付けられた感じだった。
まぁ、そうだろうな。貞子が実在するのであれば、呪いのビデオも当然ホンモノということになる。つまり俺は、もう死んでしまう……?
いや、ちょっと待て。それなら俺は。
「なぁ、おい。 一つ聞くぞ」
「な、なによ」
「呪いが本当なら、俺は"どうやって"死ぬ? というより、お前が呪い殺すんだろ?」
「……?」
「いや、ハテナって顔されてもだな。 呪い殺すのはお前だろ?」
「あ、ああ! えーっと、それは……」
「それは……?」
「…………まぁ、置いといていいんじゃない?」
「いいわけねぇだろッ!!」
「ひひゃあぁ!?」
貞子(仮)が驚いてすくんだ。その際俺は、壁に掛けてある簡素な時計にふと目が行った。
俺が呪い殺されるであろう時間から、すでに十五分は経過していた。
まぶしい。
太陽光からの熱烈な視線を回避するため枕に蹲ってみる。
「ねぇ、朝なんだけど」
うるさい。
耳元から聞こえてくる生温かい吐息を回避するため毛布を被ってみる。
「いくら休日だからって、お昼まで眠るのはどうなんだろうって私は……」
ストレスに耐えるには、無理だった。
「幽霊の癖に健康論を俺に吹っかけてくるんじゃねぇ!」
「……だって、暇だもの」
「暇だからって理由で俺の貴重な休息の時間を邪魔しないでもらいたいんだが?」
「私だって貴重な活動時間を邪魔されたくないもの」
「暇なら外でも行ってこい。 少なくとも今よりは暇じゃなくなるぞ」
「い、イヤよ。 だいたい、私の格好を見てよ。 こ、こんな薄汚れた格好じゃ恥ずかしくって表歩けないわ!」
「そもそもお前は他人から見えないだろうがッ!!」
「見えなくても私的に恥ずかしいからイヤよ」
「コイツ……」
相変わらず殴り飛ばしてやりたいくらいだが、コイツは幽霊。殴りたくても永久に殴れない。仕方ないので話を無理やりぶった切って台所に向かうことにする。
俺が移動している間も貞子(仮)は暇だ、暇だと俺にささやき続けるからたまったものではない。何が悲しくて幽霊の暇潰しに付き合ってやらなくてはならないのか。一日中砂嵐の音を聴いてるほうがマシな気がしてくる。
ともかく、起きてしまったものは仕方がないので、簡素な朝食を作ることにした。まぁ、惣菜のサラダボウルにドレッシングをかけて、トーストにチーズをのっけて焼いただけのものだが。
「なんか、質素なのね」
「当たり前だ。 一人暮らしの男はこれくらいでいいんだよ」
「でも、惣菜の野菜って食べてて空しくなったりしないの? どうせならスーパーの特売でキュウリとかまとめて買ってきてそれを野菜スティックにしたらどう?」
「……貞子から現実的な話を聞く日が来るとは思わなかったな」
俺がそういうと、貞子(仮)は少し悲しそうにしながら黙った。流石に皮肉が堪えたのだろうか。こちらとしては、静かになるからちょうどいいんだが。
俺が朝食を食べ終わるのに、十分くらい経った。貞子(仮)はその間、テーブルに肘を立てて、手に頬を乗せる形で寂しそうに窓を眺め続けていた。
使った食器を片付けるため、俺は流し台に食器を運び、そのまま水を流して洗い始める。
「ねぇ」
潜在をスポンジに付けていると、ちら、と視線を横に流すように俺を見ながら、貞子(仮)が話しかけてくる。その姿はどっか、俺に何かを遠慮しているように見えた。
「なんだよ」
洗い物してるんだから黙ってろ、と一瞬言いたくなったが、流石にそこまで辛辣にしなくてもいいだろうと自分で思い、それは心に留めておいた。
「あの、私のことなんだけど」
「お前が、なんだ?」
「私のこと、山村さんって呼んでほしい」
「……はあ?」
何を言うかと思えば、突然の苗字呼びを要求とは、どういう心理状態なんだ。まぁ、確かに貞子のフルネームは山村貞子なんだが、なんでここに来て苗字で呼んでほしいなどと。
「……お願い」
物寂しそうに、そう俺に願う貞子(仮)の姿に、その願いを無碍にすることはできなかった。
「OK、分かったよ。 そう呼べばいいんだろう? 山村さん」
山村さんと呼んで、それを聞いたときの彼女の少しだけ安堵した表情を、俺は忘れられなかった。
「そういえば、私あなたの名前聞いてないわね。 なんて呼んだらいい?」
そもそも、これからこの家にいるのは確定事項なんだろうか。そんなことを気にしながらも、半ば惰性的に、その質問に答えている俺がいるのであった。
「あー、なら苗字で。 中村でいい」
「そう、中村……じゃあ私、中村くんって呼ぶ」
なんで君付けなんだよ。俺はさん付けなのになんで君付けなんだよ。
そんな不条理を突きつけたかったが、この不合理の塊の存在の幽霊に道理も何もないような気がして、突っ込むのすら諦めてしまった。
「あーはいはい。 それでいいよもう」
「これからよろしく、中村くん」
「……はいはい」
どうやらこの幽霊がこの家に棲み付くのは完全に決定事項のようだった。
まぁ、俺が死んでしまう呪いのような危険性はほぼ零のようだし、別にいいか。
そうして、俺と山村さんは一緒に暮らすことになった。
「あ、中村くん。 あとでブラシ買ってきて。 髪を解かしたいから」
「いきなりパシリかッ!? つか幽霊なのにするのかよッ!?」
どうやら、まだまだ意味不明なことは続きそうだ。かったるい。
それからまた数日後。
幽霊と過ごす生活にも慣れが生じている辺り、人間のすばらしさを垣間見た。
毎日一度は衝撃怪奇現象を見ているのだから流石にそろそろ慣れないと俺の心臓が持たない。
「あ、中村くん。 おはよ」
まず目撃する怪奇現象その一。
洗面台で空中に浮くブラシ。と、髪を解く幽霊。こちら現場、目の前には当たり前のようにブラシで髪を解いている山村さんの姿がある。
「はぁ、おはよう」
ちなみに、鏡には山村さんの姿は映っていない。鏡にはただ空中に独りでに浮かんで動いているブラシしか映っていないのである。そのことが余計にシュールさを感じさせる。
まぁしかしこの程度のこと、既にここまで毎日行われていることである。これぐらいで飛び跳ねていては幽霊との暮らしは続けていけない。
次に大体目撃する怪奇現象その二。
トイレに侵入する生首。いやまぁ、誰かと言えば山村さんしかいないわけだが。どうも、幽霊の習慣である壁を勝手に通り抜けてしまうっていうことと、人間の生理的現象であるトイレに行くという習慣がごっちゃになった結果、時々俺がいるにもかかわらずトイレに入ってしまうようで。
ああ、見られたとも。色々と。あげく部屋の中のものを投げ散らかされましたとも。
俺のせいじゃないだろうよ……
「今日はトイレに入らないでくださいよ、山村さん」
「は、入るわけないじゃないの! 好きで入ってるわけないじゃない!」
真っ赤になって恥ずかしがる姿はかわいいんだよな。悔しいけども。代償として色々と大切なものを失うが。
「まぁ、今日は出勤しますし、いくらでも間違えてトイレに入ってもらってもかまいませんがね」
「う、うん……」
俺は会社員だ。それすなわち基本的に週末以外は出勤するわけで。平日は山村さんをほったらかしてしまうことになるわけだが、山村さんは幽霊なのでペットとは違って(こういうとなんか酷い気もするが)何も面倒を見る必要はない。
とはいえ、一人にするのは流石にかわいそうだよな。暇なわけだし。そして何より、俺が玄関から出るときに彼女が見せる切なそうな顔は反則だろうと思う。これがいわゆる、女の武器なんだろうか。クソ、こういう経験は全くと言っていいほどなかったからな残念なことに。
朝食も済ませて、身支度を整えて、玄関で靴を履く。その間、山村さんはただじっとこちらを見つめているだけだった。
「あーと……行ってきます」
「……うん」
後ろ髪引かれる思いで、俺は出勤した。
「せんぱーい、なんか最近あったんですか?」
「ねぇよ、ねぇから用もなく来んな」
「うっわー、相変わらずっすねほんと……」
「そもそも、俺とお前は同僚の関係だろうが」
「いやー、いっこ上の人はやっぱ先輩ですよー。 あくまでも俺的にですけど」
オフィスで適当な事務処理をしていると、同僚から声を掛けられた。毎月のように女をとっかえひっかえしている奴とはコイツのことだ。正直、馴れ馴れしいのが俺には苦手だ。しかも、俺のことを勝手に先輩と呼んでくる。出身校が一緒ならまだしも、俺とコイツはこの会社で知り合ったわけで。呼ばれる筋合いもない。
「とはいえ先輩、わりとマジでなんか浮かない顔してますよ? ほんとになんもないんすか?」
「……お前が心配するようなことは何もねぇよ」
「あ、もしやアレですか。 最近オカズが見つからなくて嘆いているとか」
「OK、今すぐお前を早退させてやるよ」
「ちょ、冗談っすよ! 先輩ほんと殺気込めた目で睨んで来ますよねぇ……」
そうだろうな。本気で殺気込めてるし。
「まぁいいですよ。 なんもないならそれでいいですよ。 気晴らしになるかわかんないけどガム置いていきますから、そんじゃ」
俺のデスクの上にミント味のガムを置いていくと、そのままさっさと離れていった。なんだったんだアイツは。大体、俺はミント味は好きじゃないっつの。
ミント特有のスッとする感覚を舌に感じながら、俺はガムをかみ締める。それと同時に俺は家で待っているであろう山村さんのことを考えていた。
あの人は、生きているときは何が好きだったんだろうか。
会社の業務を終え、俺は自宅に帰ってきた。片手には会社のカバンを、もう一方にはレジ袋を二つ携えて。
そんなわけで本日三度目の大体目撃する怪奇現象その三である。
「あ、中村くん。 遅かったのね」
「ああ、うん、ただいま」
「おかえりなさい」
その三。自宅の玄関でぶら下がっている幽霊。もちろん言うまでもなく山村さんであるが。玄関から逆さにぶら下がっている幽霊を目撃するのは流石に肝が冷える。初めて見たときは思わず悲鳴を上げてしまったほどだ。黒く長い髪と白い肌が月明かりによってうっすらと光るのもこれまた恐怖演出をプラスしている。
「あの、毎回言ってるけど、やめてくれないかぶら下がるの。 誰かに見られるかもわからないし、第一に怖い」
「別に、私がどこでどうしていようといいでしょう? それに、私のことが見える人なんてそうそういやしないわよ」
やめてもらえるようにお願いしてみても、全て一蹴されてしまう始末だ。まぁ、こうやって待っているのもやっぱり彼女が一人でいるのが寂しいことによるものなんじゃないだろうか。
山村さんがぶら下がっている玄関を通り抜けて、リビングのテーブルに二つのレジ袋を置いた。一つは今夜の俺の晩飯だが、もう一つは違う。そもそも普段俺は晩飯以外に買ってくるのは食材くらいしかないから、二つ買ってくること自体が珍しいのだ。そのことに山村さんも気が付いたようで、俺に質問を投げかけてくる。
「珍しい。 ご飯以外に買ってくるなんて。 ビデオかしら?」
「いや、流石に新しいビデオを買ってはこないな」
「んー他に中村くんが買ってくるようなのって何かなー」
「これは、まぁ、なんというか……」
「えい」
「有無を言わさず開けやがったよ!」
山村さんがレジ袋を開けとそこには、小さな陶器に入った観葉植物がちょこんと顔を覗かせていた。
「観葉植物?」
「そうだな。 名前はペペロミアだとか」
「いやそういうことよりも、どうして観葉植物を? 中村くんそんな趣味なかったと思うんだけど、もしかしてこれから始めるとか?」
「それは、その」
ああ、言い辛い。何より恥ずかしい。
「山村さんが家で一人だと暇そうだったから、何か良いのはないものか、と……」
襲ってきたのは、静寂と硬直だった。
一言も発さず、表情も変えずに山村さんはその状態で完全に固まっている。そんな時間が果たして何秒続いているんだろう。俺にはまるで数分のように感じられるくらい、恥ずかしい。というか、頼むから一言でいいから何か言ってくれ。何だこの凄まじい恥ずかしさは。
「その、ビデオでも借りてくるっていう選択もあったけどずっとビデオばっかりっていうのもアレだと思って、だな」
空気の読めない発言をして場が固まってるのと同じくらい恥ずかしいぞ。俺は、何かまずいことでもしたのか。それか何か失敗したのか。もしやとは思うがまさか山村さんは植物が好きでないとか植物に嫌な思い出があったりとかするのか。ああ、考えれば考えるほどに気持ちが落ち着かねぇ。
「ぷっ」
「ぷっ……?」
「あっははははははははは!!」
腹を抱えて笑われた。大口を開けて、それはもう盛大に。
なんだこの、クイズに正解だと思うものを答えたら全然違うために笑われているみたいな気分は。
「わ、笑うなよ! 帰りに花屋でこれ選ぶのに店先でめちゃくちゃ迷ったんだからな!?」
「いやーやめて! それ聞いたらなおさら、おかし、ぶっ、あっははははははははは!! やーおなかいたい!」
爆笑された。それはもう、涙が出るくらいに。
そもそもあんたに抱える腹も痛がる腹もないわけだが、俺にはそれを言い返す気力は残されていなかった。
山村さんの大笑いが収まるのに数分を要した。俺はその間、部屋の角のところでただ座り込んでいた。そして現在は。
「あの、中村くん……元気出して、ね?」
「ハハ……そうだよなぁ、柄に合わないことをしたらそりゃそうなるよな……ハハハ……」
「その、贈り物自体は嬉しかったの! けど、それを照れながら中村くんが言ってるのが、面白くて……ぷっ……」
「いいんだいいんだ。 どうせ生まれてこの方一度だって女に何かをあげたことのない奴が、贈り物だなんて不釣合い・不似合い・不相応の極まりねーからな……」
「ああ! ごめんなさい! 笑っちゃったのは謝るから、お願いだからやさぐれないでぇぇぇ!」
もう、イヤだ。
俺に立ち上がる気力は、もう既に残されているはずがなかったのであった。
数日が経って、俺の家には新たな怪奇現象が生まれていた。
時折ミニサイズのジョウロが独りでに浮いて観葉植物に水を与えるという、そんな現象が。
この調子だと、一年経つころには俺の家には百個の怪談話が生まれそうな勢いだが、仮に生まれたなら同僚にでも話してやればいい。もっとも、向こうには変な笑い話にしかならないだろうが。
「それじゃいってきますよ、山村さん」
「うん、いってらっしゃい中村くん」
なんだかんだで、そのことを楽しみにしている自分がいる。別にそれでいいんじゃないかと思う自分がいる。
「明日休みだし、帰ってきたらビデオでも見ようと思ってるんだけど……」
「いいわよ、今日の気分はホラーだからよろしく」
「はいはい」
あれから山村さんに好きなものを聞いてみた。すると
「家の中でできるのだったら大体好きだけど。 映画とか良く見てたよ」とのことらしい。ビデオ鑑賞で十分だったのかよ、と思ったが、楽だし、いいか。
「じゃあ、リングにしますか」
「やめて! 井戸の中の思い出が甦るから!」
「はは、冗談だよ。 大体目の前に山村さんがいるし」
「……う、うん、まぁそうね」
彼女の顔に少しだけ暗い影が差し込むが、俺にはその理由はわからない。無駄に明るくて騒がしいとはいえ山村さんが幽霊になっている以上、何らかの過去とか思い出があるんだろう。けどそれは無理には聞き出さないつもりだ。
「じゃ、いってくる」
「うん、いってらっしゃい」
今はただ、この奇妙な幽霊との生活をどうするかを考えるほうが忙しい。