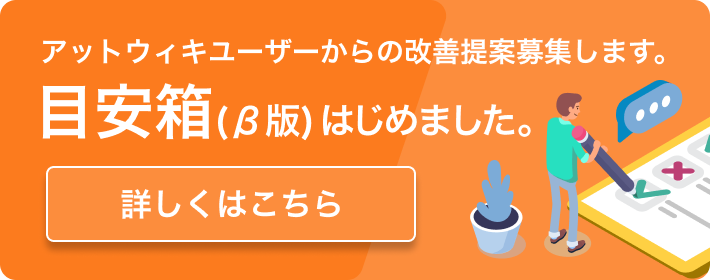「【Home Run】」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「【Home Run】」(2010/04/24 (土) 08:29:06) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
[[作品紹介ページ]]>>[[設定紹介暇人]]>>[[【Home Run】]]
----
身の丈を知るのは大切なことだと思う。
もともと分不相応だったのだろう。
うちの学校の野球部はけっこう強くて普通だ。
飛び抜けた強豪校でもなく。
さりとて弱小でもなかった。
圧倒的に強くて見てるものを虜にするプレイをするわけじゃないし、
見るものを感動させるようなドラマティックな物語があるわけじゃない。
いつ見ても素人臭い試合を繰り広げる高校だ。
監督は普通に野球の好きな体育教員だし、
僕もガラスの肘だとかカッコいいものを持ってるわけじゃない。
県下で一番強いわけじゃなく、No2でもなく。
……なんと言うかベスト4以下ベスト8以上と言うか。
七番目くらい?
それなりに優秀な成績を求められるが優勝を期待されてるわけじゃない。
そんな微妙に印象に残らない高校が県内予選で優勝してしまったのが間違いだった。
開校以来の快挙に高校は沸き立った。
ベスト4に入ったあたりで学校中で大会に関心のないものはいなくなった。
廊下を歩けば誰かしら応援の言葉をかけてきた。
決勝に進むにあたって靴箱の中にはラブレターが大量に入っていた。
決勝に勝利した翌日には緊急朝礼が開かれ連日OB会やら地元商店街やらの宴会が連日続いた。
シャッター商店街のどこにそんなお金があったのか。
みんな浮足立っていたのだろう。
浮かれた部員が隣のテーブルまで宴会を広げたのも自然の流れだったのかもしれない。
嬉しいことはみんなで分かち合いたくなるものだ。
ただその相手が怖い人だったことが問題だった。
相手はこちらが騒いでいたことが気に食わなかったのか部員の胸倉をつかみ上げた。
それがけちのつき始めだった。
このままだと警察沙汰かなーとか冷静に考えながら通報しようとした店員を手で制す。
未成年で飲酒もしてるしやばいやばい。
キャプテン四番だし部員を守らなきゃな―とか思いながら荷物をあさる。
練習帰りでちょうど持っていたバットを手に取ると僕はバッターボックスに立つ。
最近僕は全国区で注目されて期待のスラッガーらしい。
地区大会の得点王だしそんなこともあるかなぁ。
僕はそんなに目立つことは好きじゃないんだけどなぁ。
ちょっと照れちゃう。
ストライクゾーンに入った球はどんなに速かろうと曲がろうと場外まで運ぶ自信がある。
手のひらの血豆が自信だ。
日々の練習は裏切らない。
打つことだけを練習してきたから。
構えて、振る。
構えて、振る。
構えて、振る。
構えて、振る。
力一杯力を込めて。
4HR5ヒット。
得点は7-0。
コールド勝ち。
ゲームセット。
あれよあれよと言う間に裁判は進んで僕は刑務所にぶち込まれた。
判決は無期刑。
まあほぼ極刑みたいなもんだ。
野球部は甲子園出場取り消しどころか廃部。
学校側も火消しに躍起になっているらしい。
父さんが話してくれた。
家には毎日石が投げ込まれるし母さんは逃げ出したそうだ。
僕は実は野球があまり好きではなかった。
むしろ嫌いだったかもしれない。
でもバットで球を打つことが好きだった。
それだけしたくて嫌いな野球をやっていた。
野球中継もどっちらかを応援することはなく攻撃側のチームをいつも応援した。
父さんとキャッチボールをしたことはないがノックをしたことはある。
父さんを倒れるまで走らせた。
守備練習もあんまりしなかったから試合はいつも馬鹿みたいに点数取られてその倍取り返した。
それが僕の野球だ。
打つことが野球だ。
叩くことが野球だ。
殴ることが野球だ。
投手の一挙手一投足に集中してボールを見て力一杯ぶつける。
こんな気持ちいいことは他にない。
夏が来て。
甲子園が終わって。
秋が来て。
冬が来て。
選抜が終わって。
春が来て。
また夏が来た。
セミが鳴いている。
外では甲子園の季節だろうか。
深夜部屋の鍵が開けられた。
なぜこんな時間に?とも思ったが開けたのは同じ服役中の人だった。
食堂に行くように促される。
なぜ鍵を持っていたのだろうか?
職員はどこにいるのだろうか?
食堂のテレビをみんなが見ていた。
チャンネルはニュースだった。
甲子園の情報が知りたかったのだけれど緊急番組がやっていた。
地球に巨大な隕石が近付いていてもすぐ衝突するらしいことをアナウンサーがまくしたてる。
真っ青な顔をして今にも逃げ出しそうだ。
中継が始まる。
深夜の東京の映像だ。
人々が手に武器を持って商店を襲っている。
窓ガラスの割れた車が火を噴き女子供が泣いている。
どうも暴動が起きているらしい。
僕が出れたのもそれが原因のようだ。
この期に及んでまともに職務をする人間はいないということだ。
隕石がぶつかってしまえば人類は滅亡する。
その前にやりたいことは全部やってしまえということらしい。
囚人が外へ走り出して行く。
彼らは絶望しているのだろうか。
それとも出所できたことを喜んでいるのだろうか。
盗んだ原付で走りだす。
歌を口ずさむには僕は年を取り過ぎていた。
道すがらスポーツ店を襲ってバットとヘルメットと適当な服を盗む。
灰色の服はダサいから海外のチームのユニフォームを模した服を着る。
あいにくどのチームの服か僕は知らないけど。
目的地の麓に辿り着く。
整備された参道を上っていくと途中で道が無くなったので原付を乗り捨てる。
夏なのに寒い。
適当な建物の扉を壊して服を盗む。
ここにも人はいない。
山の上で最期を迎えたい物好きもいないのだろう。
暗闇の中バットを杖代わりに山を登る。
登山道なんて知らないけど上の方を目指した。
何時間経っただろうか。
いつの間にか僕は頂上にいた。
薄い空気の中座り込んで乱れた呼吸を整える。
刑務所を出た時からここに来ようと決めていた。
きっと日本一高いここなら隕石にも届くと思ったから。
疲れた身体に鞭打って適当な場所を探す。
バットを振りやすいなるべく平らな場所が良い。
ちょうど石碑の正面が良い感じだ。
石碑の根元に申し訳程度にキャッチャーミットを置く。
バッターボックスを書いて正面を見ると空が赤くなっていた。
日の出でじゃない。
隕石の光だ。
外套を投げ捨てヘルメットをかぶる。
慣れ親しんだ動作。
構えて、振る。
構えて、振る。
何億回も繰り返した動作。
入所中も繰り返した動作。
体が覚えている。
確認は十分だバッターボックスの中に入る。
バットの重さを感じないという喪失感も無く。
重く感じるという圧力も無い。
ヒットポイントにだけ心地よい重量を感じる。
自分のためだけに振るバットは身体の一部のようだった。
観客のためでもなく部員のためでもない僕だけのバット。
新品のバットだけどそこには確かに僕の血が通っている。
バットを肩に背負ってホームラン宣言。
脚を開いて腰を落とす。
バットを握りなおす。
構えただけで楽しさがあふれてくる。
球を打つのがこんなに好きになったのはどれくらいぶりだろうか。
相手はは史上最速最強。
打てるだろうか?
打てるさ。
----
[[作品紹介ページ]]>>[[設定紹介暇人]]>>[[【Home Run】]]
----
身の丈を知るのは大切なことだと思う。
もともと分不相応だったのだろう。
うちの学校の野球部はけっこう強くて普通だ。
飛び抜けた強豪校でもなく。
さりとて弱小でもなかった。
圧倒的に強くて見てるものを虜にするプレイをするわけじゃないし、
見るものを感動させるようなドラマティックな物語があるわけじゃない。
いつ見ても素人臭い試合を繰り広げる高校だ。
監督は普通に野球の好きな体育教員だし、
僕もガラスの肘だとかカッコいいものを持ってるわけじゃない。
県下で一番強いわけじゃなく、No2でもなく。
……なんと言うかベスト4以下ベスト8以上と言うか。
七番目くらい?
それなりに優秀な成績を求められるが優勝を期待されてるわけじゃない。
そんな微妙に印象に残らない高校が県内予選で優勝してしまったのが間違いだった。
開校以来の快挙に高校は沸き立った。
ベスト4に入ったあたりで学校中で大会に関心のないものはいなくなった。
廊下を歩けば誰かしら応援の言葉をかけてきた。
決勝に進むにあたって靴箱の中にはラブレターが大量に入っていた。
決勝に勝利した翌日には緊急朝礼が開かれ連日OB会やら地元商店街やらの宴会が連日続いた。
シャッター商店街のどこにそんなお金があったのか。
みんな浮足立っていたのだろう。
浮かれた部員が隣のテーブルまで宴会を広げたのも自然の流れだったのかもしれない。
嬉しいことはみんなで分かち合いたくなるものだ。
ただその相手が怖い人だったことが問題だった。
相手はこちらが騒いでいたことが気に食わなかったのか部員の胸倉をつかみ上げた。
それがけちのつき始めだった。
このままだと警察沙汰かなーとか冷静に考えながら通報しようとした店員を手で制す。
未成年で飲酒もしてるしやばいやばい。
キャプテン四番だし部員を守らなきゃな―とか思いながら荷物をあさる。
練習帰りでちょうど持っていたバットを手に取ると僕はバッターボックスに立つ。
最近僕は全国区で注目されて期待のスラッガーらしい。
地区大会の得点王だしそんなこともあるかなぁ。
僕はそんなに目立つことは好きじゃないんだけどなぁ。
ちょっと照れちゃう。
ストライクゾーンに入った球はどんなに速かろうと曲がろうと場外まで運ぶ自信がある。
手のひらの血豆が自信だ。
日々の練習は裏切らない。
打つことだけを練習してきたから。
構えて、振る。
構えて、振る。
構えて、振る。
構えて、振る。
力一杯力を込めて。
4HR5ヒット。
得点は7-0。
コールド勝ち。
ゲームセット。
あれよあれよと言う間に裁判は進んで僕は刑務所にぶち込まれた。
判決は無期刑。
まあほぼ極刑みたいなもんだ。
野球部は甲子園出場取り消しどころか廃部。
学校側も火消しに躍起になっているらしい。
父さんが話してくれた。
家には毎日石が投げ込まれるし母さんは逃げ出したそうだ。
僕は実は野球があまり好きではなかった。
むしろ嫌いだったかもしれない。
でもバットで球を打つことが好きだった。
それだけしたくて嫌いな野球をやっていた。
野球中継もどっちらかを応援することはなく攻撃側のチームをいつも応援した。
父さんとキャッチボールをしたことはないがノックをしたことはある。
父さんを倒れるまで走らせた。
守備練習もあんまりしなかったから試合はいつも馬鹿みたいに点数取られてその倍取り返した。
それが僕の野球だ。
打つことが野球だ。
叩くことが野球だ。
殴ることが野球だ。
投手の一挙手一投足に集中してボールを見て力一杯ぶつける。
こんな気持ちいいことは他にない。
夏が来て。
甲子園が終わって。
秋が来て。
冬が来て。
選抜が終わって。
春が来て。
また夏が来た。
セミが鳴いている。
外では甲子園の季節だろうか。
深夜部屋の鍵が開けられた。
なぜこんな時間に?とも思ったが開けたのは同じ服役中の人だった。
食堂に行くように促される。
なぜ鍵を持っていたのだろうか?
職員はどこにいるのだろうか?
食堂のテレビをみんなが見ていた。
チャンネルはニュースだった。
甲子園の情報が知りたかったのだけれど緊急番組がやっていた。
地球に巨大な隕石が近付いていてもすぐ衝突するらしいことをアナウンサーがまくしたてる。
真っ青な顔をして今にも逃げ出しそうだ。
中継が始まる。
深夜の東京の映像だ。
人々が手に武器を持って商店を襲っている。
窓ガラスの割れた車が火を噴き女子供が泣いている。
どうも暴動が起きているらしい。
僕が出れたのもそれが原因のようだ。
この期に及んでまともに職務をする人間はいないということだ。
隕石がぶつかってしまえば人類は滅亡する。
その前にやりたいことは全部やってしまえということらしい。
囚人が外へ走り出して行く。
彼らは絶望しているのだろうか。
それとも出所できたことを喜んでいるのだろうか。
盗んだ原付で走りだす。
歌を口ずさむには僕は年を取り過ぎていた。
道すがらスポーツ店を襲ってバットとヘルメットと適当な服を盗む。
灰色の服はダサいから海外のチームのユニフォームを模した服を着る。
あいにくどのチームの服か僕は知らないけど。
目的地の麓に辿り着く。
整備された参道を上っていくと途中で道が無くなったので原付を乗り捨てる。
夏なのに寒い。
適当な建物の扉を壊して服を盗む。
ここにも人はいない。
山の上で最期を迎えたい物好きもいないのだろう。
暗闇の中バットを杖代わりに山を登る。
登山道なんて知らないけど上の方を目指した。
何時間経っただろうか。
いつの間にか僕は頂上にいた。
薄い空気の中座り込んで乱れた呼吸を整える。
刑務所を出た時からここに来ようと決めていた。
きっと日本一高いここなら隕石にも届くと思ったから。
疲れた身体に鞭打って適当な場所を探す。
バットを振りやすいなるべく平らな場所が良い。
ちょうど石碑の正面が良い感じだ。
石碑の根元に申し訳程度にキャッチャーミットを置く。
バッターボックスを書いて正面を見ると空が赤くなっていた。
日の出でじゃない。
隕石の光だ。
外套を投げ捨てヘルメットをかぶる。
慣れ親しんだ動作。
構えて、振る。
構えて、振る。
何億回も繰り返した動作。
入所中も繰り返した動作。
体が覚えている。
確認は十分だバッターボックスの中に入る。
バットの重さを感じないという喪失感も無く。
重く感じるという圧力も無い。
ヒットポイントにだけ心地よい重量を感じる。
自分のためだけに振るバットは身体の一部のようだった。
観客のためでもなく部員のためでもない僕だけのバット。
新品のバットだけどそこには確かに僕の血が通っている。
バットを肩に背負ってホームラン宣言。
脚を開いて腰を落とす。
バットを握りなおす。
構えただけで楽しさがあふれてくる。
球を打つのがこんなに好きになったのはどれくらいぶりだろうか。
相手はは史上最速最強。
打てるだろうか?
打てるさ。
----
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: