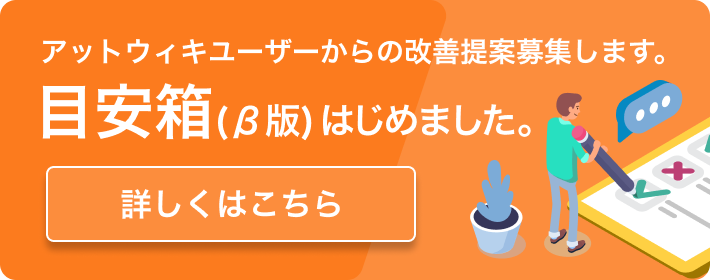「悪魔、天使、そして流される僕」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「悪魔、天使、そして流される僕」(2012/03/12 (月) 19:32:07) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
[[作品紹介ページ]]>>[[設定紹介バナナな人]]
#region(まだ秘密ー♪)
なんということだ。また彼女を調べられるのか。
いや、そんなことより僕の睡眠がとられてしまうことのほうが問題だろうか。うん、これは悩みどころだ。そして死活問題だ。車でいうならガソリンがガソリンスタンドまで持つだろうかというくらいの問題で死活問題だ。
「悪魔というのは、人間を悪い道に引き込もうとするのが元来の仕事ですから、だから春樹君を悪い道に誘うためにマリアが追っかけてくるかなーと……」
「ふうん、悪魔の仕事か。 大体予想通りだな」
というか、インターネットに書いてあった。
「それで、大方天使の仕事って言うのは人を良い方向へと導いてやるんだろう」
「あ、あたりです……」
それもインターネットに書いてあったことだが。
「つまり、君がこの世界にいるのは役目を果たすため、か。 ずいぶんとご苦労なことだなと僕は思うよ」
「……そういうつもりでいいことをしてるつもりは」
「まぁ、いいんじゃないかな。 天使という役割があるわけだし、何も悪いことではないと思うし」
「ち、違うんです! わ、私が春樹君におすそわけをしたりするのは、その……」
と、そこまでいうと、彼女は言葉をとめて、そのまま黙りこくってしまった。何がどう違うのか、僕にはよくわからないが。まぁ彼女が違うというなら違うんだろう。何かが。
「まぁ、いいよ。 話はわかったし、帰ろうか」
「……はい」
僕が公園の出口に向かって歩き出すと宮久地も後ろをついてきた。その足取りは、どこか重たげだったのが気になったが、今は家への道を歩くことに集中することにした。
後ろを歩く彼女の姿はもう、いつもどおりの"宮久地芹奈"だった。
真っ暗闇の帰り道を、二人でぶらぶらと歩いていると、背後から宮久地の声が聞こえた。
「あの、春樹君」
「なんだい」
「……私のこと、どう思ってますか」
「どうって……」
毎度毎度、おすそ分けを持ってくる変わり者の隣人だと思っているわけだが。
「昔からこうやって過ごしてきた、幼馴染、そう思ってませんか?」
「そうかもしれないな」
「……違うんですよ」
「違う?」
僕はここではじめて、彼女の方へと振り返った。そこには、スカートのすそをぷるぷると震えながら掴んで、涙を浮かべながら話し掛けてくる彼女がいた。
「春樹君が知ってる私の記憶は、みんな私がこの世界にやってくるときに植え付けた偽りの記憶っ。 だから、私はあなたと幼馴染でもなんでもないんですよっ!」
そして、彼女は泣き出した。時々しゃっくりを混ぜながら、むせび泣いていた。
思い返してみれば、僕は宮久地との直接的かつ具体的な記憶はないかもしれない。しかし。
「確かに、君と僕は幼馴染ではないかもしれない」
「……ひっ、ふぇ……?」
「けれど、君が僕にいつもおすそ分けをしてくれたことは、偽りじゃないだろう」
「あ……」
ぽかんと、口を開ける彼女を横目に、僕はもう一度帰り道へと向き直った。
「帰るぞ」
「……はい!」
心なしか、二度目の彼女の足取りは、最初よりも軽かったような気がした。
「ふむ、眠いな」
悪魔の女の子が家で眠っていた、その翌日。実に普通の一日だった。
起床するときも、学校に登校するときも、授業を受けているときも、下校するときも、何らおかしいことなどなく。まぁ強いていうと宮久地がるんるん笑顔で僕に弁当を渡したくらいで特に何もなかったわけだが。その際に数人の男子から睨まれていた気がするがそれもどうでもいい。
そんなわけで僕は睡眠を楽しもうとベッドに潜りこんでいる真っ最中なのだった。
「やっぱり、眠っているときが一番幸福な気がする――」
そうして、僕は目を閉じた。そう、目は閉じた。
次に響いたのは無機質なインターホンの音なんかではなく、トラックが衝突したようなそんな爆発的な破壊音だった。
音の原因は明らかに一階からのものだったので、僕は落ちかけていた意識を無理やりに覚醒させられた状態でその原因を確かめることにした。
そこにあったのは、惨状だった。
階段から下りて、右の方にはリビングとキッチン。そして左には玄関があるわけだが、目の前に見えているのはなぜか玄関の扉だった。様々なものを巻き込んできたらしく、一部の靴はリビングのテーブルにまで飛んでいる始末だ。
ここでようやく僕は玄関の方を見た。そこには、これらの惨状を生み出した張本人がすごい仁王立ちをしてこちらを睨みつけていた。
「せ」
「せ?」
「責任を取りなさいよぉぉぉぉっ!!」
「……は?」
前略、家族へ。僕は唐突に悪魔の女の子から責任を取れと言われたのですがどうすればよいのでしょうか。
「あれだけ弄繰り回しといて、アンタは……アンタはぁぁ!!」
追伸、おまけに靴入れの上にあった花瓶まで投げつけられたのですが僕には良く分かりません。
「……ええと、とりあえず君はなんなんだい?」
「フフフ、良くぞ聞いたわ! そう、私こそ後に七大悪魔に名を連ねるであろうマリアントワージュ・セロディアス――」
「やっぱりあなただったんですね、マリア」
「ふぇえ!? セリナぁ!?」
壮大な自己紹介。続いて訪れたのは僕の隣人宮久地芹奈だった。二人が以前友達だった、というのは本当かは分からないが、これで少なくとも顔見知りであることは間違いないだろう。
それにしても、やけにうろたえているな。ええと、名前は確かマリアだったか。さっきまで高らかに名前を叫んでいたはずなのに今では汗すら浮かんでいる。
「それにしても、今でもあの妙な口上を使っているんですね」
「な、なによぉ、いいじゃないのよ私がどんな風に自分の名前を名乗っていたとしても!」
「ええ、そうですね。 ただし、その名前が本当の名前なら、ですけど」
「うぐぅ!」
どうやら、さっき名乗ったマリアントワージュ・セロディアスなんちゃらというのは偽名だったらしい。すでに宮久地が正しているので証明も何もないが、宮久地の指摘を聞いてからマリアの額の汗の量が増加したので間違いないだろう。
そんなことより、僕にはもっと大事なことがある。
「それで、マリアだったか」
「マリアントワージュ・セロディアス! マリアって言うのはやめて」
「じゃあ、セロディアス。 君に聞きたいことがあるんだけど」
「な、何よ」
「僕の家は誰が直してくれるんだ?」
「知らないわよそんなの! 聞くならもうちょっとマシなこと聞きなさい!」
やれやれ、どうやら僕の家の玄関が吹き飛んでリビングがグチャグチャになっていることは彼女にとっては取るに足らないことのようだ。どうも、彼女以外の物は通行に邪魔であっても障害物以下の評価しかもらえないらしい。
「ごめんなさい、春樹君。 あとで私が直しておきますから」
ほう、これだけの破壊でも直せるとは、天使って便利だな。四日前に書けなくなったボールペンも直してもらえないだろうか。
「ちょっとセリナ、こんな奴の家なんて直す必要ないわよ?」
「でも、だって、私は天使だから。 それに……」
そこまでいうと僕の方をちらっと見た。いったい何だっていうんだ。
「と、とにかくこんなことやめて今までどおりに仲良くしよう?」
宮久地が右手を差し出す。しかしその右手が握られることはなかった。
「ふざけないでよ……」
「え?」
「そうやって天使、天使って、そんなんだからセリナもオヤジも!!」
「きゃあ!」
怒りの色を見せたマリアが宮久地を突き飛ばす。いきなりのことに対処できなかったらしく宮久地は靴入れに思いっきり背中をぶつけるとそのままうずくまってしまった。音からして結構な勢いでぶつかったんじゃないかと思う。
「……池田春樹!」
「うん?」
「あんたは私がぜえったいに悪の道に堕としてやるんだから! 首を洗って待ってなさい!」
というと、すでに扉のなくなった玄関から彼女は出て行った。
とりあえず、吹き飛ばされた宮久地のそばに僕は歩み寄った。
「大丈夫か?」
「は、はいなんとか……少しだけ痛いですけど」
「そうか……うんと、少し待ってて」
「え?」
ええと、確か階段の下の小さいスペースに救急箱が置いてあった気がしたんだけど。買いだめのトイレットペーパーや非常食を押しのけると、その奥にちゃんと救急箱があった。とりあえず救急箱から消毒液とガーゼを取り出すと宮久地のそばに戻る。
「見せて」
「え、いえそんな、このくらい……」
「いいから、背中を見せて」
彼女は数秒の間、考え込むように下を向いていた。けれど、僕の言葉に押されたのか首をこくりと縦に振ると、服をまくって怪我をした個所を僕に見せてくれた。いくら天使といえども、怪我をしないというわけではないみたいだ。ぶつけたところが、少しだけ青くなっていた。
「やっぱり、少し打ち身になっているな」
「は、はあ……そうですか」
「それに、体温も少し高いように思えるけど、風邪でも引いた?」
「い、いえ! それは、ち、違うんです!」
何が違うのか僕にはよくわからないが、彼女が違うというならそれは違うのだろう。たぶん。
僕は消毒液を怪我をした場所に塗りこむと、そこにガーゼを貼った。確か打ち身をしているなら冷やす必要があったはずなんだけど。
「あとは冷やせばいいと思うけど、氷でも取って」
「あの、春樹君……私は、もう大丈夫ですから」
「けど、処置は完全じゃないよ」
「いえ、いいんです。 あとは自分で治癒できますから」
服を戻して立ち上がると、ゆっくりとこちらを向いた。顔を伏せているためよく見えないがやっぱり少し赤い気がする。
「その前に、春樹君のお家、直しますね。 ご家族が帰ってきたら大変ですから」
そうすると宮久地は両手を組んで、僕には決してわからない言葉で、昨日の公園の時のように呪文を唱え始めた。それはまるで、呪文というよりは一つの歌を歌うかのような、そんな美麗さを含んだきれいな言葉だった。
周辺が一段と輝いて、それが僕の目の許容量を超えたと思った次の瞬間には、荒々しく吹き飛んでいた扉はきちんと玄関に付いていた。それだけじゃない。粉砕されかけていた靴入れは以前と何も変わらない状態になっているし悲惨なことになっていたリビングの方もこれまたマリアがやってくる前の状態にきっちりと元に戻っていた。
僕がこれらの一連の変化に驚愕していると、背後から扉の開く音が聞こえた。それは、宮久地が扉に手をかけたからだった。
「…………ありがとう」
それだけいうと、そのまま彼女は帰ってしまった。
後に残ったのは、僕が救急箱を引っ張り出したという、その事実しか残っていなかった。
「首を洗って待っていろ、か」
僕は今学校の屋上にいた。なぜか、と問われても特に答えようがない。なぜならここにいるのは僕の気まぐれでしかないからだ。ちなみに、時間なら今ごろはきっと五時間目でも始めているころだろう。なぜ授業に出ないのか。それならまだ答えようがある。理由は簡単だ。あの悪魔の女の子、マリアが気になるからだ。
首を洗って待っていろ、などと言うくらいだから、学校で授業を受けているときに例のごとくバサーッと現れてくれるんじゃないかと思い一時間目から窓をチラチラしていたが結局現れなかった。おまけに教師からはとてもにこやかな表情でチョークを投げつけられるし、なんて痛い一日だろう。少しだけ期待していた分、心も痛い。
「あー、見つけた!」
心の中で浮かべれば何とやらだ。頭で考えただけで現れてくれるなんて、それだったら一時間目から来てくれたっていいんじゃないだろうか。
「どうも。 名前はマリアだっけ?」
「マリアントワージュ・セロディアス。 言っておくけど、三度目はないわよ」
鉄柵の向こうから、思い切りにらまれた。ちなみに、現在僕がいるのは飛び降り防止用の鉄柵のすぐそばだ。だから、必然的にマリアがいる場所は鉄柵の向こう側、つまり空中ということになる。
しかし不思議なのはマリアとほぼ同じか、少し小さい程度の大きさの翼でなぜ飛ぶことができるのだろうということだ。ゆったりとバッサバッサとはためく黒い翼。やはり悪魔や天使にはまだまだ理解のできないことが多いみたいだ。
「それで、セロディアス。 どうして早いうちに僕に会いに来なかったんだ?」
こっちは今朝からずっと意識していたのにどういうことだ。僕がベッドから起き上がるときも朝食を食べるときも着替えをするときも歯を磨くときも宮久地といっしょに学校へ通学するときもホームルームが始まったときも授業が行われているときも宮久地からお弁当を渡されたときも昼食を食べているときも僕は気にしていたというのに、これじゃ拍子抜けもいいところだ。
「だって、その、アレよ」
「……あれって何だ」
「ア、アレはあれよ! 悪い!?」
「いや、あれって言われても僕にはわからないし」
「ムグググ……な、何よ! だって恥ずかしかったんだもんっ!」
頭から煙でも出てくるんじゃないかっていうほどに顔が真っ赤なんだが、大丈夫なんだろうか。なんか微妙にふらふらしてるし、この子も風邪でも引いてるんじゃないか。
「恥ずかしい?」
「ぜんぜん知らない人ばっかりいると恥ずかしいの! しょうがないでしょ!?」
何がどう仕方ないことなのか僕にはわからないが、思うに人を悪の道に誘惑しなければならない立場としてはそれは致命的な弱点なんじゃないかと思えるんだけど。
「そうなのか」
「そうなの! 私がそうって言うんだからそうなの!」
「ふうん、ところでずっと気になっていたんだけど」
「何よ」
「責任って何のことなの?」
「ぶほぉ!」
疑問をぶつけただけなのにすごい勢いで口から色々飛んだんだけど。とりあえずツバがかかって気になる。
「な、なななななななな!?」
「何を驚いてるのかわからないけど、君が言いだしたことだよ」
「それは、その、責任は責任よ!」
「いや、何に対しての責任なのかが知りたいんだけど、僕は何かしたかい?」
「何かって、あんただってそりゃ……あうう……!」
また赤くなったぞ。本当に、僕が何をしたっていうんだ。思い当たるのは彼女を調べたことくらいだけど、変なことは何もしてないはずだけどな。
「と、とにかくあんたはさっさと悪の道に堕落すればいいの!」
結局答える気はないらしい。また理解できないリストが増えそうだ。それにしてもさっきから彼女が言う悪の道っていったいどういうことなんだろう。
「それで、僕をどうやって悪の道とやらに引きずり込む気なんだい」
「…………えっと」
なんかいきなり考え出したぞ。僕はてっきり悪いことへの魅力でも語って自発的にそうさせるものだとばかり思っていたんだけど。
「あーもう、こうなったら実力行使!」
「うぐっ」
ありのままに今起こったことを話すと、鉄柵の向かいにいたはずのマリアが飛び上がって僕に向かってきたなと思っていたら屋上の壁に押さえつけられていた。
「悪いことしないなら、殺すわよ?」
彼女の左手に首根っこを握られていることで、僕は満足に動くこともできやしない。さらに、いつの間にやらマリアの右手にはバカみたいにでかい三又の槍が握られているし。というか、悪いことしないと殺すってなかなか聞かない言葉だな。
「うく……かはッ……」
「フフン。 やっぱり悪魔はこうでなくっちゃね。 心地良いわ」
しかしこれ、意外とマズいかも、しれない。呼吸をふさがれているからだんだん思考もまともに、考えられなく……
「ほら、早くイエスって答えなさいよ。 今なら下僕程度で勘弁してやらないこともないわ」
いや、こたえたいのは山々だけど、首が、ふさがって、答えが……うあ……
「あ、が……」
「下僕じゃ満足できないのかしら? じゃあ執事ならどう? 今だったら私専属の執事にでも」
「いいかげんにしなさいマリア!」
「ひゃう!?」
そのとき、屋上で一つの怒声が悪魔の少女に向けて放たれた。聞き間違えるわけも無い。その声は明らかに宮久地のものだった。声に驚いたのか僕の首からその手は離されていた。今のうちに呼吸はさせてもらおう。
「えっほ、げほ……」
「大丈夫ですか、春樹君?」
「な、なんとかね……げほっ」
宮久地に背中をさすってもらって、なんとか普通に呼吸できる状態になった。危うく答える前に死ぬところだった。
「マリア、いくら友達といえど今のは許せないですよ」
「な、何よ、だってこうやった方が手っ取り早いし、それに悪魔っぽいかなって……」
「相手が死に掛けてて、それがマトモな交渉だと本当に思ってるんですか!?」
「う、うみゅう……だって、だって……」
あからさまにマリアがへこみだした。まぁ、実の友人に本気で怒られれば落ち込むものだろうとは思うが。
「あんな風に首を絞めたら死んでしまうに決まってるでしょう!? それをマリアは――」
「ありがとう、宮久地。 けど、僕にも言いたい事があるから怒るのはそれくらいにしてくれないか」
「け、けれど春樹君が……」
「頼むよ、宮久地、話させてほしい」
「……わかりました。 春樹君がそういうのなら」
そういうと宮久地はスッと下がってくれた。流石は幼馴染――本当は違うらしいが、まぁどちらでも僕にはどうでもいいことだ――聞き分けのいい人は僕は嫌いじゃない。むしろ好感を持てる。それよりもとりあえずマリアに答えなくては。
「――マリア」
「なに……」
「とりあえず悪の道にも誘われる気も君の下僕にも執事にもなる気はない。そんなことよりもだ」
「……え?」
「君は悪魔なのに、悪魔らしさを気にしているのはなぜなんだ?」
そう、彼女は先ほどから言葉のどこかに悪魔らしさを入れ込んでいる。悪魔っぽい、悪魔らしい。それが僕にとってはとても不思議だった。だから僕は聞きたくなった。なぜ、そんなにも悪魔ということにこだわるのか。彼女、マリアは悪魔であるはずなのに。
「何よ、悪魔が悪魔らしさを気にしたら何かいけないって言うの?」
「いやそんなことを言う気はない。ただ気になっただけだよ。宮久地は――君にとってはセリナか、彼女は一度だって天使だからとか、天使らしくとかそんなことは口にしなかったのに、君はやたらと気にしているようだからね」
「むぐ……」
僕がこういうと、マリアは苦い顔をしながら口を閉じてしまった。やはり何か原因があるようだが、それが何なのかは今の僕にはわからない。
「マリア……ひょっとして、今でも気にしてるんですか?」
「セリナと話すことなんて、ない」
「マリアのお父さんの――」
「だぁかぁら! 私はセリナと話すことなんてない! 今の私の相手はこいつ、池田春樹! セリナは関係ない!」
激昂したような叫びをあげながら、僕の目の前には巨大な槍が突きつけられている。下手に動くと串刺しより酷いことになりそうなので今は黙っておこう。
「池田春樹……今日はこの辺で勘弁したげるけど、絶対に、私はあんたを悪の道に堕としてみせるんだから」
そう宣言すると、この間のようにバサバサとその黒い翼をはためいてどこかへと飛び去ってしまった。僕がそれを確認すると、後ろから走りよってくる音が聞こえる。
「春樹君、大丈夫ですか!?」
「ああ、あの馬鹿でかい槍には刺さってないよ」
「よかった……春樹君がマリアに何されるか、ほんとに心配で……」
そういいながら僕の手を握り締める宮久地。どうやら、だいぶ彼女には心配を掛けさせてしまったらしい。なぜそこまで僕のことを気にするのかはよく分からないが。心配を掛けさせてしまったならそれは僕の不手際だろう。
「ええと、すまない」
「いえそんな、私が春樹君に謝ることがあっても、春樹君が謝ることはありませんよ! 私が、ちょっと目を離した隙にこんなことになって……」
「いや、僕がここに一人できたのは独断だ。 責任が生じるならそれは僕にある。 宮久地が責任を負うことじゃない」
「で、ですけど春樹君が危うく大変なことに……」
「ちょうどいいところで君は来てくれただろう? それだけで十分だよ。 それに――」
そして僕は宮久地の右手を握って僕の胸に当てた。制服越しとはいえ、恐らく心臓の鼓動の振動くらいは伝わるはずだ。
「あわ!?……ひゃ、ひゃるきしゃん……?」
宮久地の顔がなぜかゆでだこになっているが、まぁどうでもいいだろう。きっとこの間の風邪でも続いているんだろう。
彼女の状態など気にせず、僕は自身の話を続けた。
「君のおかげで、僕は一切怪我は負わなかった。 少しだけ首は痛むけど、問題は無い。 だから、それでいいだろう」
「え、えと……!」
「僕の体を触る以上の証拠が、まだ必要なのかい?」
「か、体を触る――以上――う、うひゅう――」
僕の話が終わるのと、宮久地がばったりと倒れるのはほぼ同時のことだった。彼女の頭がコンクリートに重力に任せた衝突をする前に一応支えてはおいたけど。
しかし、顔をここまで真っ赤にさせて倒れるなんて、普通じゃないだろう。今まで僕は風邪だ風邪だと思っていたが。
「……まさか、天使の世界でインフルエンザが流行中なのか」
それなら納得がいく。現に倒れているわけだし、これはもう重症以外の何物でもないわけだし。
とりあえず、僕の六時間目の授業は宮久地を保健室に運ぶことになりそうだ。まぁ、宮久地はそこまで重くはないからできないことはないだろう。
僕は宮久地の体を一番抱えやすい格好で抱え込むと、そのまま保健室に運び込んだのだった。
しかし、後でクラスの人間全員から宮久地について質問を投げかけられまくったのだが、あれは一体なんだったんだろう。僕のクラスにはどうやら宮久地のファンが多いのかもしれない。まぁ、僕には関係ないが。
「そろそろ、だろうか」
あれから翌日、僕は家にいた。学校は既に放課後となっており、校舎に残っている人間は恐らく生徒会や委員会などの役員たちや部活動で個人個人の技術を磨いているような人たちばかりだろう。そんなことは今の僕には関係ないが。
「私を呼びつけるなんて、いい根性してるじゃないのあんた」
「ああ、来てくれたか。 いや、もしかしたら文字が読めないかもと学校で無償に気になって仕方が無かった」
「文字が読めないって、あんた私を馬鹿にしてるわよね?」
「そうあからさまな怒りを見せないでくれ。 君やセリナは僕の認識からすれば別の世界の存在だし、使ってる言語体型も違うのかとも思ったんだよ」
「……あんたが何を言いたいのかいまいちわかんないけど、馬鹿にはしていないのよね?」
「うん、してるつもりはないけど」
「だったらいいわ」
馬鹿にはしていないが、どうも僕の話がきちんと通じていない気がする。まぁ、大まかなことが伝わればそれでいいか、と僕は自分自身を納得させることにする。
「で、どうして私を呼んだわけ?」
「昨日君が知らない人間が大勢いるのは好まないと言ったから、君が僕に接触しやすいようにいつ会えばいいのかを教えようと思ったんだよ」
「それで家の窓にメモを置いたってわけ?」
「うん、そう。 しかし言葉が伝わってよかったよ。 少し気になっていたけど、この世界とそっちの世界の言葉は同じなのかい?」
「え、ええ。 そうみたいね。 何でかは知らないけど」
ひょっとしたら僕らの世界の言葉は向こうでは使われることが少なくて、こっちで言うところの外国語みたいな扱いなのかとも思っていたけど、どうやら根本的に同じらしい。しかし地球では圧倒的に英語と中国語を使ってる人間が多いはずなのによく日本語なんてきっちりと使ってるな。うん、この辺りのことは宮久地に改めて聞き直した方がよさそうだ。
「あんたがなんであんな窓にメモを置いたのかはわかった。 けど、肝心などうして私を呼んだかを説明してないわよ。 ああ、もしかしてやっぱり私の下僕になりたいっていう申し出かしら?」
「いや、違う」
昨日も断ったはずなんだけど、おかしいな、マリアの顔がみるみると赤くなっている。とりあえず話を続けて気でも逸らそうか。
「昨日聞き損ねたことを、改めて質問しようと思ってね」
「昨日のって、何よ」
「君がやたらと悪魔らしさを気にすることだよ」
「……そのことね。 とりあえず、あんたには関係ないし、話したくもないの。 わかる?」
やはり彼女はこのことに答えたくないようだ。となると、それ以上のことを知るには何かしらの状況変化が起こるか、僕が推理するかのどちらかしかない。
「まぁ、そうだろうね。 昨日君がいなくなったその後に、宮――セリナに君の事を聞いたんだけど、彼女は言わなかったからね。 自分の友達が知られたくないことを、私が話すわけにはいかないって、そう言われたよ」
「……セリナ」
「どうやらセリナは君のことが大切らしいな。 いい友達だと僕は思うけど」
「――うっさいわね、あんたは何よ――何なのよ――」
「僕はただ、気になるだけだ。 宮久地のこと、天使のこと、マリアントワージュ・セロディアスと名乗る君のこと、そして悪魔のこと。 全く知らない世界が僕の目の前にやってきた。 それが気にならないわけがないだろう」
「セリナ――」
彼女、マリアは、少しだけ声を震わせていた。そんな声の揺らぎは、それに呼応するかのように全身で表され始める。そしてとうとう振動が顕著になったとき、彼女の体は膝からストンと崩れ落ちた。
「悪魔のことは、今は聞かないことにするよ。 しばらく、君のしたいようにしてるといい」
「……礼なんて絶対言わないから」
「そうか」
彼女は床に座り込む中、僕はベッドへと向かいそのまま寝転がった。特にすることがないときは、大抵はこうしてる。そのまま眠ることも多い。今は、マリアという存在がいるので眠るとどうなるかはわかったものではないけれども。
マリアのすすり泣く音が聞こえながら、僕は寝転がっている。そんな状態が恐らく三分くらい続いただろう。唐突に、ベッドのバネがより深く沈みこむのを感じた。見れば、マリアがベッドに座っていた。泣くのは、もうやめたようだ。少しだけ目の周りが紅くなっているのは、人間も悪魔も同じらしい。
「……あんたの質問、他の事だったら一つだけ答えてあげる」
「なんか、唐突だな」
「な、何よ! なんかあんたに借り作ってる気がして癪だからっていうだけの話! それだけだからっ!」
「そうか、それじゃあ質問があるんだけど」
「……あんた、人からロボットみたいって言われたことない?」
「いや、ないけど。 なんでだ?」
「別に……」
そんなことよりロボットを知っていることのほうが衝撃なんだけど。意外とこちらの文化は向こうでも通じるものなのかもしれない。
「君は前に、天使のこと、そしてセリナと君の父親に対して怒っていたけど。 何を気にしているのかな」
「ぐっ……あんた、それさっきの奴と大して変わらないじゃない!」
「ん、そうなのか。 てっきり原因は違うのかと思ってた」
「うー……でもあんたに借りを作るのも癪だし……」
頭まで抱えて、相当悩んでいる。とりあえずわかったのは、彼女が悪魔らしさを気にするのも天使という種族を気にするのも同じ原因であるということ。そしてそのことは間違いなく彼女の父親が関わっているということだ。しかしあのとき彼女はなんて言っていたかな。ええと、確か。
「はぁ……天使、なんて……」
ああ、思い出した。「天使、天使って、そんなんだからセリナもオヤジも」だった。
そういえば、マリアは悪魔だよな。それなら父親だって当然、悪魔のはず。それなのになんで天使の話で父親が出てくるんだろう。まさかとは思うが。
「ねぇ、君の父親は、どんな感じなんだ?」
「な、なんでいきなり私のオヤジのこと聞くの!?」
「だって、君が父親に対しても怒っていたから。 余程酷い悪魔なのかと」
よくよく考えると、酷い悪魔って肩書きとしてどうなんだろう。悪魔界からしたら名誉なのかもしれない。
「……まぁ、そうね。 酷い悪魔よ。 悪魔として、甘ったれで、腑抜けた最低な悪魔」
ああ、そうか。悪魔側で酷いってなるとむしろ優しい人が酷いってことになるのか。価値観が逆で分かりにくい。しかし、父親は悪魔にしては珍しく優しい悪魔だった、ということはわかった。恐らく、その辺のことが彼女の問題として立ちふさがっているんだろう。
「そうか。 つまり君は、自分の父親が悪魔らしくないから気に食わないのか」
「……そう、そうよ。 だけどねぇあんた、人の繊細なとこそんな簡単に突っつくんじゃないわよっ!」
「……ん、すまない」
彼女の右腕がまた僕の首筋に向けられそうな雰囲気を感じ取ったので、ここは素直に謝っておく。正直、僕としても何度も首を絞められたくない。あと、意外と力あるから結構痛い。
「あーもう、腹立つったらありゃしないんだから!」
うん、そこまで強く床を蹴られると後が怖いんだけど。バキッて壊れたりしないだろうな。そうなったら宮久地呼ばないといけないんだけど。こないだ家に呼んだとき、なぜか顔が赤くなって大変なことになったから宮久地のためにもあまり呼びたくないんだけどな。
結構な勢いでマリアが床を蹴り続けて12回目。それでようやく蹴るのをやめてくれた。残念なことに床には傷どころか一
部抜け落ちかねない部分が出来上がっていた。どうやら、宮久地を呼ばなくてはならないらしい。とりあえず僕の睡眠時間を
返してほしい。
「……ねぇ、あんた。 悪の道に入る気はない?」
「さっきも断ったけど、そんな気はないよ。 なぜ聞いたんだ」
「別に。 どうせあんたのことだからそう答えるだろうと思ってたし」
「そうか」
「それじゃ、もう帰る。 言っとくけど、絶対にあんたは堕としてやるから」
力強く宣告すると、彼女はそのまま窓から颯爽と飛んでいってしまった。いい加減、窓からじゃなくて玄関から帰ることを
覚えてほしいんだけど。
まだ肌寒い春の風が入り込む窓を静かに眺めながら、僕は呟いた。
「とりあえず、宮久地を呼ぶか……」
数分後、やはり宮久地が倒れることになった。どうしろというんだ、僕に。
そして翌日。僕はベッドの上で考え事をしてた。時刻は午前11時。
今日は、休みだった。こういう日は大抵やることがない。人によっては両親から面倒ごとを頼まれることもあるかもしれないが、僕の父親は結構な割合で家にいないことが多い人間だ。母親も似たようなものだ。父親よりは家にいるってだけであまり変わらない。
ふむ、学校の宿題が面倒なものならやるけれども、宿題は出なかったしな。いつもどおり寝てるか。一応インターネットで悪魔と天使について調べものをするっていう選択肢もあるけれども。
僕がそうやって思案していると、行動を決めるより先に、僕のお腹がその欲求を直に伝えだした。
「なんか食べるか」
部屋を出て、階段を下りて、右にあるリビングに僕はたどり着いた。今この家は両親共に不在だ。朝食を食べているときに母親から、昼食は用意しておくから食べて、と伝えられているのでソレを食べることにする。
リビングを通り抜けてそのままキッチンへ向かい、僕は冷蔵庫を開ける。冷蔵庫の上から二段目、そこにあんまりパラパラとしていなさそうなチャーハンが静かにそのときを待っていた。そいつを取り出した僕は、迷わず電子レンジに突っ込んで温めた。最近の電子レンジはある程度の温度になると勝手に止まってくれるらしいのだが、僕にとってその温度は舌を焦がされるんじゃないかと思えるほどに熱い。あの温度で食事している人間は本当に食べ物の味を感じ取れているのだろうか。僕にとって疑問でしかない。
一分経つか経たないかというところで僕はチャーハンを取り出した。これ以上温めると舌を焦がす温度となりかねないからだ。流し台のそばにある引き出しからスプーンを出して、チャーハンの器と共にリビングへと戻った。清潔に保たれている木製のテーブルに器を載せて、ラップを剥がす。そうしてから、いざ食べようと思ったとき、テーブルの上に一枚の紙が置いてあることに気がついた。
「朝にはなかったはずだけどな」
朝食の時には、これは置かれていなかったはず。つまり、この紙はそれ以降に置かれた物だろう。しかしこんな紙残す人なんて限られてくるが。
「まさか、マリア?」
その可能性は当然あった。前に僕が彼女にメモを見せたわけだしその意趣返しとして置いたのかもしれない。まぁ、そんなことするくらいなら僕に直接会った方が早いとは思うけれども。
若干の興味を紙に抱きながら、僕は紙に書かれた文面を確認するために右手で手繰り寄せた。さてと、内容はいかほどのものか。
"ごめんね春樹! ままど~しても大事な用事があるから、お昼のタイムセールに間に合わないの! だから春樹が代わりに行ってきて! どこのお店かはチラシ置いとくから ほんとごめんね! ままより"
「…………」
言うまでなく、母親のだった。ある意味残念な置手紙にため息が出てくるぞ。ちょっと期待していた分、精神的打撃もなかなかに大きかったわけで。
残念なメモをぺいっとテーブルの上に手放した僕は、とりあえずお店のチラシを探すことにした。珍しいことだが、頼まれてしまったものは仕方がないし。やらないわけにもいかないだろう。母親のことだから近いけれど変なところに置いてるに違いない。
そんな風に探して二分後、使ってないイスの座るところにあった。テーブルのそばとはいえ、ここに置くのはどうかと思うんだよね。ぶっちゃけるけど。どうせ置くならメモのそばに置けばいいじゃないか。
そんな風にも思ったが、まぁそんなことは些細なことだろうし、どうでもいいか。タイムセールの時間は、午後一時半から
始まるらしい。
それじゃ、ご飯食べたらすぐ行くか。食べ終わるのはおそらく十二時半ごろ。スーパーにつくのは遅くとも一時。あとはぶ
らぶらとすればいいわけだし。
今日の予定を適当に打ち立てた僕は、それから両手を合わせてから、静かに唱えた。
「いただきます」
右手につけた腕時計をちらりと覗いた。時刻は、午後二時。頼まれた買い物は既に済まして、僕はスーパーの出口にいた。
買い物自体はすぐに終わった。タイムセールが始まったら商品をすっと取って、次のタイムセールの場所で待ち、またすっ
と取る。商品を取り終えたらすっとレジに行って。ただそれだけのことだ。ただそれだけのことのはずなのに、スーパー内部
の熱気は凄まじいことになっていた。僕が手に取った後はもうご近所のおばさんたちが、アリのようにわらわらと群がる様子
は流石に僕でも何か心に渦巻く気味の悪さを感じた。
「まぁ、買い物は終わったからいいか」
と、僕は右手に提げたレジ袋を見つめた。流行のエコバッグとやらは僕は持っていないし、家では誰も持ってない。なぜな
らレジ袋をゴミ箱の中に突っ込んで後で捨ててるからだ。規定のゴミ袋があったかは覚えてないが、もしあるならたぶんその
袋の中にそのまま突っ込んでそうだが。
とにかく、僕の役目は終わった。僕はスーパーから家へと向かうために、歩き始める。
休日の昼間、交通量は時折車が通る程度。僕の住む町は、道路的に主要の部分ではないらしく、大量の車が通ったことは一
度もないぐらいだ。それでも時々車はやってくるんだけど。
比較的大きな道路だった場所から、小さな道路ばかりしかない住宅地へと足を進めた。当然、こちらの方が家へと直線的に
近づけるからだ。
住宅地というのは、文字通り住宅が密集している地域だ。既に十六軒ほどの家を見ている。それだけの密集地のはずなのに
、不思議と静かだった。聞こえるのは遠くから響く車の走る音。近所にあるのか、公園で子供たちの遊ぶ声ぐらいで。
本当に静かな住宅地だった。もしや、この場所には誰もいないんじゃないだろうかと思わず錯覚するほどに。
――今ならボール投げ込んでも見つからないんじゃない?
僕の中に、悪魔のささやきが聞こえる。おかしいな、普段ならそんなことは考えるはずはないんだけど。
――なんだったら爆竹でも放り投げちゃったら?
まだ悪魔は僕を引きずり込もうとする。僕は、そんな幻聴を聞くような人間だっただろうか。
――ねぇ、それともモーニングスターでもぶん投げとく?
幻聴の癖に、モーニングスターとかいう僕の知らない物の名前まで出してきた。これはもう本格的に病院にでも行くべきな
のかもしれないな。
――ちょっと、聞いてるの?
いや、聞こえてなかったらこんなにも深く考えないよ。僕は今、自らを病院に連れて行くか行かないかという数年に一度の
決断を迫られているわけだし。ああ、でも保険証は家の中にあるし、やはり一度帰って
「死ねっ!!」
「うご……?」
な、殴られた。いきなり横から殴られた。おかしい。僕は誰かからいきなり殴られるようなことをしたつもりはないし、と
いうかそもそも僕を殴る相手なんかこの場にはいないはずなのに。どうしてなんだ。
「私を無視できるなんて……やっぱりあんた、ほんとのほんとは私をバカにしてるんでしょ!」
上を見上げて、僕は全てを悟った。殴ったのは、マリアだった。
「あの、さっきまでの声って、君だよね」
「そりゃそーに決まってるでしょ! 私の他に誰がここにいるっていうの? あんた見えないものでも見えちゃうわけ?」
悪魔に言われたら世話はないなと僕は思った。
僕の頭がおかしくなったわけではなく、単に考え込みすぎて彼女の存在を認識してないだけだった。内心ほっとしている。
「悪魔に見えないものが僕に見えるわけないだろう。 少し考え事してたからわからなかったんだ」
「ふーん、あっそ。 それで、何考えてたの?」
「いや、ここが不思議なくらい静かだなって」
「はぁ? それだけ?」
「うん、そうだけど、何?」
「……あんた、やっぱり変な奴だわ」
数回の会話のやり取りで勝手に変人扱いされた。僕が何か変なことしただろうか。ため息までつかれたぞ。ため息したいの
はむしろ僕のほうなんだけど。
「で、話は戻るけど、今ならイタズラしほーだいだと思わない?」
「……家に誰もいないという保証はないけど」
「こんなに静かな上にたくさん家があるわけだし、窓の一つや二つ割ったところで問題にならないはずよ!」
「いや、それって家主が帰ってきたら結局は問題になると思うんだけど」
「いいのよ、イタズラっていうのはそーいうもんなの! で、なに投げ込むわけ? ここは手堅く野球のボールで行く? そ
れともサッカーボールでもシュートする? なんだったらバレーボールでも叩き込んだりとか。 ああ、それともボーリング
の球でストライクとか?」
「うん、とりあえずそのボールがどこから出てきたかは突っ込まないことにするね。 それよりも最後の方のチョイスが酷い
と思うよ。 大体僕には重くて塀を越えてストライクする自信はない」
「ええー? じゃあ何よ。 私のモーニングスターもダメっていうわけ?」
「さっきから僕にこれでもかと見せ付けているその物騒な物のことか」
彼女が手にしているそれは、武器というよりかは凶器と呼んだほうが早そうな、明らかに人を傷つける気が満々な形状をし
ていた。ボーリングの球より確実に大きそうな鉄球。しかも、トゲトゲしい。投げつけたらそのまま刺さりそうだ。そんな鉄
球が、鎖で柄に繋がれていた。柄は手で握るより少し大きい程度で、鎖はどう考えても三メートルは超えてると思う。使用方
法は、あまり考えたくない。
ジャラ、と鎖を鳴らしながら鉄球を平然と僕のほうに差し出してくるあたり、僕に対する遠慮のなさを感じ取れる。
「ほらほら、投げ込んだら酷く冒涜的で背徳的な開放感のある窓割りができそうだと思わない?」
「窓割るのにそこまでたいそうな武器使わなくても良いと思うんだ」
#endregion
[[作品紹介ページ]]>>[[設定紹介バナナな人]]
#region(まだ秘密ー♪)
「むにゃ……ふにゅ……」
実に気持ちよさそうな寝顔だ。
肩から提げていた通学カバンをそっと床に下ろして、僕はその顔に注目した。知らない顔だ。そもそも部屋の主に何も言わずベッドを支配するような知り合いはいない。知り合いの数自体が少ないけれど。
突然の来訪者は誰なのか、確かめる必要がある。そう思いゆっくりとベッドに近づいていく。
僕のベッドは低反発な素材の表面で、内部にはスプリングが入っている。ちょっと座り込んだだけでギッ、というスプリングの沈み込んだ音がする。このベッドの素材に文句はないが、いつも思う。スプリングの音はやたらと耳に響いてウザったらしい。
僕がベッドに座ったことで例の支配者は起きるかなとも思ったが、予想に反してそいつは実に幸福な睡眠をしているらしい。 バカみたいに鼻ちょうちんまで膨らませているし。
さて、本来の調査に入ろう。気になったところから観察することにする。
まず、女の子だ。
顔の見た目、頬のぷにっと感、体格、腕の質感、どれをとってもこれは女の子だろう。
調べている間、特に起床する気配はない。やはりと思うが、この女の子は鈍感なんだろう。
髪の毛は金色で短めだ。ただし、少し余っている部分を後ろで縛っている。少しボサっとした様子も見受けられる。きちんと整えていないのかもしれない。
そんな髪の毛を主張させるかのように重量感のある黒い服装も、なんというか寒そうな服装だ。首から肩にかけて肌が見えているし、足もふくらはぎまでしか覆っていない。いくら春だと言っても今年の気温はまだ少し肌寒いことも多い。思うに女子という生き物はなぜあのように足を露出できるのだろうかと問いたい。夏以外はたいてい長袖の僕にはわからない事情でもあるんだろうか。
「すぴー……」
今はこの女の子について調べているんだった。
しかし、どうしようか。
「……羽」
女の子の頭部、そして背中に気にしてほしいと言わんばかりの黒い羽がついていることについて。
無視するか。さっきからあえて説明から外していたのも気にしたくなかったからだし。だがしかし。
「こういうときは、ネットか」
ベッドからいったん離れてデスクに向かうと、コンピューターの電源を入れて、数秒待ち、それからインターネットを開いた。検索エンジンには当然「悪魔」と打ち込んで。
「……やっぱりか」
出てきた画像群と、ベッドの上の女の子を見比べてみる。特に違いはなかった。ということは、この女の子は悪魔ということだ。よし、ある程度調べられたな。
「本物なんだろうか」
当然、本物なら、という確証が必要だ。しかしそれならば手っ取り早いであろう方法がある。触って調べるのが一番早い。
再びベッドに戻った僕は、他の部位には目もくれずその羽の部位をこれまたやんわりと触った。
「ん、ぅ」と、触ったり撫でたりするごとに女の子は声を出した。どうやらガチの本物だ。しかし逆に興味が湧いてくるというものじゃないだろうか。すなわち、どうやって生えているか。
僕にしては珍しく、鼻息を荒げながら横向きに寝ているその女の子に覆い被さり。興奮も冷め遣らぬままに僕はその調査対象の生え際を調べようとした。が、どうも興奮のために手が落ち着かず、誤ってその根元を乱暴に握り締める形になってしまったのだった。
「ひみゃあああああああああああああああああああああっ!?」
どうやら、失敗したようだ。
僕としたことが、らしくないミスをしたものだ。家には僕だけだし別にいいか。
「ひ、あ、あ、あんた……アンタ……」
僕の下ですやすやとバカみたいに睡眠していた女の子は、今では急速な勢いでその皮膚の色を変化させている。眠っていたかと思えば赤くなっているし。思うに人というのは忙しい生きも
「いやああああああああああああああああ!」
「うご」
ドン、と僕の体を突き飛ばすと、開いていた窓からバサーと音を立てて飛び立って、すでに暗くなりつつある空へ消えていってしまった。
ベッドの上から転げ落ちてしまって結構な勢いで背中を打ち付けた僕は、少々痛みを感じながらも立ち上がり、女の子の消えた空を見つめる。
「…………寝るか」
もともと寝るつもりだったのが、色々と時間がかかってしまった。まぁ、眠れるのならなんでもいいだろう。しかしあの来訪者、もしや道に迷っていたのだろうか。もしそうなら次回は別の家でもぐりこんでもらいたい。居眠り飛行をしていたために迷い込んだというのも無くはないが。今はどうだっていい。
軋むベッドの音を感じ取りながら、大きく呼吸してみた。
かいだことのない匂いが、やはり僕の知らない誰かであると、改めて知覚させるのであった。
眠い。そう思い、目を閉じた。全身にかかっていた緊張が空気中に溶け込んで、雲散するような感覚。僕の脳もそれに合わせて一時的な活動休止に入ろうとしていた。神経細胞が瞬間的に吸い上げられようとしているまさにそのとき、インターホンの無情な響きが家中に染み渡った。
「誰だ……」
誰だ、とは言ったがこの家に訪れる人物など高が知れているものだ。宅配便や新聞の人でないなら十中八九、今インターホンを鳴らしたのは彼女だ。引き抜かれそうだった脳神経を無理やり呼び込むとベッドから起き上がり一階のリビングに向かう。
一回目のインターホンが鳴ってからしばらく静かだったが、僕がリビングについたころに狙ったように二度目が鳴り出した。こいつは早々に出てやらないと面倒だな。そんなわけでさっさとインターホンのスイッチを押した。これで向こう側の人間の声が聞こえるようになる。
「どなたですか?」
「宮久地です、おすそわけにきたのですが……」
ほら彼女だ。というか、彼女以外にこの家に用のある人間など固有名詞ではいないだろうと思う。父親関連の友人が尋ねてくるなんて話もないし。
用も分かったので、僕はインターホンのスイッチを切るとそのまま玄関に足を運ぶのだった。玄関のロックを外して、扉を開けると、そこには彼女――宮久地芹奈が少し大きいお鍋を持って立っているのだった。
「なんだ、やっぱり春樹君じゃないですかー丁寧に出たのに損しましたー」
「僕は君に安眠を妨害されたんだけどね。毎度毎度おすそ分けとはほんとご苦労なことで」
そういいながら彼女を玄関の中に招き入れて扉を閉めた。というのも、外は寒いわけだし、いつまでもお鍋を持たせたままと言うのも流石にどうかとは思うからだ。
この宮久地芹奈という人間は、いわゆるお隣でことあるごとに僕の家にやってきてはこういうことをする。僕のカンだと彼女がたとえ隣に住んでいなかったとしてもこういうことをしに来る人間であろうと百パーセント読んでいるが。
「春樹君、一人でした?」
「そうといえばそうだね。父親は仕事だけど、母親は良く分からないし」
ついさっきまで悪魔の女の子がいたわけだけど。
「それより、さっさとその鍋を僕に預けたらどうだ? 重いだろうし」
「あ、うん、それもそうですね。 それじゃ渡して――え」
音としては、それは空白だった。
そして次の瞬間には大質量の物体が石のタイルにぶつかった衝撃が耳に届いたのだった。状況としては、宮久地が手渡そうとしたお鍋を落とした。ただそれだけのことだが、それだけのことにこめられた意味は何か大きいものであるということに僕は薄々気がついていた。
「宮久地?」
「は、春樹君……な、なぜそれが、君に」
それ、と言われてもいまいち把握できないが、彼女が指差した肩を指で弄ってみると、例の、悪魔の女の子の、羽がくっついていたのだった。
「これは、羽だね。だから何なのか僕には分からないけど」
「ご、ごまかさないでください! つまり、春樹君は会ったんですよね?」
さて、ココに着てさらに訳の分からないことに宮久地まで訳の分からない世界の人間だったようだ。しかしおかしいな。宮久地と僕はそれなりに長く顔を合わせてきたはずだが、そんな訳の分からない世界の人間の怪しさなんて感じなかったのに。
「……というか、ついさっきまでいたよ」
「そ、そうだったのですか!? もう、マリアは何しているんですかー!」
「そして今僕が気になっているのはマリアとやらより、君のことだよ」
ここまで普通じゃないアピールしといて、普通であるということが通るわけがないのだから。
「え、あ、ううう……それはそうですよね」
なぜか両手を組んでもじもじとしているが、僕には関係ない。さっさと真相を教えてもらいたいだけなのだが。
と、ここで何かを決めたように僕の方を向き直る。
「そ、それじゃ今から公園に来てくれません……ですか?」
「行くのはいいけど言葉が妙なことになってるよ。というか盛大に割ったお鍋はどうするの?」
「それだったらもう直ってるから、気にしないでいいですからね!」
確かに、足元で割れていたはずのお鍋が玄関の横の靴を入れる棚の上で威風を放っていた。これは、ますますもって宮久地が普通でなくなってきたな。まぁいいけど。
「じゃあ、行こうか」
そう言って僕ら二人は太陽も沈んでいる中、公園へと歩き出していた。
そういえば、僕の睡眠はどこへ行ったのだろう。まぁいいか。
「それじゃ、話します」
「どうぞ」
時刻は既に午後七時を過ぎている。だから、いかに天下の公園とはいえ、人の気配など感じられないほどに、周辺は暗闇に包まれていた。今、僕らの上を照らしているのは公園の街灯ばかりの、本当に微笑ましいくらいの明かり。
「その、私は、人間じゃないんです」
「そうなんだ」
「驚かないの?」
「いや、既にそういう予感はあったし。この世に悪魔がいることもさっき調べたからね」
まぁ、インターネットで検索掛けただけのレベルだけど。
「つまり、その、私……天使なんです!」
「へぇ、天使」
悪魔がいるくらいだし、対になる存在くらいいるのは普通か。
「あの、驚かないの?」
「いや、悪魔がいるなら天使がいるのは普通だと思うんだけど、変かな」
「ええと、変じゃないんですけど……あれ? うーん……」
宮久地はさっきからなにをそんなに悩んでいるんだろう。僕が悪魔や天使を受け入れることがそんなに変だろうか。大体悪魔を目の前で見たのだから信じるも信じないも無いと思うわけだが。
「とにかく、証明しますね! 公園に来たのもそのためでもありますし!」
そういうと宮久地は、両の手を胸のところで組むと、何事かを一言二言呟いた。そうすると、彼女の体がうっすらと発光し始めていることに僕は気がついた。
宮久地の体は、いや、体だけでない、服装も既に違っているし、何よりも僕が知っている宮久地は黒髪だったはずなのに今の彼女は銀色がかった白髪へと一瞬で染まっているのだ。そしてなにより、そんな彼女の頭の少し上で、すばらしい光沢をしているリングがぽっかり浮いている。さらには、さっきの女の子のように宮久地にも翼が生えている。違うのは、その翼がとてもふわりとした白い翼だということだ。
「宮久地……」
「やっぱり、驚きますよね。 こんな体にいきなりなっちゃったら……って、春樹君!?」
彼女の言葉を聞く前から僕は行動を開始していた。まず頭髪だ。なんていっても急に変わる髪の毛なんて見たことも聞いたこともない。さて、宮久地の髪には何度か触ったことがあるような無いような気がするがそんなことは関係ない。なんていったってこのリング。どういう理由で頭上に浮いているのか。そもそもこれは何でできているのか、気になることは多い。とりあえず手触りを確認してみた。
「あ、ああああ、ちょっ、ふやあ、春樹くん!?」
宮久地がなんか言っているが無視しよう。このまま調査を続けさせてもらう。服装の変化もすごく興味深い。今まで着ていたはずのセーターらしき服がこれまた瞬間的に何の素材でできているのかもわからないものになっているのだから。首周り、肩、脇と触っていくが、この手触りは今までに感じたことがない。おそらく、これも人間の世界にはないものでできているからこそなんだろう。
そして、やっぱりこの翼だ。あの女の子にもどういうわけかあったが宮久地の場合、突如として現れたわけだからな。こいつはもう気にするなというほうがおかしい。そんなわけで現在わさわさと僕はその翼を触っているわけだ。
「あっ、あっ、春樹、く、ん……!」
「すごいな宮久地、変わろうと思うだけでこれだけの変化をするなんて」
「待ってくだ、さ……そんな風に触っては……ひゃあ!」
それにしてもふさふさだ。あの悪魔の女の子の翼はもう少し硬い印象があったけど、やはり天使というだけあってその羽ひとつひとつがとてもやわらかい。その先端から根元のところまで。根元、つまり生え際にあたる部分はさらにすごい、血流のような温かな脈動だって感じられる。見た目がいかにこの世界の常識から外れているといえども根本的なところではあまり違いはないということのだろうか。
「い、いいかげんにしてください!!」
「うご」
と、僕はあの悪魔の女の子から突き飛ばされたように、またしても吹き飛ばされてしまった。やれやれ、僕は調べていただけなのに、やはり人というのは思うに忙しすぎる生き物じゃないかと思う。あ、しかし宮久地は人間じゃなくて天使か。
「はぁ……はぁ……と、とにかく、これで私が天使であるとわかりましたね?」
「げふ……あ、ああ、十分すぎるほどに理解できたよ」
「そうでしょうねーあんなにべたべた触ればわかってくださいますよねー」
さて、宮久地が何を言っているのか僕にはよくわからないがそんなことよりも、宮久地が天子って言うことの話は本題ではなかったはずなのだが。
「それより、もう一つ話があるんじゃなかったかな。 確か、マリアだったか」
「ああ、そうでした。 春樹君が今日会ったはずの悪魔の女の子についてお話しないといけませんね」
そういいながら、宮久地は頭のリングや背中をやたらと手で直しながら、僕に話し始めた。それにしても、翼を直すのはなんとなく髪の毛の感覚でわかるのだが、あのリングを直すのは何か意味があるんだろうか。あれの位置くらい念じたりすることでどうにかならないものだろうか。
「それで、もしも人違いだったら怖いのでもう一度、あの羽見せてくれませんか?」
「どうぞ」
僕は、ズボンの右ポケットから例の黒い悪魔の羽を取り出すと、宮久地に渡した。宮久地はそれを何度かくるくると回したりひらひらとさせたりすると、うん、と一回首を縦に振ると僕に返してきた。
「やっぱり、あのマリアのものでした……」
「ふうん、そうなんだ」
そもそも、マリアって誰なんだ。というか、悪魔にしてはずいぶんと優しそうな名前だなと僕は思った。
「それで、マリアというのは私のお友達なんですよ。この世界にくる前はそれなりに遊んでいました」
それなり、という部分が若干気になるが、まぁ許容範囲だろう。
「それで君は一足先にこの世界にやってきて、何らかの仕事をしていた。しかし、あるときになって彼女もこの世界にやってきて、それで出会ったのがこの僕だった。 そうだろう」
「……は、はい。 まさしくそうなんですけど……えーと、あれー?」
導き出される推理を言っただけなのに。いったい何をそんなに困ることがあるというのだろう。それとも彼女はこの僕が数十分にわたってうーんうーん、と頭でもひねっていろとでもいいたいのだろうか。
「うーん……まぁ、いいことにします。じゃないと私が保てません!」
と、彼女がやけに誇らしげに上に向かって宣言しているわけだが。さっぱりわからない。
「君の言いたいことがよくわからないけど、大体これで合っているんだろう?」
「ええと、はい確かにそうですー……それで、今後のことなんですが」
「今後?」
今後、と言われても特に思いつくこともないのだが。宮久地が勝手にミスをして自分が天使だとバラしたのだから、彼女が悩むことはあれども僕が悩むことはないと思うのだが。
「マリアのことですから、たぶん、春樹君にこれからちょくちょく付いて回ると思うんですよ」
「……本当に?」
「はい……」
なんということだ。また彼女を調べられるのか。
いや、そんなことより僕の睡眠がとられてしまうことのほうが問題だろうか。うん、これは悩みどころだ。そして死活問題だ。車でいうならガソリンがガソリンスタンドまで持つだろうかというくらいの問題で死活問題だ。
「悪魔というのは、人間を悪い道に引き込もうとするのが元来の仕事ですから、だから春樹君を悪い道に誘うためにマリアが追っかけてくるかなーと……」
「ふうん、悪魔の仕事か。 大体予想通りだな」
というか、インターネットに書いてあった。
「それで、大方天使の仕事って言うのは人を良い方向へと導いてやるんだろう」
「あ、あたりです……」
それもインターネットに書いてあったことだが。
「つまり、君がこの世界にいるのは役目を果たすため、か。 ずいぶんとご苦労なことだなと僕は思うよ」
「……そういうつもりでいいことをしてるつもりは」
「まぁ、いいんじゃないかな。 天使という役割があるわけだし、何も悪いことではないと思うし」
「ち、違うんです! わ、私が春樹君におすそわけをしたりするのは、その……」
と、そこまでいうと、彼女は言葉をとめて、そのまま黙りこくってしまった。何がどう違うのか、僕にはよくわからないが。まぁ彼女が違うというなら違うんだろう。何かが。
「まぁ、いいよ。 話はわかったし、帰ろうか」
「……はい」
僕が公園の出口に向かって歩き出すと宮久地も後ろをついてきた。その足取りは、どこか重たげだったのが気になったが、今は家への道を歩くことに集中することにした。
後ろを歩く彼女の姿はもう、いつもどおりの"宮久地芹奈"だった。
真っ暗闇の帰り道を、二人でぶらぶらと歩いていると、背後から宮久地の声が聞こえた。
「あの、春樹君」
「なんだい」
「……私のこと、どう思ってますか」
「どうって……」
毎度毎度、おすそ分けを持ってくる変わり者の隣人だと思っているわけだが。
「昔からこうやって過ごしてきた、幼馴染、そう思ってませんか?」
「そうかもしれないな」
「……違うんですよ」
「違う?」
僕はここではじめて、彼女の方へと振り返った。そこには、スカートのすそをぷるぷると震えながら掴んで、涙を浮かべながら話し掛けてくる彼女がいた。
「春樹君が知ってる私の記憶は、みんな私がこの世界にやってくるときに植え付けた偽りの記憶っ。 だから、私はあなたと幼馴染でもなんでもないんですよっ!」
そして、彼女は泣き出した。時々しゃっくりを混ぜながら、むせび泣いていた。
思い返してみれば、僕は宮久地との直接的かつ具体的な記憶はないかもしれない。しかし。
「確かに、君と僕は幼馴染ではないかもしれない」
「……ひっ、ふぇ……?」
「けれど、君が僕にいつもおすそ分けをしてくれたことは、偽りじゃないだろう」
「あ……」
ぽかんと、口を開ける彼女を横目に、僕はもう一度帰り道へと向き直った。
「帰るぞ」
「……はい!」
心なしか、二度目の彼女の足取りは、最初よりも軽かったような気がした。
「ふむ、眠いな」
悪魔の女の子が家で眠っていた、その翌日。実に普通の一日だった。
起床するときも、学校に登校するときも、授業を受けているときも、下校するときも、何らおかしいことなどなく。まぁ強いていうと宮久地がるんるん笑顔で僕に弁当を渡したくらいで特に何もなかったわけだが。その際に数人の男子から睨まれていた気がするがそれもどうでもいい。
そんなわけで僕は睡眠を楽しもうとベッドに潜りこんでいる真っ最中なのだった。
「やっぱり、眠っているときが一番幸福な気がする――」
そうして、僕は目を閉じた。そう、目は閉じた。
次に響いたのは無機質なインターホンの音なんかではなく、トラックが衝突したようなそんな爆発的な破壊音だった。
音の原因は明らかに一階からのものだったので、僕は落ちかけていた意識を無理やりに覚醒させられた状態でその原因を確かめることにした。
そこにあったのは、惨状だった。
階段から下りて、右の方にはリビングとキッチン。そして左には玄関があるわけだが、目の前に見えているのはなぜか玄関の扉だった。様々なものを巻き込んできたらしく、一部の靴はリビングのテーブルにまで飛んでいる始末だ。
ここでようやく僕は玄関の方を見た。そこには、これらの惨状を生み出した張本人がすごい仁王立ちをしてこちらを睨みつけていた。
「せ」
「せ?」
「責任を取りなさいよぉぉぉぉっ!!」
「……は?」
前略、家族へ。僕は唐突に悪魔の女の子から責任を取れと言われたのですがどうすればよいのでしょうか。
「あれだけ弄繰り回しといて、アンタは……アンタはぁぁ!!」
追伸、おまけに靴入れの上にあった花瓶まで投げつけられたのですが僕には良く分かりません。
「……ええと、とりあえず君はなんなんだい?」
「フフフ、良くぞ聞いたわ! そう、私こそ後に七大悪魔に名を連ねるであろうマリアントワージュ・セロディアス――」
「やっぱりあなただったんですね、マリア」
「ふぇえ!? セリナぁ!?」
壮大な自己紹介。続いて訪れたのは僕の隣人宮久地芹奈だった。二人が以前友達だった、というのは本当か分からないが、これで少なくとも顔見知りであることは間違いないだろう。
それにしても、やけにうろたえているな。ええと、名前は確かマリアだったか。さっきまで高らかに名前を叫んでいたはずなのに今では汗すら浮かんでいる。
「それにしても、今でもあの妙な口上を使っているんですね」
「な、なによぉ、いいじゃないのよ私がどんな風に自分の名前を名乗っていたとしても!」
「ええ、そうですね。 ただし、その名前が本当の名前なら、ですけど」
「うぐぅ!」
どうやら、さっき名乗ったマリアントワージュ・セロディアスなんちゃらというのは偽名だったらしい。すでに宮久地が正しているので証明も何もないが、宮久地の指摘を聞いてからマリアの汗の量が増加したので間違いないだろう。
そんなことより、僕にはもっと大事なことがある。
「それで、マリアだったか」
「マリアントワージュ・セロディアス! マリアって言うのはやめて」
「じゃあ、セロディアス。 君に聞きたいことがあるんだけど」
「な、何よ」
「僕の家は誰が直してくれるんだ?」
「知らないわよそんなの! 聞くならもうちょっとマシなこと聞きなさい!」
やれやれ、どうやら僕の家の玄関が吹き飛んでリビングがグチャグチャになっていることは彼女にとっては取るに足らないことのようだ。どうも、彼女以外の物は通行に邪魔であっても障害物以下の評価しかもらえないらしい。
「ごめんなさい、春樹君。 あとで私が直しておきますから」
ほう、これだけの破壊でも直せるとは、天使って便利だな。四日前に書けなくなったボールペンも直してもらえないだろうか。
「ちょっとセリナ、こんな奴の家なんて直す必要ないわよ?」
「でも、だって、私は天使だから。 それに……」
そこまでいうと僕の方をちらっと見た。いったい何だっていうんだ。
「と、とにかくこんなことやめて今までどおりに仲良くしよう?」
宮久地が右手を差し出す。しかしその右手が握られることはなかった。
「ふざけないでよ……」
「え?」
「そうやって天使、天使って、そんなんだからセリナもオヤジも!!」
「きゃあ!」
怒りの色を見せたマリアが宮久地を突き飛ばす。いきなりのことに対処できなかったらしく宮久地は靴入れに思いっきり背中をぶつけるとそのままうずくまってしまった。音からして結構な勢いでぶつかったんじゃないかと思う。
「……池田春樹!」
「うん?」
「あんたは私がぜえったいに悪の道に堕としてやるんだから! 首を洗って待ってなさい!」
というと、すでに扉のなくなった玄関から彼女は出て行った。
とりあえず、吹き飛ばされた宮久地のそばに僕は歩み寄った。
「大丈夫か?」
「は、はいなんとか……少しだけ痛いですけど」
「そうか……うんと、少し待ってて」
「え?」
ええと、確か階段の下の小さいスペースに救急箱が置いてあった気がしたんだけど。買いだめのトイレットペーパーや非常食を押しのけると、その奥にちゃんと救急箱があった。とりあえず救急箱から消毒液とガーゼを取り出すと宮久地のそばに戻る。
「見せて」
「え、いえそんな、このくらい……」
「いいから、背中を見せて」
彼女は数秒の間、考え込むように下を向いていた。けれど、僕の言葉に押されたのか首をこくりと縦に振ると、服をまくって怪我をした個所を僕に見せてくれた。いくら天使といえども、怪我をしないというわけではないみたいだ。ぶつけたところが、少しだけ青くなっていた。
「やっぱり、少し打ち身になっているな」
「は、はあ……そうですか」
「それに、体温も少し高いように思えるけど、風邪でも引いた?」
「い、いえ! それは、ち、違うんです!」
何が違うのか僕にはよくわからないが、彼女が違うというならそれは違うのだろう。たぶん。
僕は消毒液を怪我した場所に塗りこむと、そこにガーゼを貼った。確か打ち身をしているなら冷やす必要があったはずなんだけど。
「あとは冷やせばいいと思うけど、氷でも取って」
「あの、春樹君……私は、もう大丈夫ですから」
「けど、処置は完全じゃないよ」
「いえ、いいんです。 あとは自分で治癒できますから」
服を戻して立ち上がると、ゆっくりとこちらを向いた。顔を伏せているためよく見えないがやっぱり少し赤い気がする。
「その前に、春樹君のお家、直しますね。 ご家族が帰ってきたら大変ですから」
そうすると宮久地は両手を組んで、僕には決してわからない言葉で、昨日の公園の時みたいに呪文を唱え始めた。それはまるで、呪文というよりは一つの歌を歌うかのような、そんな美麗さを含んだきれいな言葉だった。
周辺が一段と輝いて、それが僕の目の許容量を超えたと思った次の瞬間には、荒々しく吹き飛んでいた扉はきちんと玄関に付いていた。それだけじゃない。粉砕されかけていた靴入れは以前と何も変わらない状態になっているし悲惨なことになっていたリビングの方もこれまたマリアがやってくる前の状態にきっちりと元に戻っていた。
僕がこれらの一連の変化に驚愕していると、背後から扉の開く音が聞こえた。それは、宮久地が扉に手をかけたからだった。
「…………ありがとう」
それだけいうと、そのまま彼女は帰ってしまった。
後に残ったのは、僕が救急箱を引っ張り出したという、その事実しか残っていなかった。
「首を洗って待っていろ、か」
次の日、僕は学校の屋上にいた。なぜか、と問われても特に答えようがない。なぜならここにいるのは僕の気まぐれでしかないからだ。ちなみに、時間なら今ごろはきっと五時間目でも始めているころだろう。なぜ授業に出ないのか。それならまだ答えようがある。理由は簡単だ。あの悪魔の女の子、マリアが気になるからだ。
首を洗って待っていろ、などと言うくらいだから、学校で授業を受けているときに例のごとくバサーッと現れてくれるんじゃないかと思い一時間目から窓をチラチラしていたが結局現れなかった。おまけに教師からはとてもにこやかな表情でチョークを投げつけられるし、なんて痛い一日だろう。少しだけ期待していた分、心も痛い。
「あー、見つけた!」
心の中で浮かべれば何とやらだ。頭で考えただけで現れてくれるなんて、それだったら一時間目から来てくれたっていいんじゃないだろうか。
「どうも。 名前はマリアだっけ?」
「マリアントワージュ・セロディアス。 言っておくけど、三度目はないわよ」
鉄柵の向こうから、思い切りにらまれた。ちなみに、現在僕がいるのは飛び降り防止用の鉄柵のすぐそばだ。だから、必然的にマリアがいる場所は鉄柵の向こう側、つまり空中ということになる。
しかし不思議なのはマリアとほぼ同じか、少し小さい程度の大きさの翼でなぜ飛ぶことができるのだろうということだ。ゆったりとバッサバッサとはためく黒い翼。やはり悪魔や天使にはまだまだ理解のできないことが多いみたいだ。
「それで、セロディアス。 どうして早いうちに僕に会いに来なかったんだ?」
こっちは今朝からずっと意識していたのにどういうことだ。僕がベッドから起き上がるときも朝食を食べるときも着替えをするときも歯を磨くときも宮久地といっしょに学校へ通学するときもホームルームが始まったときも授業が行われているときも宮久地からお弁当を渡されたときも昼食を食べているときも僕は気にしていたというのに、これじゃ拍子抜けもいいところだ。
「だって、その、アレよ」
「……あれって何だ」
「ア、アレはあれよ! 悪い!?」
「いや、あれって言われても僕にはわからないし」
「ムグググ……な、何よ! だって恥ずかしかったんだもんっ!」
頭から煙でも出てくるんじゃないかっていうほどに顔が真っ赤なんだが、大丈夫なんだろうか。なんか微妙にふらふらしてるし、この子も風邪でも引いてるんじゃないか。
「恥ずかしい?」
「ぜんぜん知らない人ばっかりいると恥ずかしいの! しょうがないでしょ!?」
何がどう仕方ないことなのか僕にはわからないが、思うに人を悪の道に誘惑しなければならない立場としてそれは致命的な弱点なんじゃないかと思えるんだけど。
「そうなのか」
「そうなの! 私がそうって言うんだからそうなの!」
「ふうん、ところでずっと気になっていたんだけど」
「何よ」
「責任って何のことなの?」
「ぶほぉ!」
疑問をぶつけただけなのにすごい勢いで口から色々飛んだんだけど。とりあえずツバがかかって気になる。
「な、なななななななな!?」
「何を驚いてるのかわからないけど、君が言いだしたことだよ」
「それは、その、責任は責任よ!」
「いや、何に対しての責任なのかが知りたいんだけど、僕は何かしたかい?」
「何かって、あんただってそりゃ……あうう……!」
また赤くなったぞ。本当に、僕が何をしたっていうんだ。思い当たるのは彼女を調べたことくらいだけど、変なことは何もしてないはずだけどな。
「と、とにかくあんたはさっさと悪の道に堕落すればいいの!」
結局答える気はないらしい。また理解できないリストが増えそうだ。それにしてもさっきから彼女が言う悪の道っていったいどういうことなんだろう。
「それで、僕をどうやって悪の道とやらに引きずり込む気なんだい」
「…………えっと」
なんかいきなり考え出したぞ。僕はてっきり悪いことへの魅力でも語って自発的にそうさせるものだとばかり思っていたんだけど。
「あーもう、こうなったら実力行使!」
「うぐっ」
ありのままに今起こったことを話すと、鉄柵の向かいにいたはずのマリアが飛び上がって僕に向かってきたなと思っていたら屋上の壁に押さえつけられていた。
「悪いことしないなら、殺すわよ?」
彼女の左手に首根っこを握られていることで、僕は満足に動くこともできやしない。さらに、いつの間にやらマリアの右手にはバカみたいにでかい三又の槍が握られているし。というか、悪いことしないと殺すってなかなか聞かない言葉だな。
「うく……かはッ……」
「フフン。 やっぱり悪魔はこうでなくっちゃね。 心地良いわ」
しかしこれ、意外とマズいかも、しれない。呼吸をふさがれているからだんだん思考もまともに、考えられなく……
「ほら、早くイエスって答えなさいよ。 今なら下僕程度で勘弁してやらないこともないわ」
いや、こたえたいのは山々だけど、首が、ふさがって、答えが……うあ……
「あ、が……」
「下僕じゃ満足できないのかしら? じゃあ執事ならどう? 今だったら私専属の執事にでも」
「いいかげんにしなさいマリア!」
「ひゃう!?」
そのとき、屋上で一つの怒声が悪魔の少女に向けて放たれた。聞き間違えるわけも無い。その声は明らかに宮久地のものだった。声に驚いたのか僕の首からその手は離されていた。今のうちに呼吸はさせてもらおう。
#endregion
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: