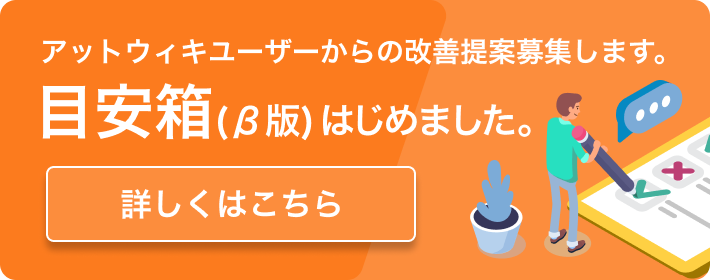「リレー小説 3」(2014/12/17 (水) 21:28:16) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
【西口 2014.07/01】
禁書騒動から早くも二週間が経過した今日、学園内は気だるげな雰囲気に包まれていた。
何を隠そう、本日から六週間もの夏季休暇の始まりであるからだ。
休みだキャッホイ、と騒げるほど、この季節にいい思い出は無かった。
が、やはり学生にとって休暇というものは至上の美酒にも似た魅力を持っているもので、知らずにやけてしまう。
さあ何をしようか。
宿題の類は一週間も経たずに終わるだろうから、まずはそれからか。ああ、それよりもエクリエルのお見舞いに行かなくては。
行こう行こうと思ってはいたが、主にダミアンのせいで先延ばしになってしまっていた。お詫びに手土産でも持って――いや、逆に怒られるか。何事もなかったかのように行こう。ルカでも誘って。
そうだ、ルカ。
事件以来会っていなかった。怪我はなかったとはいえ、”竜”なんていう御伽噺モンスターに襲われた上に
エクリエルの次くらいに慕っていたらしい副委員長が死んでしまったのだから、大分沈んでしまっているのではないだろうか。
俺が行って出来ることも限られているだろうが、何かしてやれないだろうか。
そんな事にも気付けないほど、ここ二週間は激務だったといえる。
何となく仲良くなったダミアンに引きずり回されていたというのもあるが、それ以上に、俺に考える余裕がなかったという点が大きかった。
妹の事を無闇に穿り返され、平時なら卒倒しているであろう量の血を見せられ、何だかよく分からない出来損ないの神様とやらと戦い
そして――龍の力を振るう破目になった。
結局あれ以降、白龍は一度も姿を表さない。何処で会ったのか、何故俺と”契約”なぞを交わしてくれたのか、どうして今の今まで沈黙していたのか。泉のように湧き出る疑問、質問には一切の答えが出なかった。
「ボクのお願いを聞き届けてくれるなんて、やっぱりお兄さんは賢いや! お礼に僕の身体を好きに弄んでいいよ!」
と怖気が走るような台詞を吐きながらやってきた赤龍(何故かあの埒外の情報量(チカラ)は感じなかった)に聞いてはみたのだが、飄々とかわされてしまった。
もしこの学園に入る前にあの力を自在に操れたのなら、サトリの汚名を雪ぐことが出来たのかもしれない。
意味がないとは分かっている事だが、ついそう考えてしまう。そして、結局俺は出来損ないなんだな、と痛感する。
妹に全部背負わせて、天才の名を恣にして。そしていざ『業』を背負った途端、伏神の「符術」、書記魔法以外の一切を扱えなくなるほどになってしまった。
俺は生まれてから今に至るまで、ずっとあいつに護られている。ただ兄だからというだけで、一人の少女に、己に向けられるべき罵倒を全て押し付けてしまっている。
「死にたがり」が治ってきたという事実が、彼女への思いが薄れてきているように感じられて、少し自分が嫌になる。
それでも、「ご健勝に」と願って逝ったサトリの為にも、「お前だけは死なないでくれ」と涙した兄さんの為にも、自殺する事だけはけして出来ない。
例えどんな状況になろうとも。
「ごきげんよう、ミスター。お加減は如何ですか?」
まずはルカを見舞おうか、と寮を出た途端、清流のせせらぎを思わせる涼やかな声で話しかけてきたのは、一人の少女。機界人のクロガネである。
陽光を反射し、鈍く輝く髪を風に靡かせながら、スカートの裾をつまんだクロガネはいつも通り、芝居がかった礼をする。
シルクハットでも被っていたら、こちらも仰々しくやり返すのだが。
「ああ、おはようクロガネ。加減ったって、俺別にたいした怪我してないぞ」
「お気になさらず。時候の挨拶のようなものです。それに、大怪我ならなさったではないですか」
と、クロガネが俺の左腕を指差す。
――己の中で、思考が少しだけ剣呑なそれへと切り替わったのを感じる。
「……何で知ってる?」
「見ていましたから。偽副委員長、いえ、ドネルクラルが委員長とルカ氏を磔にしているところから、ずっと。あれは見ていて滑稽でしたね」
ははは、と抑揚のない笑い声を漏らすクロガネ。その瞳の奥には、機械的な無機質さと共に、こちらを試すような輝きが見て取れた。
「ッ……! あいつの正体分かった上で、黙って見てたってのか!?」
「あれと真正面からぶつかり合える兵装は、学校の敷地内には転送できませんから
あのお二方の事についても、貴方をおびき寄せる為の餌ですから、無闇に殺す事はないと判断した上での行動です。隙を窺っていた、と言ってほしいですね」
「どっちでも同じだ、そんな事……!」
とは言いつつも、彼女の言う事は正論であるという事は認めざるを得ない。
俺だって、真川の正体があんなのだったと知っていたら、似たような事をしたかもしれない。流石に行かないという事はないが。
ルカやエクリエルが人質にとられているからこそ、冷静に、慎重に行動しなければならない。
ドネルクラルが俺をおびき寄せるために、ルカとエクリエルを浚ったという事も分かっているのならば、あれの前に姿を現す理由は絶無と言っていいだろう。
分かっている。これはただの八つ当たりだ。
見知らぬ他人が、サトリの事を知っていたという苛立ちを、人間的な反応という隠れ蓑に潜ませてクロガネに投げつけているに過ぎない。
「……悪い、言いがかりだった。お前は正しいよ」
「いえ、道徳的には褒められた行動ではありませんので。それに、責められるのは当然かと。
結局あれの処理を貴方に押し付けてしまいましたし。本来ならば、竜殺しは私の役目なのですから。深く、謝罪いたします」
「竜殺しが、役目?」
あまりにも現実離れしたその単語に、土下座をしようとするクロガネを静止するのに少し時間を要してしまった。
下級生の女の子を土下座させる高等部二年生。ううん、外聞が頗る悪い。
慌てて肩を掴んでクロガネを制止すると、お決まりのようにセクハラだと詰られた。俺は起こってもいいと思うが、その問題は後回しだ。
竜殺しが役目とはどういうことか。何故真川(偽)の正体を知っていたのか。そもそも竜とは何なのか。
矢継ぎ早に質問責めする俺を、今度はクロガネが制止した。
とりあえず場所を変えましょう。促す彼女に連れられ、俺が向かったのは旧校舎。
大規模降霊魔法の暴走により、それはもう尋常じゃなくおどろおどろしくなっているという学園内屈指の魔境である。
やれ巨大な鋏を持った小柄な男が徘徊してるだの、チェーンソーを持ったホッケーマスクの男が潜んでいるだの、人の夢の中を飛び回る殺人鬼が封印されているだの。
そんな噂が恐怖と共に、実しやかに語られている。
「死にたがり」の頃さえ近づきもしなかったその場所に、俺はクロガネと共に向かっている。
何でここなんだ? もっと別の場所があるだろ。
道中、言いすがる俺にクロガネは「怖いんですか?」と、無表情な彼女にしては珍しく、心底馬鹿にしたような表情で言い捨てた。
見事な煽りだ。年下の女の子にこう言われて動かなければ男じゃない。
それに仮に俺が歩みを止めたとしても、この調子ではクロガネは一人で行ってしまう事だろう。それだけは決して出来ない。
……けして、旧校舎に近付くにつれ薄暗くなっていく林道を、一人で帰るのが怖いわけではない。けして。
何故旧校舎がこんな僻地にあるのかと、この学園に来たばかりの人間が、時たま口にする疑問だ。
俺もその例に漏れず、疑問を解消するために図書本館にしばらく篭った事がある。
どの資料を紐解いても、事故があった旧校舎を隔離するために、敷地を拡張したとしか書かれていなかったが
何故かその事故が起こった時期がどこにも書いていなかった。
更に、かなり長い年数勤めているらしいグダグダエル先生も、赴任した時にはすでに事故が起きた後だと言っていた。
その他にも、事故以降放置されたとはいえ、幾らなんでも青々と茂りすぎている樹木や、設立当初からあったという寮の跡地の類が全く無いことなど、疑問点は多々あった。
それを解消したいがために、一度だけ旧校舎に近付いたことがあるが、怖すぎたのですぐに逃げ帰り、旧校舎関連のことは思考と記憶の外に放り出していた。
陰陽師の家系だからといって、怨念の類に耐性があると思うなよ。
旧校舎に一歩一歩近付くたびに、その疑問が再び湧き上がってくる。
疑問が氷解する可能性に心が躍ると同時に、どんどんと暗くなる道に恐怖心も沸きあがってくる。
クロガネがいる分、前回よりは心強いとはいえ、怖いものは怖い。せめて【怠惰】は持って来るべきだったな。
旧校舎の、年月を経てもなお異様を誇る、巨大な鉄扉。
あらゆるものを拒絶するが如く、中にある何某かを内奥に封じ込めるが如く硬く閉ざされたそれを前に、足が竦んでしまっている。
クロガネは何事もないように平然としているというのに、情けない。
「中に入りましょうか。そこならば誰に聞かれることもないでしょう」
「いや、ここでもいいだろう。誰もこんなとこまでこねえよ。そもそも校則違反だぞ」
努めて冷静に、恐怖心を悟られぬように。そう心がけたつもりだが、やはり彼女には筒抜けだったようで。
「そう怯えずとも危険はありませんよ、ミスター」と、彼女はひどく穏やかに言った。
そのあまりにも自然な表情からは、普段の無機質が微塵も感じられなかった。
「立ち入りが禁じられているのは、私以外の人間だけです。いわゆる怨霊に襲われる人間も。
私と、私が許可した人間に対しては、旧校舎(ここ)は広くその門扉を開きますよ」
これこのように、とクロガネが扉に触れた途端、かすかに聞こえた音。
あまり聞き覚えの無いそれは、たしかモーターとかいう機械が駆動する際に出す音だ、と昔の記憶を穿り返す。
その音に連動するように、大扉が老朽など微塵も感じさせぬ滑らかさで、ひとりでに開いた。
魔力反応は一切感じ取れなかったということは、全て機械による作用という事だろう。
旧校舎の大広間。鉄扉によって外界と隔絶されたそこに、一体どんな光景が広がっているのか。
貧困な想像力で思い浮かべた数々の情景を、しかし現実派荒々しく踏み砕いた。
劣化している箇所は見受けられなかった。
老朽も、また。電気による灯り特有の、白色の光に照らされるそこは、外観の古めかしさとは真逆の空間だった。
壁や床を縦横無尽に走るケーブル類。用途の分からぬ計器類。涼やかな空気を吐き出し続ける空調機械。
魔術の類が一切無い、純粋な鉄と電気だけの空間。
学園内ではありえない、機械一色の内装。輸出入・製作ともに厳しく取り締まられている機械群が、溢れんばかりに内在していた。
おどろおどろしさなどとは、無縁。憎念など欠片も感じられない。
ただひたすらに、命令された計算を繰り返すだけの機械の群れ。度肝を抜かれるとはこの事だろう。呆気に取られるとはこの事だろう。
驚愕の声さえ上げることすらできず、俺は入り口の前で、足に釘でも刺されたかのように棒立ちになっていた。
「五界統合政府直轄機関『第六世界対策室』第七文室へようこそ、ミスター・ソウジ。歓迎いたします」
そう言って、いつものような恭しいお辞儀。
一度に提示された多数の情報に、頭がこんがらがる。
竜殺し。旧校舎の機械。政府直轄機関。第六世界。咀嚼して飲み込もうにも、あまりも多すぎる。
一旦整理させてほしいと告げる俺の出鼻を挫くように、クロガネが「両手を出してほしい」と懇願してくる。
特に断る理由も無いので、ほぼ反射的に彼女の言う通りにしてしまった。これがいけなかった。
思えば、この時全力で逃げていれば、後々の面倒は無かったのかもしれない。
差し出した両手に嵌められる、「8」の字をした鉄製の器具。反応の遅れた俺を思いやることも無く、クロガネは無情にも慣れた手つきで、その器具に鍵をかけてしまった。
本や映像でしか見たことが無いその器具。その名称はわざわざ言うまでもない程にはっきりしている。
手枷。それも機界製の最新鋭のモノ。
爆弾だの、テイザーだの、非人道兵器マキビシだの、逃亡を図った囚人を痛めつけるための仕掛けがこれでもかと詰め込んだ、引く程高い拘束器具。
「情報保持の為、身柄を拘束させていただきます。もう逃がしませんよ、ミスター」
それは天使の笑みと評すべき、至上の微笑み。パッと花でも開いたかのようなそれを、何故このタイミングで浮かべることが出来るのか。俺には理解に苦しむね!
◇
第六世界とは、”竜”を内在する非物質世界なのだと、俺を旧校舎内の何処かへと連行する道すがら、クロガネは語った。
竜。神のなりそこない。
世の管理者たる龍になる事を夢見るそれらは、しかし己の身体を持たないが故に、五界にそのまま顕現することは出来ない。
そこで彼らは、五界の人間の身体を媒介に、この世界に現れようとしているというのだ。
強い渇望を持つ者。欲望に飲まれかけている者。精神的に不安定な者の心を、甘言で以って弄し、一時的に力を貸し与える事と引き換えに、その存在を乗っ取っていく。
やがて精神をも飲み込まれた人間は、その全てを竜に明け渡し、晴れて竜はこの世に生を受けることが出来る。
ドネルクラルもそんな竜の一体であり、風紀委員・伊庭甲子郎の身体を乗っ取り、現れたのだという。
そしてクロガネは、竜を屠り、その存在を隠匿する「第六世界対策室」の一員であり、この学園にも、その任務の一環で入学してきたらしい。
「ミスター・コウシロウが竜だと気付いたのは、残念ながら副委員長が殺害された後です。
ドネルクラルの能力は、ここのセンサーをフル稼働させても看破できないもので、あれの正体に気づけたのはほぼ偶然と言ってもよいものでした」
沈んだ顔で、クロガネは呟いた。
クロガネ本人が言うには入学してから一年。対人コミュニケーションを不得手とする彼女が、風紀委員の一員として馴染めたのは、真川敦の存在が大きかったとの事だ。
エクリエルに代わり、風紀委員の陣頭指揮を執っていたという彼。
当然、人望もあっただろう。慕っていた者も随分多かったに違いない。ルカでさえ、彼の事を好いていたくらいだ。
真川のことはよく知らない。しかし、彼の死がどれだけ大きな損失だったかは分かる。
本当にどうしようもなかったのか。もしかしたら助ける事も出来たのではないか。
どうしようもなかったと、頭では分かっているのだが、自分を責めずにはいられない。傲慢だとは思うが、どうしても。
「今回の禁書騒動も、元を正せば私の対応の遅さが原因と言えましょう。
処理するチャンスは幾度もありましたが、どうしても副委員長の顔を撃ち抜くのを躊躇ってしまいまして。
その結果、貴方をあのような目にあわせてしまいました。申し訳ありません」
先導する彼女は振り返りもせずに呟く。消え入りそうになっていく語尾、震える声が。これ以上ない謝罪の意を示しているように思えた。
あれと戦ったことに、然したる心のしこりはない。
謝罪なんてするな。お前の反応は人として当然だ。そう言おうとすると、クロガネがくるりと振り返った。その顔にはいつも通りの無表情が浮かんでいる。
「と、情緒溢れる話を機界人から聞く事により、いわゆるギャップ萌えで恋に落ちる人間が多いと聞くのですが、如何でしたミスター・ソウジ。フォーリンラブしましたか?」
「お前ほんっと、こういうの台無しにするの好きだな!」
無駄に感情移入しちまったよ!
「さて、楽しい歓談はこのあたりで終了です。着きましたよ、ミスター。私の個室です」
楽しいという部分に大いに疑問が残るが、そこを突っ込んでは話が進みそうもないので、黙っておく。
そもそも話を進めたくもないし、今すぐ逃げ帰りたいのだが、未だに俺の両腕を戒めているえげつない手枷がそれをけして許さない。
政府直轄組織の一員だとか、そういう類の与太話を聞かされるとは流石に予想外すぎた。
いや、この巨大な機械設備を見るに、あながち嘘でもないのだろう。
第六世界云々のことはともかくとして、少なくとも学園の監視の目をここから逸らさせる程度の影響力を持つ組織が、バックについていることは間違いない。
ああ、帰りたい。しかし、クロガネに促されるままに俺はついていく。どんどんまずい所に首を突っ込まされているような気がするなあ。帰りたい。
クロガネの個室は、何も無いと言っても過言ではなかった。
壁面が青白く光る、正六面体の個室。部屋の中央に小さな円卓と、幾つかの椅子が置かれているだけだ。それ以外に何一つとして無い。
シンプルイズザベストとフォローするのも不可能だろう。
「シンプルイズザベストでいいんですよ、ミスター」
「心を読まれたッ!?」
鉄板ネタが出来つつある気がする。
「さて、本題に入りましょう。正直に言ってしまいますが、第六世界や竜のことに関して貴方にベラベラ喋ったり
事件の事を匂わせてここに連れ出したのは、貴方の監視・保護をする正当な理由が欲しかったからです。
それと言うのも、ミスター。貴方の存在は、一部の人間にいらぬ妄想を持たせてしまうのです。
ただの人であろうとも、神なる存在である”龍”の力を振るう事が出来ると。貴方の『中身』を仔細に観察すれば、神へと手が届くのではないかと」
淡々と語るが故に、その言葉の重みは尋常ではなかった。和やかな、砕けたような空気が、一瞬で凍りつく。
「”龍”と”竜”の存在に関しては、政府は大分前から知っていました。
それどころか、一部機関は竜の検体を集め、第六世界、並びに龍への干渉の方法を模索していたくらいです。
しかし、竜はともかく龍の事に関しては、研究は遅々として進んでいません。そんな状況で貴方のように、龍の力を宿した人間が現れてしまった。
これの意味する所は、わざわざ説明するまでもありませんね?」
竜の存在。第六世界の存在。それに対応する政府の組織。それに対する疑念は、もはや無い。
彼女は真実を語っている。ほぼ直感で、根拠なんて無いと言ってもいい。それでもだ。彼女は真実を語っているのだろうという、謎の確信があった。
「俺みたいなのは、今まで一人もいなかったのか?」
「肯定です。竜に蝕まれた人間の例は枚挙に暇が無いほどありますが、龍を内包した人間は、少なくとも我々のデータベースには存在しません」
我が事ながら愕然としてしまう。史上初のびっくり人間。特別といえば特別なのかもしれないが、嬉しさなど微塵も感じられなかった。
「そんな絶好の実験台、何をしても手に入れたいって事か……」
「ご安心ください。対策室は、そして私個人は、貴方を守りたいと考えています。勿論、監視や観測はいたしますが」
理解してくれとは言わない。受け入れてくれとは言わない。理不尽な事を言っているという事は分かっている。それでも。
「私はここに来て、初めて友人と呼べる存在に出会うことが出来ました。ルカ氏に、エクリエル委員長。彼らを悲しませたくは無いのです。
だから、お願いいたします。私に貴方を守らせてください」
分かっていっているのだろう、彼女は。
こういう頼み方をすれば、俺が断れないと。お前の身柄が危ないから守らせろ、では、余計なお世話だと言われる可能性があるという事を。
ペコリと頭を下げた彼女は、恐らく俺が承諾した後に、無表情で顔を上げ、言質を取ったと平然と言い放つのだろう。
だが、俺にNOの選択肢は無い。
苦笑を漏らしながら、承諾の返事をした後のクロガネの反応は、やっぱり予想通りで、少し笑ってしまった。
◇
日は未だ高い。
旧校舎でクロガネと分かれた俺は、一人帰路に着き、空を見上げていた。
一人で歩くひと気の無い道は中々に、さすがに寂しさを感じずにいられないが、無理矢理詰め込まれたいくつもの情報を整理するには、うってつけと言えた。
伊庭甲子郎。竜に乗っ取られたという彼には、一体どんな渇望が、欲望があったのだろう。
クロガネ。守らせてくれと言った彼女の言葉には、真摯さが感じられた。ルカとエクリエル、そして真川の存在は、彼女に何を与えたのだろうか。
竜。何故彼らは神などという途方も無い存在へとなる事を夢見るのだろう。
ぐるぐると回るいくつもの疑問。道中ではけして解消しないと思われたそれを、一旦脇へと置かせるに足る効果が、その電子音にはあった。
ポケットの中から感じる、微かな振動とともに鳴り響く特徴的な雅楽の音色。
知っている人間などそういないそれは、設定したはいい物の、今まで一度も聞けなかった。
心臓が早鐘のように打ち鳴らされる。掌が手汗でじっとりと湿っていく。
ゆっくりと取り出した携帯電話の着信者の画面には、「伏神劔(ツルギ)」と表示されていた。
「……も、もしもし?」
『おう、ソウジか。久しぶりだな。どうした、声が震えているぞ?』
洞穴に響くかのような低い声でありながら、その声音は優しさに満ちていた。
何年ぶりだろう。この学園に来て以来、一度も会えなかった。一度も声を聞けなかった。
もう一生会えないかもしれないと、何となく思っていた。
鼻の奥が、キューっと縮むような感覚を覚える。鼻声になりそうなのを必死に堪え、俺は電話口の声に応答した。
「悪い、ちょっと疲れててさ。久しぶりだな――兄さん」
【Kの人 2014.07/03】
あの一件で当時の当主――叔父を含めた継承者の大半が消失し、繰上げで伏神家の当主になった兄からの突然の電話は、聡治にとっては衝撃的であった。
家出同然の出奔を行い、ある意味伏神家の血筋だけで五界統合学院に転がり込んで以降、互いに連絡を取っていなかった。その上、先の騒動に関しての諸々の裏事情をクロガネから聞かされた直後であり、此れで動揺するなという方が、土台無理な話だ。
聡治は後ろめたさから連絡を拒み、連絡が来ないのも家を捨てた己を勘当した物だと聡治は思い込んでいたが、それはどうにも違ったらしい。
勘当した相手に、どうして、その様な優しい……事件以前と変わらない、しかし大人になったその声で話しかけられるだろうか。
思わず涙ぐみそうになった聡治ではあったが、竜の話が思考に差し込んだ為、ぐっと堪えて眼を細める。
あの一件は直接的には関わっていないとはいえ、兄も相当に心的外傷を負ったに違いない。
ならば喪失を補う為に何かを欲して竜に飲まれた可能性も零とは言い切れない。時期が時期だけに、聡治は一層、懐かしさに包まれるからこそ意識的に警戒の意識を高める。
『そうか、疲れた時には素直に休むんだぞ。お前は昔から、何かあれば頑張り過ぎる事があるからな』
高めるが、どうにも無駄になりそうだと表情を和らげる。
渇望が竜の餌となるのならば、竜の傾向もそれに従う。故に先のドネルクラルも龍に昇華する事を渇望し、其処から禁書盗難事件に関係する様々な事件を引き起こした。
仮に竜と化していたとしても、声色を聞く限りは、ぎらついた渇望は片鱗さえ存在しない。
「ああ、無理し過ぎない程度に頑張るよ。……ところで兄さん、突然の電話だけど何かあったのか?」
社交辞令的に聞いてはおくが、十中八九先の事件……其処で竜に殺されていた面々に関わってくるだろう。
龍へ昇華する事を渇望したドネルクラル……元々は伊庭甲子郎であった彼に殺められたであろう者は、現在行方不明になっている者を含み、校内外含めて十二名にも及んでいる。
殆どが校外の者であるか、自主退学後である為に騒動は表面化してはいないが、犠牲者は二桁もいるのだ。
犠牲者の誰かが伏神と接点があり、其処から情報収集の為に掛けてきたというのが、尤もらしい理由だ。
『ああ……いや、そうだな。んー……聡治は確か十六歳、だったか?』
「いや、もう十七歳だが」
『あ、そうか。……そうか、聡治ももうそんなに大きくなったんだな』
「言い回しが老人みたいだぞ、兄さん」
『……じ、自覚はあったけど弟に指摘されると少し傷付くな』
だったらもう少し言い回しに気をつけるべきだろうと、何かとうっかりしている所は変わらないなと、聡治は苦笑する。
どうしようもなく懐かしい遣り取りだ。
どうしようもなく懐かしい遣り取りだからこそ、もうあの頃には戻れないのだという現実が心を滅多刺しにしてきた。
最早慣れた痛みだ。
聡治は突き立てられた現実という刃を意に介さず、少なくとも言い辛くはあるが暗い話ではなさそうだと推測づける。
だが、そうなると今更電話を掛けられる理由がまるでなくなってしまった。
「……それで、落ち込む前に用件を教えて欲しいんだが。何でもない理由で掛けた、って訳でもないんだろ?」
『ああ。……あ、大丈夫。学院で起きたらしい事件とは別件だから』
「……いよいよ今更連絡が来る理由が見当たらないんだが」
『そう、だな。とりあえず叫ばれる覚悟が済んだから、そろそろ本題に移ろうか』
叫ばれる覚悟? と聞き返すよりも早く紡がれた爆弾的発言に、聡治は一瞬聞き間違えたかと感じた。
しかし繰り返し告げられたそれは間違いなく現実に起きた物だと脳が理解すると同時、聡治は無意識の内に声を上げてしまっていた。
◇
自室へ辿り着くなり、鞄を乱雑に投げ捨てて寝台に身を投げる。
ぎしりという軋む音はするが、流石に機界人の巨体も受け止められるように強化した材質で作られた寝台だけあって、びくりともしなかった。
そのまま意識を投げ出したい衝動に駆られた聡治ではあったが、ぐっと堪えて身を捩り、仰向けになって天井を見上げる。
「展開の速い小説でも此処まで突っ込まねぇぞ」
午前中にはクロガネから竜及びそれに纏わる関係機関や事情を聞かされ、一般生徒ならば踏み入る事もない暗部に踏み込んでしまった。
それだけでも十分な出来事だが、しかし兄である伏神劔から先程掛かってきた電話の内容は、方向性は違えど破壊力は同程度だ。
方向性は前者をダークファンタジーとするならば、後者はラブコメになる程度に方向性は真反対だ。
今年一番の盛大な溜息と共に、懐から携帯電話を取り出して通話履歴を確認する。
白昼夢ではなく、確かに兄から電話があったという事実が其処には表示されており、先ほどの発言も間違いではないという事になる。
「アホくせぇ……」
連絡通りであるのならば、間違いなく実家へと帰らないとならない用事が出来た事に他ならない。
そしてその用事は間違いなく、伏神聡治という少年にとって五指に入るほど重大な物に他ならなかった。
暫く無気力に寝台で横たえていた聡治ではあったが、緩慢に状態を起こして勉強机へと向かう。
どれ程時間を要するかは不明だが、下手をすれば夏休みを全て食われかねないのだ。
配布された課題を半ば作業的にこなしながら、夏季休暇の予定を考え直そうとし、結局纏まらなかった。
無論配布された宿題の内容など殆ど頭に入っておらず、休業明けの課題考査で戦慄したのは、此処では関係のない話であった。
◇
課題を終了したのが夏季休暇が始まって四日目明け方の話であった。
最終日も斯くやといった勢いで敢行された課題処理を片付けた勢いのまま、聡治は実家付近までの公共交通機関の経路と時間、必要経費を確認する。
明日の晩から夜行駆動機関車に乗って早朝に実家に最も近づく場所まで行き、其処からは一日と少し程の陸路になる。
五界統合学院での生活に慣れていたため忘れていたのだが、学院外ではまだ乗合駆動機関車が一般的ではない。
大分根付いては来ているが、生憎実家付近まで直行でいける物はまだ通っていない。
故に最も近づく場所からは自力での移動となるのだが、距離が距離である為、徒歩ならば一度野営を挟まなければならない。
費用にしても夜行駆動機関車は自由席でも高価であり、貯金を崩してどうにか足りる程度なのだ。
此ればかりは後日請求させて貰おうと思いつつ、聡治は確認した情報をメモ帳に書き残し、今度は明日の夜までにしておくべき事を脳内に列挙する。
ぱっと思いついたのが寮の管理人への里帰りの連絡だ。
一応学院側に里帰りで学院を一時離れる事に対しての申請を出したが、まだ承認されたという連絡は来ていない。
緊急時に書類に代わって寮長への連絡で済ませる事も可能であり、最悪二重申請になってしまうかもしれないが、そもそも部屋を空ける以上は伝えて置くべきだろう。
しかし此れは出発当日でも問題ない為、優先順位は低いなと考えた聡治は、他にすべき事を考える。
続いて思いついたのは、エクリエルの見舞いに、先の一件で不覚にも深部に踏み込んでしまった事に由来するクロガネへの連絡だ。
どちらも課題処理に入る前に片付けておくべき事案ではあったが、開始当日はそんな事を考える余裕は一切なかった。
現実逃避気味に課題処理を行っていた為に、その最中に行動するという考えもまるで思い浮かばなかったが為の遅延だ。
一先ず何時でも行えるクロガネへの連絡よりかは見舞いの方が優先度は高いだろうと、ルカを誘おうとした矢先であった。
着信を告げる無機質な電子音が炸裂した。
背面液晶に表示されていたのは間違いなくエクリエルという五文字であり、何の用だとも思うよりも早く、聡治は通話状態にしたそれを耳元に近づけた。
『私だ。一一〇〇に中央区商店街南口にて待つ』
時間にして僅か五秒程度。
一方的に用件だけを告げられ、一方的に通話遮断される通話は、エクリエルという存在の気質を知らなければ眉を顰めて然るべき物ではあった。
しかし乱層区画調査を含めた個人的な交流の最中で慣れた……傍から見れば調教されたと言っても過言ではない聡治は、静かになった携帯電話を静かに懐に戻し、天井を仰ぐ。
天井を見上げながら通話内容を関して考え、残作業の延長戦が始まった訳ではないだろうと、一先ずは安堵の溜息を吐く。
仮に残作業の延長戦開始であるのならば、高等部学生に人気な遊び場である中央区商店街に呼び出される道理は存在しない。
そもそも其処へ呼び出されるという事は、少なくとも彼女は既に退院済みという事に他ならない。
予定が一つ消えた代わりに一つ増えたなと、呼び出された理由について聡治は考える。
電話で理由を聞き返すのは簡単だが、説明をしなかったという事は、彼女にしてみれば現状の情報で十分理由を導き出せるという事に他ならない。聞き返すと、現地に到着するなり被虐主義者垂涎の絶対零度の視線に晒される。
大きく息を吐いた聡治は、一先ずそれを置いておき、十一時から用事が入った場合の本日の予定を考え直す事にした。
が、それは一瞬で終わる。
元々、特に予定もなく、今から予定を組んでいる状況なのだ。今更増えたところで変わりはしない。
そういえばと、証拠として学院側に回収されていたが、最近になって帰って来た破れた制服の上着を見る。
上着の制服の左袖は、大体肘の辺りから先端が失われている。真川敦の『伸びる居合い』を奪った竜、ドネルクラルの一撃によって左腕から断ち切られた為に切断されたのだ。
結局日付が変わり、明るくなった頃から風紀委員によって捜査が行われたが、あの戦闘に関しての痕跡は殆ど残されていなかった。
殆どと言うのは断ち切られた聡治自身の制服の布地程度であり、其処に竜が居たという痕跡はおろか、真川敦との戦闘の痕跡さえも消え失せていたのだ。
やたらと開放的な制服からは夢ではなく、間違いなく現実世界で戦闘があったのだが、踏み砕いたはずの灯篭流しの欠片が一片たりとも見当たらない事から、現状は有象無象の証言の一つとして処理されている。
今となっては、恐らく第六世界対策室の圧力が加わったのだろうという事も考えられる。
もしかしたら此れが呼び出された原因かもしれないと聡治は思う。
……風紀委員の活動によって被害を受けた一般学生への補填は、その規模にもよるがある程度は補償される。
今回は風紀委員の直接的活動という訳ではないのだが、ある意味で風紀委員会が語られぬ者の動向を早期に把握して対処しておけば発生し得なかった事案だ。
そうなればドネルクラルは別の手段で禁書を奪っていたかもしれないが、その場合は一般生徒である聡治が関われる問題ではないのだ。
そう考えれば十分に補填の対象であり、その購入の為に呼び出されたのだろう。
五界統合学院においては、確固たる制服は存在はない。
理由は五界から様々な種族が集まる関係上、単一の制服では対応出来ない為である。それは種族的な特徴であったり、思想的な問題であったりと、兎に角対応出来ないのだ。
それに対して学院は、学院が幅広く選定した物であればそれが制服として認められるという校則を定めている。
故に各学区の商店では様々な指定服が販売されている。勿論人間界に古くから存在する学生服も指定されているが、所謂私服と言えるような物まで含まれている為、適当に制服を補填すれば良いという問題ではない為、呼び出されたのだろう。
あとは書記魔法で使用した札も補填対象かどうか考えてみるが、制服代が浮かぶだけでも御の字だ。それ以上求めるのは期待しすぎであろう。
「結構値が張るんだけどなぁ、あれ」
風紀委員会室で使った方は五枚で千イェン。学食一食が四百イェンであるが、大怪我を負った際の治療費を思えば安過ぎる。
携行禁止級の防壁を張る魔法に使った札も、それの数倍程度で多少は高価ではあるが、まだ問題ない。
問題は【暴食】、【憤怒】の二枚の大罪魔法に使用していた札だ。
あれに関しては購入時点で既に経年劣化を起こし始めていたが、元々は軍事的機関で使用される様な強力な書記魔法を使用する為に使う物である。
当時行き着けの魔法道具店の店長が廃棄予定だったそれらを趣味で集めており、軍需品で元々の単価は千イェン程のそれを、口止め料や諸々の付加価値を含めて十枚五万イェンで手に入れたのだ。
内包魔力自体は劣化していたが、札自体の強度はやはり軍事用であるが故に頑丈であり、その為大罪魔法というあれな病気を患っている時に思いついた書記魔法にも耐えられたのだ。
二枚で一万イェンの損失は大きい。普段着ている制服が大体二千イェン前後であり、その五倍は損失している。
おまけに作成に掛かる時間も中々に長い。複雑な構成式を、多重記述という複雑な書き方で記入した物を、降雨等で劣化しないようにコーティングして漸く完成する。無論、コーティング液もそれなりの物を使わなければならない。
補填対象になればとは思うが、元々所持自体が校則違反すれすれの代物だ。確認した所で、咎められる可能性の方が高い。
「十一時に待つ……か」
その言い回しならば五分前に目的地に着けば良いと、聡治は乗合駆動機関車の時刻表を脳裏に思い浮かべ、十時二十三分に寮の付近を通るそれで中央区へ行けば良いだろうと考えを止める。
何時に待つという言い回しであれば、およそエクリエルはその時間通りに現れる。逆に、何時に集合という表現であれば往々にして彼女より遅く現れれば、先の乱層区画調査時の様に鉄拳が飛んでくるのだ。
言い回しの法則性は一応あり、気分が良い時は前者の言い回しであり、機嫌が悪い時は後者の言い回しになる事が多い。
ならば今日は何らかの良い出来事があったのだろうと思いつつ、恐らく、体調不良で臨時的に書記に任せていた事件の残作業が一先ず落ち着いて気分的に楽になっているのだろうと聡治は推測した。
今日の予定を脳内で確定させる。
十一時にエクリエルの用事に合わせて中央区へ向かい、其処で用事を片付ける。
帰って来たタイミングでクロガネに連絡を行い、最悪調整事項があれば明日対応。ついでに寮長への連絡を行っておけば、現状思いつく限りの用事は片付くのだ。
まずは幾許かの仮眠を取るべきだと、それが遅刻フラグであると知りつつ聡治は、徹夜で重たくなった瞼を閉じて夢の世界へと旅立つのだった。
◇
中央区商店街。
五界統合学院においてはその中枢部を担う区画であり、当然其処に存在する商店街は大規模だ。
此処で手に入れられない物は学院外から仕入れる他に入手手段がないと言われる程に多様な商品が存在しており、また娯楽施設も同様に豊富である事から、高等部学生の主な遊び場としての一面もある。
何かとカップルが多く、単に人込みが其処まで好きになれない聡治にとっては基本的に近寄らない領域であり、精々寮の存在する第四区に存在する商店街で手に入らない物があった場合のみに訪れていた。
今日も男女一組で行動する連中が多いなと周囲を一瞥しつつ、エクリエルに指定された中央区商店街南口の、待ち合わせに良く使われるらしい置物《オブジェクト》の付近に立ち、時計を確認する。
現在時刻は午前十時五十分。流石に、寝坊は出来なかった。
そろそろエクリエルが来るだろうと、聡治は暇潰しに背面に存在する置物を、見返りつつ眺める。
それは一言で言えば、子供が適当に拵えた粘土細工の様な混沌とした物体であった。魔界出身の著名な芸術家が手掛けた、『秩序』という名前の、見た目が見事に一致していない像である。
評論家は確固たる秩序など存在せず、人々の思いが集まる混沌とした状態からこそ秩序が生まれる事を表している云々という事が書かれている記事を以前見たことがあるが、無論詳細は覚えていない。
此れが待ち合わせに使われる理由は、単にその不恰好さが整然としている空間では極めて良く目立つからである。
他にも、此れが何故か恋愛成就や、恒久的な友情が続くようにという願掛けを担っているというのもある。
何処が秩序だと突っ込みを受けつつも何故か撤去されないという事から、不確かながらも其処に常に在り続ける事から、感情という見えない物を強く繋げられる……という由来があり、実際に成功例も嘘か真か噂話になる程度には存在している為、一概に嘘とは言い切れないのだ。
特に待ち合わせ場所を指定していないという事は最も待ち合わせに使われるそれの付近に居れば良いだろうと正面に向き直した時、視界の隅に白銀が映り込んだ。
「よう、エクリエル。身体の調子はもう大丈夫なのか?」
「元々過負荷による身体への外傷だ。あの程度なら直ぐに治る」
不要な心配だと蒼い眼を細める彼女は、確かに心配不要と言える程、堂々とした立ち姿をしていた。
今日は公務である事を証明するかのように、彼女は徽章を取り付けた服装をしている。全体的に白を基調とした装いであり、頭髪や色素の薄い肌と相俟って、其処だけ色が欠落したかのような存在感がある。
輸血を要する程に大量に血を流した怪我をあの程度と言う事に少々違和感を覚えるが、事実元気そうだから何の指摘も出来ない。
「今日は先の事件の、風紀委員会からの補填という解釈で良いのか?」
「そうだ。物損に関しての補償が二千オール(一万イェン)分、解決貢献報酬として千オール(五千イェン)分が出ている」
合わせて一万五千イェンかと、エクリエルが語ると同時に差し出してきた一枚の書類を眺めながら、聡治は思う。
死にかけてたったの五千イェンかと思うが、死に掛けたという事実を知るのは少なくとも聡治自身と、観測していたクロガネ及び、第六世界対策室関係者程度だろう。
公的には大した活躍は出来ていなく、それを考えれば妥当と言えば妥当なのかもしれない。
「現金支給じゃいかんのか?」
以前から思っていた質問をエクリエルにぶつけてみるが、曰く補填行動時には不正が起きない様に風紀委員が同行する決まり事が存在するらしい。
同行者は他の連中で良かったのでは? と思う聡治ではあったが、盛大に破損した風紀委員会室の復旧に忙しく、買出し同行という比較的負荷の少ない仕事で身体を慣らしていく心算なのだろうと推測した。
「行くぞ。立ち話は時間の無駄だ」
踵を返して買物を行う本人より先に行動を起こす彼女を見る限りは、完全に復活しているなと、エクリエルに見えない事を良い事に、聡治は苦笑いを浮かべながらそれへ追従する様に歩き始めた。
◇
買物自体は直ぐに終了した。
理由は言うまでもない。最寄の衣服店で学校指定の衣服を選ぶのに数分も掛からなかったからだ。
エクリエルも先の乱層区画調査時に血塗れにして廃棄を余儀なくされた衣服の代わりを購入していたが、それにしても即決だ。元々何を買うのか決めていたかのような清々しい決断であり、聡治よりも早く選び終えていた。
書記魔法に使用していた札も、残った金額全額を投じて近くにある魔法道具店で購入したが、正直に言って買物に要した実時間よりも移動時間の方が数倍以上掛かっている。
しかしやはり、大罪魔法に使用した札は購入できなかった為、やはり損失は補填し切れていない。
その事をやんわりと聞いてみようかと、帰りの乗合駆動機関車を、冷房の効いた総合待合所でエクリエル共々待ちながら考える聡治であったが、流石に生肉を抱えたまま肉食獣の群れの最中を疾駆するような真似は出来なかった。
そういえばと、ルカの様子に関して聞いておこうと口を開いた時だった。
『なぁ』
見事に被ったなと思う矢先、エクリエルが顎で先に話せと示してきた。
それを断る道理など何処にも存在しなかった為、聡治は了承の頷きを返し、話そうとしていた事をそのまま告げる。
「ルカの様子はどうだ。先の一件で落ち込んでたりはしてないか?」
「むしろ事件前より元気だな。奴は失敗を踏み台にして頑張れるから、心配する必要はない」
今は風紀委員会室の復興作業で物理的な処理を頑張っていると、一昨日……退院寸前の見舞いの際に報告があったようだ。
その一方で今回殆ど何も出来なかった事を気にしており、次に騒動があった時は頑張れるように鍛錬を増やしたとも言っていたらしい。
てっきり何も出来なかったと落ち込んでいる物だとばかり思っていたが、それを踏み台に出来ているなら大して心配する必要も無さそうだ。
「それだけか?」
「ああ。身内から犠牲者が出てるだろ? だから気になってね」
「曲がりなりにも奴は魔界人だ。そういった出来事に対しての耐性を他界人と一緒にしない方が良い」
それも道理だと、聡治は頷く。
死に対しての耐性は、統計上は魔界人は比較的高いとされている。元々魔界では頻繁に戦争が繰り広げられており、それに適応してきた結果らしい。
ちなみに最も耐性があるのは霊界人だ。
何せ元々死を経験しており、その存在自体も中々に希薄であり、個々の繋がりも他界人に比べて強くはない。身内に死人が出たとしても、『あの子? う~ん……三日ほど前に消えちゃった』程度の一言で済ます者もいるくらいだ。
「駄目なら駄目で支えてやれば良い。私達が、先人達に支えられてきた様に」
口元に微笑みを浮かべたエクリエルであったが、言った人物が人物なだけに何処か納得しきれない。
どうにも、生まれて直ぐに二足歩行し始め、傲岸不遜な立ち居振る舞いをしている光景は直ぐに思い浮かんでも、誰かに支えられる光景は想像できないのだ。
ただ言っている事自体はまともである為、肯定の為に聡治は頷いた。
「……で、そっちは何だ?」
此方が聞きたい事は此れでお仕舞いだと、エクリエルに何を話そうとしていたのかを問い掛けると、彼女は無言のまま鞄から一枚の札を取り出した。
それを渡してきた為、聡治は受け取る。
何の札だと一瞥した聡治であったが、外見や内包魔力からそれの正体を理解すると同時、それとエクリエルの顔を交互に見比べた。
「お前、これ」
「ソーエル社の四〇四系魔符の正統発展型である四〇四系魔符弐式だが?」
「いや、それは知ってる。何でお前がそれを……ってその前に何故俺に?」
手渡されたのは新品の書記魔法用の札であった。
五枚で千イェンという廉価な物ではない。先の戦闘で消耗した携行禁止級の一枚に使った物でもない。
それは今月の月刊マジックライター……書記魔法専門雑誌で特集を組まれていた、軍事的機関向けの札だ。
正式採用する機関はまだ無いが、多方面で試験運用が行われており、その性能は従来品を上回るという報告があり、実際に記事では比較検証を行っていた。
大罪魔法に使用したのも軍事的機関向けの札だが、当時譲ってくれた店主には悪い話だが、あんな劣化した上で型落ちとも呼べる物とは比較にならない。
何故そんな物を彼女が持っているのか、そもそもそれを渡された理由が分からず混乱する聡治に、エクリエルは淡々と告げた。
「――聡治。先の一件で……いや、”旧第四運動場で何があったか”は、私は追究はしない」
その声は周囲の雑音に紛れる程に小さな声ではあったが、聡治の鼓膜を容赦なく貫いた。
聡治が動揺を表情に出さないようにしようとしたのは一瞬だけだ。そんな努力をする素振りを見せた時点で、何かあった事を白状しているのと同意義なのだ。
元々何かあったことは確信していたようであったエクリエルは表情を変える事はなかった。
「夏季休暇中は学院を離れるのだろう? それは護身用として与えておく。休暇が終われば直ぐに処分しておけ。基本的には校則違反品だ」
「……何、を」
「禁書盗難事件、伊庭甲子郎の失踪事件、真川敦死亡事故……果たして此れ等は孤立した案件だろうか。私は、此れ等の案件が何らかの点で関係している気がしてならない。同時に、まだ根本的な解決がされていないと考えている」
お前はどう思うとばかりに視線を向けてくるエクリエルに対し、聡治は肯定の頷きを行った。
竜ドネルクラルによって引き起こされたのだ、その点では共通している。同時に竜という存在が現れれば再び似たような事が起こる可能性も零ではないのだ。
その事実を知っているかどうかは別として、エクリエルとしては根本的な解決がされていない為、関係者……あるいは知人関係に注意喚起をしているのだろう。
軍事的機関向けの札を渡したのは、特に旧第四運動場での出来事に対し、彼女なりに思うことがあるからだろう。
あるいは校外は風紀委員の管轄外だから自分の身は自分で守れ、という事かもしれない。
「……分かった。ところで何で学院を離れる事を知ってるんだ?」
「風紀委員の夏季休暇中の巡回割振りで、どの地区からどの程度里帰りするか把握して適切な人員数を振る必要がある。その過程で知った」
個人情報も何もあった物ではないとは思うが、元々首のチョーカーで常にではないがある程度の動向が確認されているのだ。今更である。
不意に室内に無機質な音声案内が響く。内容を聞く限りは、エクリエルの乗る乗合駆動機関車の発車時刻が近づいているようだ。
「私は帰る。予想が外れる事を祈っておこう」
「ん、また夏休み明けにな」
すっと立ち上がって立ち去っていくエクリエルを見送ると共に、聡治は札を鞄に仕舞う。
聡治が乗る予定だった乗合駆動機関車の知らせが響いたのは、それから十分後であった。
◇
昼ごろに帰宅した聡治は、クロガネに里帰りする事を伝えた。
夏季休暇初日の遣り取り通り、同行して監視を行いたいと言われたが、出来れば其れは止めて欲しいと伝えた所、最終的には以下の様に落ち着いた。
クロガネを含む第六世界対策室関係者は、聡治の知覚範囲外から監視を実施する。有事の際にまず安全を確保する為の自立兵装転送座標補足に使用する道具を聡治が携行する。
その道具は1/10クロガネと黒い金属製の指輪の二種類を選ばされたが、聡治は迷う事無く指輪を選択した。
理由は言うまでもなく、傍から見ればフィギュアを肌身離さず持ち歩いているように見えるからである。
クロガネからは探索阻害加工が施され、更に光学迷彩障壁の展開が可能な為、滅多な事がない限り存在が露見する事はないとは言われたが、持ち歩く事を強制される時点で指輪の方が便利なのだ。
そして日付は替わり、里帰りの旅路に就く当日の夕暮れ時。
「アルバートさん、行って来るよ」
「道中気をつけろよ。それと、私はアルバーンだ」
寮の管理人であるアルバーンという魔界人の老人に伝えた聡治は、道中に徒歩がある事を考慮した必要最低限の荷物を詰め込んだ鞄を持ち、寮を後にする。
其処から一旦中央区まで乗合駆動機関車で行き、中央区からは夜行駆動機関車に乗り込んで実家を目指すのだ。
本日を含めて約三日間という聡治の旅路が、始まった。
【クロ 2014.07/22】
雲がまばらに散る夕焼けの下、学院前駅舎には人々が集り、乗合駆動機関車に群がっている。
聡治はそれを窓際の席から、横目でちらと見た。
機界からもたらされた技術により完成したそれは、常に衆目の的であった。その走る観光名所は次第にファンを増やし、人を、物を走らせる。
聡治はそういった流行に対して冷ややかではあったが、乗った際の程よい振動と緩やかに流れる景色が、割と気に入っていた。
本を読む者、隣の席の者と談笑する者、荷物に頭を預けて寝ている者、様々な乗客がいる中、聡治はもっぱら景色を眺める者である。
あんな事件があった直後であるから、書物にはしばらく関わりたくないというのが人情であるが、それとは関係なく聡治は景色を楽しみにしていた。
郷愁を誘う夕日、優しく灯る星星、空を塗り替える暁、流れ行くそれらを車窓より眺めようと決め込んでいたのだ。
しばらくして汽笛が鳴り渡り、ゆっくりと汽車は笛の音を追いかける。次第に加速していく振動と駆動音は、聡治の足に、リズムを取らせた。
茜色に染められた街並みはそれはもう美しいもので、人も、建物も、何もかも、常に一つの絵画の中にあった。
汽車が中央区に近づくにつれ、景色はあっという間に流れ去っていく。夕日も、雲も、ずっとそこにあるというのに、人と物だけがとてつもない速さで枠外に消えた。
聡治はそれを目で追うこともなく、夕暮れの背景として眺める。ふとため息を漏らすも、汽車の走行音がすかさず巻き込んだ。
「は!?夢か。乗合駆動機関車は汽車じゃなくてバスだったな。次からが汽車だ。」
聡治はうっかり寝入ってしまったことを少し後悔した。
乗合駆動機関車が中央区についた頃、日は落ちかけ、グラデーションの美しい時間ではあったが、雲の配置の偏りが聡治の癇に障った。
不恰好な空模様にへそを曲げた聡治は、そそくさと乗合駆動機関車を降り、夜行駆動機関車の席取りに急ぐ。
聡治にはちょっとしたこだわりがあった。15両編成である夜行駆動機関車の、中ごろの車両の窓際の席が、聡治にとっての一等席である。
幸い混雑はしていなかったため、難なく一等席に座ることができたが、発車時刻までは少々間が空いていた。
聡治は窓の外を見やる。あたりは段々と暗くなり、星が雲の隙間から覗いていた。
やがて乗客がぽつぽつと乗り始め、少しばかりの暑苦しさを覚えた聡治は窓を開ける。じめっとした風ではあったが、何とも言えぬ夜の匂いを運んできてくれたことに感謝した。
車掌の声が遠くに聞こえる。発車の時刻が近いのだと聡治は察した。
力強い汽笛が鳴る。機関の駆動する音、線路と車輪の擦れる音、車体が風を切る音が聡治を包んだ。
「窓、閉めたほうがいいよ」
「……ん?は!また眠ってしまっていた!」
優しい男の声に聡治ははっとする。
不覚にも景色を見逃してしまった聡治は、うなだれると共に顔に付着する水滴に気づいた。
雨だ。小雨ながらも雨が降っていたのだ。幸いにも降り始めたばかりのようで、聡治は顔が少し濡れただけで済んだ。
慌てて窓を閉めた聡治は恥ずかしそうに頭を下げる。
「雨が、降ってたんですね……。ありがとうございました」
声の主は手を横に振った。
「いやいや、と言うか、そろそろトンネルに入るからね。窓を開けてると顔に煤がついちゃうから」
「ああ、なるほど」
「隣、いいかな?」
空いている席は他にいくつもある。わざわざ自分の隣の席を選んだその男に、聡治はちょっとした不信感を覚えた。その男の姿を捉えるまでは。
聡治は隣の席へ手を差し伸べる。男は軽く会釈をした。
「ええ、どうぞ」
「ありがとう」
男は座席を揺らさず、静かに柔らかく腰を掛ける。そのまま優しく語りかけた。
「色々、迷惑をかけたね」
「いえ」
「体の方はもう大丈夫なのかい?」
「ええ」
「それは良かった。お礼が言いたくてね」
「いえ、俺は……」
「相棒のことさ。君が踏み砕いてくれた」
「あれは……」
「おかげで取り返すことができたよ。今では、前以上にこいつと一つになれている気がする……」
「……」
山道を走る汽車はトンネルに差し掛かる。線路を走る振動音が変化し、雨空は置き去りにされた。黒煙と暗闇に包まれる。
「あー、そうだ。ボスは……どんな様子かな?」
「ああ、あれは何があろうと変わりませんよ。いつも通りです。ただ……」
「ただ?」
「絶対に見せないでしょうが、心のうちでは傷ついている」
「そうかな?」
「わかりません。決め付けですから」
「……やっぱりね。なるほどなるほど……」
「……?」
何やら一人で納得されたことが腑に落ちない聡治であったが、特に詮索する気は起きなかった。
やがてトンネルを抜け、視界がひらける。窓に当たる雨粒は強く多くなっていた。
汽車は右に大きく曲がり、聡治の席からは、雨粒の向こうの先頭車両、その煙突から上がる煙が、雨雲と混じっていくのが辛うじて見える。
列車の左側には山々が重なり、一つの大きな壁がずっと続いているかのようだった。
聡治は、連続する山の起伏から、景色の流れる速さが、徐々にゆっくりとなっていることに気付いた。
やがて停止した車体の窓から身を乗り出して前をのぞくと、汽車を停止させた原因がかすかに見えた。落石か、土砂崩れか。黒い塊が路線上を塞いでいる。
珍しいことではない。開通してはいるものの、鉄道の舗装は万全ではなかった。障害物に阻まれることも当然予想されていたため、必ず運転士以外に優れた術者が添乗している。
線路上のあらゆる異物を知覚し、場合によっては車体を保護する結界魔法に秀でた術者と、破損した際に車体とレールを修理する練成魔法に秀でた術者である。
今回のケースでは事前に障害物を察知し、無理なく停止した形だ。
眠っている乗客も多い車内では大したざわつきもなく、少数の人間だけが窓から様子を窺っている。
そこに車掌であろう制服を着た初老の男性が、落石により3時間ほど停車するとの説明をしてまわった。
「どうやら、恩返しの機会が早々に巡ってきたようだ」
男は落石を確認すると窓から外に躍り出た。
直径10mほどの大岩と、その付近に人のいないことを確認した男は、そっと愛刀「灯篭流し」に手をやり、居合いの構えをとる。
抜刀するやいなや、剣舞の如き流麗な居合いは既に余韻を感じさせていた。
聡治は見た。深い夜にもかかわらず、はっきりと見えた。刀身ではなく、太刀筋でもなく、降り注ぐ雨を数多切り裂く、軌跡の残像を。
斬られ、弾かれ、散った雨粒は、しばしの間霧の層となり、雲の隙間から僅かに覗いた月に照らされ、月光を反射し合う。
真っ直ぐと流れ霧散していったそれは、うたかたの雨の川。
斜めに断たれた巌は、雨に濡れて滑り落ちる。
かつてのドネルクラルのそれとはまるで異なるその美技に、聡治はただただ驚かされた。
真川敦は苦笑する。
「うーん、あと20回くらい斬らないと駄目かな」
◇
真川敦の働きもあり、予想よりも1時間ほど早く出発の準備は整った。夜は明け、いつの間にか雨は上がっている。
自身にとっての一等席に腰を掛ける聡治に、真川敦は窓の外から手を振った。聡治は問う。
「これから、どうするんですか?」
真川敦は笑顔で答えた。
「君と同じさ。実家へ帰るよ」
「そうですか」
「駅まで乗って戻るより、ここからのほうが近いんだよね。ここで止まってくれてラッキーだったよ」
聡治は苦笑しながら、握手を求め手を差し出す。
「いいものを見させていただきました。ありがとうございます」
真川敦は快く受けた。聡治が思っていたよりもその手は温かかった。
「こちらこそ。えー……君の家のことは知ってるよ。その……大変だったみたいだね」
不意の言葉に硬直する聡治だったが、触れ合った温もりが緊張をほぐす。
「……そうですか。……もしや真川家の?」
「まあね。お互い、色々思うところがある帰郷だとは思うけど、きっと待ってくれている人がいるはずさ」
風が吹いた。
暁光を乗せた爽やかな風が、握られた手と手を童のように駆け抜けていった。追い風であった。
機関車が止まらなければ見ることのできなかった、窓の内と外を繋いだその景色を、聡治は堪能する。
汽笛が、風と遊ぶように鳴り響いた。
【タタリ 2014.08/20】
伏神の本家は上伏(かみふせ)町の最奥に位置している。蒸気機関車で行けるのは手前の百埜(ももや)町までであり、そこからは馬車なりの交通手段を使って数時間がかかる。
道中のトラブルもあって時間を費やした俺たちは百埜町で旅籠を探して一泊し、明け方に馬車に相乗りして上伏町を目指していた。
「真川の家って確か、伏神山の先だっけか?」
「ですね。伏神山はいわゆる霊山、聖地ですから、麓をぐるりと回り込む事でしか進めませんが」
「……そりゃまた、だいぶ時間がかかりそうだな。このまま馬車に乗ってても着くのは夜半になるぞ」
「道中、君と過ごせて退屈しませんでしたし、何より今の僕は霊界の者。夜は全く苦にはなりませんよ」
向かい席でこちらに微笑みかけながら、真川は左手を前に差し出す。その手は死者特有の青白さこそあるが、生前と同じく実体がある様に見える。
しかしその実、真川の体は物理的に触れる事はできない。彼の体は霊体であり、物質などを通過してしまうのが霊界人の特徴なのだ。
生物が生きる際に熱量(カロリー)を消費するのと同じで、霊界人は熱量ではなく自らの存在を構成する霊質を消費する。霊界人、引いては幽霊(ゴースト)と呼ばれる者の体は、魂の密度を自在に変える事ができるのだ。
故に、霊界人は摂食(カロリー)を必要としない。彼らが必要とする栄養素は周辺に漂う同胞(はらから)であり、それらを取り込む事で存在の構成に必要な霊質を確保する。
そして、霊質の密度を極限まで凝縮する事で、先日の大岩のように、物理的な接触も可能とする。人間が全力疾走をすれば大量の熱量を発散してしまうように、霊界人は霊質密度を操作するだけ大量の霊質を損なってしまい、やはり消滅する。五界統合以前から幽霊の目撃談は絶えないのに、近世から古代にかけて徐々に幽霊の目撃談が少なくなるのは、魂が古いほど霊質を損なう量が多くなる……霊界人にも寿命がある証明である。
「急ぎの用でもなけりゃ、うちに一泊してもいいんじゃないか?」
「……真川の者が伏神の本家に出入りするのは、少しからず問題がある気がしますが」
「んな小いせぇこた気にするな。道中じゃお前のお陰で余計な時間を食わずに済んだからな。そのくらいなら謝礼のうちに入るだろ」
そういうものですかね、と苦笑する真川に笑って返した。
これは夢だ。幸福な夢だ。
「お兄様はあれですか、猿ですか?」
「気付けの開幕からそれか。心が折れそうだ」
剣道着で正座したまま俺を見下ろす黒い長髪を後ろで束ねた少女、聡理は竹刀の紐を結びながらため息を吐いた。一方で仰向けに倒れていたのであろう俺は、痛みを通り越して高熱を帯びた左頬を押さえながら起き上がる。うん、触った感じ当社比一・五倍くらいに晴れ上がってるな。
先程のことは鮮明に思い出せる。上段に構えた俺の振り下ろしに対し、聡理は剣先を巻き込みながらの振り上げる一刀。先の一撃に対する後の先を機した単純なカウンターである。それが俺の首筋にダイレクトアタック、呼吸器に強いショックを受けて酸素を失い気絶したと言ったところか。
「貴方の太刀筋は至極読み易い。隙も多いし、打とうとする意志が剣に現れている。ところでお兄様、私がこの評価を下したのは幼少より実に二百三十三回目ですが、言い訳はございますか?」
「攻撃は最大の防御だ。そっちの方が恰好いいし」
「猿ではなく猪の類でしたか」
眉を八の字に歪めながら、聡理はハンっと鼻で嗤う。あからさまに馬鹿にされてる。なんだこの女、親愛なるお兄様に向ける態度じゃねぇぞオイ。
「攻撃はどこまで極めても攻撃でしかありません。相手の動きと鏡合わせに対応する防御とは違います。先んじて動く以上、相手に手の内を見せぬ事こそ肝要というもの。それを……何ですか、先の体たらくは。ああ失礼、お兄様の醜態は今に始まった事ではありませんでしたね」
「おっとそこまでにしておけ聡理。今の俺はあれだぞ、頬っぺたの激痛と相俟って既に泣く寸前だぞ。それともお前は男が大泣きする姿を見て性的興奮を得る変態なのか?」
「仰る意味が皆目見当つきませんが、見苦しい行いをするのであれば御自由に、私の目が届かぬところで」
「……本当に可愛げの無い妹だぜ、本当に」
負け犬根性丸出しの捨てゼリフを吐いた瞬間、聡理の竹刀が俺の頭頂部を叩き割った。たぶん、手加減していたであろう先のカウンターより、剣速はだいぶ速かった様に思う。
「ぎゃあああああ! No! 脳(ノー)!」
「頼りげのない次期当主と可愛げの無い妹。我々らしく結構な事かと」
「えっ、いや、いいの!? じゃあ何で俺はいま殴られたの!?」
視界が白黒と明滅する中、口元に手を添えて肩を震わせる聡理を見上げ、抗議する。彼女は伏神の直系として淑女になるべく教育を施されている。くつくつと肩を震わせて笑いを堪えている現状は、普通であれば大爆笑と言ったところだ。
脳天をぶち抜かれて意識が寸断されているせいで、彼女の顔が見えない事が心残りではあるが……なに、聡理はいつだって俺たち伏神と共に在る。彼女の笑顔はこの先も見る事はできるのだ。
「……楽しそうだな、お前ら」
ふと、道場の入口方面から声が聞こえた。聡理は手拭いで汗を拭きながら、俺は眩む頭を振って正気を取り戻しながら、聞きなれた声の主へ向き直る。
「ああ、劔兄さん、帰ってたのか」
「おう、さっきな。四十七氏への根回しがようやく一段落したところだ」
「……? よく分かりませんが、帰られたのでしたら、これから昼食でもどうですか? 久しぶりに三人揃ったのですし」
「そうしたいのは山々なんだがな、ゆっくりもしてられんのだよ。……急で済まんがソウジ、後で爺さん連中が話があるとさ。汗を流したら本殿に行くぞ」
「……面倒だな、俺にいったい何の用があるんだか。ああ、そんな顔するなよ兄さん。分かった分かった」
俺の竹刀を聡理に投げ渡しながら、ようやく安定してきた視界を頼りに劔兄さんの後を着いて歩く。聡理は事情を呑み込めないながらも何か只ならぬ事態を悟ったのか、一礼して竹刀を持って道場を出て行った。
「気を遣わせたか……」
「聡理は賢いからな。あの問題さえなければ、俺達なんかよりよっぽど当主に向いてる」
「俺もお前も、当主ってガラじゃないのは分かる」
天は二物を与えず、という諺の通り、才色兼備の才媛である我らが妹は、どういう訳か魔法に関する才能が全くなかった。五界統合以後、魔法は文明化され、学問として確立する事で「学べば誰にでも扱える」様になったと言うのに、彼女は伏神符術の基礎すら扱えないのだ。
お偉方いわく、先天的に魂魄を魔力変換する機能が一筋たりとも備えられていない事が原因との事らしいが、近年確立した学問など、田舎魔法師である俺が理解できるものではない。
そもそも、魔法が扱えない者の心理が、俺には分からないのだから。
「五界統合にご立腹な爺さん共は、数百年間も王朝に滅私奉公してきた守手四十七氏がぞんざいな現状を打破したいらしいな」
「くっだらねぇ。魔界人の運動能力に天界人の魔法適性、機界人の技術水準に霊界人の不死特性。そんな化け物連中に、数しか優ってない人間が、ない知恵しぼったところで打倒できる筈もないって分からないのかね」
「ところが、頭でっかちの爺には分からないんだろう。だから強硬手段に出ようとしてるんだ」
「はっ、違いねぇ。信心深い爺さん連中の暇潰しに付き合わされるのはいつだって若者の仕事だってか? 事が発覚したらどうなるか、現実が見えてない夢想主義者は厄介極まりない」
濡れた手拭いで腫れた頬を冷やしながら、俺と兄さんは愚痴を零し合う。兄さんは伏神の資産を使って独断で守手四十七氏に根回しをして、今回の件をあらかじめ「何も起きない」様に小細工した事を上役の爺どもは何も知らない。恐らく知られれば懲罰じゃ済まないかも知れない。二重の意味で、兄さんはこの一件を表沙汰にならない様に事前に封じ込めたのだ。
伏神に代々伝わる符術は、現在では書記魔法なる系統の一端に分類されるらしい。話を伝え聞くに、文字に魔法の意味を持たせる書記魔法と、霊や神などを憑依させる降霊魔法など複数系統の魔法の応用らしいのだが、詳しい事はよく知らん。何かそういうあれやこれやがあるらしい。
王朝最先端の呪(まじな)い家であった伏神の符術も、五界統合にかかれば片田舎の芋とさして変わらない。その技術をいくら結集したところで田舎者の田舎自慢でしかないのだ。それを理解できていないのは、未だ我らこそが時代の申し子であると信じて疑わない世代の堅物と、その堅物に洗脳されている現代の若者だけである。
そりゃ、時代の移り変わりに廃れるのであれば努力不足であると嘆き、励む事は出来るだろう。同情は出来ないが理解は出来る。それが、五界統合で時代が劇的に変化し、技術が追い付いてない現状を認識できないのであれば、それはただの愚者でしかない。
中庭の流し場で冷水を浴びて汗を流し、濡れた剣道着は女中に渡して干してもらい、単に着替える。暑苦しいので羽織りはいらないか。どうせ話を聞くだけだし。
かっぽかっぽと下駄を鳴らしながら邸内の杉林を抜け、離にある書斎兼茶室に到着する。茶の間とは現世と隔絶された空間である事が大前提だが、ここには伏神が記してきた数百年間の歴史書などが保管されている。俗を絶ってるのか俗に塗れてるのか定かではないが、これを設計した奴には矛盾の故事を聞かせてやりたいものだ。
しかもこれから話す内容は現政府への謀叛だ。ますます以て茶室とは何だったのかと問いたくなる。
「失礼、臣老(しんろう)方。伏神当主、巌斎(がんさい)が次男坊、伏神ソウジが遅参いたした」
戸の前で声を張り上げ、中から声がかかるのを待つ。認可が下りたところで戸を潜り、真の一礼。茶室に座する四人の爺婆と父・巌斎、兄の劔の計六人に順に礼を行い、下座に座って再び一礼。
「さて、揃ったな」
茶釜の湯の温度を確かめている臣老の一人がにたりと笑いながら、全員の顔を見渡した。
──今になって思えば、彼らのうちの誰かが、ドネルクラルの様に竜と同化していたのかも知れない。
「伏神くん、伏神くん。着きましたよ」
「んあ……?」
「よく眠る人ですね、君は」
「あー、長旅で疲れたかな」
伸びをしながらあくび混じりに適当な推論を答える。実家に帰るだけで一泊二日、道中はほぼ拘束時間となる。軽いストレッチや筋トレで体を解していたが、それでも疲労は溜まる一方である。
馬車の運賃を払い、久々に踏みしめる地面に地味に感動しつつも辺りを見渡す。俺がこの町を離れてから数年経つが、良くも悪くも変わらぬ町並みがそこに広がっていた。町の最奥には標高千五百メートル程度の伏神山がそびえていて、その中腹ほどにある大屋敷が最終目的地である伏神本家だ。
現在時刻は午前十一時。日が昇る前に旅籠を出たせいか、意外と早くに着いてしまったらしい。劔兄さんとの待ち合わせはもう少しあるし、茶屋にでも寄って、少し時間を潰すのもいいかも知れないなぁ。
【どあにん 2014.09/04】
「いや、しかし予想以上に早く着いたな、さてどうするか……」
「そうですね、せっかくなんでお茶でも」
いやちょっと待て、真川さん今幽霊じゃないかと言うツッコミを入れた伏神聡治と真川敦は茶屋で適当に時間を潰す事にした。
小さい頃は良く両親に連れられて来たなぁ、と物思いに耽りながら色褪せた暖簾をかき分けて扉を開くと懐かしい香りが鼻孔を擽った。
建物全体に染み込んだような優しく甘い香り、殆ど変わって無い"稀口甘味処"の看板が幼い頃の記憶を引き出してくる。
「どーも、やってますか」
「あーらソウちゃん!久しぶりじゃないの!」
店主のおばちゃんが出てくるや否や聡治の頭が乱暴に撫でる、これが昔から続いてるおばちゃんなりの愛情表現なのだ。
……髪の毛が逆立ったりする程はやめて欲しいとは思ってはいるが。
「ソウちゃん大きくなったわねー、注文は何にする?」
「それじゃ、私はあんみつで」
「あー、じゃああんみつとみたらし団子3本で」
了承の声と共におばちゃんは暖簾の奥へと姿を消し、代わりに怒声が響いてくる。
変わらない、此処は何も変わらないが俺だけは変わってしまった。
軽く唇を噛む聡治に対して、真川は眼を伏せるだけで何も言わなかった。
「アンタ!お客様をいつまで待たせてるんだい!?」
「うっせーな!こっちだって忙しいんだよ!バイトにやらせろよ!」
アンタが店主ヅラしてんじゃないよと再び怒声が響き、ソウジが乾いた笑みを浮かべた次の瞬間だった。
特徴的な熊のワンポイントが目を引くエプロンを掛ける男、髪の毛は優しい太陽の光を思わせるオレンジ色だ。
それがあんみつと団子を持って現れたのだ。
「ん、アンタもしかして伏神聡治かい?」
「お前は?」
初対面のはずなのに何故ソウジの名を知っているのか、しかも五界統合学院から遠く離れた故郷の地で。
男があんみつと団子をテーブルに置いている時、暖簾をかき分けて勢い良く入ってきた新たな男が二人。
ソウジはしばし思案し、そして脳の片隅に追いやっていた記憶を引っ張りだした。
「あー……確かお前は、リョタ……だっけ?」
「そういうお前は朝霞さまの尻に敷かれマンのソウジだな!」
「なんだと!?コイツ朝霞さまの尻に敷かれてるだと!?」
「うらやましいな!俺に変われコノヤロー!早くしろよ!」
◇
ソウジは完全に思い出してしまった。
禁書盗難事件に極めて微妙に関わっていた三人で、事件後は勝手に朝霞について回る三馬鹿であったと。
真川にとっては自分が殺された忌まわしい出来事であったが表情は一切崩さない辺りは流石と言うべきか。
時刻は昼過ぎで店は既に休憩時間に入っている為、客はもうソウジと真川しか居ない。
オレンジ髪の少年に続くようにオッドアイの少年と眼鏡の少年が名乗り出るがどこか芝居がかっている印象を受けた。
「自己紹介しとこう!俺はリョタ=マレグチ!稀口茶店次期店主だ!こんな事言うとカーチャンに殴られるけどな!」
「俺っちはジョエル=ラザイエフだ!」
「僕はフィル=ヴェラクマレンです、伏神さんのお話は朝霞さまから聞いてます」
ソウジは特製みたらし団子を1つ頬張る、しつこくない甘さが口中に広がる懐かしい味に舌鼓を打つ。
変わらないと言う事は停滞を意味するが、変わらない方が好きだと言う人間がいる事もまた事実。
難しいな、と誰にも聞こえないように独り言を吐いてから思い出したように三人に疑問を投げかける。
「でだ、お前らは何をしに此処に?ただ実家に手伝いする為だけに戻ったわけじゃ無いだろ?」
オッドアイの少年、ジョエルはわざとらしく大きな被りを振りながら小さく舌を打った。
「そうだな、冒険……そう、失われし秘宝がこの伏神山のどこかに眠っていると情報を掴んでな」
「伏神山の秘宝……ですか、真川家の人間としてはそれは分かりませんが、ソウジ君はなにかご存知で?」
「いや……伏神山にそんな秘宝があるなんて初めて聞いたぞ」
こいつらはまた何か一騒動起こすのか、得意げな顔でフィルは眼鏡を人差し指でズレを直すとキラリと眼鏡が一瞬光った、ような気がした。
「伏神山に封じられし賢者の書物、読んだ者を悟りの境地へと導く伝説の書……僕達はそれを探し求めてやって来ました。
稀口茶店はその活動拠点、とでも言っておきましょうか」
「まぁぶっちゃけエロ本だ」
リョタの一声にソウジは「そう……」としか答える事が出来なかった。
【西口 2014.09/08】
稀口の茶菓子は、昔と変わらぬ味であった。
両親に連れられ、劔兄さん、聡里と共にこの店に訪れていた頃を、鮮明に思い出せるほどに。
きっと一人だったなら、食べている間に涙ぐんでいたことだろう。真川さんと、あの三人組には感謝しなくてはなるまい。
三人組に関しては、その後のエロ本云々の話さえなければ親しくなりたいと思っていたことだろう。
逆説的に言えばもう親しくなりたいとは思わないが。何だ、伝説のエロ本って。
この上なく無駄な時間を過ごしたような虚脱感を背負い、稀口甘味処を後にした俺は、真川と連れたって兄・劔との待ち合わせ場所に向かっている。
目に映る町並みは、本当に変化が無い。
まるで過去にタイムスリップをしたかのような錯覚を覚えるが、当然そんなものは幻覚だ。
死人は死んだまま。生き返ることは決してありえない。その姿を再び拝むことなど出来ようはずもない。
あの日と変わらぬ怒りと後悔と希望と絶望とを背負って、俺はこれからも生きていくのだろう。この数年後の未来さえ見通せない不安定な世界を。
「ところで伏神くん。一つ聞きたい事があるのですが」
待ち合わせ場所に向かう道中、真川がソウジに尋ねる。
人の姿形をしているとはいえ、今の真川は普通の人とは明らかに異質な存在だ。
他世界との交流が少ない人間界の中でも、とりわけド田舎で他世界人の往来が無いに等しい上伏町では、当然ジロジロと無遠慮な視線がその姿に注がれてしまう。
それにハハ、と苦笑を漏らすだけで、さして気分を害した様でもない真川の姿に、ソウジは改めて尊敬の念を抱いた。
ルカが懐くのも当然といえる。
人の上に立つ人間とはこの人のようなことを言うのだろう。
「聞きたい事?」
「はい。何故、帰郷をしようと思ったのでしょう。確か貴方は入学以来、長期休暇とはいえ、こちらに帰ったことは無かったはずですが」
これでも四拾七氏の末席に名を連ねていますからね。嫌でも耳に入ってくるのです。
少し申し訳なさそうにそう付け加えて、真川は質問を投げかけた。
旅の間のソウジの様子を見て、そう深刻な理由ではないと判断した上での質問なのだろう。言ってしまえばただの世間話だ。
そして、確かにソウジが帰郷した理由は深刻なものではない。ないのだが……ソウジにはどうにも、その「理由」が未だに信じられない。
もしかしたらあれは白昼夢やいたずらの類で、自分は担がれているのではないかと、半ば本気で疑っているくらいだ。
数日前、電話口で劔が何気なく言ったその内容は、それほどまでに衝撃的だったのだ。
前後の事情も含めて説明するべきか。いや、流石にそれはプライバシーの問題で兄さんに失礼か。
どう伝えるべきか考えあぐねているソウジを見て、何を勘違いしたのか真川が謝罪の言葉を呟いた。
「すみません。無神経な事を聞いてしまいましたか?」
「え、あ、いや。全然、全然。そういうんじゃないから」
どうやら変に気を遣ってしまう性質らしい。これは包み隠さずに言った方がいいだろう。
そう判断したソウジは、渋々と言った様子でポツリと語りだした。
「実は、さ。兄が一人いるんだけど、どうやら……祝言、挙げるらしくて。神前式に参加してくれって連絡があったんだ」
「それはそれは、めでたい事ですね」
真川は笑顔で言祝いだ。
めでたい。そう、めでたいのだ。
妻を娶り、跡取りを作ってようやく一人前、という旧態依然の古臭い価値観が当然のようにまかり通っているこのド田舎においては、尚の事だ。
だから、真川の反応は正しい。理想的とさえ言える。弟たるソウジが最優先で吐くべき台詞だ。
そんな事分かりきっているほどに分かっているつもりなのだが……ソウジにはそれがどうにも「信じられない」。
「兄さんが女の人と結婚って言うのがなあ……。尋常じゃない違和感を覚えずにいられない」
「……まさか、男色の気が?」
「なにとんでもない事を言ってんの!?」
しかも至極真面目腐った顔で。
そういう事じゃなくて。兄さんって凄い奥手って言うか、初心って言うか……。女性慣れしてないんだ」
言うなればそう、筋金入りの童貞。女性を前にした伏神劔は、まるきりのでくの坊になってしまうのだ。
10代の少女であったり、身内であった場合はそうはならないのだが、電話で聞いた相手の年齢は24歳。4つしか変わらない。
そんな女性と一対一で相対する兄が、ソウジには一切想像できなかった。
「お見合い戦績50戦50敗。何度か様子を見たことがあるけど、相手の女の人がどれだけ盛り上げようとしても、兄さんは一言もまともに返せていなかった」
「……確かにそれならば、結婚すると聞いて驚くのも無理はないですね」
「でしょう」
未だに信じられないわけはそこにある。
何か性質の悪い詐欺に引っかかっていると考えるべきか。
いや、流石にそれは考えすぎだろう。自分の知る伏神劔は、飽くまで家を出るまでの彼でしかない。
この4年間は、彼を変えるにも十分な時間だったに違いない。
あの事件で傷ついたのは、変わらざるをえなかったのは、自分だけではないということだ。
……ダメだ。シリアスに思考しようとしてもどうしても違和感が拭えない。
(会話すら出来なかったのに、結婚? 結納? 挙式? ……いや、いやいやいや。無いわ)
兄の結婚を全否定する弟。何たる非情さか。
「ところで、待ち合わせ場所とは一体どのような場所なんです?」
疑念を振り払えずにうんうん唸っているソウジを横目に微笑し、救いの手を差し伸べるように真川が再び質問を口にする。
堂々巡りに陥りかけた思考を中断し、その質問に答えたソウジは、気遣いの出来る人だなぁ、と幾度めかの関心をするのだった。
「町の中央に、講和の証として記念碑が建ってるんだよ。そこで待ってるってさ。
造型は悪趣味だけど、使われてる金属に自然光を吸収して微発光する性質があるから、まあそれなりに綺麗だよ。そろそろ見えてくるはずだ」
「微発光する記念碑……。あ、もしやアレですか」
真川が指差した先には、開けた広場があり、その中央に特徴的なモニュメントが鎮座していた。
ウェディングケーキめいた積載構造の噴水の上で、塔のように屹立する記念碑。
異なる五つの人種が複雑怪奇なポーズで絡み合い、その周囲をらせん状に取り囲んでいる。
何でも五界の恒久的な平和を表現しているらしいが、人体の骨格をまるきり無視したそれらは、どう控えめに表現しても地獄の業火にもだえ苦しむ亡者としか言いようが無い。
初めて見た子供は必ず泣く。纏わる怪談の数は両手足の指を用いてなお余りある。
不気味という感覚をあらん限り詰め込んだようなそれこそが、五界戦乱終結の記念碑「夢と希望の階《きざはし》」だ。
数年ぶりに拝むそれは、ソウジの記憶の底に残っていた昔の姿と寸分も違わず気色が悪い。
顔を見ずとも、傍らの真川が若干引いているのが手に取るようにわかった。
嘗ての自分もそうだったとはいえ、よくもまああんな物を待ち合わせの目印に出来るものだ。
一歩一歩近付いていくたびに、より精細なディテールが判明してきて、その不快さが加速度的に増大していく感覚は、ちょっとした心霊体験だ。
何故無駄に芸術性を取り入れようとしたのか。オーソドックスに加工岩に字を刻めばよかったじゃないか。
(四拾七氏の地位向上とか謳うなら、せめてコレの建設捨て身で止めろ、亡爺ども)
胸中で毒を吐き、知らず記念碑に釘付けになっていた視線を逸らしたソウジの視界に、一人の大男の背が映った。
短く切り揃え、刈り上げた頭髪に、日に焼けて浅黒い肌。
甚平に下駄というこの上なくラフな恰好は、とても元名家の現当主とは思えない。それは薄手の服装故に、より激しく自己主張するその隆々たる筋骨もそうだ。
190を越える長身と合わせて見ると、その男は人の形をした巌のように思えた。
彼こそが伏神聡治の実兄、伏神劔である。
――昔より、また大きくなったんじゃないか。
対象との距離、10メートル。
口元が無意識に綻んでいる事にも気づかず、ソウジは右手を上げ、「兄さん」声を掛けようとして、そのままの状態で停止した。
劔の陰になって見えなかったが、ソウジに背を向ける彼の眼前には、どうやら何者かがいたようだ。
なにやら不機嫌な様子でその陰から飛び出してきた人物を見て、ソウジは固まってしまったのだ。
透き通るような、それこそ「雪のように」白い短髪に、それとは相反するかのような褐色の肌。
一般的な和服の人間が多い街中にあって、その顔以外の全てをローブで覆った出で立ちは非常に目立つ。
その顔立ちは整っているが、その鋭い目つきは遠くから見ても分かるほどに剣呑な輝きを放っており、右目尻から頬を通り、顎先まで奔る一条の赤い刺青も相俟って、明らかに尋常なものとは思えない。
身長は160程度。体格は判然としないが、ただ立っているだけで油断の無さがうかがい知れる。
見覚えが、ある。本人を知っているわけではないが、その面影に重なる人間を、ソウジは知っていた。
だが、彼の足を止めさせたのはその事ではない。その人物の性別である。
女性であった。まがう事無き、女性であった。
「兄さんが女の人と口喧嘩してるッ!?」
「叫ぶほどの衝撃ですか……!」
実際に目の当たりにした衝撃は相当のものだったらしい。
見れば、たしかに劔とその女性とはなにやら言い争いをしているようだ。
別に大声を上げているわけではないため、話している内容はまるで分からないが、ソウジが衝撃を受けるには十分だった。
言うまでも無い事だが、口喧嘩となれば普通に会話を交わすよりも、その押収量は増大する。
「女の人が視界に入るだけで、図体がデカい分デク人形より邪魔臭くなる兄さんが、口論だなんて。やっぱり、兄さんは竜に憑かれているんじゃ……!」
「伏神くん、お兄さんの事嫌いなんですか?」
「兄さんにとり憑くなんて、何て卑劣な竜だ! 出来る限りむごたらしくぶっ殺してやる!」
「躊躇いが無い!?」
真川の声も右から左に、ソウジは駆け出した。彼の懸念は心の底からのものであったのだ。酷い話だな。
俄かに膨れ上がる殺意。だが、その距離が近付いて徐々にその声が聞こえてくるにつれ、針をつき立てられた風船めいて、それも萎んでいく。
だが、竜は殺さなければならない。
あふれ出そうな涙をこらえ、エクリエルからの贈り物を片手に忍ばせたソウジは、劔に擬態するドラゴン(事実無根)に向かってビシリと人差し指を突きつける。
「兄さん! 兄さんの意志がまだ残っているなら聞いてくれ! 今、楽にしてやるから! 出来るだけ惨たらしく!」
「……何故、俺は数年ぶりに再会した弟に殺害を仄めかされているんだ?」
「日頃の行いじゃない?」
口論を止めたという意味では、彼の行動はファインプレーと言えただろう。
遅れてやってきた真川の取り成しによってなんとか落ち着きをとり戻したソウジは、とりあえず兄に詫びた後、促されるままにその後についていく。
その足の向く先は、上伏町の最奥にてその威容を誇る伏神山。その中腹にある伏神本家だ。
「紹介しよう。こいつが不本意ながら妻、いや式を挙げていないからまだ婚約者か。不本意ながら婚約者の夕霧だ」
「不本意ながらこのデカブツの婚約者の夕霧。キリとでも呼ぶといいわ。いつ破綻するとも分からない関係だけど、一応貴方の義理の姉になるわね。まあよろしく」
「単刀直入に聞くけど、何で婚約したの?」
「ひ、人の愛の形は様々と言いますから……」
伏神兄弟と真川、そして先ほどまで劔と言い争っていたローブ姿の謎の女性――劔の婚約者である夕霧は、自己紹介をまじえた雑談を交わしつつ、伏神邸へと歩いている。
そこで明かされる衝撃の事実。なんと婚約するという話はまじりっけの無い事実だったのだ。
「しかし、本当に兄さんが結婚するなんて。どうやって治したんだ、あの癖」
「ああ、実はな。情けない事だが、未だに全く改善していないんだ、アレ」
癖とは言うまでも無く、女性の前に出ると石像めいて硬直してしまう極度のあがり症の事である。
「ええ、じゃあどうやって婚約まで漕ぎ着けたんの!? ま、まさか金を握らせて……!」
「伏神くん。それはただの悪口です」
ハハハ、と劔が快活に笑う。
――良かった。
彼はそう心の底から思ったのだ。
家で同然に家を飛び出していったっきり、一度も帰ってこなかったソウジの事を、劔は当然案じていた。
しかし「電話」の使い方が未だに理解できておらず、毛筆にて認めようにも何を書いていいか分からず、『仕事』の忙しさも手伝い、結局先日の結婚報告まで一度も連絡できなかった。
嫌われていたらどうしようという不安があった。何か取り返しのつかない事態に陥っているのではないかという懸念があった。
しかし、向こうから連絡が無い事をいい事に、もうソウジは家に戻るつもりは無いのだろうと無理矢理自分を納得させ、あえて彼を避けてきた。
もし連絡して、ソウジに拒絶されたらどうしよう。聡里を守れなかったと憎まれていたらどうしよう。
ガタイに似合わぬ女々しい考えに支配されていた。
それでも、劔はソウジの事を変わらずに愛していた。幸せになって欲しいと、そう願っていた。
だからこそ、劔は今のソウジの姿に、笑みを零さずにはいられなかった。
最後に見た陰鬱な無表情とは違い、今の彼の表情は喜怒哀楽に富んでいる。――まあ喋っている内容はアレだが。
この数年間がソウジに対して齎したものは、けして悪いものではなかったのだ。
それが嬉しくてたまらない。
「でも、僕も少し気になりますね。女性が苦手だといいながらも、夕霧さんとは普通に会話をしている上に、結婚までなされる。一体どのような経緯で?」
「ふむ、なれそめというやつか。うーん、と言ってもそう特別なものではないぞ」
「まあ、そうね。単純に女性が苦手とか言ってられない場所にいたってだけだもの」
要領を得ない答えに、ソウジ、真川の両名は揃って首をかしげる。
まあそうよね、とため息をついた夕霧は、何でもないような口調で
「初めて会ったのは10年前。そのときの私達は、殺しあう関係だったの」
そう、あっけらかんと言い放った。
【クロ 2014.10/09】
「いやいや、よさないか」
劔は手のひらを夕霧に向けて制止した。もう片方の手は後頭部を掻き、顔は俯き気味だ。照れ隠しである。
「とりあえずあれだ。そういう話は家に戻ってからだな……」
劔がボソボソとそう言うと、ソウジはやれやれといった感じでため息を吐いた。
「やっぱり、兄さんなんだなぁ」
ソウジは何度目かの懐かしさと、兄の存在の温かさをかみしめる。そして、これから実家へ赴くことを考えれば、大層心強くもあった。
「では、僕はこの辺でお暇させていただきます。僕にも僕の、里帰りがありますので」
真川は丁寧に頭を下げ、別れを告げた。ソウジから付き添ったことへの感謝を受けた真川は、三人が見えなくなるまで手を振って見送った。
真川は懐から携帯端末を取り出す。慣れた手つきでそれを操作し、通話を開始した。
「僕です。お久しぶりです」
「ええ、実は……まあ、そんなところです」
「はい、もちろん戻りますよ」
「今は里帰り中で……そうそう彼と道中一緒でしたよ。ええ彼です。お兄さんとも会えて元気そうでした」
「え?それだけですけど。何故って?あー……何となく、ってやつですかね。では。」
何かを遮るように通話を切った真川はふと空を見つめ、ため息を漏らす。
「さて、帰ってどう話したものだろう……。信じてもらえるだろうか……」
【タタリ 2014.10/12】
八百段の石段を上り抜け、伏神山の麓にある上伏神社へ出る。境内を少し歩くと更に蛇行して君臨する石の階段。その数、実に千五百。それが伏神本家へ通じる「舗道」である。
無論、物資や生活消耗品などの搬入に使う車道も存在するが、そちらは馬車馬の負担を減らす様にやや勾配のあるほとんど平坦な道になっていて、人が歩く分には遠くなる。何とも恐ろしい事に、直通するなら二千三百段もの階段を歩いた方が早いのだ。
更に恐ろしい事実をもう一つ。伏神の祭殿はもっと山頂に近かった。そこに到達する為には更に二千三百段の石段を登らねばならない。まぁ、今は過去のアレコレのせいで、中途あたりからクレーターみたく抉れて跡形もないんだけど。
「……ああ、もう。エスカレーターとか設置しようぜ、兄さん」
「えすか……れぇたぁ……? 何だそれ?」
段差を一つ一つ踏み抜き、登りながら、先を歩く劔に提案するが怪訝な表情を返された。しまった、そもそもこのクソ田舎、電気すら通ってないんだった。
旅行バッグは麓の分家に預け、後で届ける様に伝えてある。分家の人が馬車を出すと提案してくれた時は渡りに船と感動したものだが、兄さんが健康の為には少しくらい運動しないとなハッハッハーなんて言い出さなければこんな事には……!
というか、オイそこの筋肉。そもそもその筋肉に少しくらいの運動が必要あるのかと問いたい。
「休憩……神社に着いたら休憩しよう、兄さん。マジで足腰がもたない……」
「おいおい。もうへばったのか? このくらい、昔は麓に行くのに何往復もしてただろう?」
「機界の利器は人を駄目にするって絶賛実感中だよ!」
改めて帰省してみて当時の異常さがよく分かる。あの頃の俺はどうやってこの階段を下って麓の学習塾に向かい、昼には家に帰って食事を済ませ、夜深くまで外で遊び歩いていたと言うのだろうか。こんなの片道でギブアップだよ!
「まぁ、いいんじゃないかな? たぶんこの時間帯は私の妹も神社にいるだろうし、顔合わせはしておくべきだろう?」
夕霧さんの提案に、劔兄さんが「それもそうか」と同意する。思わぬ方向からの援護射撃に感謝の極みである。ありがとう夕霧さんとやら。
……しかし妹、妹ときたか。俺は改めてフードを目深に被った夕霧さんの顔を横目で眺める。
フードの裾から覗く銀の髪に、吹雪の夜を彷彿とさせる紫色の瞳は切れ長で眼光鋭い。肌は白く、それだけに顔の右半分を覆い尽す様な赤い刺青がよく映える。
うん。もう嫌な予感しかしない。帰るんじゃなかった。
日差しは木々に遮られているとは言っても、残暑は残暑だ。階段登りで披露はピークに達しようと言う現在、俺は汗だくである。やがて神社の鳥居が見えて来た頃には四肢を使い、登ってるのか転んでるのか判断つかない様な状態であった。
「「暑っつい……」」
鳥居を潜り、上伏神社の境内に入った開口一番に吐いた俺の悪態は、鳥居の日陰で日差しを避けていた人物と見事にハモった。お互いに首を向けて、お互いに存在を確認し、観念した様に同時にため息を漏らした。
「まぁ、なんつーか……夕霧さんに妹がいるって聞いた時点でお前だろうと思ったよ」
「姉さんの婚約者が伏神なんて珍しい苗字の時点で、こうなる事は分かってたさ……」
俺、および鳥居にいた人物はそれぞれ左右の鳥居の脚に腰を下ろし、息も絶えだえに諦める事にした。長い階段を登ってきた俺は疲労で、あちらさんは残暑にやられて言い争う力さえ残っていない。
劔兄さんと夕霧さんは俺たちが知り合いだと思っていなかったらしく、きょとんとした表情でこちらを見ていた。
「あぁ、自己紹介はとっくの前に済ませてる。クラスメイトだよ、俺ら」
そう。何を隠そう、鳥居の下で日差しを避けていた人物とは驚くべき事に、クラスメイトであるガングロ雪女の柳瀬川朝霞だったのだ。(棒読み)
「で、お前はこんなところで何をやってたんだ?」
「姉さんが婚約者の弟を迎えに行くって言うから、着いていこうとしてたんだよ。……あたしは努力はした。超頑張った」
「その努力は買おう。気持ちは分かる」
大人組が神社の神主である織守拓人(おりがみタクト)に挨拶に行っている間、俺と朝霞は適当な会話で時間を潰す事にした。朝霞の態度がいやにしおらしいと思うなかれ。これは単に夏バテしてて喧嘩腰になるのも億劫だというだけだろう。
「それだけじゃないけどな」
「どういう事だ?」
「そうだな……テメェにあたしらの事情を喋んのは癪だが、伏神の末裔ならいずれ分かる事だし、仕方ねーか」
言いながら、朝霞は神社よりやや高い場所を指差す。そちらに視線を預けてみると、よくよく見れば一部の森が伐採されている事が分かる。火を起こしているのだろう、僅かな煙が立ち上がっている。
先にも述べたが、伏神山は霊山であり、一部の登山ルートを除いて一般人の立ち入りは禁止されている。標高が高い訳ではなく、地盤も安定しているので雨災時の土石流などもあまり発生せず、生活は安定しているにも関わらず、だ。
その一部が開拓されている。これは俺が五界統合学院に行く頃にはなかった。つまり、俺が実家を空けている間に何らかの介入が行われたという事に他ならない。
「あの辺に、あたしたち魔界人の移籍集落がある。区画整備で居所を無理やり造っただけの杜撰な物だがな」
「知らなかったな、初耳だ」
必要最低限すら連絡を取ってなかった訳だから、当然といえば当然なのだが。
「伏神山が霊山って事は知ってる。僅か数十人だけとは言え、居所を与えてくれた劔さんには感謝してるよ。……まぁ、御意見役の老人たちと一悶着も二悶着もあったって聞いてるけど」
「あの老害どもは本当にしょうもないな」
「で、居住区を提供するための交換条件が、集落から一名の代表者を伏神家で生活させること。そして、定期的に集落の状況を伏神家に報告させること。最後に、代表者の親族を五界統合学院に編入させること」
「……お前、それって……」
老害どもは、本当に姑息で卑劣な手を使ってくるものだ。誇るつもりは微塵もないが、同じ伏神の血統として実に腹立たしく思う。
つまり、体の良い人質だ。魔界人が不審な行動を行った場合、柳瀬川姉妹がどうなっても知らないぞという脅し文句だ。わざわざ五界統合学院に朝霞を編入させたと言う事は、守手四十七氏の権力を経由して人間界政府とも手配済みだろう。
魔界人の脅威を出来る限り分散させて、意思の疎通を物理的に切断する。そこに白羽の矢が立てられたのが、柳瀬川姉妹という訳だ。
「幸いと言うか何と言うか、劔さんと姉さんは元々知り合いだったらしいから、形だけでも結婚という体裁を執る事で御意見役たちの意見を通したらしい。姉さんは今や伏神の本家で生活してるって話だが、少しは待遇も緩和されてるんじゃないかな」
「兄さんらしいや」
困った人を見捨てられなかったり、理不尽な権力を嫌ったりするところは相変わらずらしく、かつての記憶と変わらぬ兄の姿にほっとため息を吐く。
しかし、これで合点がいった。初対面の朝霞は俺にやたらと辛辣な態度を取っていたが、あれは俺がどうという問題だけではなかったのだろう。いや、第一印象が最悪だったからこそ原因は全く別とは思わないが、あれはたぶん……人間界そのものへの憎悪があったのだろう。
「ま、あたしがこの辺の事情を知ったのは、つい昨日の事なんだけどな」
「そういや、先にここに来てたって事は、俺より早く出たって事だもんな。俺は兄さんから連絡を受けた翌日に都内を出たが、お前は休日前に出立してたのか」
「あぁ。伏神ってのは少なからず嫌いだが、劔さんとは少し話して、悪意がない事は分かった。テメェは未だにいけ好かねぇが、劔さんの面子もあるし、まぁ少しくらい認めてやらんでもない」
「どんだけ上から目線だよお前」
いやまぁ、別にいいんだけどな。ゴミ屑からゴミにランクアップしたところで実数値的な差はなかろうて。
そんな事情を聞き終わった頃、織守と話を終えた大人組二人が帰ってきた。手には風呂敷を抱えている。おそらく織守さんち秘伝のおはぎだろう。あれは昔から美味いんだ。
「仲良さそうだな、二人とも」
「「いや、全く良くねぇよ」」
くつくつと笑いながら歩み寄ってくる夕霧さんに向かって、顔の前でパタパタと手を振る俺と朝霞。コイツと仲がいいなんて死んでもゴメンだ。アシュリーとよろしくやってる方が百倍マシってもんだよ。
さて。だいぶ時間を食ってしまったが、いよいよ本家に足を踏み入れる事になってしまった。
ああ嫌だ。覚悟は決めていた筈なのに、いざ帰るとなると本当に憂鬱だ。当初の予定であった兄さんの結婚報告は聞いたのだし、もう帰っても問題ないと言うのに。
……って言うか。その前にもう千五百段ほど階段登らなくちゃならないってのが一番イヤなんだが。
【どあにん 2014.11/04】
ようやく1500段を登り切って後ろを振り向くと空は橙色に染まり、麓の村々がまるで宝石をまき散らしたかのように輝いている。
幼い頃に幾度と無く見てきた光景は、今も変わらないままそこにあった事に、つい涙腺が緩みかける。
本当に泣きたくなるのは、これからだと言うのに。
「お帰りなさいませ、聡治様」
開けた瞬間、音の波がソウジの鼓膜を叩く。
屋敷中の女中全員が石道の脇で頭を深く下げている、そんな事など一切望んで居ないのに。
だからソウジは心を殺して無心になる、脇にいるのは全員石なのだ……そう考えていなければ居心地の悪さに押し潰されそうだから。
最も、玄関の前に佇んでいるのはその居心地の悪さの発生源とも言うべきか。
「……戻ったか、聡治」
伏神家27代目頭首、伏神楯一郎。
御年80を超える肉体は大きな隆起が彫り込まれている為老いによる衰えを一切感じさせない。
着物から見える肌からは勿論、顔にも巨大な傷痕が刻み込まれている事から、歴戦の強者だと言う事を認識させられる。
ソウジは幼い頃から自分の祖父はあまり好きになれなかった、なぜならば。
「……ただいま、爺ちゃん」
「ぬわぁぁあああああん!!!会いたかったよぉぉおおおお!そうじぃぃぃいいいい!!」
……超が千個付いても足りないくらいの孫LOVEだからだ。
「見苦しい所を見せたな、聡治」
「あー……うん、いいよ気にしなくて……」
はだけた衣装を直しながら今更威厳たっぷりに言っても遅いよ爺ちゃん、とそっと呟いた。
第一に筋骨隆々の老人がソウジの足元でゴロゴロと転がりまわるカオス過ぎる光景を見た劔や朝霞に夕霞も苦笑いしていた。
伏神一族は変人一族だと思われそうで怖い。
「ま……何はともあれ、お祖父様もお元気d」
「お前には話しておらん、黙っておれ」
何故か楯一郎は劔に対して厳しいと言うより嫌ってるようなフシがある。
息子を未だ溺愛する姑の如き嫌われっぷり、短く笑う劔だったけどその眼には微かな涙。
そして夕霞と朝霞の冷ややかな眼が劔に追い打ちをかける、その眼はあぁやっぱり変人一族だ、と無言の罵倒。
夕霞さんの表情が"なんでこんな奴と結婚しちまったんだろ、今から離婚届出そうかな"みたいな顔をしている。
ソウジは内心"やめてくれマジで"と叫び続けた、そんな事になったら余計劔が楯一郎にあーだこーだ言われそうだからだ。
「うむ、長旅で疲れたろう 上がっていけ。 夕霞さんにその妹さんもな」
背を向けて一人家の中へ入っていったのを皮切りに、女中達が本来やるべき仕事へと戻っていくのを脇目に、劔と夕霞さんは歓談しながら、朝霞は面倒くさそうなしながら家の中へ入っていった。
ソウジはと言うと荷物を置く為に自分が使っていた部屋に行こうとした際、楯一郎がソウジの名前を連呼しながら跳ねるような音が聞こえたので、ソウジはそっと聞こえないフリをした。
部屋に荷物を置いて面倒くさそうに必要最低限身支度を整える、ソウジにとって最も嫌いな時間である御意見役の老人達への報告があるからだ。
最終決定権は楯一郎にあるものの、近頃は暴走が目に余ると劔から言われていた上に楯一郎を決定を待たずして執行する事が多くなってきたからだ。
幼い頃からずっと御意見役の老害に嫌われていたソウジ、唇を軽く噛み締めてから力無く歩き始めた。
◇
一方その頃。
「俺のセンサーがビンビンに感じてるぜ!多分あっちだ!」
「言っとくけど、股間にぶら下がってる粗末なモンの事指してるならブン殴るからな!」
「ま、待って……おいてかないで……」
三馬鹿はジョエルの無駄に元気な一声を元に道なき道を行っていた。
【西口 2014.11/06】
夜の森林は、月明かりすら遮る漆黒の要塞である。
人工灯のない人間界の奥地にあると来れば、それは言うまでもない。
獣すら近寄らぬそこに跋扈する魑魅魍魎は、はたして悪鬼の類か、それとも精霊か。
「彼」の容姿のみを見れば、誰もが前者だと答える事だろう。
草臥れた漆黒のスーツに身を包んだ、巌の如き頑健な肉体を持つ青年。
その眼光は右手に握る太刀のそれにも劣らぬほどに冷たく輝いており、その瞳で射竦められて正気を保てる者はそういないだろう。
地面に横たわり、首元に太刀の切っ先を突きつけられているローブ姿の女性は、その数少ない一人であった。
「届かせて貰ったぞ、キリ。些か手古摺ったがな」
青年――伏神劔は、普段弟に向けているそれとは打って変わったような、ゾッとするほどに冷たい声音で呟いた。
地面に横たわる夕霧を逃がすつもりなど毛頭無いのだろう。勝敗が決したと思しき場面でありながら、総身には未だ緊張が漲っている。
夕霧はその顔を無感情な目で見返し、やがて大きなため息を吐いた。
「……ええ、完敗ね。情けないことこの上ないわ、劔」
そうして彼女は恭順の意思を示すかのように両目を閉じる。
フードから投げ出された白雪色の髪は土に汚れ、見る影もなくなっている。
普段の彼女ならばこの上ない渋面を浮かべるだろうが、疲労の極致にいる今となってはそんな事言っていられないのか、何も言わない。
いや、ただ諦めているのだろう。
人は死ねば唯の肉。その見てくれを演出する必要などない。
彼女は死を覚悟しているのだろう。このような状況に陥ってしまったがゆえの、当然の報いだと。
「殺しなさい。一廉の戦士なら、敗者を辱める様な事はしないんでしょ? 私は守った事ないけど」
「そもそも尖兵たる露払いにそんな矜持は求められないものなんだが。というか、それ以前に――」
――約束をたがえる気か?
どこか砕けた声音で、劔は言う。
夕霧はいまさらといったタイミングで、この上ない渋面を浮かべた。
「ストーカー気質ね。何でまだ覚えているのよ」
「差し迫ってきたからだよ。早急に君が欲しくなった」
「斬新な婚活ね。まあ、貴方みたいな人間の所に嫁いでくる人間なんているわけないとは思うけど」
「……相変わらず、口が減らないな」
ぼやきながら刀を引き、納刀。
キン、という特徴的な金属音が、一瞬だけ夜のしじまを侵した。
「俺が勝ったら何でも言うことを聞くんだろう? 死ぬ事は許さんぞ」
手を差し伸べて、劔は言う。
渋々といった様子でその手を取り、立ち上がった夕霧は、「仕方ないわね」と本当に嫌々といった様子で呟く。
「14歳の頃から6年間、貴方に負ける日が来るなんて思わなかったけど、もうダメね。今後貴方に勝てるようになるヴィジョンが浮かばないわ
よくもまあここまで鍛え上げたものだわ。何かきっかけでもあるの?」
「ああ、ちょっとな」
劔の顔に、微かに陰影が差す。その中に微かに灯るのは、憎しみの色だろうか。
夕霧が初めてみる表情だった。
戦争当時の機界人めいた冷徹さや無感動さを纏った彼の姿には慣れていたが、そこまで剥き出しの感情を面に出す劔の姿は、初めてだった。
「……本当に、何があったの?」
「――妹が死んだ」
表情を見られまいとしているのか、劔は天を仰いだ。
「母が死んだ。叔父が死んだ。祖母が死んだ。従兄弟が死んだ。使用人が死んだ。彼ら、彼女らの子供も死んだ。沢山、沢山な」
きつく握り締めた劔の右手から血が流れる。気付く夕霧だが、話の腰を折ることも出来ず、無言のまま続きを促す。
「父が、老害どもが見果てぬ妄執に取り付かれたせいで、皆死んだ。だというのに、伏神はまだ残り、そこにへばり付く老害どももまだ大量にいる」
「貴方、まさか……」
「伏神を潰す。あの死にぞこないどもを、一人残らず地獄に叩き落してやる」
劔の視線が、夕霧のほうへと戻る。
「夕霧。君たち雪女全体にではなく、君個人に頼む。力を貸してくれ」
そうして、頭を下げた。
◇
「あら、どうかしたの?」
伏神邸、自室。
伏神劔は開け放った窓から見える、茜差す伏神山の光景に目を細め、見入っていた。
じっとりと汗ばんではいるものの、薄手の甚平一枚という格好は妙に涼しげである。
それと正反対のような暑苦しいローブを纏った夕霧が、その後姿に声を掛けつつ、開け放たれた障子戸を閉めつつ入室する。
「物思いにふけるなんて、貴方らしくもない。耄碌でもしたのかしら?」
「いや、お前の手を取った日を思い出してな。そうか、あの日からもう四年も経つのか」
「走馬灯を見るには早すぎるわよ。まだ何も終わってはいないわ」
その傍らに寄り添うように座り、夕霧は忠告めいた口調でそう言う。
「ああ、そうだな。……チャンスは明日の夜。ソウジと朝霞ちゃんに気付かれる前に全てを終わらせよう」
「ええ、分かっているわ。そのためには、貴方の右腕の力が必要になる。ちゃんと使いこなせているのね、その竜の力」
劔は首肯のみで以ってそれに応じ、右腕を撫でる。
分厚い筋肉に鎧われたそれは、強靭ではあるものの、さしておかしな部分は見当たらない。
――今はまだ、であるが。
「しかし、まさかお前と結婚する事になるとはな。都合がいいとはいえ、流石に予想外だったぞ」
「それは私の台詞よ。伏神家は前々から嫌いだったけど、上が「ああ」じゃ腐ってて当然ね」
「耳の痛い話だ。全てが終わったら、婚姻関係を解消してくれて構わない」
「……して欲しいの?」
眉を顰めながら、不機嫌さの塊のような声でそんな事を言った夕霧に、劔は驚いた。
夕霧は劔の顔を真っ直ぐ見つめ、「私が妻じゃ迷惑かしら」と続ける。
「いや、そういう事じゃなくて、お前の自主性を重んじようと思ってだな」
「答えになってないわ。貴方はどうかと聞いているの」
ずずいと身を乗り出して聞く夕霧。その勢いに気圧され、仰け反る劔。その巨体を威圧する眼光はただ事ではない。
彼女は今、紛れもなく怒っている。
「あーと、それは、だな……」
「口ごもらない。好きか否かを、娶るに足るか否かだけを答えなさい。今すぐに。ナウ」
「す、あー。好き、だよ。お前が妻になってくれるのなら嬉しい」
「……そう、ならいいわ」
潮が引くように萎んで行く彼女の怒り。
睨んだ相手の心臓を鷲掴みにするかのような威圧感も、また同時に。
劔は心底からの安堵のため息を漏らした。
「貴方気付いていなさそうだから言っておくけれど、私貴方の事大好きなのよ。勿論恋愛的な意味で。
突き放すような事言わないで頂戴。悲しくなるから」
「は、初耳なんだが」
「初めて言ったもの。ああ、恥ずかしい。顔から火が出そうだわ」
顔を逸らしながらそういうが、夕霧の声音は飽くまで平坦である。
だがそれが紛れない真実であることが分かる程度には、劔と彼女の関係は深い。
劔は無言のままその頭を抱き寄せ、夕霧もされるがままだ。
窓の外。伏神山に野鳥の声が木霊する。
少し紫がかった夕空に、沈み行く夕陽。徐々に降りてくる夜の帳が、それらを美しく演出する。
劔にとっては慣れ親しんだ光景だ。幾度となく流し見してきた光景だ。
だが改めて見ると、そのためいきでも出そうなほどに幻想的な風景はどうだ。
これで見納めかもしれない。
そう無意識かに思っているのだろう。二人はただ黙って、日が没するその時まで共にその光景を眺めていた。
【クロ 2014.12/01】
邸内の杉林の奥、離にひっそりと佇む茶室に、無数の灯りが微かに揺れる。薄暗い茶室の中には、昏い眼光とか細い息遣いが潜んでいた。
その一つがため息を吐くように発す。
「まさかあれが帰ってくるとはのぉ」
他の一つが口の中を汚く鳴らす。
「あれを呼んだは劔のようじゃ。まだあれに情があったか……」
また他の一つが鼻息で灯を崩す。
「それよりまさかあの柳瀬川の娘を娶るとは……。なんぞ企みがあると見た……」
そのまた他の一つが音もなく笑う。
「然り……柳瀬川にあれ、時が時だけに臭いよる……」
それのまた他の一つが歯を擦る。
「それならようやっとあれに使い道が生まれたのぅ。あれも駒に成れる日がくるか……」
それらは一同に灯りと共に身体を揺らし、浮かぶ顔に数多のしわを刻んだ。
「そりゃあええ……そりゃあええ……」
【タタリ 2014.12/09】
夜中、不意の気配に目が覚めた。
片目だけを薄く開けて自室をゆっくりと見渡す。昔取った杵柄というか、エクリエル達と共に乱層区画に出入りしてるせいで、気配の察知が敏感になってるのは常人離れしている様でなんか嫌になる。
俺が実家を逃げる様に飛び出してからも、使用人たちが甲斐甲斐しく手入れしてくれていたお陰で、自室はかつてと変わらない状態でいつでも使える様になっていた。寄宿舎よりも広いし、実に快適である。
そんな光源一つない真夜中、薄らと目を開けると、そこには銀髪の女が立っていた。……自分で言っといてなんだが、このシチュエーションすごいコワイ。
「……お前、何やってんの?」
「チッ、起きたか。とりあえず蹴り起こそうかと思ってたんだがな」
身を起こしながら銀髪の侵入者こと柳瀬川朝霞に答える。枕元に置いていた腕時計を手繰り寄せ、現在が午前一時である事を確認する。いやマジで何してんだコイツ。人の安眠妨げるとか万死に値するぞ。
とりあえずはだけた寝間着を居直しながら、文机からランタンを取り出してマッチで火を付ける。ここでようやく視界が良好になった訳だが、朝霞の姿を見て怪訝に思う。
彼女は寝間着ではなく、平時の私服だった。いや、私服というには厚手であり、肌の露出を限界まで制限している。昼に比べて夜は幾分かマシだと言っても、まだまだ熱帯夜は続いている。人間でも参る様な残暑を、雪女である彼女が厚手の服で耐えられるとは思えない。
「……クソ、マジ眠い。アタマ働かねぇ。殺されてぇのかお前」
「やれるもんならやってみろ人間風情が。……あ~、いや待て、今のは言葉の綾だ。そうじゃなくてだな、何て言えばいいか」
「夜這いじゃなけりゃ相談だろ。ちょっと待て、準備するから。先に聞いとくが、俺の部屋に入る前に後ろは確認したか?」
「うんにゃ、それは大丈夫だ。魔界人の知覚をなめんなよ」
「自信過剰の自意識過剰で何よりだ。年頃の女を連れ込んだとか、使用人に見られて噂とかされたら恥ずかしいし」
アクビを噛み殺しながら荷物を漁り、八枚のカードを取り出す。機能は単純な消音。それを部屋の四隅の天井と床それぞれに投げ放ち、部屋全域に結界を張る。
書記魔法は事前準備が必要な分、準備さえ済ませておけばどんな魔法体系より早く発動させる事が出来る。また、文字や記号として保管する事が可能な性質上、一所のみに魔法効果を限定する結界魔法との相性は良い。
あらかじめ文字を設置さえしてしまえば、任意のタイミングで時間差発動を行えるところもメリットの一つと言えよう。先日のドネルクラル戦では人質奪還のため敵拠点を攻撃する必要があったゆえ結界として使用する事はなかったが、伏神家は元より陰陽師の家系、攻勢より防衛に重きを置いている。実はこちらが正しい使い方なのだ。
そもそも普段から乱層区画で戦闘を行う場合には、エクリエルやルカと言った攻撃力カンストしてる様な化け物と一緒なのだから、わざわざ俺が前衛に立つ必要がないってのが一番の理由である。いやアイツら本当に凄いんだって。地面えぐったり地形変えたり焦土にしたりは当たり前なんだから。マジで。
「とりあえず音が漏れない様にしたから、普通に話していいぞ。このカードなら……まぁ十分がいいとこだがな」
「……お姉ちゃんから話は聞いてたが、お前って実は凄い奴なのか?」
「アホ吐かせ。この程度なら学院生は誰でも出来る」
「いや、確か書記魔法ってあらかじめ文書に込めた魔力で効果が上下するから、全て均等な魔力量でないと結界は維持できないだろ」
魔力を別に保存しておき、術者の魔力に負担を掛けずに済むのも書記魔法の特徴だ。反面、作成後に魔力量を調整する事が出来ないので、複数枚を同時に使用する場合の運用が難しいというデメリットもある。
現在構成している消音の結界にしても、カードに充填した魔力が均等・一定でなければ結界が崩壊してしまい、カード自体が消滅する事もある。故に、書記魔法使いは用途に応じて魔力量ごとにカードを分別するか、全て均一にして互換性を持たせるかのどちらかを選ぶものだ。ちなみに俺は基本的には後者である。【憤怒】や【怠惰】などの特殊な物を除き、どのカードを起点にしても連鎖(コンボ)を行えるよう調節している。
「魔力量を均等にするって事は、ミリ単位の誤差も許されない、機械の様な精密さが必要な筈だが……まぁいいか。テメェの技量には一切興味がねぇ。本題に移ろう」
「人の安眠を妨害してまで頼み事しようとしてる奴の台詞じゃねぇ!」
なんなのコイツこんな夜中に喧嘩売りに来たの? 今なら高価買取期間中だよ?
「昼間、あたしが一人で行動してた事を覚えてるか?」
「ああ。神社でへばってたな」
「あれな。実は、伏神山を攻略しようとして失敗してたんだ」
「うん。ごめん、一から説明頼む」
伏神山を攻略とかちょっと何言ってるか分かりませんね。あれかな、現実と仮想の区別もつかないRPG廃人の末路がこれって事かな。俺はこうならないよう気を付けよう。ゲームは一日一時間が基本だね。
「いや、この山が霊山で一般の立ち入り規制してるのは分かるが、あの警戒は正直、異常すぎるぞ。魔界人のあたしもドン引きだ」
「俺が上伏にいた頃はそんな事はなかった筈だが、具体的にどう異常だった?」
「簡潔に言うなら辺り一帯すべてが結界の地雷原。たぶん、伏神の中でもごく僅かな人間しか歩き方を知らないだろうってくらい密集してる。あれは侵入者や脱走者を殺す為の配置だと思った」
「それマジ? 俺の知らない間に上伏も物騒になったもんだ……。いつからここは世紀末になったんだか」
とは言うものの、だいたいの見当は付いてる。この場合、何を以て「侵入者」や「脱走者」とするのかが問題だが、現状の伏神の情勢を鑑みればすぐに解答は見えてこようと言うもの。
上伏は伏神の領地である。市井は伏神の決定には逆らえないし、霊山立ち入れば祟られると教育されてる者が面白半分に立ち入る事はない。……いや、ごめん、あるわ。
幼少期や少年期の一時期、その手の度胸試しが流行った事がある。子供ながらの怖いもの知らずによるものだが、爺ちゃんや親父にこっぴどく叱られた事を思い出した。主犯の俺は特に厳重に。
「で、お前はどうしたいんだ? というか改めて聞くが、俺に何をさせたいんだ?」
「もちろん、攻略のサポートをして欲しい。あれは明らかに──あたし達を敵視している。理由は反乱防止と、幽閉の為ってところか」
「十中八九そうだろうな。伏神が山の一部を開放してるってだけでも充分に異常事態なのに、きな臭いとは思ってたんだ」
さて、朝霞の趣旨は理解した。理解した上で再三述べるなら、だからなんだ、である。
見も知らず、特に仲の良い訳でもない──というか最大の天敵である──柳瀬川朝霞ちゃんの同胞の為とか言われたって、素直に従う理由も義理もあるまい。夕霧さんにでも頼めよ。
「そもそもお前、考えが足らなすぎるだろ。俺だって伏神の血族なんだぞ。探られてるなんて伏神に密告されたらどうするつもりなんだ。兄さんと夕霧さんが築いてきた物をお前のワガママで潰すつもりかよ」
「お前が本当に心底から伏神の人間なら、そんな忠告はしねぇだろ。あたしが起こしに来た時点で人を呼んでる。だからあたしの事情を話そうと思ったんだよ」
「どんな博打屋だよ。一か八かってレベルじゃねーぞ。勝率低すぎる賭けだろそれ」
「でも、勝った。ならあたしはそれでいい。さあ手伝え」
「すいませんね柳瀬川さん、朝一でいっぺん死んでくれませんかね」
眠いっつってんのに隠密登山とか本当に勘弁してくれ。付き合う動機なんてないんだってば。
仮に付き合うとしても、俺に出来る事なんてたかが知れてる。地雷の設置場所どころか存在そのものを今知ったのだ。探知しながら歩ける様ならいいが、曲がりなりにも伏神は陰陽師の名家だぞ。やってみない事には何とも言えんが、俺みたいな一介の学生が攻略できるならお前も最初から苦労せんだろう。
「頼めるなら地雷を無力化していきながら里まで行きたいんだが、最悪、あたしの前を歩いてくれるだけでいいからさ」
「本当に最悪すぎるだろ!」
俺に死ねと!?
【西口 2014.12/09】
リリリ、リリリ、と静寂を侵すでもなく、寧ろ彩るような虫の声に聞き入るかのように、彼女は眼を閉じ、身動ぎもしない。
艶めく黒曜石の如き黒い髪。どこか陶磁器めいた無機質さを湛えた白い肌。
総身を包む瀟洒なドレスから覗く手足は、彼女の名前を象徴するかのように昏く、鈍い輝きを放っている。
半機人の少女――クロガネは一人、深夜の伏神山でひっそりと、静寂の渦中にいた。
「……これは、少々予想外の事態ですね」
誰にともなく、クロガネは呟いた。
周囲に人影はない。
だが彼女の言葉は夜闇の漆黒に溶ける事無く、「彼」の耳朶を打っていた。
「全面的に同意だヨ、01《ゼロワン》。いやはや、まさかこんな東の辺境に《竜》がいるとは。それも1や2では利かないほど。
対策室の情報収集能力というのも、存外当てにならない。これでは作った意味がない」
電子的な通信手段によるものではない。それは紛れもなく肉声だった。
クロガネ以外の何物もいないはずのだというのに、「彼」の声は真実、周囲の大気を震わせていた。
「結果論的な物言いになってしまいますが、やはり貴方についてきて頂いて正解でした、室長」
「もうセンセイとは呼んでくれないのかい? おじさんは寂しいヨ」
おどけた調子で言う「彼」にクロガネは心底面倒そうにため息を吐いた。
あからさまにうんざりとした表情を浮かべる彼女を見たら、ソウジなどの普段のクロガネを知っている人間は驚くことだろう。
楽しそう、というわけではないが、今の彼女は驚くほどに喜怒哀楽に富んでいた。
恐らく彼女自身も自覚しているわけではないのだろう、その仕草はこの上なく自然であった。
「阿呆なことを言っていないで、早急に対象の護衛に向かってください。私は《竜》を追います。
下手をすれば、貴重な《龍憑》のサンプルが失われる事態になりかねませんからね」
「サンプル、か。無機質な呼び方だね。お前もすっかりウチの連中と似てきてしまった」
「……室長」
「ああ、ああ、分かったヨ。怒らないでおくれ。はあ、若者に酷使されるのも老人の宿命かな」
肩を竦めているのであろう事がはっきりと分かるような声音で言い、「彼」はクロガネのそばを離れる。
周囲には、誰もいない。当然、誰かが走り去る音もなどするはずもない。
だというのに、鬱蒼と茂る樹木の間から降り注ぐ月光は、確かに「それ」を浮き彫りにしていた。
起伏に富んだ山肌を難なく駆ける影を。
疾走する影「だけ」を。
「さて、01ご執心の男の子か。ここはセンセイとして、しっかりと見極めなければね」
心の底から楽しそうに、「彼」は笑う。
人の形を失いながらも、一つの執念と、己の内で蠢く竜の力のみで存在を維持する異形。
人間でも、魔人でも、天使でも、機械でも、幽霊でもない第六の存在。
第六世界対策室長にして、悠久の時を生きる《竜憑》。
ズールー・イングリッド・エンド――ジ・エンドはまるで人間のように、くつくつと。
◇
「彼」が去り、真に一人となったクロガネは依然として眼を閉じている。
比喩ではなく、瞼の裏に映し出される光景をただぼう、と眺めていた。
先日、伏神ソウジに渡した指輪から送られてくる彼の生体情報が、そこには所狭しと表示されている。
プライバシーを考慮して、映像・音声の類は送られてきてはいないが、彼の体内全てをリアルタイムでモニタリングしているので
少なくとも今どういう状態なのか、何をしているのかは完全に分かってしまう。
ソウジはこの事実を知らないのだ。
故に、クロガネはなんだか悪いことをしているような気分になるが、これもソウジの安全のためだと己に言い聞かせる。
これで彼が、いわゆる思春期の男性によくある「アレ」でもしていたら、その罪悪感も一入だったろうが、幸いにも今の所はそのような情報は送信されてきてはいない。
そういった類の現象に嫌悪感やいらぬ羞恥心を抱かないのだから、半分とはいえ機械の体というのは便利な物だ。
いつもは少々疎ましく感じることもあるが、今日ばかりは感謝しなければ。
網膜に映る情報は、ソウジが未だ深い眠りについていることを示している。
ジ・エンドも向かったことだし、今ばかりはいいだろうと、クロガネは瞼を開けた。
伏神山。腐っても霊地と呼ばれるだけの事はあり、青白い月光に照らされるそこは、どこか神聖な静謐が満ちている。
その光景を美しいと思えないのは、自分の半分が機械だからだ。
その様な言い訳は通用しないということを、彼女は知っていた。
機械人にも、芸術家はいる。詩人はいる。作家はいる。コメディアンだっている。
だからこの心の冷たさは、自分自身の問題なのだろう。
鈍く輝く己の腕を撫ぜると、指先のセンサーがその冷たく、つるりとした触感を生体脳に伝達する。
本当にそれが冷たいという感覚なのだろうか。
稼動年数10年。「調整」に要した時間を含めれば、生誕14年。自我が目覚めて以来抱いてきたその不安は、今尚褪せる事無く彼女の胸にあり続ける。
彼女はずっと、人間に憧れ続けてきた。
国際的な定義での「人間」ではない。生身の体と、感情などという非合理なタスクを保有する機・霊界以外全ての世界に存在する生物。
それになりたいと、ずっと、ずっと思い続けていた。
過去形だ。恐らくこの先ずっと、彼女の些細にして見果てぬ夢は、膨大な過去の底に埋もれたままだろう。
学園に編入し、自分と対策室員、研究者を除く人間に接したとき、彼女は悟った。
人であるのは、自分にはあまりにも荷が重過ぎると。
「普通」の人間に比べて、自分の心はあまりにも無味乾燥で、ズレていて、機械的だった。
何となく同じように振舞えるだけで、喜怒哀楽を理解できていない存在が名乗るには、人間というものはあまりにも重過ぎる。
こんな両腕では、支えきれないほどに。
「……仕事もせずに何をやっているんでしょう、私は」
クロガネは軽く息を吐くと、その思考をすぐに外へと追いやった。
いっそ完全な機械ならば、こんな感傷に浸る事もなくなるのだろうか。……いや、より一層人への渇望が強くなるだけだろう。
クロガネはまるで踊るような足取りで――結界をかわすためだ――その場を去る。
まぎれもない「人間」が一人、そこにはいたが、それに気付いているモノが果たして存在したろうか。
変わらぬ調子で鳴き続ける虫々の声が、真夏の夜空に音高く響いた。
【Kの人 2014.12/17】
月が淡い微笑みを湛える夜天の下、聡治と朝霞は屋敷を抜け出す。
攻略とは要するに、朝霞は正規の道以外――つまり監視の目を潜り抜けて、魔界人の集落へと潜り込みたいのだと、聡治は受け取っていた。
夕暮れ時に集落の規模を確認した限りは、あの領域だけで全ての食料を賄う事は出来ないのだ。
詳細こそ不明ながら、少なくとも物資の遣り取りの為に安全な道が存在する事は確かであろう。
勿論その道がどの道かは聡治には分からないし、仮に知っていたとしても、監視の目を潜り抜けたいのなら使う道理はない。
ただその場合確実に言えるのは、そんな道は間違いなく関係者か、あるいは魔法的に監視されている為、通れば露見する。
故に地雷原とも呼称出来る立入禁止区画……正確に言えば、伏神家の屋敷とそこへ到る為の道、一部の登山道を除いた場所を、攻略する必要があるのだ。
聡治がその地雷原を攻略する必要性は一切ない。
精々朝霞からの評価が良くなる程度の利点しかなく、その利点も大きな物ではない。
零が百になれば心が動くかもしれないが、零が一になる程度では、大した動機にはならない。
むしろ欠点の方が大きい、というよりも大き過ぎる為、本音を言えば申し出を断り、久方振りの実家での安眠を満喫したいのだ。
それでも聡治が動いてしまったのは、多大な好奇心故の事だ。
四年という歳月の間に、伏神家は大きく変化している事は、聡治も理解している。
表面的な部分では懐かしさを感じるのだが、一歩踏み込んでしまえば、何とも言えない不気味さを容易に感じ取る事が出来る。
それに……と、聡治は自身の左腕へと視線を向けた。
――妙に疼くのだ。
意識を向けなければ気にならない程度なのだが、それでも、伏神山に近付くに連れて、違和感が徐々に増してきているように、聡治は感じていた。
左腕と言えば夏季休暇の前、禁書事件の際に真川敦……ではなく、彼を殺めたドネルクラルによって一度切断された。
その事件の際に白龍の左腕が一時顕現し、あれ以降一切の反応がなかったのだが、今はこうして違和感を訴えている。
ならば左腕が疼く原因はと考えるが、流石に、近くに竜がいるからという安易な事ではないだろうと、聡治は考える。
聡治に分かるのは左腕が違和感を訴えている事と、その違和感は伏神山へ近付くに連れて増してきているという事だけだ。
黙々と考えながら敷地を抜け出し、暫く歩けば文字通りの意味での伏神山であり、ここから先は、例えるならば地雷原だ。
考え事をしながら踏み抜いて死ぬのは馬鹿馬鹿しいと、溜息と共に思考を入れ替えた聡治は、改めて眼前の光景に意識を向ける。
――確かに、朝霞が言う通りに、異常な密度での警戒が行われているらしかった。
ぱっと視界に映っただけでも、両手では数え切れないだけの札が樹の幹に貼り付けられている。
通りからでも見える場所である為か、流石に朝霞が言っていたような殺害を目的とした物は構築されていないようだ。
精々、近付きたくないと感じる程度の畏れを芽生えさせる程度の物であり、それにしても、その結界が張られていると知っていれば、意味を持たない程度である。
「……四年前はなかったんだがな」
聡治の記憶にある伏神山には、そのような結界は張られていなかった。
本当に近付いてはならない場所には流石に、人払いの結界が張られていたが、山の入り口から張られていた記憶はない。
幸い、配置や札の記述を読む限りは、侵入した事が露見するような構成ではないようだ。
そもそもそのような構成であれば、朝霞が一度挑んだ時点で、大騒動に発展しているだろう。
つまり朝霞はそれなりの深さまでは潜り込んだが、彼女が言うところの地雷原に辿り着き、引き返す事を余儀なくされたようだった。
暫く道沿いに張られた結界を眺め続けていた聡治だったが、このままではどうにもならないと、朝霞に向かって結論を告げる事にした。
「……無理だな。何が無理って夜目が利かないのに符術……ああ、書記魔法の群れを掻い潜れって時点で、そもそも俺には無理だ」
幸い月明かりに照らされているお陰で、道沿いに展開されている結界……その発生源である札は読める。
しかし鬱蒼と茂る森では月明かりが差し込む事はなく、文字通り何も見えない状態になる。
そんな状況下で読み取れという事は、翼も無しに空を飛べ、あるいは玉もないのに球技を始めろと言われる程度に無理なのだ。
仮に操作魔法で、視力強化が出来ればまた話は別なのだが、というところまで聡治が考えると同時、朝霞に肩を叩かれる。
何だと振り向くと同時、目元に激痛が走った。
「――ッ!?」
明確に感じ取った二箇所への衝撃は、宛ら目潰しを受けたかのようであった。
暫く目元を押さえて悶絶する聡治だったが、徐々に収まってくる痛みに、ゆっくりと目を開いていく。
先ほどよりも鮮明に広がる視界は、それこそ、聡治が仮に……と考えていた操作魔法を受けた際の明度であった。
「お、前」
朝霞が何をしたのか理解出来ない程、聡治は馬鹿ではない。
方法は酷く暴力的だが、操作魔法を掛けてくれた事は間違いない事だ。
涙目のまま朝霞の顔を見やれば、褐色の健康的な顔に、嗜虐的な笑みを貼り付けていた。
「これで見えるだろ? なら、もう無理じゃないな」
態とやりやがったな、という抗議の叫びが聡治の喉元まで込み上げて来たが、それをぐっと呑み込んだ。
文句は山ほどあるのだが、一々吐き出して騒ぎにしても面倒なだけなのだ。
「……無理だと判断したらすぐに退き返すぞ」
「その位は、あたしもアホじゃないから分かってる。テメェに言われるまでもない」
赤字覚悟の喧嘩大安売り。
そんなフレーズが脳裏を過ぎり、聡治は大きく溜息を吐き出すのだった。
◇
伏神山の山中は足場が悪い。
霊山として扱われているのは良いのだが、逆に言えば人の手が殆ど加わっていない山は、自然の思うが侭に隆起と陥没をした地形となっている。
ただでさえ札を見つけてはそれを読み取りながらである為、足取りは遅々としており、体力と精神力だけは経過時間以上にごっそりと削られていく。
昼間に朝霞が到達したのは、里までの道程の二割程度であった。
逆に言えばその段階から既に致死率の高い符術が仕掛けられていたという事であり、実際、伏神山に入って暫くも歩かない内に、それらに出くわした。
種類も豊富である為に、聡治が覚えていないような構成の符術は迂回し、覚えている物は解除して進む。
聡治の体感的には既に半日程経過したように感じられていたのだが、胸元から取り出した携帯電話の表示を見る限りは、数時間程度しか進んでいなかった。
何度も迂回を強いられた為に、歩数で言えば往復する程度には進んだものの、距離としてはようやく折り返したかどうかというところである。
携帯電話の湛える朧気な光を眺めた聡治は、目潰しされずともこれで確認出来たのでは? と考えるが、もう遅い。
そもそも、最後に充電したのが五界統合学院の寮を出る前であり、電池は切れ掛かっている。
下りは速いだろうが、それでも時間的には間に合わない。昇った事は露見するだろう。
言い訳を考えておこうかとも思う聡治だったが、言い訳の思考に気を取られて、致死性の高い物を見落として命を落とす事ほど、馬鹿らしいことはない。
「っと……また密度が上がってきたな」
先ほどまでは、まだ解除せずに通れる道があったのだが、最早一々解除しなければ通れないほどに、札は密集している。
不幸中の幸いなのは、密度を上げたが故に、複雑な物が一気に姿を消している事である。
尤も、それは解除出来なかった物と比べればの話であり、何の知識もない者が解除出来る程単純という訳ではない。
何の知識が無い者が見れば、樹の幹に変な文字の書かれた札が貼られているだけにしか見えないだろう。
「……ん?」
「どうした?」
「……いや、何でもない」
自身の思考の何処かに違和感を感じた聡治だったが、何に違和感を感じたのか理解する前に響いた朝霞の声に、それを思考の隅に追いやった。
何にせよ、今は目先の地雷原の処理が優先される。
変に迂回を求められない為、ここからは一気に進む事が出来るだろう。
札を剥がし、あるいは構成を変化させて無力化させていると、視界が僅かに良くなっているのを感じ、聡治は頭上を見上げた。
鬱蒼と茂る木々の隙間から覗く空は、夜天の漆黒から群青色へと移ろいつつある。
もうじき夜が明けると思うと、里帰り早々、徹夜で地雷処理をしていた事に気づき、聡治は溜息を吐いた。
ただ、明るくなる分には困る道理は……抜け出したのが露見して怒られる事を除けば、ない。
明るくなれば、幾ら山が木々に覆われていると言っても、操作魔法の補助無しで見る事は可能だ。
そうすれば数時間も操作魔法で視界を確保してくれている朝霞の負担もなくなる。
「……負担、も」
やや眠気で鮮明さを欠いた思考に浮かび上がった事柄を、そのまま流しそうになるも、聡治は必死に掴み上げた。
自分で使うならまだしも、他人に数時間連続で操作魔法が使えるほど、朝霞の実力は高かっただろうか?
学院での授業態度は……そもそも授業であまり見かけない為詳しくは知らないが、たまに見る朝霞は、確かに操作魔法には長けていた。
自分で使うならまだしも、他人に操作魔法を掛けるのは中々に負担が大きい。
根本的に操作魔法というのは、生体を魔力で補助する技術全般を指す。
動作の補助として扱えば身体能力強化、逆に負荷を与えれば弱化となる。魔法というよりも、最も初歩的な魔力操作を突き詰めていった結果の技能と言える。
操作魔法は他人に掛けるのも可能ではあるが、対象が持っている魔力の干渉や、想定外の挙動を起こされる事で、補助の心算が負荷になる事もある。
眼球だけの補助ならばいけるのか? と思う聡治ではあるが、操作魔法などまともに使えなくなって久しく、朝霞の実力を全て知っている訳でもないので断言は出来ない。
何にせよ、今更、朝霞の真偽を問うたところで事態が変わる訳でもない。
質問は、全てが終わってから。
ひとまず目先の地雷を処理しようと手を伸ばすと同時、伏神山の何処かで爆音が轟いた。
◇
劔が目を覚ましたのは、空がまだ漆黒から群青色へと移ろいつつある、夜とも朝とも区別がつかない時間であった。
普段であれば空が群青色に染まりきり、山の稜線から朝日が顔を覗かせる寸前が劔の起床時間であったが、今日だけはそうではなかった。
今日の事を想い、神経系が鋭敏になっていたという訳ではない。
ただ単に伏神山に響いた爆音――それが、劔の耳朶を打ち据えたからに他ならなかった。
反射的に飛び起きれば既に、閨を共にしていた夕霧は窓際に寄り、伏神山の方角を眺めている。
「何があった」
何にせよ普段通りの朝ではないと、出来る限り声を荒げずに問い掛けながら、劔は夕霧の傍らに立ち、山の方を見やる。
伏神山の一角では濛々と煙が立ち昇っていた。宛ら、何かが爆発したかのように。
思わず間の抜けた表情を浮かべそうになった劔だったが、脛から響いた痛みにはっと我に戻る。
ちらりと視線を横に向ければ、鋭く目を細めた夕霧がおり、先ほどの痛みは夕霧が蹴っ飛ばした為の物らしい。
何にせよ冷静に戻った劔は、状況把握の為に思考を廻らせる。
どう考えても山中に仕掛けていた指向性対人符術が作動した規模の爆発であり、つまり誰かが伏神山へと立ち入ったという事に他ならない。
誰が、というのは分からない。
麓には人払いの結界がある為、何も知らない部外者が迷い込んだという事はなさそうではある。
ならば魔界人集落から誰かが逃亡したのか、とも考えたのだが、それもなさそうであった。
場所が明らかに集落からは離れており、そこへ辿り着くにしても幾つかは絶対に解除しなければ辿り着けない場所だ。
符術に精通している者がいれば話は別だが、山中に仕掛けられた物は別として、集落周囲は忌々しくも、本来の出入り口以外には複雑な物が仕掛けられているはずなのだ。
そうなってくれば、可能性は必然的に絞られてくる。
「まさか――」
「――劔様っ!」
脳裏に過ぎった想像を口にしようとする寸前、転がり込むように侍従の老人が部屋に飛び込んで来る。
普段であればありえないような行動を見て、劔は、自身の表情が思わず歪んでしまったのを感じ取っていた。
「急ぎでも来室の知らせは欲しいところだが」
「申し訳ございません! しかし、早急に知らせねばならない事故にっ」
侍従が叫ぶ様に告げたのは、屋敷のどこにも、聡治の姿が見当たらないという事であった。
また、伏神山への侵入者に関しての緊急会議が開かれる為、そこへ急いで欲しいというのは、考えてはなかったが、十分に予想出来る事であった。
想像通りの出来事が起きている事に、劔は思わず顔に手を当てて仰天する。
その体勢のままで大きな溜息を吐き出すと、ゆっくりと開いた目を細め、目先に迫った決断に対する思考を廻らせる。
――本来であれば、神前式の際に行動を起こすべく、計画を練ってきたのだ。
しかし、伏神山に侵入者が現れたとなれば、御意見番の者達は確実に集まる事であろう。
表向きには心配を装って。
本音では、本家の勢力を口論にて削ぐ為に。
「……夕霧」
十年来の好敵手、そして現在は婚約者である女性の名前を呟けば、分かっているという言葉が短く、そして鋭く返ってくる。
「すぐに行くと伝えておいてくれ」
「畏まりました。その、聡治様は」
「何とも言えん。捜索だけは続けてくれ」
了解の返事も程々に、慌しく去っていった侍従から劔は視線を外し、夕霧へと視線を向ける。
決意の済んだ美しい顔立ちではあるが、僅かながらに戸惑いを隠しきれていない様子である。
心配は要らないと微笑みを投げ掛けた劔に返ってきたのは、脛蹴りという肉体言語であった。
「事は計画通りにすべきだと思うのだけど」
「かもしれないな。ただ、都合が良いと言えば都合が良いんだ」
それに、という呟きの直後。
出来れば口にしたくない恥ずかしい言葉ではあるが、それでも、言わなければ伝わらない事だと、紅潮しかけた表情を隠すように、劔は視線を逸らす。
何を言わんとしているのか察しが付いたらしく、夕霧は大きく溜息を吐くと、呆れた表情を浮かべた。
「気にしなくても良いわ。最初からそういう式だって覚悟は決めてたから」
そういう式というのは、伏神家の膿を搾り出す為の決起の事だ。
幾ら女性に疎い劔でも、神前式が女性にとって憧れの式である事は、流石に理解している。
ただでさえ申し訳なく思っていたのだ、好意を知ってしまったのなら、尚更。
式を紅く染める必要がないのならそれに越した事はない。
この決起自体で式が破綻するのだが、それでも、いつかは式を開き直す事だって可能なのだ。
劔はそっと、夕霧の体躯を抱き寄せる。
柔らかな女体の感触は、力一杯抱き締めてしまえば壊れてしまいそうなほどに儚く感じられる。
かつてはそれも含めて女性が苦手であったのだが、夕霧とだけは、幾度となくぶつかりあってきた為に、そうでない事は理解している。
下手をすれば、もう二度と味わう事のないその感触。
常人よりもやや体温の低い身体を抱き締めれば、不思議と、身体の深奥で疼く不快な熱も引いてくる。
「劔」
「俺は負けんさ。……俺にはこいつがある」
視線の先にあるのは劔自身の右腕ではあるが、そこに宿るのは人間の力ではない。
劔はかつて――そう、聡理を失った日。喪失感を埋めんとばかりに擦り寄ってきた竜を、無理矢理に押さえ込んで、己の力としていた。
竜の名前を、劔は知らない。名乗った気もするが、単純に興味が無かった為に覚えていないのだ。
流石に、竜の全てを解き放つ事は危険である為出来ないが、全身に薄らと、あるいは右腕限定で顕現させる事は、これまでの訓練で可能となっている。
伏神家の膿は、流石に腐っても御意見番であり、実力が高い者も多い。
それでも所詮は人間の身であり、元から劔は高い実力を備え、更に竜の力を帯びれば、負ける道理はない。
それに……と、呟いた劔は視線を夕霧に戻し、手触りの良い銀髪を指先で梳き、撫でる。
「護るべき者を護る時の男ってのは、不思議と、誰にも負ける気がしないからな」
そんな劔に対する夕霧の返事は、照れ隠しの脛蹴りであった。
◇
爆音はあの一度きりであり、伏神山は再び静寂に包まれていた。
爆音の際に、聞き覚えのある声が、無事に下山したら朝霞に踏んで貰うだのと言っていたのを聞いた。
そして木々の隙間から、それぞれ金、橙、黒の頭髪が覗いたのは、間違いなく聡治の幻聴と幻視だ。
どうにも聞き覚え、そして見覚えのあるそれらだったが、決して知り合いの物ではないのだと、聡治は現実逃避を行っていた。
確か伏神山にエロ本を探しに行くとは言っていたが、まさか本当に探しに行っているはずがないのだ。
あれは伏神山に住まう物の怪であり、爆音が響いたのは、経年劣化を起こした札が誤作動を起こしたのだろう。
そう結論付けて、魔界人集落を目指して淡々と処理を続けて、十分ほどが経つ。
迂回路を探す必要が無い分は、処理の時間を含めても、十分もあれば相当進む事が出来る。
木々の隙間から開けた地が垣間見え、もう少しで地獄のような夜も終わると、聡治が安堵の溜息を吐こうとする寸前。
ぞくり――と、まるで電流が流されたかのように、聡治の左腕が跳ねた。
違和感止まりだったそれが、いきなり感じた衝撃に、聡治は左腕を押さえた。
幸い、その衝撃は一度だけであり、暴れる左腕を抱える滑稽な様を、朝霞に見られる事はなかった。
ちらりと視線を向ければ、朝霞は怪訝な視線を向けてきているが、直に興味もなくなったらしい。
ついと視線を逸らした先は、木々の奥に見える魔界人集落だ。
視線を周囲へと向ければ、流石に集落周辺という事もあってか、規模は小さいながらも複雑かつ殺傷性の高い物が張り巡らされている。
流石にそれを処理する事は出来ず、もしも処理するならば、多少集落に影響は出るが、物理的に作動させて処理する他になかった。
「悪い、俺の知識で解除出来るのはここまでだ。見た感じ、一帯を囲むように貼られてるから、迂回も出来ん」
「そうか……チッ、目と鼻と先だってのに」
ちらりと視線を向けて来た朝霞が、何を言おうとしているかは、大体予想がついた。
登頂前に言っていた、聡治を前面に押し出す感じで行けば、どうにか行けるのでは? とでも言いたいのだろう。
「三人分引っ掛かれば通れる道が出来るが、生憎俺達は二人しかいないからな」
聡治は敢えて、物を投げて作動させるのも無理だと言わない。
確かに物体の動きを感知して作動する物もあるのだが、山に仕掛けられているのは対人用だ。
厳密に言えば実体を持つ人間に対して作動する物であり、殆どの霊界人と大体の機界人は引っ掛からない。
前者は基本的に実体が無いので、実体を顕現させた状態で突っ込まない限りは大丈夫だ。後者は生体部品を多用していなければ引っ掛かる事もない。
つまり範囲内で石が横切ろうが動物が入ろうが作動せず、その代わり子供が入り込んだ場合でも作動するという物である。
「集落の様子ならここからでも見えるだろ? これで勘弁してくれ」
あふっと欠伸を漏らしながら視線を集落へと向ける聡治だったが、流石に夜とも朝とも判別出来ない時間のせいか、人気はない。
建物自体は木造であり、そして夕方見た通り、自活出来そうな領域とは言えなかった。
ただ予想とは異なり、集落一帯を囲むようにしてある。正規の道など、そもそも存在しないようであった。
ならば、どうやって集落の食料を賄っているというのだろう。
一々周囲の結界群を解除している訳でもないだろうし、山中を突っ切って食料を運ぶのは非効率的だ。
そもそも――この集落に誰かが住んでいるのだろうか?
「なぁ、朝霞……お前」
視線を集落から、横にいる朝霞へと戻せば、しかし、聡治の視線の先に朝霞はいなかった。
ふらりと、まるで誘われるような素振りで地雷原へと歩んで行くその背を見つけ、聡治は反射的に叫び声を上げた。
「馬鹿、止まれ!」
作動範囲内に入ったのを視認した聡治は、直後に訪れるだろう惨劇から目を背ける。
身を伏せて衝撃に備えるも、その衝撃どころか、爆音さえ響く事はなかった。
恐る恐る身体を起こして朝霞の方を見やれば、範囲内にいるにも関わらず、符術は発動していなかった。
経年劣化で破損しているのか、とも思う聡治だったが、見た限りはどれも正常なはずであった。
「朝、霞?」
呆然と呼び掛ける聡治の声に反応してか、朝霞はゆっくりと振り返った。
切れ長の紫の眼に、健康的な褐色の肌。そして新雪を思わせる白く輝く澄んだ銀髪。
それらは朝霞と同じ物だったのだが、その顔は朝霞の物とは異なっていた。
尊大さなどどこにもなく、御伽噺で語られるような、淡く儚いという言葉が良く似合う悲しげな表情。
「ちょっと待て……お前は誰だ? そもそも、何で作動してないんだよ」
震える声で問い掛けた聡治の言葉は、雪女らしき女性に届く事ない。
ただ短く、唇を動かして何かを告げた直後、まるで春先の陽光で雪が解かされるが如く、その女性は姿を消した。
助けて――聡治が聞き間違えてなければ、確かに、目の前で消えた女性はそう告げていた。
いよいよもって、夢でも見ているのか。先程のはやはり幻視だったのか。
脳内を蠢く、不快とも感じられる思考の錯綜に立ち尽くす聡治だったが、懐から響く無機質な電子音に、はっと我に返る。
携帯電話の背面には見慣れない数列が並んでいた。
一瞬、脳裏を過ぎったのは夏季休暇前の、ドネルクラルからの呼び出しだ。
ただ奴は既に死んでおり、そもそも、背面に表示される数列は、一切似ていなかった。
「も」
『この馬鹿! テメェ今どこをふらついてんだ!?』
鼓膜を叩いたのは甲高くも威圧感のある、それでいて喧嘩腰の口調であり、間違いなく朝霞の物だ。
「っ……電話で大声出すなって。……そもそも、何で俺の電話番号知ってんだよ」
『そんな事は後だ、大変なんだよ! だから、早く戻って来い!』
「状況が分からん。せめて何がどう大変なのか」
『劔さ』
「……あ? おい、朝霞? 兄さんがどうしたんだ? おい……くそ、こんな時に充電切れかよ!」
突如として途絶えた声に、携帯電話を見れば、ついに充電が切れて沈黙してしまっていた。
今まで持ったというべきか、それとも、重要な情報が伝わる寸前に切れやがったというべきか。
どちらでも構わないと、携帯電話を懐に戻した聡治は、踵を返して山を駆け下りていく。
魔界人集落の件も気になるのだが、やはり身内の事の方が、聡治にとっては優先される事であった。
胸元はざわつき、そして、比例するかのように左腕の違和感が再発している。
「一体、何が起きてやがる……」
そんな聡治の独白は、誰が答えるでもなく、伏神山に溶けて消えた。
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: