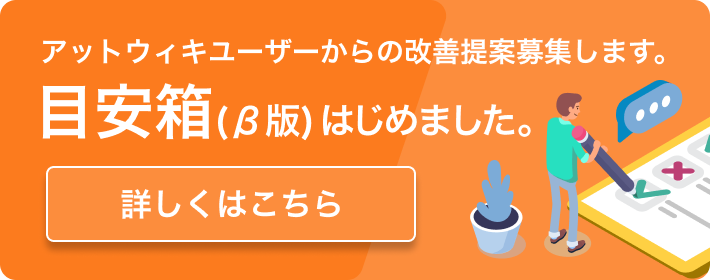歴代鬼太郎が兄弟だったらまとめ@wiki
マヨイガ
最終更新:
reki-kita
-
view
俺の通う大学の近くには大きな森、と言うよりは樹海がある。昼間でもその周辺だけは薄暗くて近所の人でも好んで近付かない。
…ここだけの話、森には割と有名な都市伝説が存在していて『森の中の廃墟には四人の子供の霊が住み着いていてその森に近付いたものを一人残らず呪い殺してしまう』とか『森に入った者は二度と出てこない』という話ばかりを聞く。
いずれにせよ、好き好んで行く場所ではないのでこれからもずっと訪れることはないと思っていた。
…ここだけの話、森には割と有名な都市伝説が存在していて『森の中の廃墟には四人の子供の霊が住み着いていてその森に近付いたものを一人残らず呪い殺してしまう』とか『森に入った者は二度と出てこない』という話ばかりを聞く。
いずれにせよ、好き好んで行く場所ではないのでこれからもずっと訪れることはないと思っていた。
…そう、あの日までは。
「カラス…煩せぇなぁ…。」
…どうしてこんなことになってしまったのか。俺は今その曰付きの森に来ていた。
隣では先日やっと出来たばかりの彼女が体をガタガタ震わせながら俺の右手に両手を絡めて来ている。
これが普通のデートならば普通に可愛いなぁ…とか思えるのに、この不気味な森のせいで全てが台無しだ。
隣では先日やっと出来たばかりの彼女が体をガタガタ震わせながら俺の右手に両手を絡めて来ている。
これが普通のデートならば普通に可愛いなぁ…とか思えるのに、この不気味な森のせいで全てが台無しだ。
…只、本当に興味本位だったのだ。俺は仲間二人と彼女の四人でドライブに来ていた。ドライブ中、誰が呟いただろうか。
「なぁ、あそこの樹海の都市伝説知ってるか?」
その言葉がきっかけで俺たちは肝試しをすることになった。
ルールは簡単で、森の廃墟の中から何か持ち出して来ること。仲間の一人は、廃墟は森の入口から近いらしいから安心しろと俺に懐中電灯を手渡しながら言った。
何を安心して良いのか全く分からないが、やたらと急かす仲間にもう何も言う気が起きず俺は彼女と廃墟を目指すことにしたのだ。
ルールは簡単で、森の廃墟の中から何か持ち出して来ること。仲間の一人は、廃墟は森の入口から近いらしいから安心しろと俺に懐中電灯を手渡しながら言った。
何を安心して良いのか全く分からないが、やたらと急かす仲間にもう何も言う気が起きず俺は彼女と廃墟を目指すことにしたのだ。
…………………………
廃墟はすぐに見つかった。見てくれは廃墟と言うよりは只の古ぼけたツリーハウスと言った方が正しいが中は蜘蛛の巣と埃だらけでとてもじゃないが見れたものではない。
足元の床板がギシリと鳴った。…懐中電灯で照らしてみて漸く分かったけど足元にはスニーカーなどの足跡がいくつもついていた。
物好きな人がいるものだ。床や壁にはマジックでここを訪れた人の名前やメッセージが無遠慮に残されていた。…いずれも埃まみれではあったけど。
廃墟はすぐに見つかった。見てくれは廃墟と言うよりは只の古ぼけたツリーハウスと言った方が正しいが中は蜘蛛の巣と埃だらけでとてもじゃないが見れたものではない。
足元の床板がギシリと鳴った。…懐中電灯で照らしてみて漸く分かったけど足元にはスニーカーなどの足跡がいくつもついていた。
物好きな人がいるものだ。床や壁にはマジックでここを訪れた人の名前やメッセージが無遠慮に残されていた。…いずれも埃まみれではあったけど。
「…ね、何かあった?」
「ちゃぶ台と…欠けた茶碗位かな」
「茶碗?」
「ちゃぶ台と…欠けた茶碗位かな」
「茶碗?」
ほら、と俺は頭や服に蜘蛛の巣やら埃やらを盛大にくっつけて取って来た茶碗を彼女に渡した。
落書きをしていく人がいる割にはちゃぶ台やら茶碗やらに悪戯が及んでいないところを見ると、これはなにか曰く付きのものであったりするのだろうか。
茶碗にくっついた蜘蛛の巣を軽く取り払って彼女が俺のほうを向いた。
落書きをしていく人がいる割にはちゃぶ台やら茶碗やらに悪戯が及んでいないところを見ると、これはなにか曰く付きのものであったりするのだろうか。
茶碗にくっついた蜘蛛の巣を軽く取り払って彼女が俺のほうを向いた。
…白い。何がって彼女の顔が、だ。
よく容姿の形容で陶磁器のような白さとか言うもんだけど、今の彼女は本当に白かったのだ。本当に血が通っているのかと疑ってしまうくらいに。
よく容姿の形容で陶磁器のような白さとか言うもんだけど、今の彼女は本当に白かったのだ。本当に血が通っているのかと疑ってしまうくらいに。
「茶碗も手に入ったし、はやいトコみんなのところに」
「…ねぇ、此処だけの話なんだけどさ。」
「…ねぇ、此処だけの話なんだけどさ。」
今までと違う、妙に低い声で彼女は俺の話を遮った。何故だろう。彼女より俺の身長は10cmも高いはずなのに彼女の顔が良く見えない。
暗闇だから?俯いてるから?分からない。だけど、彼女の顔が見えない。何を考えているのか分からない。
暗闇だから?俯いてるから?分からない。だけど、彼女の顔が見えない。何を考えているのか分からない。
「奥のほうへ、いこうよ。…わたしたちのこと、みんながまってる。」
「奥の方って…何、言ってるんだよ。奥のほうになんか何もないだろ?」
「だいじょうぶ、すぐにわかるよ。だって、わたしたちこいびとでしょ?」
「奥の方って…何、言ってるんだよ。奥のほうになんか何もないだろ?」
「だいじょうぶ、すぐにわかるよ。だって、わたしたちこいびとでしょ?」
彼女が能面のような顔で俺の腕をぎゅっと掴んだ。何を言っている?何が分かるんだ?
背中に冷たいものが走る。逃げろ、と俺の脳内で誰かが告げた。
彼女の手を振り払おうとすると、途端彼女が物凄い形相で掴んだ腕を握り締めた。ボキボキと手の骨が悲鳴を上げる。
背中に冷たいものが走る。逃げろ、と俺の脳内で誰かが告げた。
彼女の手を振り払おうとすると、途端彼女が物凄い形相で掴んだ腕を握り締めた。ボキボキと手の骨が悲鳴を上げる。
情けないことに悲鳴を上げそうになった俺に、彼女は告げる。
「あなただけなんてゆるさない。あなたもわたしたちといっしょになるべき。」
だってわたしたちこいびとでしょ?なかまでしょ?と壊れたテープレコーダーのように彼女は呟いた。
からん、とまだ若干蜘蛛の巣を被ったままの茶碗が床に落ちた音が響く。いや、茶碗だけじゃない。
白くて細い指。カラフルな色使いのネイルアートがその指先を彩っている。
からん、とまだ若干蜘蛛の巣を被ったままの茶碗が床に落ちた音が響く。いや、茶碗だけじゃない。
白くて細い指。カラフルな色使いのネイルアートがその指先を彩っている。
正確に言えば、落ちたのは茶碗ではなくて彼女の手首だったのだ。
「う……うわあぁぁぁぁぁぁぁ!!!」
耐え切れなかった俺はとうとう大きく悲鳴を上げてしまった。
がくがくと膝が笑い、立位を保てなくなった俺はぺたんと埃の積もった床へ盛大に尻餅をついた。
逃げろ、とにかく此処から逃げなくては。あれは彼女じゃない。彼女ではないヒト在らざるモノだ。
がくがくと膝が笑い、立位を保てなくなった俺はぺたんと埃の積もった床へ盛大に尻餅をついた。
逃げろ、とにかく此処から逃げなくては。あれは彼女じゃない。彼女ではないヒト在らざるモノだ。
「ねぇ、あなたもいっしょに」
「霊毛ちゃんちゃんこ!」
「霊毛ちゃんちゃんこ!」
まるで風、そう形容するしかなかった。一瞬のうちに彼女が何かに巻かれて行く。
「松兄、いたよ!いま高兄が捕まえた!」
……?何が、起こった?
声にならない声が口から漏れた。今、目の前には豹変した彼女の変わりに同じ格好をした四人の少年達が立っている。
そして、一人の少年の腕に抱かれている黒と黄色の布に包まれた何か。
声にならない声が口から漏れた。今、目の前には豹変した彼女の変わりに同じ格好をした四人の少年達が立っている。
そして、一人の少年の腕に抱かれている黒と黄色の布に包まれた何か。
「…大丈夫でしたか?」
「きみ…達は?一体…」
「きみ…達は?一体…」
一番背の高い少年が無表情で俺に言った。
「僕達は、鬼太郎といいます。『鬼太郎兄弟』なんて呼ぶ人もたまにはいらっしゃいますが、ね。」
「鬼太郎、兄弟……?な、なぁ、彼女は一体どうなったんだ?」
「鬼太郎、兄弟……?な、なぁ、彼女は一体どうなったんだ?」
互いに顔を見合わせた四人の兄弟達は、互いに言いたいことが分かるのかもしれない。一言も言葉を発することなく同時に頷くと再度俺のほうへ向き直った。
一歩、また一歩と大きな布の包みを持った少年が俺のほうへと近づいてくる。
一歩、また一歩と大きな布の包みを持った少年が俺のほうへと近づいてくる。
「彼女、って?」
「俺の隣にいただろう?…その、腕の取れた女、が。」
「あぁ、その人でしたら此処にいますよ。…まぁ、最も正面に話が出来るような状態では無いみたいですけど。」
「俺の隣にいただろう?…その、腕の取れた女、が。」
「あぁ、その人でしたら此処にいますよ。…まぁ、最も正面に話が出来るような状態では無いみたいですけど。」
ほら、と差し出された布の塊はじたばたと動いて少年の腕の中からしきりに逃げ出そうとしている。思わず後ずさってしまった俺に、近寄って来た少年が布の塊を前に突き出した体勢のまま話しかけて来た。
「貴方は此所にいるべき人間ではありません。早く帰ったらどうですか?…さもないと、体…盗られてしまいますよ?」
にたりと少年達が笑った。子供が浮かべるような無邪気なものではない。
…それは、正しく『もののけ』の笑みだった。
…それは、正しく『もののけ』の笑みだった。
――――――――――
「…?此処、は…」
白い。天井の色を知覚すると同時に病院独特の消毒の匂いが鼻を突いた。どうやら、俺は病院のベッドに寝かされているらしい。
…何故俺はここにいるのか。俺はあの森にいて、訳の分からない子供に囲まれていたのではなかったか?
ゆるゆると動く範囲で首を動かしてみると、右側には扉が左側には落ちかけた夕日が差し込む窓が見えた。
先ほどまでのあれはなんだったのか。そこまで思考が働いたところでずきんと頭部に痛みが走る。怪我でもしているのかと頭部の方を探ると、なにか紙の束が手に触れた。…これは、新聞?
…何故俺はここにいるのか。俺はあの森にいて、訳の分からない子供に囲まれていたのではなかったか?
ゆるゆると動く範囲で首を動かしてみると、右側には扉が左側には落ちかけた夕日が差し込む窓が見えた。
先ほどまでのあれはなんだったのか。そこまで思考が働いたところでずきんと頭部に痛みが走る。怪我でもしているのかと頭部の方を探ると、なにか紙の束が手に触れた。…これは、新聞?
「酒気帯び運転で崖から転落…四人死傷…」
仲間二人と、彼女と、俺の名前がそこにはあった。そして理解したこと。あの日ドライブに行った四人の中で、生きているのは俺だけなのだ…ということ。
「貴方、どうして彼女に襲われそうになったのか分かりますか?」
「きみ、は…」
「きみ、は…」
足元からどこかで聞いたような声がした。さて、誰だったかと考えながら足元に視線を向けると…忘れもしない。
黒と黄色のちゃんちゃんこを着た少年のうちの一人が俺のベッドの足元に立っていたのだ。
黒と黄色のちゃんちゃんこを着た少年のうちの一人が俺のベッドの足元に立っていたのだ。
「彼女、貴方を殺そうとしていたんですよ。…貴方と一緒にいたかったのか、貴方が生きているのが不満だったのかは分かりませんけど。」
ベッド脇のパイプ椅子に座り床に着かない足をゆらゆらと軽く揺らして少年は無感情にそう言った。
「…彼女達は亡くなってしまったけど、貴方は生きている。そのことを覚えて置いてください。」
カラン、と少年の履いている下駄の音が乾いた音を立てた。ドアが開いて静かに閉まる。
その音だけで少年が部屋を出ていったのだと言う事が理解出来た。
その音だけで少年が部屋を出ていったのだと言う事が理解出来た。
何処からが夢で何処からが現実だったのか。俺達は本当に森に行ったのだろうか?どこで道を間違えてしまったのだろうか。
「いっしょにいこう」
…耳元で誰かが囁いた気がした。
カラン、コロン
「のう、高山。どうして黙っておったのじゃ?」
「何を、ですか?」
「さっきの青年、二人程背中に背負っておったじゃろう」
「あぁ、事故で亡くなった人達ですね。…魂とは言え彼が僕らの家に無断で上がり込んだ事は事実です。罰は受けるべきでしょう。」
「何を、ですか?」
「さっきの青年、二人程背中に背負っておったじゃろう」
「あぁ、事故で亡くなった人達ですね。…魂とは言え彼が僕らの家に無断で上がり込んだ事は事実です。罰は受けるべきでしょう。」
カラン、コロン
青年に憑いている二人の霊の手は彼の首に回されていた。…彼の命が再度危うくなるのも時間の問題だろう。
青年に憑いている二人の霊の手は彼の首に回されていた。…彼の命が再度危うくなるのも時間の問題だろう。
「さ、日が暮れる前に帰りましょう。父さん。」
カラン、コロン。カラン、コロン。
その日の夕焼けは自棄に赤い気がした。
終
短編作品一覧へ戻る