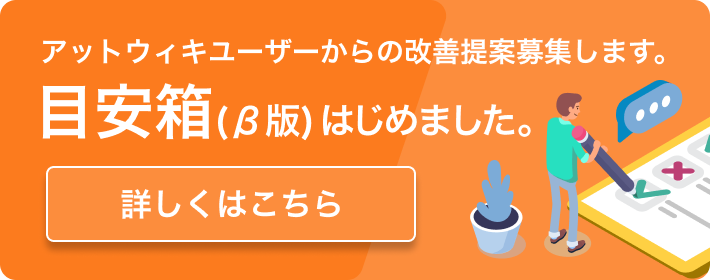男が魔法を使って、 ナニが悪いっ!!
第一章 ~初めての奇跡~
この日、僕の目が覚めたのは日の光のためじゃなく、一人の女の子の声によるものだった。
「おはようございますユウキさん」
「……」
今、何時なんだろう。とりあえず眠たい。 まだ閉じていたいと懇願するまぶたに鞭打つように手でこすりながら時計を手元に手繰り寄せる。
「……六時」
なんてことだ。アラームが鳴るまであと三十分もあるじゃないか。そんなわけで僕は再びベッドにもぐりこんで……
「ユウキさん朝ですよ!」
もぐりこめなかった。というかいきなり布団を引っぺがすのは非常に肌寒く感じるのでやめてほしい。
観念した僕が目を開けると、特に悪びれた様子がないニコニコ笑顔の天使が布団を持って立っている。僕の記憶に間違いがないのならその天使は。
「……あれ……エナ!?」
「はい!」
やっぱりエナだった。いやそんなことより聞かないといけないことがある。すばやくベッドから起き上がって僕はエナに質問を投げかける。
「どうしていきなり僕の目の前からいなくなったんだ?」
「それは、私の魔力が関係してるんですけど……」
「魔力って……魔法の力の源、でいいのかな」
「そうです。 そしてその魔力というのは私たちの存在を支える根本的なものでもあります」
「存在を支える……?」
「私たちの体は確かに人間とあまり違いがありません。ですが私たちにとって重要なのが魔力なのです。 これは私たちの肉体の全体にまで及んでいて全ての部位にまで影響を及ぼします」
朝っぱらから結構な難しい話が飛び出してきたものだ。僕はなんとか覚醒したばかりの脳を活動させてエナの話に集中する。
「具体的にはそれって、どういうこと……?」
「つまり私たちの体は魔力によって作られているといっても過言ではないんです。だから魔力をたくさん持っている大天使様などは私とは違って大きな――人間で言うところの大人のような体なんです」
ていうことは力を持っている人はそれ相応の体でいるってことなのかなと、僕がおおよその考えをまとめている途中であることに気が付いた。
「え、それじゃ反対に魔力がなくなっていったら……?」
「そうなってしまえば今の体は保てなくなってしまいますから、完全に失われてしまったら……」
「――消える」
その一言に、ただ首を縦に振ることでその答えを示した。
けど、本当にそうであるなら昨夜のエナのあの状態は……
「そ、そうだ、それよりもエ、エナは大丈夫なのか!?」
「あ、ごめんなさい。それは単純に眠たかったので一度天界に……」
それを聞いて、僕の足から体を支える力は瞬間的に失われ、当然のように体はぐらっとよろけた。よくテレビで芸人とかがズッコケるけど、いわゆるその状態になった。正直ちょっとでも心配した僕はいったい何なんだ。
「てっきり君が危ないのかと思ったじゃないか!」
「ご、ごめんなさい。あの時は魔力の保持が大変だったので、つい帰っちゃいました」
「え……」
「どうも人間界というのは天界とは違って魔力が豊富にあるわけではないみたいで、それで体を保つことに力を使いすぎたら眠くなっちゃいました……」
えへへ、と笑いながら困ったように頭を抱える彼女を見て、僕はとりあえずため息をついた。
「はぁ……」
彼女の身に酷く大変な問題が発生していたことと、そのことに対する彼女の態度とのギャップが、僕には少し理解できなくて。行き場のない文句や不安は、言葉じゃなくてため息として吐き出された。
天界の住人というのは自分の存在が危ぶまれても大した問題としては認識しない人たちなんだろうか。それとも、単にエナという天使がそういう性格なのか。
「それで、その問題は解決したの? でないと人間界じゃまともに過ごせないだろうし」
案外、必要なときだけ出てきてそれ以外のときは天界で過ごす。なんていう天使ライフなのかもしれないけど。
それに対するエナの返答はこうだった。
「あのときは普通の等身大サイズで来たのが悪かったんです! なので……えい!」
その掛け声と共にエナの体が昨夜のように発光し始める。そして数秒がたつと
「あ、あれ……エナ?」
以前と同じように、エナの姿は消えてしまっていた。
「ちょ、な、なんで」
まさか失敗したんじゃあるまいな。正直エナならやりかねないような気がする。
僕が彼女の存在が消えてしまったんじゃないかと心配したそのときだった。
「ユウキさん、ここですよ」
声が、聞こえた。それも相当近い。というか、近すぎる。しかも右耳だけ。
僕は、ゆっくりと、顔を右に向けて、じーっと、ソレを見た。
「あの……そんなにジロジロと見られるのは恥ずかしいですよ?」
そこにはちょっとだけ赤面したエナがいた。ただし、その大きさはずいぶんと縮小されてはいたが。大体、ちっちゃなフィギュア程度。恐らく三十センチもないと思う。
「つまり、保持するのに必要な魔力を減らすためにミニマム化したと」
要するにさっき消えたように見えたのは、小さくなったことで僕の視界から外れたためだろう。というか、この子に驚かされすぎだろう、僕。
「でも仕方がない……仕方がないんだ……」
「あの、どうしましたか?」
「いや、なんでもないよ。うん、なんでもない」
いつのまにか口に出していたようだ。だけど、しかし、しょうがないんだよ。エナには、そう、よちよちと歩く子供みたいな危なっかしさがあるのだ。
いたって普通な高校生男子としては保護しなきゃならない気持ちというのが沸いてくるものだろう。あくまでも、保護者として。というか、こんなこと考えてる場合じゃない。
「それよりも、昨日は話が途中だったよね?」
「あ、お話していて忘れてましたけどそうでしたね」
「魔法使いが人間界から選ばれる。僕が聞いたのはここまで。そして聞きたい」
エナが消えてから、僕はずっと考えていた。どうしてなのかと。
お風呂に入っているときも、ご飯を食べているときも、そしてベッドに潜り込んだときも。ずっと思っていた。
どうしてなんだと。
「どうして、僕に?」
足が速いわけでも。頭が良いわけでも。手先が器用なわけでも。人より抜き出て優秀なわけでもない。
こんな、どこにでもいるような、平均でしかない僕に。
「どうして?」
そう、僕は、ヒーローじゃない。僕より優れた人なんて、いくらだっているはずなのに。
そんな僕の疑問に、エナは答えた。
「……運命って、信じますか?」
「うん、めい?」
よく運命的な、という使われ方をする、あの運命のことだろうか。確かにエナとの出会いも運命的ではあったけど。
運命はっていうのはあるような気がするけど、でも僕の行動が神様によって定められているとは、正直信じがたい気もする。だって、もし運命があるなら、僕個人の意思はどうなってしまうんだ。
「因果、ともいえるんですけど……ともかく、セイラ様によれば、ユウキさんにはそういう運命がある、と……」
なるほど。
つまり、僕にはそういう運命があると、決まっていると。
「ははは……」
「……どうしました?」
エナが少し困惑している。まぁそうだろう。目の前の人間が前触れもなく笑い出したら誰だって困惑する。正直変だろう。
だけど、だってそうだろう? ある日目の前に現れた少女から、僕は魔法使いになるためにいると、そんな風に宣告されたら。
ここまでくると笑うしかないだろう。
「僕に、そんな運命が……? あるわけないだろ……? 僕は普通の高校生だぞ? 超能力があるだとか裏の世界に通じているだとか宇宙人と知り合いだとかそんなものあるわけがない! 僕は普通の一般人でしかないんだっ!」
一気にしゃべったことで、僕の息は完全にあがってしまって。情けなく肩を上下させて大きく呼吸することしかできなかった。
たぶん、これまでの僕の人生でここまで叫ぶことは滅多にないだろう。
その証拠に、僕の母さんが、階段を上ってここまでやってくる音が聞こえてきた。
それから物の数秒もせずに、母さんは部屋に入ってくる。
「優希? 大きな声が聞こえたけど大丈夫なの?」
「ご、ごめん……ちょっと友達と喧嘩しちゃってさ」
そう言って、机にあった携帯電話を手にとって母さんに見せた。もちろん、嘘だ。
だが母さんはそれで納得したらしく、特に深く聞くことはなかった。
「……何もないのなら、それでいいわ。もう七時過ぎてるから、早く下りてご飯食べなさい?」
それだけ言うと母さんはそのまま下へと降りていった。
気づけば、時計はすでに七時二十分ほどになっていた。話に夢中になっていたみたいだ。
そういえば、エナはどこに行ったのだろう。
「あの、ユウキさん……」
ベッドから出てきたエナがおずおずと僕に話しかける。あの一瞬でなんとか潜り込めたのだろう。
「えと、その、ごめん。いきなり、あんな風に怒鳴っちゃって、ほんと、ごめん」
今の様子を他人が見たら誰だって最低と思うに違いない。相手には悪意などこれっぽっちもなかったのだ。
ただ僕が、現実に対して、理解することを拒否しただけなのだから。
「ほんとに、ごめん」
「あの……大丈夫ですよユウキさん。ただ、ちょっとだけびっくりしちゃいました……えへへ」
少しだけ困りながらも、笑ってくれるエナに、感謝するのと同時に、良い子なんだなって、僕は思った。
けど、そんなことを素直に伝えられない僕は、照れ隠し気味に言葉を続けた。
「と、とにかく、僕は普通の人間だし、いきなり魔法使いになってって言われても、すぐには答えられないよ」
なるかどうかはわからない。
そんな不明確な答えを出して、僕の中では一応の区切りがついていた。
事はきっと急を要するものだろうし、いるかはわからないけど、他の候補たちに回されるんじゃないだろうか。なるかどうかわからない奴をうだうだ待つよりは、よっぽど可能性はある。そうなればきっと、僕に持ちかけられていた話は、少なくとも僕が生きている間に来ることはないだろう。
そう思って僕は、エナとの永劫の別れを感じていた。だが。
「そうですか……あ、でもセイラ様から、しばらくはユウキさんのそばにいるようにって言われてますから、大丈夫ですよ」
おい。
神様というのはあれか。僕の予想をことごとく無視してくれるみたいだな。狙ってるのかと言いたいくらいだ。というかちょっと待て、おい。
まさかこれからどこまでもついてくる気なんじゃないだろうな。
「あの、僕これから学校なんだけど」
「あ、大丈夫です! 私こう見えても隠れるのは得意ですよ!」
「付いてくること前提かよ。むしろ家の中で隠れていてくれよ。というかそもそも天界にいてくれよ。そっちの方が苦労しないだろう?」
「ユウキさんにくっついていろ、ということでしたので。あと、天界に帰るのもそれはそれで苦労があるんですよ?」
学校にまで来ることは確定事項らしい。これはたぶん何を言っても無駄だろう。きっと。
こうして、僕の普通の高校生としての暮らしは急激な終わりを迎えていた。
そして、普通の魔法使いとしての始まりが、すぐそこに迫っていることなど、僕は。
知る由もなかったんだ。
「おはようございますユウキさん」
「……」
今、何時なんだろう。とりあえず眠たい。 まだ閉じていたいと懇願するまぶたに鞭打つように手でこすりながら時計を手元に手繰り寄せる。
「……六時」
なんてことだ。アラームが鳴るまであと三十分もあるじゃないか。そんなわけで僕は再びベッドにもぐりこんで……
「ユウキさん朝ですよ!」
もぐりこめなかった。というかいきなり布団を引っぺがすのは非常に肌寒く感じるのでやめてほしい。
観念した僕が目を開けると、特に悪びれた様子がないニコニコ笑顔の天使が布団を持って立っている。僕の記憶に間違いがないのならその天使は。
「……あれ……エナ!?」
「はい!」
やっぱりエナだった。いやそんなことより聞かないといけないことがある。すばやくベッドから起き上がって僕はエナに質問を投げかける。
「どうしていきなり僕の目の前からいなくなったんだ?」
「それは、私の魔力が関係してるんですけど……」
「魔力って……魔法の力の源、でいいのかな」
「そうです。 そしてその魔力というのは私たちの存在を支える根本的なものでもあります」
「存在を支える……?」
「私たちの体は確かに人間とあまり違いがありません。ですが私たちにとって重要なのが魔力なのです。 これは私たちの肉体の全体にまで及んでいて全ての部位にまで影響を及ぼします」
朝っぱらから結構な難しい話が飛び出してきたものだ。僕はなんとか覚醒したばかりの脳を活動させてエナの話に集中する。
「具体的にはそれって、どういうこと……?」
「つまり私たちの体は魔力によって作られているといっても過言ではないんです。だから魔力をたくさん持っている大天使様などは私とは違って大きな――人間で言うところの大人のような体なんです」
ていうことは力を持っている人はそれ相応の体でいるってことなのかなと、僕がおおよその考えをまとめている途中であることに気が付いた。
「え、それじゃ反対に魔力がなくなっていったら……?」
「そうなってしまえば今の体は保てなくなってしまいますから、完全に失われてしまったら……」
「――消える」
その一言に、ただ首を縦に振ることでその答えを示した。
けど、本当にそうであるなら昨夜のエナのあの状態は……
「そ、そうだ、それよりもエ、エナは大丈夫なのか!?」
「あ、ごめんなさい。それは単純に眠たかったので一度天界に……」
それを聞いて、僕の足から体を支える力は瞬間的に失われ、当然のように体はぐらっとよろけた。よくテレビで芸人とかがズッコケるけど、いわゆるその状態になった。正直ちょっとでも心配した僕はいったい何なんだ。
「てっきり君が危ないのかと思ったじゃないか!」
「ご、ごめんなさい。あの時は魔力の保持が大変だったので、つい帰っちゃいました」
「え……」
「どうも人間界というのは天界とは違って魔力が豊富にあるわけではないみたいで、それで体を保つことに力を使いすぎたら眠くなっちゃいました……」
えへへ、と笑いながら困ったように頭を抱える彼女を見て、僕はとりあえずため息をついた。
「はぁ……」
彼女の身に酷く大変な問題が発生していたことと、そのことに対する彼女の態度とのギャップが、僕には少し理解できなくて。行き場のない文句や不安は、言葉じゃなくてため息として吐き出された。
天界の住人というのは自分の存在が危ぶまれても大した問題としては認識しない人たちなんだろうか。それとも、単にエナという天使がそういう性格なのか。
「それで、その問題は解決したの? でないと人間界じゃまともに過ごせないだろうし」
案外、必要なときだけ出てきてそれ以外のときは天界で過ごす。なんていう天使ライフなのかもしれないけど。
それに対するエナの返答はこうだった。
「あのときは普通の等身大サイズで来たのが悪かったんです! なので……えい!」
その掛け声と共にエナの体が昨夜のように発光し始める。そして数秒がたつと
「あ、あれ……エナ?」
以前と同じように、エナの姿は消えてしまっていた。
「ちょ、な、なんで」
まさか失敗したんじゃあるまいな。正直エナならやりかねないような気がする。
僕が彼女の存在が消えてしまったんじゃないかと心配したそのときだった。
「ユウキさん、ここですよ」
声が、聞こえた。それも相当近い。というか、近すぎる。しかも右耳だけ。
僕は、ゆっくりと、顔を右に向けて、じーっと、ソレを見た。
「あの……そんなにジロジロと見られるのは恥ずかしいですよ?」
そこにはちょっとだけ赤面したエナがいた。ただし、その大きさはずいぶんと縮小されてはいたが。大体、ちっちゃなフィギュア程度。恐らく三十センチもないと思う。
「つまり、保持するのに必要な魔力を減らすためにミニマム化したと」
要するにさっき消えたように見えたのは、小さくなったことで僕の視界から外れたためだろう。というか、この子に驚かされすぎだろう、僕。
「でも仕方がない……仕方がないんだ……」
「あの、どうしましたか?」
「いや、なんでもないよ。うん、なんでもない」
いつのまにか口に出していたようだ。だけど、しかし、しょうがないんだよ。エナには、そう、よちよちと歩く子供みたいな危なっかしさがあるのだ。
いたって普通な高校生男子としては保護しなきゃならない気持ちというのが沸いてくるものだろう。あくまでも、保護者として。というか、こんなこと考えてる場合じゃない。
「それよりも、昨日は話が途中だったよね?」
「あ、お話していて忘れてましたけどそうでしたね」
「魔法使いが人間界から選ばれる。僕が聞いたのはここまで。そして聞きたい」
エナが消えてから、僕はずっと考えていた。どうしてなのかと。
お風呂に入っているときも、ご飯を食べているときも、そしてベッドに潜り込んだときも。ずっと思っていた。
どうしてなんだと。
「どうして、僕に?」
足が速いわけでも。頭が良いわけでも。手先が器用なわけでも。人より抜き出て優秀なわけでもない。
こんな、どこにでもいるような、平均でしかない僕に。
「どうして?」
そう、僕は、ヒーローじゃない。僕より優れた人なんて、いくらだっているはずなのに。
そんな僕の疑問に、エナは答えた。
「……運命って、信じますか?」
「うん、めい?」
よく運命的な、という使われ方をする、あの運命のことだろうか。確かにエナとの出会いも運命的ではあったけど。
運命はっていうのはあるような気がするけど、でも僕の行動が神様によって定められているとは、正直信じがたい気もする。だって、もし運命があるなら、僕個人の意思はどうなってしまうんだ。
「因果、ともいえるんですけど……ともかく、セイラ様によれば、ユウキさんにはそういう運命がある、と……」
なるほど。
つまり、僕にはそういう運命があると、決まっていると。
「ははは……」
「……どうしました?」
エナが少し困惑している。まぁそうだろう。目の前の人間が前触れもなく笑い出したら誰だって困惑する。正直変だろう。
だけど、だってそうだろう? ある日目の前に現れた少女から、僕は魔法使いになるためにいると、そんな風に宣告されたら。
ここまでくると笑うしかないだろう。
「僕に、そんな運命が……? あるわけないだろ……? 僕は普通の高校生だぞ? 超能力があるだとか裏の世界に通じているだとか宇宙人と知り合いだとかそんなものあるわけがない! 僕は普通の一般人でしかないんだっ!」
一気にしゃべったことで、僕の息は完全にあがってしまって。情けなく肩を上下させて大きく呼吸することしかできなかった。
たぶん、これまでの僕の人生でここまで叫ぶことは滅多にないだろう。
その証拠に、僕の母さんが、階段を上ってここまでやってくる音が聞こえてきた。
それから物の数秒もせずに、母さんは部屋に入ってくる。
「優希? 大きな声が聞こえたけど大丈夫なの?」
「ご、ごめん……ちょっと友達と喧嘩しちゃってさ」
そう言って、机にあった携帯電話を手にとって母さんに見せた。もちろん、嘘だ。
だが母さんはそれで納得したらしく、特に深く聞くことはなかった。
「……何もないのなら、それでいいわ。もう七時過ぎてるから、早く下りてご飯食べなさい?」
それだけ言うと母さんはそのまま下へと降りていった。
気づけば、時計はすでに七時二十分ほどになっていた。話に夢中になっていたみたいだ。
そういえば、エナはどこに行ったのだろう。
「あの、ユウキさん……」
ベッドから出てきたエナがおずおずと僕に話しかける。あの一瞬でなんとか潜り込めたのだろう。
「えと、その、ごめん。いきなり、あんな風に怒鳴っちゃって、ほんと、ごめん」
今の様子を他人が見たら誰だって最低と思うに違いない。相手には悪意などこれっぽっちもなかったのだ。
ただ僕が、現実に対して、理解することを拒否しただけなのだから。
「ほんとに、ごめん」
「あの……大丈夫ですよユウキさん。ただ、ちょっとだけびっくりしちゃいました……えへへ」
少しだけ困りながらも、笑ってくれるエナに、感謝するのと同時に、良い子なんだなって、僕は思った。
けど、そんなことを素直に伝えられない僕は、照れ隠し気味に言葉を続けた。
「と、とにかく、僕は普通の人間だし、いきなり魔法使いになってって言われても、すぐには答えられないよ」
なるかどうかはわからない。
そんな不明確な答えを出して、僕の中では一応の区切りがついていた。
事はきっと急を要するものだろうし、いるかはわからないけど、他の候補たちに回されるんじゃないだろうか。なるかどうかわからない奴をうだうだ待つよりは、よっぽど可能性はある。そうなればきっと、僕に持ちかけられていた話は、少なくとも僕が生きている間に来ることはないだろう。
そう思って僕は、エナとの永劫の別れを感じていた。だが。
「そうですか……あ、でもセイラ様から、しばらくはユウキさんのそばにいるようにって言われてますから、大丈夫ですよ」
おい。
神様というのはあれか。僕の予想をことごとく無視してくれるみたいだな。狙ってるのかと言いたいくらいだ。というかちょっと待て、おい。
まさかこれからどこまでもついてくる気なんじゃないだろうな。
「あの、僕これから学校なんだけど」
「あ、大丈夫です! 私こう見えても隠れるのは得意ですよ!」
「付いてくること前提かよ。むしろ家の中で隠れていてくれよ。というかそもそも天界にいてくれよ。そっちの方が苦労しないだろう?」
「ユウキさんにくっついていろ、ということでしたので。あと、天界に帰るのもそれはそれで苦労があるんですよ?」
学校にまで来ることは確定事項らしい。これはたぶん何を言っても無駄だろう。きっと。
こうして、僕の普通の高校生としての暮らしは急激な終わりを迎えていた。
そして、普通の魔法使いとしての始まりが、すぐそこに迫っていることなど、僕は。
知る由もなかったんだ。
通学路というのは、僕が知る上でだが限りなく日常そのものだ。通勤するサラリーマンや電気店の前を掃き掃除する店員、同じように通学する中学生にゴミを捨てに行く主婦。同じように日常を生きる人たちを見かけるこの通学路は、とても日常的に日常だった。
「人間界を覗くたびに思うんですけど、人間は朝になるととても慌しいですよね」
「……息苦しいとは思うけどできればカバンの中から首だけ出すのは遠慮してほしいな」
「いえ、呼吸は問題ないんですけど……むしろ私の方こそ未熟で……」
自分で言いながら、しょんぼりとした様子でカバンの中に引っ込んでいくエナ。
「いや、いいよ別に。だって人間界には元々魔力が少ないんだろ? 仕方がないよ」
「ううう……セイラ様だったら簡単にできちゃうのに……」
さて、なぜエナが落ち込んでいるかというと、話は登校する前の僕の部屋でのことだ。
「人間界を覗くたびに思うんですけど、人間は朝になるととても慌しいですよね」
「……息苦しいとは思うけどできればカバンの中から首だけ出すのは遠慮してほしいな」
「いえ、呼吸は問題ないんですけど……むしろ私の方こそ未熟で……」
自分で言いながら、しょんぼりとした様子でカバンの中に引っ込んでいくエナ。
「いや、いいよ別に。だって人間界には元々魔力が少ないんだろ? 仕方がないよ」
「ううう……セイラ様だったら簡単にできちゃうのに……」
さて、なぜエナが落ち込んでいるかというと、話は登校する前の僕の部屋でのことだ。
「先ほども言いましたけど、こう見えても隠れるのは本当に得意なんですよ?」
朝食を済ませて制服に着替えた僕は部屋に戻ってきた。というのも、カバンに必要なものを入れるためにだけど。
そこで僕を待ち構えていたのはある種憎たらしいほどに純粋な笑顔を向ける天使の姿だった。もちろん、姿はさっきと変わらず、ちっちゃなままだった。
「……結構間が空いてるにも関わらずそこから?」
「え、何か問題がありましたか?」
いや、まぁそれはないけど。常識というか当然のことというか、所詮は僕の中でのことにしか過ぎないけれど。
ともかく彼女にこれだけの自信があるということはきっと何かしらの対策でも用意してあるんだろう例えば
「透明になれたりする、のかな。その様子だと」
「もちろんです!魔力の応用ですからユウキさんもやろうと思えばできると思いますよ」
「僕が魔法使いになれば、の話だけどね。そろそろ学校に行かなくちゃ行けないし早速やってみてくれないか」
「はい!」
元気よく彼女が答えるとそのままスッと両の手を胸の前で組み合わせる。そうして目を閉じて神様に祈るように――実際祈っているのかもしれない――彼女は何事かを呟き始めた。
なぜ、何事か、なんていうあいまいな表現を使っているのかというと、僕にはその呪文と思われるものが全くさっぱり聞き取れないっていうか。初めて外国人と話をしたときの状況というか。聞こえてるのに聞こえてないというか。うん、ちょっと落ち着こうか僕。
僕が思うに人間の声の大きさはある程度口の大きさに比例しているものだと、思っていたんですがありのまま今起こってることを説明すると。
口を大きく開けて呪文を唱えているはずなのに全然声が聞こえてこない。ときどき、ノイズのような音が漏れるくらいで、あとは何も聞こえてはこない。まるで、僕だけプールの底に沈められたように。そこだけが別世界のように。いや、というよりこれは、むしろ。
エナの周りに防音の空気の壁があるみたいな、そんな感じ。
「……えへへ、どうですかっユウキさん!」
「えと」
なぜ僕はエナからこんなにも得意げな顔を向けられているのか。誰か解答を持っているなら即刻持ってきてください。僕にはわかりません。
なんで彼女は特に"何も起こってない"のにあんなに胸を張って堂々としているんですか。
「……何にも変わってないよ?」
「やだなーユウキさん、もしかして人間界のジョークですかー?」
そう言いながらそろりそろりと僕の背後に回ろうとしている様子は、なんか悲しいほどに滑稽で。恐らく僕を驚かそうと企んでいるのだろうが、見えている状態でそれをやられても別になんとも思わないのが現実で。
「えい」
僕のデコピンという名の右手人差し指の強襲によって、彼女の企みはあっけなく――そもそも企みとして成立していないが――崩れ去った。
「あうっ!? あ、あれ? まさかユウキさんすでに解析魔法を会得済みなんですか!?」
彼女の的外れな突っ込みは無視して、ただ単純な真実を、さっさとわからせなければ。というかそんなことしてるうちに登校時間が近づいてるし。
「さっきも言ったけど、僕は今まで何にも知らなかったただの人間だよ。僕が、じゃなくて君が何にも変わっていないだけだよ」
「そ、そんな、確かにかけたと思ったのに……も、もう一度!」
朝食を済ませて制服に着替えた僕は部屋に戻ってきた。というのも、カバンに必要なものを入れるためにだけど。
そこで僕を待ち構えていたのはある種憎たらしいほどに純粋な笑顔を向ける天使の姿だった。もちろん、姿はさっきと変わらず、ちっちゃなままだった。
「……結構間が空いてるにも関わらずそこから?」
「え、何か問題がありましたか?」
いや、まぁそれはないけど。常識というか当然のことというか、所詮は僕の中でのことにしか過ぎないけれど。
ともかく彼女にこれだけの自信があるということはきっと何かしらの対策でも用意してあるんだろう例えば
「透明になれたりする、のかな。その様子だと」
「もちろんです!魔力の応用ですからユウキさんもやろうと思えばできると思いますよ」
「僕が魔法使いになれば、の話だけどね。そろそろ学校に行かなくちゃ行けないし早速やってみてくれないか」
「はい!」
元気よく彼女が答えるとそのままスッと両の手を胸の前で組み合わせる。そうして目を閉じて神様に祈るように――実際祈っているのかもしれない――彼女は何事かを呟き始めた。
なぜ、何事か、なんていうあいまいな表現を使っているのかというと、僕にはその呪文と思われるものが全くさっぱり聞き取れないっていうか。初めて外国人と話をしたときの状況というか。聞こえてるのに聞こえてないというか。うん、ちょっと落ち着こうか僕。
僕が思うに人間の声の大きさはある程度口の大きさに比例しているものだと、思っていたんですがありのまま今起こってることを説明すると。
口を大きく開けて呪文を唱えているはずなのに全然声が聞こえてこない。ときどき、ノイズのような音が漏れるくらいで、あとは何も聞こえてはこない。まるで、僕だけプールの底に沈められたように。そこだけが別世界のように。いや、というよりこれは、むしろ。
エナの周りに防音の空気の壁があるみたいな、そんな感じ。
「……えへへ、どうですかっユウキさん!」
「えと」
なぜ僕はエナからこんなにも得意げな顔を向けられているのか。誰か解答を持っているなら即刻持ってきてください。僕にはわかりません。
なんで彼女は特に"何も起こってない"のにあんなに胸を張って堂々としているんですか。
「……何にも変わってないよ?」
「やだなーユウキさん、もしかして人間界のジョークですかー?」
そう言いながらそろりそろりと僕の背後に回ろうとしている様子は、なんか悲しいほどに滑稽で。恐らく僕を驚かそうと企んでいるのだろうが、見えている状態でそれをやられても別になんとも思わないのが現実で。
「えい」
僕のデコピンという名の右手人差し指の強襲によって、彼女の企みはあっけなく――そもそも企みとして成立していないが――崩れ去った。
「あうっ!? あ、あれ? まさかユウキさんすでに解析魔法を会得済みなんですか!?」
彼女の的外れな突っ込みは無視して、ただ単純な真実を、さっさとわからせなければ。というかそんなことしてるうちに登校時間が近づいてるし。
「さっきも言ったけど、僕は今まで何にも知らなかったただの人間だよ。僕が、じゃなくて君が何にも変わっていないだけだよ」
「そ、そんな、確かにかけたと思ったのに……も、もう一度!」
「あれから結局十回もするとは思わなかったけどね」
「ううう……」
そんなこんなで、エナはカバンに隠しながら僕は学校に通うことになってしまった。呪文自体は簡素なものだったようで、一応短時間で済んだことが唯一の救いか。そうじゃないと僕は朝から全力で走ることになる。
原因をエナに聞いてみると、そもそも人から見えなくなる呪文というのは、自身の体の周囲に魔力を貼り付けることで透化する、というもので。現在、自分の体を保つ魔力のバランスの調整で四苦八苦している状態だから上手くできないのだと言った。人間界にある程度慣れれば、少しは魔法も使えるようになるかもしれないとは言っているが、このままだとただ居候が一人増えただけのような気がする。まぁ、その知識力は有用かもしれないが。
このままずっとエナにしょんぼりされても僕としては心苦しいところもあるので、とにかく違う方へ話を振って気をそらすことに決めた。
「あのさ、聞きたいことがあるんだけど」
「は、はい、なんですか?」
「エナは何か呪文を言っていたみたいだけど、僕にはほとんど聞こえなかった。聞こえたとしてもノイズのような、意味不明の音だったし、それはなぜなんだ?」
この問いかけに対しエナは予想通りに、僕の話に乗ってくれた。
「それでしたら、たぶん魔法言語を使ったからだと思います。多少なりとも魔法に関わる人じゃないと認識することができないみたいなので、それでユウキさんには聞き取れなかったんじゃないかと思います」
なるほどな、と普通に納得しかけたが、よくよく考えると魔法に関わってることで認識できる言葉っていったいどういう原理で成り立っているんだ。
「あの、それって」
と、言いかけたところで、やっぱりやめた。というのも、それに対する答えが僕のような一般の高校生が普段使ってるような言葉で説明されるとは到底思えなかったからだ。ファンタジーな人たちが自分たちの常識を説明するのにどういう言葉を用いるか、どう考えてもファンタジーだろう。「魔法言語は魔力や呪文と密接な関係にあって~」とか、よくわからない説明をされるに違いない。
「どうしましたか?」
「……やっぱりなんでもない。 それより」
「ねえ、そんなとこで立ち止まって何やってるの?」
「うわあ!」
背後から突然声をかけられて、思わず叫んでしまった。僕は、カバンをなるべく足の後ろの位置で持ちながら声をかけた人物の方へと向き直る。そこには、一人の女の子が僕のことを唖然とした様子で、目をぱちくりさせていた。
「な、何?」
「何、じゃない! 声かけた私の方がビックリした!」
「ご、ごめん」
「……ほんとに、昔からあんまり変わってないよね優希って。 気弱でこれといって目立つこともないけど、たまに不気味なくらいに不思議っこでさ」
「驚かせてすいませんでしたお願いですから過去のことを出すのはやめてください」
「はいはい。わかりましたよー。けど、ぼやぼやしてると遅刻になるから急いだほうがいいよ?」
そういってニヤニヤしながら僕の前にいる少女――日向陽花(ヒナタ ハルカ)は学校に向かう道を歩き出して、僕の前から去っていった。
日向陽花――僕の中では陽花と呼んでいるが――と僕は、いわゆる幼馴染という関係にある。家は微妙に距離があるが、それでも近いと言えるものだろう。補足しておくとマンガのように彼女が毎朝家にやってきて僕を起こしにやってくるだとか僕のために料理を作ってくれるだとかそんなことは一切ないのであしからず。これは僕の友人にも常々言っていることだが、彼は全くもって相手にしてくれない。まぁそんなことはどうでもいい。
幼少期によく母が「まるできょうだいね」と僕らを見て言っていたのだが、そう言われるほどに、僕らはよくいっしょにいることが多かった。そのころは陽花も今のように気が強くはなかったような気がするし、現在は彼女が主導権を握っていることが多いが、昔は対等の立場で遊んでいた気がする。そんなことは、今となっては関係ないかもしれないけど。
「び、びっくりしましたね……あの、ユウキさん、今の人は?」
ひょっこりと、エナがカバンから顔を出した。雨が止んだので窓から顔を出してみた、といった感じだ。最も、雨というよりかは嵐だったが。
「日向陽花って言って、僕の幼馴染だよ」
「なんだか元気が良い人でしたね……」
ほへー、と唖然とした様子のエナだが、正直僕にはどちらも似たようなものじゃないかと思う。
「エナも大概だと思うんだけどな」
「うーんと、そうですか?」
きょとんと僕を見つめているところから考えて完全に自分では自覚してないことが窺えるな。
「……まぁいいや。僕もさっさと学校に行こう」
長話して遅刻でもしたら、それこそ馬鹿以外の何物でもない。止めていた足を再び動かして、学校への道を歩き出す。
「学校」というワードを出した途端にエナから笑顔がこぼれた。なんだっていうのだろう。
「うーん、楽しみですねぇ~人間の学校ってどんなところなんでしょう?」
「これといった面白いものはないと思うけどね」
「それは人間の視点だからですよー。 うーん一体どんなところなんでしょうか!」
なにやらエナが思いを馳せ始めたのでとりあえず放っておこう。
僕は、僕の日常を今日も繰り返す。
ただそれだけのことをしに行くだけなのだから。
「ううう……」
そんなこんなで、エナはカバンに隠しながら僕は学校に通うことになってしまった。呪文自体は簡素なものだったようで、一応短時間で済んだことが唯一の救いか。そうじゃないと僕は朝から全力で走ることになる。
原因をエナに聞いてみると、そもそも人から見えなくなる呪文というのは、自身の体の周囲に魔力を貼り付けることで透化する、というもので。現在、自分の体を保つ魔力のバランスの調整で四苦八苦している状態だから上手くできないのだと言った。人間界にある程度慣れれば、少しは魔法も使えるようになるかもしれないとは言っているが、このままだとただ居候が一人増えただけのような気がする。まぁ、その知識力は有用かもしれないが。
このままずっとエナにしょんぼりされても僕としては心苦しいところもあるので、とにかく違う方へ話を振って気をそらすことに決めた。
「あのさ、聞きたいことがあるんだけど」
「は、はい、なんですか?」
「エナは何か呪文を言っていたみたいだけど、僕にはほとんど聞こえなかった。聞こえたとしてもノイズのような、意味不明の音だったし、それはなぜなんだ?」
この問いかけに対しエナは予想通りに、僕の話に乗ってくれた。
「それでしたら、たぶん魔法言語を使ったからだと思います。多少なりとも魔法に関わる人じゃないと認識することができないみたいなので、それでユウキさんには聞き取れなかったんじゃないかと思います」
なるほどな、と普通に納得しかけたが、よくよく考えると魔法に関わってることで認識できる言葉っていったいどういう原理で成り立っているんだ。
「あの、それって」
と、言いかけたところで、やっぱりやめた。というのも、それに対する答えが僕のような一般の高校生が普段使ってるような言葉で説明されるとは到底思えなかったからだ。ファンタジーな人たちが自分たちの常識を説明するのにどういう言葉を用いるか、どう考えてもファンタジーだろう。「魔法言語は魔力や呪文と密接な関係にあって~」とか、よくわからない説明をされるに違いない。
「どうしましたか?」
「……やっぱりなんでもない。 それより」
「ねえ、そんなとこで立ち止まって何やってるの?」
「うわあ!」
背後から突然声をかけられて、思わず叫んでしまった。僕は、カバンをなるべく足の後ろの位置で持ちながら声をかけた人物の方へと向き直る。そこには、一人の女の子が僕のことを唖然とした様子で、目をぱちくりさせていた。
「な、何?」
「何、じゃない! 声かけた私の方がビックリした!」
「ご、ごめん」
「……ほんとに、昔からあんまり変わってないよね優希って。 気弱でこれといって目立つこともないけど、たまに不気味なくらいに不思議っこでさ」
「驚かせてすいませんでしたお願いですから過去のことを出すのはやめてください」
「はいはい。わかりましたよー。けど、ぼやぼやしてると遅刻になるから急いだほうがいいよ?」
そういってニヤニヤしながら僕の前にいる少女――日向陽花(ヒナタ ハルカ)は学校に向かう道を歩き出して、僕の前から去っていった。
日向陽花――僕の中では陽花と呼んでいるが――と僕は、いわゆる幼馴染という関係にある。家は微妙に距離があるが、それでも近いと言えるものだろう。補足しておくとマンガのように彼女が毎朝家にやってきて僕を起こしにやってくるだとか僕のために料理を作ってくれるだとかそんなことは一切ないのであしからず。これは僕の友人にも常々言っていることだが、彼は全くもって相手にしてくれない。まぁそんなことはどうでもいい。
幼少期によく母が「まるできょうだいね」と僕らを見て言っていたのだが、そう言われるほどに、僕らはよくいっしょにいることが多かった。そのころは陽花も今のように気が強くはなかったような気がするし、現在は彼女が主導権を握っていることが多いが、昔は対等の立場で遊んでいた気がする。そんなことは、今となっては関係ないかもしれないけど。
「び、びっくりしましたね……あの、ユウキさん、今の人は?」
ひょっこりと、エナがカバンから顔を出した。雨が止んだので窓から顔を出してみた、といった感じだ。最も、雨というよりかは嵐だったが。
「日向陽花って言って、僕の幼馴染だよ」
「なんだか元気が良い人でしたね……」
ほへー、と唖然とした様子のエナだが、正直僕にはどちらも似たようなものじゃないかと思う。
「エナも大概だと思うんだけどな」
「うーんと、そうですか?」
きょとんと僕を見つめているところから考えて完全に自分では自覚してないことが窺えるな。
「……まぁいいや。僕もさっさと学校に行こう」
長話して遅刻でもしたら、それこそ馬鹿以外の何物でもない。止めていた足を再び動かして、学校への道を歩き出す。
「学校」というワードを出した途端にエナから笑顔がこぼれた。なんだっていうのだろう。
「うーん、楽しみですねぇ~人間の学校ってどんなところなんでしょう?」
「これといった面白いものはないと思うけどね」
「それは人間の視点だからですよー。 うーん一体どんなところなんでしょうか!」
なにやらエナが思いを馳せ始めたのでとりあえず放っておこう。
僕は、僕の日常を今日も繰り返す。
ただそれだけのことをしに行くだけなのだから。
訂正する。やっぱり日常じゃない。
「いやーやっぱり人間界って天界とは全然違うんですねー」
「ああ、そうかい」
僕は今、学校の屋上にいる。それだけ聞けばただの休み時間の休憩と思えるだろうが、残念ながら今の時間は一時間目の真っ最中だ。それではなぜこんなところにいるかというとやっぱりその原因は目の前にいる極悪天然少女エナのためである。正直つれてこなければ良かったと思っている。家に帰せるものなら今すぐ帰したい。
事の発端は国語、もとい現代文の授業で教師である宮田先生が生徒に質問をしたことから始まる。
「いやーやっぱり人間界って天界とは全然違うんですねー」
「ああ、そうかい」
僕は今、学校の屋上にいる。それだけ聞けばただの休み時間の休憩と思えるだろうが、残念ながら今の時間は一時間目の真っ最中だ。それではなぜこんなところにいるかというとやっぱりその原因は目の前にいる極悪天然少女エナのためである。正直つれてこなければ良かったと思っている。家に帰せるものなら今すぐ帰したい。
事の発端は国語、もとい現代文の授業で教師である宮田先生が生徒に質問をしたことから始まる。
「あーと、それじゃここの文章の『まがりなりにも』の意味分かる奴いるか?」
そのときの僕は窓際の席で、外の風景を流し目で見ながら授業を聞いていた。雲がゆったりと流れているのがよくわかった。校門の外の道路を時々自転車が通ったりもした。
正直、授業に対して真面目かといわれればどちらかといえばそうではないと答えるだろう。黒板に書かれたことをノートに写して、質問を当てられたらとりあえず答える。やってることはやっている。だが、それだけでしかない。積極的に発言するわけでもないしテストの点数を上げようと努力しているわけではない。ただその場に参加しているだけに過ぎない。だが、世の中の生徒の半数はそんなものだろう。どうせこの質問だって誰も自分から答えようとはしないだろう。
そう思ったときだった。
「はい!」
声が聞こえた。それだけなら別に問題はない。問題なのは僕の「カバン」から聞こえてきたことだ。顔から血の気が引くとはこのことだろうと思った。
「い、今のは池田、なのか?」
「え、あ、その、はい」
正直、このときは僕も無我夢中だったんだろう。カバンに速攻で手を突っ込んでから全力で
「すいません保健室行ってきますッ!!」
「ちょ、おい池田?」
そのときの僕は窓際の席で、外の風景を流し目で見ながら授業を聞いていた。雲がゆったりと流れているのがよくわかった。校門の外の道路を時々自転車が通ったりもした。
正直、授業に対して真面目かといわれればどちらかといえばそうではないと答えるだろう。黒板に書かれたことをノートに写して、質問を当てられたらとりあえず答える。やってることはやっている。だが、それだけでしかない。積極的に発言するわけでもないしテストの点数を上げようと努力しているわけではない。ただその場に参加しているだけに過ぎない。だが、世の中の生徒の半数はそんなものだろう。どうせこの質問だって誰も自分から答えようとはしないだろう。
そう思ったときだった。
「はい!」
声が聞こえた。それだけなら別に問題はない。問題なのは僕の「カバン」から聞こえてきたことだ。顔から血の気が引くとはこのことだろうと思った。
「い、今のは池田、なのか?」
「え、あ、その、はい」
正直、このときは僕も無我夢中だったんだろう。カバンに速攻で手を突っ込んでから全力で
「すいません保健室行ってきますッ!!」
「ちょ、おい池田?」
こうして僕は屋上にやってきた。あれから教室がどうなったとかは考えたくない。
「人間界はああやって人に答えさせるんですねー。天界ではみんな黙って聞くだけなんですよー」
訂正する。こんなのが日常であってたまるか。
「あのさ、自分が目立っちゃいけない存在だってことわかってる?」
「で、でも答えられるか、と問われたので……」
「わ、かっ、て、る?」
「ご、ごめんなさい……」
もしや、今日一日中こんな調子で進んでいくんだろうか。
「……頭が痛くなってきた」
「頭痛ですか? 横になってお休みになったほうがいいですよ?」
「主に君のせいだよコンチクショウ!」
「ご、ごめんなさいぃ!?」
「人間界はああやって人に答えさせるんですねー。天界ではみんな黙って聞くだけなんですよー」
訂正する。こんなのが日常であってたまるか。
「あのさ、自分が目立っちゃいけない存在だってことわかってる?」
「で、でも答えられるか、と問われたので……」
「わ、かっ、て、る?」
「ご、ごめんなさい……」
もしや、今日一日中こんな調子で進んでいくんだろうか。
「……頭が痛くなってきた」
「頭痛ですか? 横になってお休みになったほうがいいですよ?」
「主に君のせいだよコンチクショウ!」
「ご、ごめんなさいぃ!?」
次の二時間目、僕が保健室で横になったのは言うまでもないことだった。
それから時間は過ぎていき、現在はお昼の真っ最中。当然僕も昼食を食べていた。
「あの、ユウキさん、本当に反省してますからそんなムスッとした顔しないでください……」
「別にー僕の顔はいつもこんな感じだろうからなー。 それより人がいないからって無用心だぞ。 屋上とはいえ人が来ることもあるから、僕の側を飛んでたら絶対見つかるからね」
「あう……ごめんなさい」
購買部で買ったサンドイッチを口にしながら、エナに注意を促す。けど、転落防止用のフェンスに背中を預けながら、体育座りで食事をするのは僕ぐらいなものだろうから普通の生徒は来ないはずだけどね。
「よーっすユッキー!」
うん、普通の生徒は来ないはずなんだけどね。うん、コイツは仕方ない。というか、しょうがない。
幸い屋上のドアをこれでもかというくらい自己主張するように開けたからエナが隠れる時間は十分だったけど。
「いきなり、どうしたんだ杉原」
「おいおいおい、毎度ながら冷たいなお前……まぁそれもお前の面白いとこだけどさ」
「で、ただ会いに来たっていうわけじゃないだろ」
「流石のユッキーちゃんには俺の思惑なんざお見通しってわけか」
「毎度毎度ノート借りに来たら用件ぐらい分かるしその前にそのユッキーっていうのはどうにかならないのかよ。つか、まずちゃん付けすんな!」
「あ~、そいつは無理だね、俺の中じゃユッキーはユッキーだし」
「……それで、今日は英語のノート?」
「あからさまに不機嫌そうにすんなよ~。 俺とお前の仲だろ~?」
そう言って杉原は僕の隣に移動して右肘をぐりぐりと擦り付けた。
「質問に答えないと貸さない、っていうか貸せないぞ」
「ほんとお前素っ気無いよなぁ……俺だって疲れてんだよ~ちょっとくらいあいつからのストレスを発散させてくれよ~」
「……ああ、なるほど、飛田の授業か」
「ただでさえ俺数学嫌いなのによ~オマケに今日なんか当てられちまって……ああ思い出しただけでムカツクぜっ」
基本的にコイツとは話を合わせたくないのだが、数学教師・飛田先生については僕も賛同する。
飛田先生の授業について、この学校の生徒の半数以上が「嫌だ」と話しているのを耳にする。
成績の良い生徒については当たり障りもなく、しかし反対に成績の悪い生徒には嫌味なくらいしつこく質問する。それが教科書の内容に関するだけならまだしも参考書などに書いてあるようなことまで触れてくるから余計に性質が悪い。
さらに問題が分からなければしつこく怒られ、また質問の的にされる。
僕自身、解答するのに少し時間がかかっただけで分からないとみなされ怒られたこともあって、だいぶ、いやかなり嫌いだ。
「まぁ仕方がないよ。あれはもう事故か災害だと思うしかない」
「だよなあ……にしたってあのハゲメガネはほんとムカツクぜ……」
がっくりと肩を落とす杉原だったが、すぐに気を取り直したのか僕に向き直って。
「ま、落ち込んでてもしゃあない。 ありがとよ」
「別に、何かした覚えはないけどな」
「英語のノート借りるのと、愚痴聞いてくれたことの礼だよ。そんじゃな」
そうして杉原は屋上から走り去っていった。いつもどおり、変な奴だと僕は思った。
「ええと、今の人はユウキさんの友達ですか?」
どこに隠れていたのか分からないが、いつのまにか僕の隣にエナがいた。
「まぁ、そんなものだよ。 杉原 涼っていうんだけどね」
「なんだか、あの人もヒナタさんに負けず劣らず元気な人でしたね~」
「正直うっとおしく思えるレベルだけどね」
「でもユウキさん、楽しそうに見えましたけど?」
「うんとねそれはきっと気のせいだろうそろそろ休み時間も終わるし僕らも戻ろうか」
「ああ! 私を置いて行かないでくださいよユウキさ~ん!」
見た目お花畑に見えても、やはりエナは鋭いというか、きちんと見ているというか。悔しいが、確かにそのとおりだ。
だって、アイツは僕に親しげに話しかけてくる数少ない人間の一人だから。
それでも、ウザイところは本当にウザくは思ってるんだけどね。
「あの、ユウキさん、本当に反省してますからそんなムスッとした顔しないでください……」
「別にー僕の顔はいつもこんな感じだろうからなー。 それより人がいないからって無用心だぞ。 屋上とはいえ人が来ることもあるから、僕の側を飛んでたら絶対見つかるからね」
「あう……ごめんなさい」
購買部で買ったサンドイッチを口にしながら、エナに注意を促す。けど、転落防止用のフェンスに背中を預けながら、体育座りで食事をするのは僕ぐらいなものだろうから普通の生徒は来ないはずだけどね。
「よーっすユッキー!」
うん、普通の生徒は来ないはずなんだけどね。うん、コイツは仕方ない。というか、しょうがない。
幸い屋上のドアをこれでもかというくらい自己主張するように開けたからエナが隠れる時間は十分だったけど。
「いきなり、どうしたんだ杉原」
「おいおいおい、毎度ながら冷たいなお前……まぁそれもお前の面白いとこだけどさ」
「で、ただ会いに来たっていうわけじゃないだろ」
「流石のユッキーちゃんには俺の思惑なんざお見通しってわけか」
「毎度毎度ノート借りに来たら用件ぐらい分かるしその前にそのユッキーっていうのはどうにかならないのかよ。つか、まずちゃん付けすんな!」
「あ~、そいつは無理だね、俺の中じゃユッキーはユッキーだし」
「……それで、今日は英語のノート?」
「あからさまに不機嫌そうにすんなよ~。 俺とお前の仲だろ~?」
そう言って杉原は僕の隣に移動して右肘をぐりぐりと擦り付けた。
「質問に答えないと貸さない、っていうか貸せないぞ」
「ほんとお前素っ気無いよなぁ……俺だって疲れてんだよ~ちょっとくらいあいつからのストレスを発散させてくれよ~」
「……ああ、なるほど、飛田の授業か」
「ただでさえ俺数学嫌いなのによ~オマケに今日なんか当てられちまって……ああ思い出しただけでムカツクぜっ」
基本的にコイツとは話を合わせたくないのだが、数学教師・飛田先生については僕も賛同する。
飛田先生の授業について、この学校の生徒の半数以上が「嫌だ」と話しているのを耳にする。
成績の良い生徒については当たり障りもなく、しかし反対に成績の悪い生徒には嫌味なくらいしつこく質問する。それが教科書の内容に関するだけならまだしも参考書などに書いてあるようなことまで触れてくるから余計に性質が悪い。
さらに問題が分からなければしつこく怒られ、また質問の的にされる。
僕自身、解答するのに少し時間がかかっただけで分からないとみなされ怒られたこともあって、だいぶ、いやかなり嫌いだ。
「まぁ仕方がないよ。あれはもう事故か災害だと思うしかない」
「だよなあ……にしたってあのハゲメガネはほんとムカツクぜ……」
がっくりと肩を落とす杉原だったが、すぐに気を取り直したのか僕に向き直って。
「ま、落ち込んでてもしゃあない。 ありがとよ」
「別に、何かした覚えはないけどな」
「英語のノート借りるのと、愚痴聞いてくれたことの礼だよ。そんじゃな」
そうして杉原は屋上から走り去っていった。いつもどおり、変な奴だと僕は思った。
「ええと、今の人はユウキさんの友達ですか?」
どこに隠れていたのか分からないが、いつのまにか僕の隣にエナがいた。
「まぁ、そんなものだよ。 杉原 涼っていうんだけどね」
「なんだか、あの人もヒナタさんに負けず劣らず元気な人でしたね~」
「正直うっとおしく思えるレベルだけどね」
「でもユウキさん、楽しそうに見えましたけど?」
「うんとねそれはきっと気のせいだろうそろそろ休み時間も終わるし僕らも戻ろうか」
「ああ! 私を置いて行かないでくださいよユウキさ~ん!」
見た目お花畑に見えても、やはりエナは鋭いというか、きちんと見ているというか。悔しいが、確かにそのとおりだ。
だって、アイツは僕に親しげに話しかけてくる数少ない人間の一人だから。
それでも、ウザイところは本当にウザくは思ってるんだけどね。
あれから、特に問題になるようなこともなく僕にとって当然の時間が過ぎていった。いやそもそもこれ以上不可思議なことがあったら困るわけで。エナには一応おかしなことはするなと言っておいたが、あの性格だ。何度言ってもやりかねないそんな恐怖が離れない。
僕がそんなことを思いながらカバンの中を見つめると、心の中を見透かすようにニッコリとエナが笑った。もしや狙っているんじゃないだろうなこの天使。いや、流石にそれはない、と信じたいのだけれど。
「それにしても、人間っていつでも忙しそうですねユウキさん」
「まぁ、朝と夕方っていうのは特に忙しいかもね」
それは僕の周りを見るだけでも確認できることだった。まず、車の通行量が多いわけだし。他にも僕と同じように帰宅途中の学生もちらちらと見える。自分がいる道の先を見ると、元気に走り回る小学生が、律儀に右手を上げて横断歩道を渡ろうとしているところだった。
そして、僕がそこに到達するころには信号は赤く変わり、僕はその場でただ立っている。
何も変わらない現実、いつもと同じあの空を、僕は見上げてみた。
「やっぱり、変わらないな」
「……変わらないって、何がですか?」
「別に、大したことじゃないから大丈夫」
そう、大したことじゃない。それでいいんだ。
気づけば、信号はいつの間にか青に変わっていて、僕はその表記に従って再び歩き始めた。
アスファルトの乾いた音が、僕の耳に酷く纏わりつくの感じた。
「……ユウキさん、今朝の話のことなんですけど」
エナが、言いにくそうに聞いてきた。その表情から、何を言いたいのかなんとなく察したが、あえて知らぬふりをしてみる。
「えっと、なに?」
「その、魔法使いになるっていうことについてなんですけど……」
「言っただろ、僕はただの高校生だって」
「でも、私……」
なにが、でも、なんだろう。どうにしろ、僕がそんな不思議ヒーローになる理由はどこにもない。
僕はただ、池田優希という人間として生きるだけなんだから。
いつからだろう。自分が、ただ"池田優希"としての日常を過ごすだけの機械人形のようにしか感じられなくなったのは。
何かが変わるって、そうやって自分にありもしない幻想を言い聞かせて、漫画とかゲームだとか、そんなありえない非現実の世界を欲しがって。
僕が何を思おうと、現実は現実のままだった。だから僕は非現実を諦めて、ただのつまらない日常を淡々と過ごすようになっていたんだ。
神様とやらがいるのなら。
なんで、今なんだ。なんで、僕なんだ。なんで。なんで。
「あの、ユウキさん?」
「……あ、な、なに?」
「なんだか、朝通った道とは違うところを歩いているような気がしたので……ユウキさん?」
考えすぎるのは悪いところだと自分でも思っているけど、まさか道すらも間違うとは予想していなかった。言われたとおり自分のいる場所を確認すると僕が普段使っている帰り道とは違う場所だった。住宅が密集していて、すぐそばには広めの公園がある。夕方ではあるが、子供の声が聞こえることからまだ遊んでいる子もいくらかいるみたいだ。
「う、うんと、道間違えちゃったみたいだな。でも方角は合ってるから家には帰れるよ。少し、遠回りだけど」
いくらなんでも道を間違うなんて、ひょっとしたら疲れてるのかもしれないな。まぁエナがいるから、っていう理由が一番それっぽい気もする。
「ええと、たぶんこの公園を突っ切って向こうに行けばいいはずなんだけ……」
悪寒が走った。ぞわりと立ち上ったそれは僕の髪の毛の先にまで浸透した。ただの寒気とは、何かが違う。
「エ、エナ、今……」
僕がエナに疑問をぶつけようとするのと、公園の方から明らかな悲鳴が聞こえてくるのはほぼ同時のことだった。
「い、今のって叫び声ですよね?」
「た、たぶん」
そのときの僕は、別に何を思って公園に走っていったわけじゃなくて。
何か起こっていると、そう感じたときにはすでにその場に向かって全力で走っていた。無我夢中って、こういうことなのかもしれないな、などと微妙に冷静に考えながらも僕は現場にたどり着いていた。
公園のだいたい中央部分に、女の子が倒れていた。たぶん小学生くらいだ。そこまでは普通に事故でも起きたのかと、そう思えた。
女の子の向こう側に、黒い翼の怪物を見るまでは。
「グ、グリー? そんな、もうですか!?」
「ぐりー、って、あの怪物!?」
その怪物の姿は、なんだか酷く歪んでいて。見るだけで嫌悪感とか恐怖とか、そんなマイナスの感情がこみ上げてくるのを感じた。全体的に黒く、周りをもやのようなものが包んでいて正確な姿は分からないが、どう考えてもこの地球上で生息しているあらゆる生き物とは根本的に何かが違う。何がと聞かれると分からないが、少なくともこんなに嫌な気持ちにさせる生き物がいてたまるか。
そう思っていると、怪物がゆったりとではあるが移動し始めた。どう見ても、女の子を狙っている。そして、その女の子は恐怖からか、転んだような姿勢から全く動けないでいる。どうなるのかはわからないが、良くないことが起こるのは確かだろう。
「ユウキさんお願いします!魔法使いになってくださいっ!」
真剣な目で、エナは僕を見つめた。でも、僕は。僕はただの。
「僕は普通の高校生で……」
「私は信じてます! ユウキさんは普通の高校生じゃないって信じてます!」
「どうしてだよ!? なんでだよ!? 僕はただの」
「だってユウキさんは私と普通にお話して、私と普通に関わってくれました!」
それがどうしたんだ。そう思うときには、エナは言葉を続けていた。
「本当は怖かったんです。 いきなり人間界に降りて、気味悪がられたりして、拒絶されたらどうしようって……殴られたりするのかな、なんて思ってたんです。 でもユウキさんは、受け入れてくれました! 私の話を信じてくれました! だから、私も信じます! ユウキさんは魔法使いになるって信じてます!」
「エナ……」
本気の言葉。彼女は、本当に信じている。こんな、ただ人生をのらりくらりと生きてきたような人間を。
「ずるいよ」
「……え?」
「そんなこと聞かされたら」
どんな奴だって。
僕がそんなことを思いながらカバンの中を見つめると、心の中を見透かすようにニッコリとエナが笑った。もしや狙っているんじゃないだろうなこの天使。いや、流石にそれはない、と信じたいのだけれど。
「それにしても、人間っていつでも忙しそうですねユウキさん」
「まぁ、朝と夕方っていうのは特に忙しいかもね」
それは僕の周りを見るだけでも確認できることだった。まず、車の通行量が多いわけだし。他にも僕と同じように帰宅途中の学生もちらちらと見える。自分がいる道の先を見ると、元気に走り回る小学生が、律儀に右手を上げて横断歩道を渡ろうとしているところだった。
そして、僕がそこに到達するころには信号は赤く変わり、僕はその場でただ立っている。
何も変わらない現実、いつもと同じあの空を、僕は見上げてみた。
「やっぱり、変わらないな」
「……変わらないって、何がですか?」
「別に、大したことじゃないから大丈夫」
そう、大したことじゃない。それでいいんだ。
気づけば、信号はいつの間にか青に変わっていて、僕はその表記に従って再び歩き始めた。
アスファルトの乾いた音が、僕の耳に酷く纏わりつくの感じた。
「……ユウキさん、今朝の話のことなんですけど」
エナが、言いにくそうに聞いてきた。その表情から、何を言いたいのかなんとなく察したが、あえて知らぬふりをしてみる。
「えっと、なに?」
「その、魔法使いになるっていうことについてなんですけど……」
「言っただろ、僕はただの高校生だって」
「でも、私……」
なにが、でも、なんだろう。どうにしろ、僕がそんな不思議ヒーローになる理由はどこにもない。
僕はただ、池田優希という人間として生きるだけなんだから。
いつからだろう。自分が、ただ"池田優希"としての日常を過ごすだけの機械人形のようにしか感じられなくなったのは。
何かが変わるって、そうやって自分にありもしない幻想を言い聞かせて、漫画とかゲームだとか、そんなありえない非現実の世界を欲しがって。
僕が何を思おうと、現実は現実のままだった。だから僕は非現実を諦めて、ただのつまらない日常を淡々と過ごすようになっていたんだ。
神様とやらがいるのなら。
なんで、今なんだ。なんで、僕なんだ。なんで。なんで。
「あの、ユウキさん?」
「……あ、な、なに?」
「なんだか、朝通った道とは違うところを歩いているような気がしたので……ユウキさん?」
考えすぎるのは悪いところだと自分でも思っているけど、まさか道すらも間違うとは予想していなかった。言われたとおり自分のいる場所を確認すると僕が普段使っている帰り道とは違う場所だった。住宅が密集していて、すぐそばには広めの公園がある。夕方ではあるが、子供の声が聞こえることからまだ遊んでいる子もいくらかいるみたいだ。
「う、うんと、道間違えちゃったみたいだな。でも方角は合ってるから家には帰れるよ。少し、遠回りだけど」
いくらなんでも道を間違うなんて、ひょっとしたら疲れてるのかもしれないな。まぁエナがいるから、っていう理由が一番それっぽい気もする。
「ええと、たぶんこの公園を突っ切って向こうに行けばいいはずなんだけ……」
悪寒が走った。ぞわりと立ち上ったそれは僕の髪の毛の先にまで浸透した。ただの寒気とは、何かが違う。
「エ、エナ、今……」
僕がエナに疑問をぶつけようとするのと、公園の方から明らかな悲鳴が聞こえてくるのはほぼ同時のことだった。
「い、今のって叫び声ですよね?」
「た、たぶん」
そのときの僕は、別に何を思って公園に走っていったわけじゃなくて。
何か起こっていると、そう感じたときにはすでにその場に向かって全力で走っていた。無我夢中って、こういうことなのかもしれないな、などと微妙に冷静に考えながらも僕は現場にたどり着いていた。
公園のだいたい中央部分に、女の子が倒れていた。たぶん小学生くらいだ。そこまでは普通に事故でも起きたのかと、そう思えた。
女の子の向こう側に、黒い翼の怪物を見るまでは。
「グ、グリー? そんな、もうですか!?」
「ぐりー、って、あの怪物!?」
その怪物の姿は、なんだか酷く歪んでいて。見るだけで嫌悪感とか恐怖とか、そんなマイナスの感情がこみ上げてくるのを感じた。全体的に黒く、周りをもやのようなものが包んでいて正確な姿は分からないが、どう考えてもこの地球上で生息しているあらゆる生き物とは根本的に何かが違う。何がと聞かれると分からないが、少なくともこんなに嫌な気持ちにさせる生き物がいてたまるか。
そう思っていると、怪物がゆったりとではあるが移動し始めた。どう見ても、女の子を狙っている。そして、その女の子は恐怖からか、転んだような姿勢から全く動けないでいる。どうなるのかはわからないが、良くないことが起こるのは確かだろう。
「ユウキさんお願いします!魔法使いになってくださいっ!」
真剣な目で、エナは僕を見つめた。でも、僕は。僕はただの。
「僕は普通の高校生で……」
「私は信じてます! ユウキさんは普通の高校生じゃないって信じてます!」
「どうしてだよ!? なんでだよ!? 僕はただの」
「だってユウキさんは私と普通にお話して、私と普通に関わってくれました!」
それがどうしたんだ。そう思うときには、エナは言葉を続けていた。
「本当は怖かったんです。 いきなり人間界に降りて、気味悪がられたりして、拒絶されたらどうしようって……殴られたりするのかな、なんて思ってたんです。 でもユウキさんは、受け入れてくれました! 私の話を信じてくれました! だから、私も信じます! ユウキさんは魔法使いになるって信じてます!」
「エナ……」
本気の言葉。彼女は、本当に信じている。こんな、ただ人生をのらりくらりと生きてきたような人間を。
「ずるいよ」
「……え?」
「そんなこと聞かされたら」
どんな奴だって。
「魔法使いに、なるしかないじゃないか」